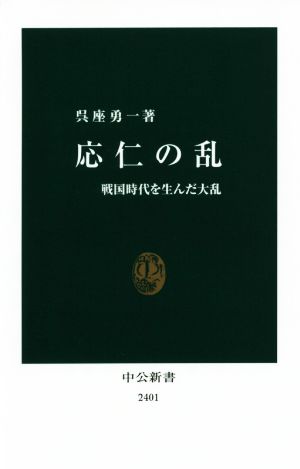応仁の乱 の商品レビュー
数年前にこの本がかなり売れていたと聞き読んでみた。応仁の乱は「あー学校で習ったな」くらいの知識量だったのでとにかく読み進めるのに苦労した。とにかく登場人物が多いし関係も複雑。それだけ応仁の乱が難解ということか。 第三章に入ってからは割とすんなり読めた。 笑ってしまったのは、戦乱が...
数年前にこの本がかなり売れていたと聞き読んでみた。応仁の乱は「あー学校で習ったな」くらいの知識量だったのでとにかく読み進めるのに苦労した。とにかく登場人物が多いし関係も複雑。それだけ応仁の乱が難解ということか。 第三章に入ってからは割とすんなり読めた。 笑ってしまったのは、戦乱が長期化してきた頃、西軍の仲間うちで正月の遊びをしたところ勝敗を巡った喧嘩に発展し、80人の死者負傷者が出たと言う箇所。いやなにやってんの?!と思わず突っ込んでしまった。 せっかくこの本を読んだので、応仁の乱が舞台の小説「室町無頼」を読んでみようと思う。
Posted by
戦国時代の契機となったとされる応仁の乱を大和国興福寺の視点を交えつつ描く。戦国時代の始まりは、応仁の乱とされるが、明応の政変がきっかけと著者は指摘。応仁の乱後もかろうじて維持されていた守護在京制は、明応の政変を機に完全に崩壊し、守護は国元帰り国人を統率せねば領国を維持できなくなっ...
戦国時代の契機となったとされる応仁の乱を大和国興福寺の視点を交えつつ描く。戦国時代の始まりは、応仁の乱とされるが、明応の政変がきっかけと著者は指摘。応仁の乱後もかろうじて維持されていた守護在京制は、明応の政変を機に完全に崩壊し、守護は国元帰り国人を統率せねば領国を維持できなくなった。
Posted by
呉座勇一氏の作品は2作目。前作「陰謀の日本中世史」が面白かったので手に取ってみた。応仁の乱というと学生時代に1467年(人の世むなし応仁の乱)というゴロで覚えさせられたのしか記憶にないが、本書を読むにあたっては最低でも東軍と西軍の主な顔ぶれくらいは知っていた方がより楽しめる。ごく...
呉座勇一氏の作品は2作目。前作「陰謀の日本中世史」が面白かったので手に取ってみた。応仁の乱というと学生時代に1467年(人の世むなし応仁の乱)というゴロで覚えさせられたのしか記憶にないが、本書を読むにあたっては最低でも東軍と西軍の主な顔ぶれくらいは知っていた方がより楽しめる。ごく簡単にいうと東軍は細川勝元、畠山政長、斯波義敏、京極持清、赤松政則、武田信賢。西軍は山名宗全、畠山義就、斯波義廉、一色義直、土岐成頼、大内政弘。これに将軍家の跡取り争いである足利義尚と義視が加わるのだがこの義尚と義視が東軍についたり西軍についたり両軍入れ替わりするので話がややこしくなる。この乱は結局東軍が勝つのだが東軍の大将・細川勝元の当初の真意は、足利義政→義尚という伊勢路線でもなく、足利義政→義視という山名路線でもなく、足利義政→義視→義尚という規定路線の維持だったと考えられる。また乱の前に伊勢貞親・季瓊真蘂(きけいしんずい)・斯波義敏らの失脚=文正の政変があり伊勢貞親という共通の敵がいなくなると、細川勝元と山名宗全の激突は避けられないものになったという。応仁の乱が勃発した要因は複数あるが、直接の引き金になったのは畠山氏の家督争いである。つまり政長と義就の争いである。そして朝倉孝景の寝返りが応仁の乱の戦局の転換点であったことは学界でも共通認識となっているらしい。(朝倉孝景は東軍に寝返った。)詳細→ https://takeshi3017.chu.jp/file10/naiyou34402.html
Posted by
何年も前に話題になった本で、ずっと読みたいとは思っていたのですが、ついつい後回しにしてしまい、このタイミングでようやく手に取りました。 応仁の乱については、小学校でも中学校でも高校でも習ったはずなのですが、戦いの中身についてはほとんど記憶に残っておらず…。 そんなわけで、新たに...
何年も前に話題になった本で、ずっと読みたいとは思っていたのですが、ついつい後回しにしてしまい、このタイミングでようやく手に取りました。 応仁の乱については、小学校でも中学校でも高校でも習ったはずなのですが、戦いの中身についてはほとんど記憶に残っておらず…。 そんなわけで、新たに学ぶつもりで、読み進めました。 応仁の乱は、領地の争いや家督の争い、後継者問題、役職の争い、武士としての仁義、過去のしこりに由来する仇討ち、といったものが入り組んでの戦いであり、しかも、戦い開始時の東軍の総大将の細川勝元と西軍の総大将の山名宗全は、別にバチバチの関係にあるわけではなく、むしろ畠山氏の家督争いに巻き込まれた結果、いずれも総大将になるなど、応仁の乱は、覚悟を決めてのスタートではなく、やむにやまれぬ事情で始まったのですね。 まったくの素人の自分からすると、詳しすぎてついていけない部分も多かったのですが、それでも、応仁の乱の概略はつかめた気がします。 ちなみに、本書は、奈良の興福寺にまつわる二人の僧(経覚(きょうがく)と尋尊(じんそん))が残した記録が柱となって構成されているのですが、約500年前でありながら、京都での出来事を奈良にいながら把握していた二人の情報網は、驚き以外の何物でもありません。 本書を読んでいて思ったのですが、応仁の乱をもっとちゃんと理解するには、当時の価値観や道徳観や生活や制度をもっと知らないとだめですね。 今回は、それらがないまま読んでしまったので、浅い理解で終わった気がします。 そこはやむを得ないとは思いつつも、反省点。
Posted by
応仁の乱(1467-1477)は、日本史の画期と言われる。 画期というからには、日本史は「応仁の乱」前と、「応仁の乱」後に区分出来るということだ。 ということは、我々は「応仁の乱」後を生きている、と言える。 日本の文化、日本人の宗教観•意識、日本語は、この乱を境に大きく変貌した。...
応仁の乱(1467-1477)は、日本史の画期と言われる。 画期というからには、日本史は「応仁の乱」前と、「応仁の乱」後に区分出来るということだ。 ということは、我々は「応仁の乱」後を生きている、と言える。 日本の文化、日本人の宗教観•意識、日本語は、この乱を境に大きく変貌した。 本書は、その画期を成す乱をコンパクトにまとめているが、その全容を掴むのは極めて難しい。 何故なら、保元•平治の乱のように、敵対勢力を明確に区分して、勝ち負けをはっきりさせることができないからだ。 最初は、敵味方、勝ち負けがはっきりしているように見える。 しかし、それがズルズルと全国レベルに広がり、10年以上もそんな状態が続くのだから、明確さを欠くこと夥しい。 我々が歴史で習うのは、将軍家、摂関家、各大名家の対立による、京都を戦場とした戦いだ。 「応仁の乱」は、細川勝元と山名宗全を両対象とする戦乱であると習ったはずだ。 だが、それは「応仁の乱」の発端に過ぎない。 守護大名から、寺院、地侍に至るまで、あらゆるレベル、あらゆる地域で、内紛、抗争が、燎原の火のように広がり、日本列島全体が混乱の坩堝に巻き込まれたのだ。 それが「応仁の乱」の捉えどころのない真の姿だったのだ。 誰もが直ぐに終わると思っていた京都の擾乱は、直ぐに地方に飛び火し、従来の体制を悉く破壊し尽くし、遂には、戦国時代の幕を切って落とす。 本書は、日本史の時代の変革を画する日本最大の内乱の動的メカニズムを詳細に描く。 しかし、それも簡単ではないことは言うまでもない。 読み通すには、忍耐が必要とされるが、読む価値はある。
Posted by
戦国乱世の扉を開いた応仁の乱はいかに起こり、なぜ長期化したのかを読み解いた本。 高校日本史の知識が身についていることが必要。授業だけでは見えてこない、戦の経緯や室町時代の本質を学べます。
Posted by
経覚・尋尊という奈良 興福寺の僧侶の眼を通しての、新しい「応仁の乱」像。 経覚の父は関白・九条経教、母は浄土真宗大谷本願寺の出身。尋尊の父は関白左大臣一条兼良、母は中御門宣俊の娘と言う、所謂良家の出家者。当時はこのように公卿からの出家者は、大きなお寺の今で言う貫主の地位につけたよ...
経覚・尋尊という奈良 興福寺の僧侶の眼を通しての、新しい「応仁の乱」像。 経覚の父は関白・九条経教、母は浄土真宗大谷本願寺の出身。尋尊の父は関白左大臣一条兼良、母は中御門宣俊の娘と言う、所謂良家の出家者。当時はこのように公卿からの出家者は、大きなお寺の今で言う貫主の地位につけたようだ。 さて新しい視点の「応仁の乱」と言っても、高校の授業で、恐らく教科書の数行程度の記述でしかなかったと思われ、自分にとっては新しいも古いもなく、そのまま素直に読解することを心がけた。 この時代、敵になったと思ったら寝返ったり、親子・兄弟の間でも敵味方になったりと、実にややこしい。で、なかなか読み進めることが出来ない。 自分にとっての発見は、この時代、新しい文化が武家の経済的支援によって花開いていったということ。 15世紀後半以降、在国するようになった守護・守護代は、国元に立派な館を築いている。 実際守護館(守護所)の遺跡は発掘調査によって全国各地で見つかっているが、そのほとんどが平地の、一辺が150~200mほどの方形館で、その敷地内には連歌や茶の湯を行う建物「会所」があった。主殿・常御殿・遠侍などの配置も判で押したようである。主家斯波氏に対する「下剋上」を果たした朝倉氏の居城として知られる越前一乗谷の朝倉氏館も例外ではなく、地域的な特色・個性は見られない。こうした守護館の構造は、「花の御所」(室町殿)などの将軍邸を模倣したものだったらしい。 山ロも周防守護の大内氏によって、京都をモデルにした地方都市として整備された。しばしば「小京都」と呼ばれるこの都市の原型は、大内氏が抱いた京都文化への憧れによって生み出されたのであるとのこと。 一方、現実の京都はというと、守護や奉公衆の在国化によって住民が激減し、市街域も大幅に縮小した。 と言うことだ。 京都のほとんどが焼けただけではなく、新しい芽が外に伝播して行ったのね。
Posted by
享徳の乱の勉強をするにあたって、中央で起こった大乱を無視することはできんやろうと思って、再読。 まぁ理解度は6割ってとこだけど。
Posted by
再読。以前にベストセラーとなった本だが、複雑怪奇な応仁の乱を前後を含めて、大和の僧の視点から論述しているが、分かりやすく読みやすい。
Posted by
年号は覚えたが、前後の出来事はほぼ知らない状態で読み始めた。一応、最後まで読んだ感想は、難しかったの一言。 しかし、少なくとも読む前よりは「応仁の乱」の理解が深まったので、2回目があればより理解できると思う。特に、応仁の乱後の戦国時代への流れや京の文化が全国的に広がった経緯など、...
年号は覚えたが、前後の出来事はほぼ知らない状態で読み始めた。一応、最後まで読んだ感想は、難しかったの一言。 しかし、少なくとも読む前よりは「応仁の乱」の理解が深まったので、2回目があればより理解できると思う。特に、応仁の乱後の戦国時代への流れや京の文化が全国的に広がった経緯など、なるほどと思う。 「終章 応仁の乱が残したもの」がまとめ的だったので、この章を先に読むのも有りかと思った。
Posted by