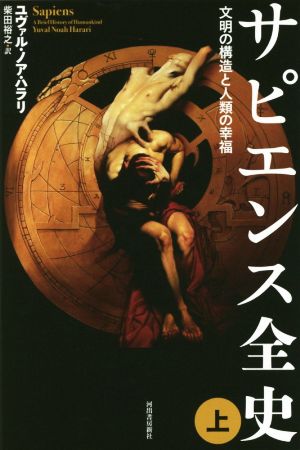サピエンス全史(上) の商品レビュー
クローズアップ現代での特集に興味を持ち読んでみる。途中で挫折しそうかなと思っていたが意外と読みやすい。ただけっきょくどんな結論になるのか下巻を読むまでわからない。下巻に進みたい。
Posted by
私はいつも自分の存在が人間という枠の中でもがくしかない絶望感にとらわれて悲しみにとらわれていた。本書は救いの書である。新しい解釈で、新しい視点で人間というものの存在を再確認できる。この本を読んで、渋谷の交差点を見下ろしてみるがいい。人間の存在が実にばらばらであるが、妙に統一感があ...
私はいつも自分の存在が人間という枠の中でもがくしかない絶望感にとらわれて悲しみにとらわれていた。本書は救いの書である。新しい解釈で、新しい視点で人間というものの存在を再確認できる。この本を読んで、渋谷の交差点を見下ろしてみるがいい。人間の存在が実にばらばらであるが、妙に統一感がある不思議に、本当に感動する。
Posted by
ちょっと難しすぎてよく呑み込めなかったが、共同主観的秩序が虚構を信じこむことによって法律、貨幣、神々、国家国民を想像し、成立させる。なんか分かり切ったことを言ってるのに過ぎないとは思うのだが、、、 男女間の格差は性に対して能動的受動的行動差に起因するような気がする。
Posted by
世界的話題の書ということで繰り上げ読了。アフリカで細々と生きていた人類の祖先(食物連鎖でいうと中程度)が、なぜこの星の支配者になったのか、その答えの鍵は「フィクション」であるという。国家、文明、貨幣、宗教、企業、法律、平等や将来は今より豊かになるというフィクション。これらのおかげ...
世界的話題の書ということで繰り上げ読了。アフリカで細々と生きていた人類の祖先(食物連鎖でいうと中程度)が、なぜこの星の支配者になったのか、その答えの鍵は「フィクション」であるという。国家、文明、貨幣、宗教、企業、法律、平等や将来は今より豊かになるというフィクション。これらのおかげで見知らぬ人と協力するようになり、進化の法則を飛び越えて力を得た。一方、狩猟社会から農耕社会になったおかげで安定的かつ豊かな社会を手に入れたと教えられたが、労働時間は増え、人口は増えたが飢餓も増えた。むしろ穀物を活かすために働いているようなもので、主人は穀物だという視点は新鮮。生物学的に数を増やすことが成功ならば、歴史上最も成功した動物は家畜となった牛であるが、狭い檻の中で過ごし、初めて歩くのは解体される時という生物が果たして幸せなのか。そしてこれは人間にも当てはまるのではないか。
Posted by
ホモ・サピエンスの歴史を筆者の視点、持論で解説した本。学校で習った「歴史」は、かなり大まかにざっくりと、それも主流の解釈を学んだだけだったことに今さらながら気付きました。そして、学生時代に苦手科目だったのに、歴史ってこんなに面白いんだ〜と思いました。好奇心をかなり、くすぐられまし...
ホモ・サピエンスの歴史を筆者の視点、持論で解説した本。学校で習った「歴史」は、かなり大まかにざっくりと、それも主流の解釈を学んだだけだったことに今さらながら気付きました。そして、学生時代に苦手科目だったのに、歴史ってこんなに面白いんだ〜と思いました。好奇心をかなり、くすぐられました!
Posted by
まだ上巻ですが、感心した着眼点が2つ。1つは、総合的に優位なネアンデルタール人を絶滅させたのは、サピエンスに共同で虚構を信じる能力にあったという仮説。(認知革命) おそらく人類はこの能力によって現在も進化を続けていると気づきました。もう1点は、狩猟から農耕に移行したことは、格差を...
まだ上巻ですが、感心した着眼点が2つ。1つは、総合的に優位なネアンデルタール人を絶滅させたのは、サピエンスに共同で虚構を信じる能力にあったという仮説。(認知革命) おそらく人類はこの能力によって現在も進化を続けていると気づきました。もう1点は、狩猟から農耕に移行したことは、格差を生み多くの人を幸せにしていないという指摘です。(農業革命) 実は、ここで搾取層が生まれています。延々と現代まで続く搾取層の存在にエリート理論を思い出しました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ホモサピエンスが如何様にして発展し栄華を築いてきたのか? 新旧の学説を用いて多角的に立てられる仮説には説得力があり、かつ興味深い。 上巻はサピエンス以外の人類がいた時代が主体であり、 あまり馴染みのない歴史が語られるがそれでも頁をめくる手がとまらないほど。
Posted by
nhkで紹介あり。 オバマ大統領が、読んでいる。 図書館予約済み20170108 五章の農業革命までは、面白かった。 六章の神話から難しくなった。 またの機会に読み直そう。 20170402
Posted by
2016年を代表する本として各所で絶賛されているが、確かにこれは凄まじく知的好奇心を揺さぶってくれる。 イスラエルの歴史学者である著者が明らかにするのは、ホモ・サピエンスという生物種がなぜ他の生物種と異なり、地球でここまでの文明を作り上げることに成功したのかという問いへの答えで...
2016年を代表する本として各所で絶賛されているが、確かにこれは凄まじく知的好奇心を揺さぶってくれる。 イスラエルの歴史学者である著者が明らかにするのは、ホモ・サピエンスという生物種がなぜ他の生物種と異なり、地球でここまでの文明を作り上げることに成功したのかという問いへの答えである。そのカギを握るのは、「認知革命」・「農業革命」・「科学革命」という3つの革命であった、というのが骨子となる。 上巻では、歴史学者としての丁寧な史実関係叙述と不確実な事柄はそのまま不確実さを伝えるという真摯なスタンスにより、「認知革命」と「農業革命」についてが解説される。 「認知革命」は、ホモ・サピエンスが言語を発明したことや、言語により相互のコミュニケーションが可能になったということではなく、「虚構」を生み出すことにより、様々な共同体を組成できるようになったこと、そしてその共同体とは虚構、別の言葉を用いれば幻想の存在であるということこそが革命の主たるポイントとされる。例えば、宗教や国家、引いては我々の多くが所属する企業に至るまで、あらゆる共同体は「その構成員全てが、会ったことがない他の構成員に関して自らとの同一性を感じ、何らかの協力体制を構築できる」というのが特徴になるが、共同体とは自ら触れて確かめることができないにも関わらず、その存在が疑われないという点で、一種の虚構性を帯びる。 「農業革命」について刮目すべきは、「人間は小麦などの作物を農業に適した形で栽培化することで、狩猟採集よりも安定的な生存基盤を獲得できた」という考えが実は誤解であるということが明らかにされる点にある。事実はむしろ逆で、「人間は小麦により家畜化され、小麦という種が世界にその遺伝子を残すべく繁栄することに成功した」、つまり人間は小麦の利己的遺伝子を残すためのビークルとして利用された側であるという。これは我々が通説的に考えている狩猟採集社会から農業社会への移行のバックグラウンドの言説を覆す説であり、非常に面白い。 本書の面白さは、例えば「認知革命」だけを例に取れば、おおむねその主張はベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」で語られていることと軌を同じくしていると思うが、そのスコープが農業、科学など多岐に渡り、なおかつ時間的・空間的な広がりを持っている点において、この一冊で広範な人類の活動の謎を全て知ってしまえるのではないかという奇妙な錯覚を与えてくれる点にある。引き続き下巻へ。
Posted by
ホモ・サピエンスが高度な文化を持つようになった経緯を説明した歴史書。ホモ・サピエンスの進化の歴史が分かる。これにより、人類の本質を知ることになる。ホモ・サピエンスは、認知革命による進化を遂げ、地球の生物の頂点に立つことになった。さらに農業革命で狩猟生活から定住生活へと変化し、現代...
ホモ・サピエンスが高度な文化を持つようになった経緯を説明した歴史書。ホモ・サピエンスの進化の歴史が分かる。これにより、人類の本質を知ることになる。ホモ・サピエンスは、認知革命による進化を遂げ、地球の生物の頂点に立つことになった。さらに農業革命で狩猟生活から定住生活へと変化し、現代に至っている。本書で意外に感じたのは、農耕生活は狩猟生活からの進化だと思われるが実はそうではないこと。栄養バランスや社会を維持するための苦労が狩猟社会よりあるというのだ。もちろん納得する説明があるので、奇っ怪な説だという疑いは持たない。農耕生活の方が狩猟時代より厳しい生活を強いられているのは目からウロコ。また、農耕生活に移行したことで、栽培されるようになった小麦から見ると、子孫を増やした小麦が勝者であるというのは面白い観点だ。人類は小麦にいいように使われているだけなのかもしれない。下巻も同様な面白さだと期待したい。
Posted by