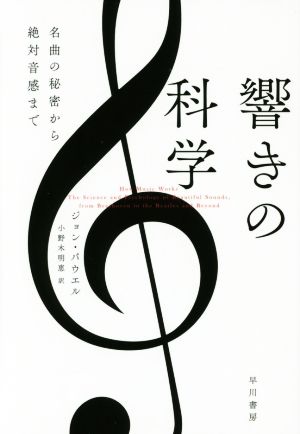響きの科学 の商品レビュー
最近、音楽理論を勉強しようとしてたところ、この本を見つけました。 家にギターがあるので、音を出しながら確かめたりしました。 これをきっかけに再度音楽理論の勉強を深掘りする気になりました。
Posted by
物理学者でありミュージシャンでもあるジョン・パウエル氏が、音楽と雑音はどこが違う? 絶対音感は必ずしも役に立たない?アナログとデジタル、音がよいのは? なぜ短調は悲しげに聞こえるのか? クラシックとロックの名曲の共通点とは?などの音楽にまつわる素朴な疑問にわかりやすく答えてくれる...
物理学者でありミュージシャンでもあるジョン・パウエル氏が、音楽と雑音はどこが違う? 絶対音感は必ずしも役に立たない?アナログとデジタル、音がよいのは? なぜ短調は悲しげに聞こえるのか? クラシックとロックの名曲の共通点とは?などの音楽にまつわる素朴な疑問にわかりやすく答えてくれる一冊。 なんか聞いたことあるようなお名前?って調べたら有名な映画音楽たくさん手掛けてらっしゃるじゃないの。P.S. アイラヴユー。
Posted by
「音」を科学的な観点から考察する本。4年前に買ったままにしていたが「何故もっと早く読まなかったんだろう」と思わされた。 著者は物理学者だが、堅苦しいものではなく平易でユーモアのある言葉で「そうだったんだ、、、!!」ということが書いてあり、音楽を仕事としてやっている人にも、趣味とし...
「音」を科学的な観点から考察する本。4年前に買ったままにしていたが「何故もっと早く読まなかったんだろう」と思わされた。 著者は物理学者だが、堅苦しいものではなく平易でユーモアのある言葉で「そうだったんだ、、、!!」ということが書いてあり、音楽を仕事としてやっている人にも、趣味としてやっている人にもとても面白く読めるはず。是非多くのこういった人たちに読んでほしい。 特にオーケストラをやっている人には、各楽器の音色の違いを生み出す波形やその理由といったことから、音階のできた経緯・調に抱く印象神話の解明・交響曲や協奏曲が生まれた経緯まで扱っているので、はじめから終わりまでとても楽しめると思う。
Posted by
音楽全般にわたる物理のお話。 物理学者でミュージシャンの著作と言うことで、どちら方面にも専門的になりすぎることなく、とてもわかりやすく楽しい本だと思いました。 音楽をする人は読んでおいてもいいんじゃないかな。 もしかすると、読んでいて納得のいかない年季の入ったリスナーや熱心な演奏...
音楽全般にわたる物理のお話。 物理学者でミュージシャンの著作と言うことで、どちら方面にも専門的になりすぎることなく、とてもわかりやすく楽しい本だと思いました。 音楽をする人は読んでおいてもいいんじゃないかな。 もしかすると、読んでいて納得のいかない年季の入ったリスナーや熱心な演奏家の人もいるかもしれませんがね。(^^;
Posted by
同じ楽器を使って、同じ音を出しているはずなのに、その音色の違いが圧倒的すぎて打ちのめされることがしばしばある。 音とはいったいなんぞや、ということが、この本を読んで少しわかるようになった気がする。
Posted by
音楽の仕組みがわかる。 音と音楽は違う(包含関係にある)。波長に規則性を持った音が音楽となる。楽器は何かを振動させて、それを反響させて拡大させる。アンプやスピーカーもそれと同様の仕組み。 和音が綺麗に聞こえるのも半音なら、チューンを間違えた音のようになるがそれ以外なら綺麗な波長に...
音楽の仕組みがわかる。 音と音楽は違う(包含関係にある)。波長に規則性を持った音が音楽となる。楽器は何かを振動させて、それを反響させて拡大させる。アンプやスピーカーもそれと同様の仕組み。 和音が綺麗に聞こえるのも半音なら、チューンを間違えた音のようになるがそれ以外なら綺麗な波長になる。 12にオクターブを分けたのは長期間にわたる歴史の成り行き。しかし、弦の長さを5.6%ずつ縮めることがわかったのは今から数百年前のことで、そこから今の葉もにーの基礎となる、12音階が誕生した。ピアノの白鍵で表されるイオニア旋法であり、その他5つの始まり方がある(イロハニホヘト)。短調は長調ほど完璧ではなく、最後の音を半音ずらしたりするなど3つの短音階がある。長調短調の中での始まり方に性質はなく、それが感じられるのは転調した時にキーが上がれば明るく、下がれば落ち着くだけである。
Posted by
学部生のときに、ギターを使った音響学の実験を行ったことがある。 ギターの弦を振動させ、周波数を測定して、長さと弦の張力の関係を観る、といった内容だったと記憶している。 弦の振動の基礎理論は高校物理の範囲であり、それほど難解な数学を使用するわけではない。 音波を基本波に分解す...
学部生のときに、ギターを使った音響学の実験を行ったことがある。 ギターの弦を振動させ、周波数を測定して、長さと弦の張力の関係を観る、といった内容だったと記憶している。 弦の振動の基礎理論は高校物理の範囲であり、それほど難解な数学を使用するわけではない。 音波を基本波に分解するFourier変換の理解はさすがに大学の物理数学ではあるけれど、波が正弦波で表せることができて、全ての波長はこの正弦波の重ね合わせであるということは高校物理の弦の振動の本質である。 話を簡単にするため、高校物理では一つの単純な正弦波のみを考える。(上記から、現実はその重ね合わせであるからそれほど大胆な簡易化ではない) たとえば、フルートのような吹奏楽器でフルートの長さによってどうのような周波数の音がでるか、端を塞いだ場合と解放した場合とで周波数はどう変化するか、という問題が良く出題される。 言ってしまえば、高校物理を良く理解していれば本書を読む必要はないのだけれど、読み物として「音」を科学的に理解してみよう、というのは本書以外にあまり見たことがない。 また、良く考えれば当たり前だが、一昔前ヨーロッパで標準規格が整備される前は、各国で音の音色が異なっていたのだ。 たとえば、イギリスのピアノでド(A0)を弾いた場合とドイツのピアノでド(A0)を弾いた場合、周波数が違うのだ。 音は基準を決めれば、数学的にほかの音も決めることができる。 A1はA0の2倍の周波数とすればよく(つまり、弦の長さを半分にすればよい)て、A0とA1の間の12音は前の音の約94.4%だけ短くしていけば、きれいな音色がでる。 ただし、これはヨーロッパ式であり、別にA0とA1を1オクターブでなくともよく、A0とA1の間は12音でなくてもいい。 (上記は、仮りにA0とA1は2倍の周波数にして、その間は12音にするという決まりを設けたとしても、基準のA0の取り方は全く自由で良いということ) 実際、モーツァルトが作曲に使用したピアノは、現在よりも半音低いそうだ。 なんでわかるかというと、使ったピアノが残っているからだ。 とまぁ、響きの「科学」は高校物理で勉強するけれど、復習の意味もあるし、歴史的なところは面白く読めた。 筆者が文章の途中にはさむユーモアもセンスがあり、どんどん読み進めることができる。
Posted by
科学をとおしておもに楽器や楽典の成り立ちを解説。 説明がわかりやすくとてもおもしろい。 例としてのバンドで、ステイタス・クオーがでてくるなど、 ちょっとニヤリなところも多くて満足。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・ジョン・パウエル「響きの科学 名曲の秘密から絶対音感まで」(ハヤカワ文庫)は実に分かり易い内容の書である。例へば第10章「アイ・ガット・リズム」は音楽の中心にあるであらう「リズム、テンポ、拍子」を説明する。この中で、ダンスには、リズム、テンポ、拍子の「三つの要素のうち、リズムが最も重要ではないという驚きの結論に至る。」(291頁)とある。メヌエット、ガボット、ワルツとくればリズムが関係ありさうに思はれるのだが、実際はさうではないといふ。「音楽のテンポによってどれくらい速く踊るかが決まり、拍子によって、どういう種類のダンスを踊るかが決まる。」(同前)らしい。「健康な若い成人がクラブで踊っている場合、毎分九〇から一四〇拍の音楽が流れてい」(292 頁)る。これに対して「ワルツの拍数はおよそ毎分一〇〇回であ」(293頁)る。少々遅い。なぜか、「ワルツでは、やるべきことがもっとたくさんあるからだろう。」(同前)踊り手2人が動きを合はせ、フロアを移動せねばならぬ。速くては踊れないのである。更にエリザベス朝のヴォルタ、三拍子の軽快な舞曲で ある。「ヴォルタでは、女性を持ち上げたり低い位置に落としたりという動作が多く」(同前)といふわけだから、「男女ともにうれしいことに、偶然に手がすべるチャンスが豊富にあった。」(同前)ある程度の速さがあるからこそかういふことにもなるのである。ワルツとかタンゴとかいふとりズムが重要に思へるのだが、それ以上に速さなのであつた。実はこの章、ダンス以前に、五線譜の成立と仕組みについて分かり易く説明してゐる。私は一応楽譜の仕組みは承知してゐるつもりだが、それでもこの説明を分かり易く感じる。普通の楽典の比ではない。 ・第1章「音楽とはいったい何?」にこんな文章がある。「音楽や科学の専門教育を受けていなくてもこの本を理解できる」(11頁)。また「訳者あとがき」 には、「数式や物理学の専門用語をほとんど用いずに、音楽にくわしくない読者にとってもわかりやすく(中略)音楽の原理を明らかにしている。」(374 頁)確かに実に分かり易い。楽音と雑音の違ひをかう説明する。「最終的に鼓膜に到達する雑音の波形は、互いに関係のない個々の波が無秩序に集まったものからできているため、極度に複雑になる。」(45頁)これに対して「あらゆる音楽の音は、ひとつの波形を何度も繰り返すという点で、他の雑音と異な」(46 頁)る。つまり、楽音は同じパターンを繰り返す波形を持つ音である。さうか、さういふことなのかと、改めて楽音の波形を思ひ出しながら思ふ。これなどは音響学の領域であらうか……と書いて、目次を眺めると、本書には楽典に出てきさうな内容は少ない。音声学や音響学等の楽典とは異なる領域での音楽の書であると知れる。本書が「響きの科学」たる所以である。音階や和声の説明も分かり易い。かみ砕いて、時にはたとへを入れたりしながら説明する。周波数と倍音についての説明、知らないわけではないと思つてゐたが、これを読むとやはりまともには分かつてゐなかったのだと思ふ。弦を弾く位置によつて音が変はる理由は、 「弦のどこを弾いても基本周波数は同じだが、それ支えるその他の振動の混合比率が変わってくる」(58頁)からであつた。納得である。私にはこんなのばかりであつた。改めて確認したことの報告ばかりである。何となく知つてゐるつもりのことが実はさうではなかつた、正にこれであつた。その意味で、本書は私に は正に蒙を啓いてくれる書であつた。専門家でなくとも、あまりいい加減な知識ではよくない。これを再出発としようと思ふ。
Posted by
楽譜と数式があったほうが読みやすいと感じる人は多いと思う。それでも、音の「強さ」についての幾つかの説明(デシベルとホーン、音波の干渉と音量など)については役に立った。
Posted by
- 1
- 2