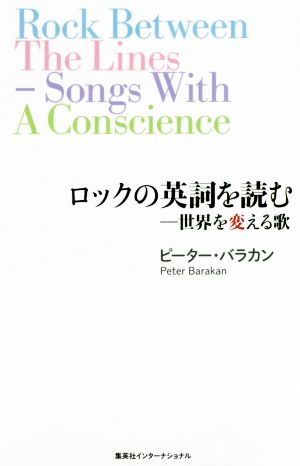ロックの英詞を読む 世界を変える歌 の商品レビュー
ピーターさんのラジオ番組は以前から興味があったが、なかなか時間が合わず継続して聴けなかった。最近になってようやくスマホアプリの聞き逃し配信で聴けるようになったので、さらに深く彼の勧める音楽を知りたいと思い本書を手に取った。 読んでみて歌詞の奥深さに驚嘆した。クラシックもそうだ...
ピーターさんのラジオ番組は以前から興味があったが、なかなか時間が合わず継続して聴けなかった。最近になってようやくスマホアプリの聞き逃し配信で聴けるようになったので、さらに深く彼の勧める音楽を知りたいと思い本書を手に取った。 読んでみて歌詞の奥深さに驚嘆した。クラシックもそうだが、軽音楽も、正直これほど日本が遅れているとは思わなかった。中でも政治的なプロテストに至っては、日本の音楽ではあまり取り上げられることはないので、ここまで表現しているのかとちょっと衝撃的だった。 ピーターさんのように日本語にあれだけ堪能な人が、こうして洋楽を紹介してくれる同時代に生きる私たちはラッキーだと思う。日本にとどまらない、より多面的な視点で音楽、ひいては政治、生活を捉えることができるようになる。これからも彼の番組を聴きながら、他の著書も読み続けたい。
Posted by
ブラック・ミュージックの勉強の過程で、こちらの本に出会って購入。 ジョニ・ミチェルやランディ・ニューマンなどこの本を通じて改めて理解を深める。 英語の歌詞は、独特の言い回しや省略などあって実はなかなかわかりにくい。こういう本がたくさん出るといいと思う。
Posted by
著者のラジオ番組を時々聞いていて、最近聞き逃しサービスができたので、とても嬉しい。 ラジオでお話しされていることが活字になって、さらに英語の歌詞を、非常にわかりやすく解説してある。 詞というのは、翻訳が非常に難しい分野だと思う、センスも問われるだろう。ダブル・ミーニングや韻を踏ん...
著者のラジオ番組を時々聞いていて、最近聞き逃しサービスができたので、とても嬉しい。 ラジオでお話しされていることが活字になって、さらに英語の歌詞を、非常にわかりやすく解説してある。 詞というのは、翻訳が非常に難しい分野だと思う、センスも問われるだろう。ダブル・ミーニングや韻を踏んでいるところとか・・・後、社会情勢やアーティストの生まれ育ちなどの背景も知っておかねばならないから。 ディスクジョッキーの話を耳で聞くだけでなく、時々活字を読むのも面白いなと感じた。
Posted by
著者のピーター・バラカンは、とても良心(Conscience)が強い。 ピーターのような感覚が世界を変える「力」のひとつでもあるのだろう。 私は本書で紹介された音楽を聴きながら、この記事を書いている。
Posted by
社会派ソングばっかり。勉強にはなるが。 Les McCannのCompared to What?の歌詞知らなくて驚いた。
Posted by
とりあえず、洋楽の日本盤CDに付いている訳詞はひどいな、と薄々思っていたことは本当らしい、ということが分かったことが収穫。 マニアックな、というか日本で無名なアーティストが多い選曲はバラカンさんだから想定内。 英語教材本としての一面も意識して作られており、「セルフ・カバー」等...
とりあえず、洋楽の日本盤CDに付いている訳詞はひどいな、と薄々思っていたことは本当らしい、ということが分かったことが収穫。 マニアックな、というか日本で無名なアーティストが多い選曲はバラカンさんだから想定内。 英語教材本としての一面も意識して作られており、「セルフ・カバー」等の英語圏で全く通用しない(!)和製英語や、歌手名で定着している高名音楽家たちの正しい発音の正誤表だけでお腹いっぱい。 スラングの説明もあるし、イギリス人から見たアメリカ文化への距離感も面白い。 ジャクスン・ブラウン「プリテンダー」、ランディ・ニューマン「ポリティカル・サイエンス」やジョン・プラインの「サム・ストーン」の歌詞の正確な意味が分かっただけでお釣りが来ました。 バラカンさん、日本の英語教育を考えるナントカ委員会か何かのご意見番に就任してくれないかな。
Posted by
20世紀初頭から現代に至るまでの強いメッセージを持った英語の歌22曲の著者独自の訳と解説。 選ばれた曲は、確かに有名な曲ですが、カーペンターズやイーグルスといった英語の教材に出てきそうな歌詞よりもむしろスラングや詩的表現を含んだものが多いです。また、“Ohio”で扱った事件で兵...
20世紀初頭から現代に至るまでの強いメッセージを持った英語の歌22曲の著者独自の訳と解説。 選ばれた曲は、確かに有名な曲ですが、カーペンターズやイーグルスといった英語の教材に出てきそうな歌詞よりもむしろスラングや詩的表現を含んだものが多いです。また、“Ohio”で扱った事件で兵士が発したとされる“We are not tin soldiers.”という言葉を下敷きにしているといったハイコンテクストな歌詞もありますが、そのような解説もきちんとされているため、歌詞を読んだだけではひっくり返っても本来の意図に辿り着けない意味も含めて歌詞を味わうことができます。 この本の特徴で面白いのは、曲の並び順が年代やテーマ、ジャンルなどではなく、曲名のABC順であるということです。そのため、ベトナム戦争を扱った歌がポツポツと何度も出てきたり(実際、ベトナム戦争と公民権運動がロックの社会運動の一番強かった時期に重なったのでしょうから、このテーマを扱った曲が多く選ばれています)、“Strange Fruit”の雰囲気の直後に“The Pretender”が来たりといった妙が生まれています。 しかし、見方を変えれば、現実世界の複雑性と、様々な共存しがたい問題—社会問題にしろ個人の葛藤にしろ—を同時に抱えた姿を反映させているのだといえます。その中で、力を持った歌が悩める人の心を刺激して、前進させてくれる、これまで観察された歴史の一部分を見ることが出来、同時に未だ解決しない問題に個々人がどう向き合うかを考えさせる力が依然としてあることが分かり、そして当然これからも新しい力を持った歌が生まれることを確信させます。 現代において、収録されたほぼ全ての歌がインターネットを通じて聴くことができます(Apple Musicには今のところ“Day After Tommorow”以外は全てあり、もちろんこれもYouTubeで聴くことが出来ます)。是非、原曲を聴きながら読んでください。
Posted by
テレビ・ラジオ等で活躍するピーター・バラカン氏の最新刊。 バラカン氏がセレクトしたロック・ソウルなど22曲の行間に込められたメッセージの新訳と、曲が収録されたアルバム・カバー曲など関連する曲が収録されているアルバム紹介等がなっています。 YouTubeで曲を確認しながら読みまし...
テレビ・ラジオ等で活躍するピーター・バラカン氏の最新刊。 バラカン氏がセレクトしたロック・ソウルなど22曲の行間に込められたメッセージの新訳と、曲が収録されたアルバム・カバー曲など関連する曲が収録されているアルバム紹介等がなっています。 YouTubeで曲を確認しながら読みました。ほとんどの曲が初めての出会いでしたが、ジャンルは違えども共通するのは、時代を反映したものであること・表現が深く多様であり聴くものに様々なメッセージを伝えるものでした。どこか言いたいことが言えなくされていっている社会の中で、そうであってはならないというバラカン氏の思いに、とても共感しました。 音楽の持つ人々をつなぐ力を感じ、ますます好きになりました。また、自分の日々の暮らしの中でも豊かな表現を目指して工夫していこうとも思いました。 お勧めの一冊です。 追伸… どれも良かったのですが、あえてあげるとすると次の3曲かな。 ・「ブラック、ブラウン・アンド・ワイト・ブルーズ」(ビッグ・ビル・ブルーンジー) ・「ノー・ワン・ノウズ・ナシング・エニモア」(ビリー・ブラッグ) ・「シャイン」(ジョーニ・ミチェル)
Posted by
- 1