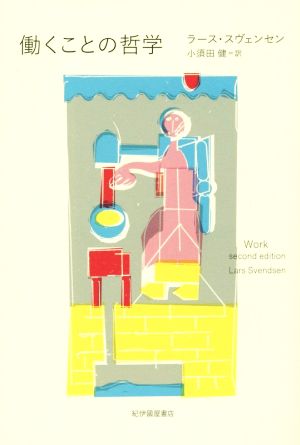働くことの哲学 の商品レビュー
作者がノルウェーの哲学者でお国柄なのか過労死について反応が薄い印象。 作者自身の体験をもとに個として労働に向き合う姿勢を考えてる内容で、日本のようにまわりの雰囲気にのまれ集団の中の一労働者として考えるとはまた違った。 もう少し自立して個として労働に携わり読み返したら印象が変わるか...
作者がノルウェーの哲学者でお国柄なのか過労死について反応が薄い印象。 作者自身の体験をもとに個として労働に向き合う姿勢を考えてる内容で、日本のようにまわりの雰囲気にのまれ集団の中の一労働者として考えるとはまた違った。 もう少し自立して個として労働に携わり読み返したら印象が変わるかもしれない。
Posted by
仕事は人生において何かしらのの意味を持つということを大前提とした上で、人の仕事との関わり方についてさまざまな観点で考察を行なっている。 基本的に筆者が序文の中で述べているように労働に対する一つの真理を与えるものではなく、何らかの示唆を与えるものになっている。 この手の本は大体骨太...
仕事は人生において何かしらのの意味を持つということを大前提とした上で、人の仕事との関わり方についてさまざまな観点で考察を行なっている。 基本的に筆者が序文の中で述べているように労働に対する一つの真理を与えるものではなく、何らかの示唆を与えるものになっている。 この手の本は大体骨太で読むのに苦労する印象だがこの本はいい具合の長さでまとめられていて、自分はどう考えるのかという思索へ導くという意味ではちょうどよかった。
Posted by
一時的に働いていない今、働くことについて考える時間だと思って読んだ本。 産業革命の時代には、賃労働に対して強い反発があったのに、徐々に賃金が生活に十分かどうかに関心が向くようになった。これは、賃労働を労働者が受け入れたことになり、資本主義パラダイムに反抗するのではなく、その内部で...
一時的に働いていない今、働くことについて考える時間だと思って読んだ本。 産業革命の時代には、賃労働に対して強い反発があったのに、徐々に賃金が生活に十分かどうかに関心が向くようになった。これは、賃労働を労働者が受け入れたことになり、資本主義パラダイムに反抗するのではなく、その内部で改善していくという慎ましい野心へと変わった。 この内容を読んだ時、人生を良くしようと努力した結果、資本主義という大きなものに飲み込まれてしまったのに、飲み込まれたことにも気づかない、そのどうしようもなさになんとも言えない気持ちになった。とはいえ、やはり現状、資本主義の中にどっぷり浸かっている中では、程度の差こそあれ賃金も大切。 こういうことを考える時間も必要だなぁと思う。
Posted by
人生の中における仕事の位置づけを考えるヒントになるいい本でした。 本の中では、仕事の中にどっぷりと浸かってしまうことは避けるべきものとして書かれている一方、 仕事というものが、かなりの時間を費やすものであり、アイデンティティーの源泉であることは事実で、単なる生活の為の手段にして...
人生の中における仕事の位置づけを考えるヒントになるいい本でした。 本の中では、仕事の中にどっぷりと浸かってしまうことは避けるべきものとして書かれている一方、 仕事というものが、かなりの時間を費やすものであり、アイデンティティーの源泉であることは事実で、単なる生活の為の手段にしてしまうことも、筋がいいとはいえないと言うことが指摘されています。 左派的な考えに共感することが多かった自分ですが、一度踏みとどまって、仕事の大切さを過小評価していないか、考えるようになりました。 仕事に振り回されないようにしつつ、得るものは得る、公私の状況に応じてバランスをとっていきたいところです。 また、過去を振り返ると現代人は働きすぎというわけでもなく、実はレジャーに振り回されているのではないかという指摘にもドキッとしました。 この本ではヨーロッパの歴史を中心に、仕事の捉え方の変化を紹介していましたが、東洋の歴史もフォローしていきたいと思いました。
Posted by
愉しい活動とは、自己目的的なものだ。 レジャーは何もしないことができる時間であるが、現代のレジャーは労働時間以上に枠にあてはめられている。 奴隷→テイラー式管理 働くことの意義は自分にとって何なのか?を明確にしておく。
Posted by
( ..)φメモメモ ——「管理」に関する近年の文献をみて得た一般的な印象は、1960年代と1970年代のカウンター・カルチャーのスローガン「自由と個性と想像力」の変形にすぎないのではというものだ。 それはまったくのところ色褪せたヒッピーの決まり文句でしかないが、いまや企業向けに...
( ..)φメモメモ ——「管理」に関する近年の文献をみて得た一般的な印象は、1960年代と1970年代のカウンター・カルチャーのスローガン「自由と個性と想像力」の変形にすぎないのではというものだ。 それはまったくのところ色褪せたヒッピーの決まり文句でしかないが、いまや企業向けに言いかえられている。
Posted by
労働が、歴史的にどういう風に捉えられ方を変えてきたか(厄災から天職へ、この部分は面白かった!)、労働に伴う状況(賃金、管理、グローバリゼーション、レジャーなど)について解説がされています。 著者の哲学論は展開されておらず、エッセイ的なミニエピソードを挟みながら気軽に読めました。...
労働が、歴史的にどういう風に捉えられ方を変えてきたか(厄災から天職へ、この部分は面白かった!)、労働に伴う状況(賃金、管理、グローバリゼーション、レジャーなど)について解説がされています。 著者の哲学論は展開されておらず、エッセイ的なミニエピソードを挟みながら気軽に読めました。 5章「管理されること」で、巷に溢れる経営哲学啓蒙書に筆者が辟易している描写が笑えました。ほんとあんな個人の成功エピソードを有り難がるって不思議だなぁと常々思ってたので。仕事に管理が必要になったのは、経営者と従業員の利害が一致しないからだ、と書かれておりました。つまり経営視点が従業員全員に染み込んでたら管理は不必要?? 2章「仕事と意味」の最後の部分も素敵でした。 >有意義な人生を送るにはしかるべきことがらにそれも可能であればしかるべき相手に気遣いを示さねばならない。あなたの気遣うことがらが、あなたの人生に目的をもたらす。その事柄を本当にきちんと気遣っていれば、その振る舞いのうちにあなたがどのような人間であるかが表現されていることがわかる。 私は今休職中なのですが、働かなくても充実した人生を送れるということを実感しています。著者はそんなことないって書いてましたが、余暇を潰す方法が増えてきたので、今後は金銭的余裕があっても働く、という選択をする人が減っていくかもしれないですね。
Posted by
2021/9/3 将来得られる救済のために働くプロテスタントの精神が、目先のものを消費する姿勢に転じ、働かなくても良くなった時代を享受できていないというのは何たる皮肉か。 そしてその消費の姿勢は仕事にも向けられ、仕事こそが自己のアイデンティティを確立する道具となる。これは仕事...
2021/9/3 将来得られる救済のために働くプロテスタントの精神が、目先のものを消費する姿勢に転じ、働かなくても良くなった時代を享受できていないというのは何たる皮肉か。 そしてその消費の姿勢は仕事にも向けられ、仕事こそが自己のアイデンティティを確立する道具となる。これは仕事を外在的なものとして捉えているから起こり得ることで、それを内在的なものとして捉えなきゃいけない。 さらに、仕事を好きでいることを善と信じて疑っていなかった姿勢にも疑問を抱くようになった。グラデーション豊かな人生を仕事色だけに染めるのか。それらのバランスは個々の判断によるので、仕事との距離は絶えず考えていかなければならない。
Posted by
気鋭の哲学者として名高い著者による働くことに関する哲学書。仕事に対する向き合い方をゼロから考える機会を供してくれる良書でした。 古くは狩猟採集民族時代に遡り、膨大な時間軸の中で、人間にとって働くことの意味合いがどんな変遷を辿ってきたのかを振り返りながら、現代人が働くことに対して...
気鋭の哲学者として名高い著者による働くことに関する哲学書。仕事に対する向き合い方をゼロから考える機会を供してくれる良書でした。 古くは狩猟採集民族時代に遡り、膨大な時間軸の中で、人間にとって働くことの意味合いがどんな変遷を辿ってきたのかを振り返りながら、現代人が働くことに対して抱いている姿勢に疑問を投げかけるとともに、倫理的な示唆をもたらしてくれる。 「仕事は私たちの人生に豊かさをもたらすものの1つではあるが、一方で人間が幸福になるうえでの全てではあり得ないし、ゆえにそれを仕事に求めたとしても、相応の対価を得ることはできない。」 このパラドックスと、ある意味では当然の帰結を、忙しく熱中しているうちに見過ごしてしまうからこそ、「読書」という営みの中にこれを確認する作業が人生には必要なのだと改めて。
Posted by
哲学者が書くエッセイやコラムのような趣です。けれどもテーマは決して軽くなく、働くという事について広く考えを展開していきます。 複業を始めてから仕事って何だろう?とよく考えるようになりました。「単なるお金を稼ぐ手段」から「働きがいを得る」まで様々です。サラリーマンの仕事と自分の会...
哲学者が書くエッセイやコラムのような趣です。けれどもテーマは決して軽くなく、働くという事について広く考えを展開していきます。 複業を始めてから仕事って何だろう?とよく考えるようになりました。「単なるお金を稼ぐ手段」から「働きがいを得る」まで様々です。サラリーマンの仕事と自分の会社の仕事とを比較する機会は多いし、色々と考えさせられる事が起こります。 著者は古代ギリシャの哲人から現代まで、様々な考えを引用しながら読者に対して考えるように導いてくれます。 当然読むだけで答えは出ないものの、これからも考え続ける勇気を与えてもらい背中を押された感じです。
Posted by