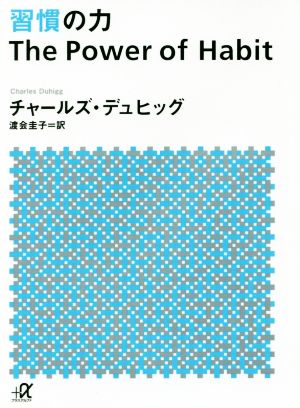習慣の力 の商品レビュー
本書を読み、習慣の恐ろしさと秘めたる力を知った。次の文章が特に印象に残っている。 「大切なのは『神』ではない、と研究者たちは気づいた。『信じること』そのものが差を生むのだ。いったん何かを信じることを覚えると、その能力が人生の他の部分にまで影響を及ぼし、自分は変われると信じ始める...
本書を読み、習慣の恐ろしさと秘めたる力を知った。次の文章が特に印象に残っている。 「大切なのは『神』ではない、と研究者たちは気づいた。『信じること』そのものが差を生むのだ。いったん何かを信じることを覚えると、その能力が人生の他の部分にまで影響を及ぼし、自分は変われると信じ始める。」 私は常々不思議に思っていたことがある。宗教を信仰する人は、なぜ口を揃えて「神を信じてから人生が好転した」と言うのか分からなかった。だが、上記の言葉で納得した。彼らは神を信じることで、自分自身を信じる力を無意識のうちに鍛えていたのだ。本書のおかげで新しい発見に出会えた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1つの習慣に狙いを定めることにより、他の行動もプログラムし直すことができる →自分にとって影響の大きい習慣は何か? 毎日の人の行動の40%がその場の決定ではなく、習慣だと言われている 習慣は脳を楽させるためにできる そのため特定のきっかけには特定の反応をするようになる ささやかなことで、習慣は変えられる シンプルでわかりやすいきっかけを用意 具体的な報酬を設定すること 嫌な臭いを消すためにファブリーズはかけない(新しい習慣) 掃除の後に、さっとふりかけることはする(既存に追加) きっかけは、ルーチンを生み出すだけでなく報酬を期待させる 口の中がひんやりしないことで、その歯磨き粉を使わなかったことがわかる →それをしないと、してないなぁーって気になるような習慣形成
Posted by
<習慣>:無意識+有能 →自分の習慣が何か意識しないと変えられない。 きっかけ→ルーティン→報酬→きっかけ→・・・という構造 <きっかけを知る方法> ①どの場所 ②どの時間 ③心理状態 ④自分以外の人物はいた? ⑤直前の行動はなに? <報酬が何か知る方法> 報酬をいくつか変えて...
<習慣>:無意識+有能 →自分の習慣が何か意識しないと変えられない。 きっかけ→ルーティン→報酬→きっかけ→・・・という構造 <きっかけを知る方法> ①どの場所 ②どの時間 ③心理状態 ④自分以外の人物はいた? ⑤直前の行動はなに? <報酬が何か知る方法> 報酬をいくつか変えてみる 例)どうしてもチョコを食べてしまう。 報酬は?→空腹感を満たしたい?、時間を潰したい?、リラックスしたい? それぞれの代替行動をとってみて「欲求」や「期待」を探る <習慣を変えるのに大切な力> ①自分は変われる、いい方向に進むと「信じる力」 ②自分を応援してくれたり、励ましてくれる「グループ」 ③誰かの習慣を変えるには相手を「信じきる」 <意志力は鍛えられる> ①感情や行動をコントロールすること自体を習慣化 ②意志力を弱らせる転換点に対しての対処法を事前に決めておく <キーストン・ハビット> それを習慣化することで連鎖的に好影響を生み出す習慣 例)読書、運動、瞑想など →小さな勝利→自分は変われるという信念→小さな勝利の積み重ね→大きな勝利へ 7/20追記 コメント 『説得とヤル気の科学』においても言及があったので、習慣に関する書籍の名著中の名著なのだろう
Posted by
【習慣のループ】 きっかけ→ルーチン→報酬が結びつき、その後、欲求が生まれてループを作動させる。 習慣を変えるには、自分にその行為をさせている欲求を分析することが重要なのだ。 また、最後は信じる力の重要性がキーになってくるのだと感じた。あらゆるストレスや困難にも対処するためには...
【習慣のループ】 きっかけ→ルーチン→報酬が結びつき、その後、欲求が生まれてループを作動させる。 習慣を変えるには、自分にその行為をさせている欲求を分析することが重要なのだ。 また、最後は信じる力の重要性がキーになってくるのだと感じた。あらゆるストレスや困難にも対処するためにはやり切れることを信じるのだ。信じ切ることができないと過去の有害な習慣に流されるのが人間。 論点とは関係ないが、1973年までホモセクシュアリティが精神疾患とされていたことには驚いた。 物事に挑戦するうえで、やめたいという気持ちが一番強くなる瞬間「転換点」を中心に計画を立てることの重要性 営業をするうえで転換点・有事が起こった時の対処法を事前に計画することは重要になりそう ターゲット社のマーケティングが人々の習慣を探って計画されていることが興味深かった。まさにデータ社会だ。
Posted by
人間の行動を決めるのが習慣であると述べた本である。本書でKeystone habitと名付けられた習慣は、人間の思考や行動を根本から操る。本書には脳に損傷をもつ人物でさえも習慣的行動だけはこなしてしまうという例が挙げられている。 習慣は都合のいい結果も悲惨な結果も生み出す。繰...
人間の行動を決めるのが習慣であると述べた本である。本書でKeystone habitと名付けられた習慣は、人間の思考や行動を根本から操る。本書には脳に損傷をもつ人物でさえも習慣的行動だけはこなしてしまうという例が挙げられている。 習慣は都合のいい結果も悲惨な結果も生み出す。繰り返し同じことをトレーニングすれば、迷わずに勝利できるスポーツの例もある。一方で悪習にはまりカジノで損をしても、同じことを繰り返してしまう事例もある。 こうした習慣は自己分析し、それが生じるメカニズムを理解すれば、ほかの習慣に置き換えることができるとも述べられている。そのための方法も示されているのは興味深い。 この習慣を学習に当てはめるならば教育の分野で何をすればよいのかというヒントになる。
Posted by
"この本を読むと人間は習慣で生きていることがよくわかる。 驚くべきパワフルで、この本を読んだことのある人と、読んでいない人ではのちの人生に大きな差が生まれるであろう本。 自分で治したい癖や悪習慣があれば、その行為を行う 「きっかけ」をまず見つけること! 「ルーチン」(...
"この本を読むと人間は習慣で生きていることがよくわかる。 驚くべきパワフルで、この本を読んだことのある人と、読んでいない人ではのちの人生に大きな差が生まれるであろう本。 自分で治したい癖や悪習慣があれば、その行為を行う 「きっかけ」をまず見つけること! 「ルーチン」(癖そのもの)を変えてみる 「報酬」 このサイクルを理解し、客観的に眺めることができれば、健康的で生き生きと生活できる習慣を身につけることが可能になる。 様々な依存症(ギャンブル、酒など)からも立ち直れる。 今年一番の本"
Posted by
【由来】 ・ 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
Posted by
きっかけと報酬そのものには新しい習慣を長続きさせる力はない。 脳が報酬を期待するようになってはじめて (達成感や満腹感など)、無意識化する ファブリーズ_「さわやかな香りへの欲求」 報酬→きっかけ(掃除)→ルーチン→報酬・・・ メール_「気晴らしへの欲求」 報酬→きっかけ...
きっかけと報酬そのものには新しい習慣を長続きさせる力はない。 脳が報酬を期待するようになってはじめて (達成感や満腹感など)、無意識化する ファブリーズ_「さわやかな香りへの欲求」 報酬→きっかけ(掃除)→ルーチン→報酬・・・ メール_「気晴らしへの欲求」 報酬→きっかけ(着信)→ルーチン→報酬・・ はみがきは、ヒリヒリしないと綺麗になった気がしない! 意志力は筋肉などと一緒で、使うと疲弊する (クッキーとラディッシュの我慢実験)
Posted by
習慣に興味があり、日々意識することが多いので、即買。 「私たちの生活はすべて、習慣の集まりにすぎない(p11)」「習慣とは、「自分で選んだものである」と気づくことだ(p450)」 「第1部 個人の習慣」「第2部 成功する企業の習慣」「第3部 社会の習慣」が興味深い事例とともに述べ...
習慣に興味があり、日々意識することが多いので、即買。 「私たちの生活はすべて、習慣の集まりにすぎない(p11)」「習慣とは、「自分で選んだものである」と気づくことだ(p450)」 「第1部 個人の習慣」「第2部 成功する企業の習慣」「第3部 社会の習慣」が興味深い事例とともに述べられている。 成果としては、「キーストーン・ハビット(要となる習慣)」、「きっかけ→ルーチン→報酬」の3段階ループと、やはり「GRIT」(根性、やり抜く力)かなぁ。
Posted by
"きっかけがあり、ルーチンが起こり、報酬がある 悪習をもたらすきっかけを排除し、良き習慣の報酬を強く意識する"
Posted by
- 1
- 2