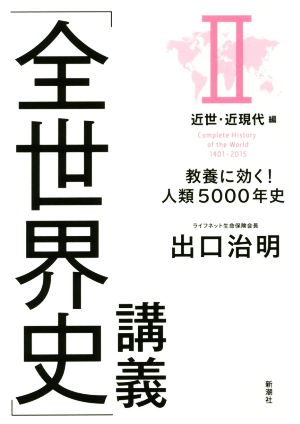「全世界史」講義 教養に効く!人類5000年史(Ⅱ) の商品レビュー
近世から現代まで丁寧に世界史を解説。それなりにリベラルアーツがないと内容についていけないか楽しめないかも。
Posted by
イギリスで産業革命が起こったのはインドが原因、という独特の史観?が興味深い。ただし、全体的には細かな事柄がダラダラと羅列されているだけで、味気ない教科書的な内容。よって「お勉強」にはいいのかもしれないが、読んでいて楽しいものではない。
Posted by
NDC 209 古代・中世編に続き、ルネサンスから現代までを一気読み。複雑な歴史の流れが手に取るようにわかる、全ビジネスマン必読の傑作講義! 「教養の達人」のライフワーク、ついに登場! 文明の誕生から現代まで、人類5000年の歴史を一気読み! 複雑な歴史の流れが手に取るようにわか...
NDC 209 古代・中世編に続き、ルネサンスから現代までを一気読み。複雑な歴史の流れが手に取るようにわかる、全ビジネスマン必読の傑作講義! 「教養の達人」のライフワーク、ついに登場! 文明の誕生から現代まで、人類5000年の歴史を一気読み! 複雑な歴史の流れが手に取るようにわかる渾身の名講義! 歴史の新常識をふんだんに取り入れた人類共通の歴史「5000年史」を学べば、世界がひとつにつながり、歴史がいきいきと動きだす。現代人必読のグローバルスタンダードの教養。 目次 第4部 第五千年紀前半=1001‐1500(クアトロチェント) 第5部 第五千年紀後半=1501‐2000(アジアの四大帝国と宗教改革、そして新大陸の時代;アジアの四大帝国が極大化、ヨーロッパにはルイ一四世が君臨;産業革命とフランス革命の世紀;ヨーロッパが初めて世界の覇権を握る;二つの世界大戦;冷戦の時代) どしゃ降りの雨で始まった第六千年紀
Posted by
1396 ニコポリスの戦い バヤズィト1世 痛風なければローマまで攻めた 1453 コンスタンティノープルの陥落 メフメト2世 1473 アナトリア半島 バシュケントの戦い バヤズィト2世 白羊朝とのバシュケントの戦い(Battle of Otlukbeli)では、イェニチェ...
1396 ニコポリスの戦い バヤズィト1世 痛風なければローマまで攻めた 1453 コンスタンティノープルの陥落 メフメト2世 1473 アナトリア半島 バシュケントの戦い バヤズィト2世 白羊朝とのバシュケントの戦い(Battle of Otlukbeli)では、イェニチェリとヨーロッパ人からなる部隊を指揮し、ウズン・ハサンの甥が率いる騎兵隊と交戦した 騎馬軍団対イェニチェリの戦い。歩兵と鉄砲の完勝。これまで中央ユーラシアの騎馬軍団が敗れたことはなかった。「全世界史II」P28 出口著 1529 第1次ウィーン包囲 1566 スィゲトヴァール包囲戦(シゲットの対トルコ防衛) 1683 第2次ウィーン包囲 イエズス会とイングランド国教の誕生
Posted by
近世、近代は戦争ばかりで混乱してくる。原因がどこにあったかすら忘れてしまうほど、仕返しにつぐ仕返しという印象。人間はいつになったら仲良くできるのかなあ。
Posted by
この本をきっかけに、世界史のもうちょっと詳しい本を読みたいと思いました。 1.この本を一言で表すと? ・近代世界史まとめ 2.よかった点を3〜5つ ・GDPの世界シェア →概算でしかないと思いますが、今まで聞いたことない内容でした。 ・20世紀だけでなく、19世紀も戦争の...
この本をきっかけに、世界史のもうちょっと詳しい本を読みたいと思いました。 1.この本を一言で表すと? ・近代世界史まとめ 2.よかった点を3〜5つ ・GDPの世界シェア →概算でしかないと思いますが、今まで聞いたことない内容でした。 ・20世紀だけでなく、19世紀も戦争の時代 →欧州では常に戦争していたから国家や政治に対する意識が高いのだと思います。 ・アメリカが日本に求めたこと →アメリカの思惑とペリー来航目的がわかり、日本史と世界史がつながった。 ・歴史を学ぶ意味は、人間がこれまでやってきたことを後からケーススタディとして学べるところにあります。 2.参考にならなかった所(つっこみ所) ・古代中世編と同じく、セクションごとに、話題となる地域の地図を載せて欲しかった ・ 3.実践してみようとおもうこと ・とくになし 4.みんなで議論したいこと ・どのあたりの時代が面白いと感じましたか? 5.全体の感想・その他 ・近現代史のほうが、以前読書会を開催した「昭和史」とつながりがあり、面白く感じました。 ・戦争を繰り返したことから、人間の愚かさも感じますが、それでも最後の終章からは希望が持てて良かったです
Posted by
まずは書店で現物を見ておきたいね。そして、2ヶ月くらいしたら、電子書籍版が出ていないかチェックしたい。
Posted by
・1531年、ドイツのプロテスタント諸侯と諸都市によって、シュマルカルデン同盟が結成される ・1555年「アウグスブルクの宗教和議」ドイツ諸侯が自分の領地内でルター派を信仰することが認められた。ただしカルヴァン派は認められず ・1562年からフランスで第8次、約40年にわたるユグ...
・1531年、ドイツのプロテスタント諸侯と諸都市によって、シュマルカルデン同盟が結成される ・1555年「アウグスブルクの宗教和議」ドイツ諸侯が自分の領地内でルター派を信仰することが認められた。ただしカルヴァン派は認められず ・1562年からフランスで第8次、約40年にわたるユグノー戦争(フランスのローマ教会派とカルヴァン派の戦い)が始まる。ユグノーとはカルヴァン派に対する呼称。1598年、アンリ四世が「ナントの勅令」を発布。ローマ教会をフランスの国家的宗教であると宣言するとともに、プロテスタントにもローマ教会と同等の権利を認めた。この英断によってユグノー派とローマ教会派の対立と憎悪は、大きく緩和された ・三十年戦争(1618年〜)はドイツを舞台としたプロテスタント派とローマ教会派の争い。ボヘミア王となったハプスブルク家のフェルデナント二世が、ボヘミアに対してやらなくてもいいプロテスタント弾圧を始めたのが原因。1648年のウエストファリア条約締結で終結 ・サファヴィー朝の極盛期を現出させたアッバース一世は、1598年に首都をイスファハーンに移した。この都は17世紀に「世界の半分」と形容されるほど栄えた ・1915年にフサイン・マクマホン協定を結んだ大英帝国は、1916年、サンクトペテルブルクでフランス、ロシアとオスマン朝の領土分割を秘密裏に取り決めた(サイクス・ピコ協約)。シリアをフランスの勢力範囲と認め、「パレスチナは国際管理地域とする」ことが合意されている
Posted by
やや史実の列挙気味であるが、もう一度読み返したい 時間切れで読めずに返却してから、5ヶ月振りに借りることができた?巻。 1400年から2000年以降の現代までの5千年紀の近代、現代編。 馴染みのある話題が多い反面、膨大な史実が盛り込まれている。。 著者独自の史観に基づくコメント...
やや史実の列挙気味であるが、もう一度読み返したい 時間切れで読めずに返却してから、5ヶ月振りに借りることができた?巻。 1400年から2000年以降の現代までの5千年紀の近代、現代編。 馴染みのある話題が多い反面、膨大な史実が盛り込まれている。。 著者独自の史観に基づくコメントもあるのだが、ページ数に収めるために相当苦労されているようだ。 また、GDP比率比較は引き続き行われて興味深い。 ?産業革命 こんなフローで国家の変遷を考えていたが、 →市民革命→国民国家→産業革命→資本主義→帝国主義→… 当然個々のケースは異なる。 なぜ、連合王国(英)でいち早く産業革命は起こったのか? 議会がいち早く成熟して、前述フローが他国より先行したからか? 著者は、あっさりと「インドのマネをしたから」という。 国民国家、資本主義、帝国主義は、混然一体で進行していた。 インドの綿産業の工業化というニーズが結びついたもの。 ?戦時中からの出口戦略(WW2) ルーズベルトは、戦争よりも、終戦後の出口戦略に注力したようだ。 一方、日本政府は、行き当たりばったり、終戦後のビジョン描こうともしていない。 (満州国傀儡政権擁立の裏工作など、関東軍独走で国際孤立しか招かない) ?20世紀後半の日本は、世界で類を見ないほど、平和で豊かで幸福だった。 『終戦→高度成長→オイルショック→バブル経済』 あくまで歴史的、相対的な総括だが、21世紀も継続できるかは不明。 ?幸福の配当 冷戦終結で軍事関連ストックが民間に還元されること。 (悲しいような、優しいワード) ex.インターネット、GPS 最近、軍事関連ストックが蓄積していないかな(軍事ロボット)
Posted by
五千年史の後半は15世紀から始まる。ユーラシアの文明は草原の騎馬民族の脅威から解放され始めるのだが、そうして生まれた余裕をどう使うかで、文明の消長が決まってくる。近代の始期に中国とインドは圧倒的なGDPシェアを誇っていたが、工業化と植民地支配の果実をいち早く得たのは欧州だった。広...
五千年史の後半は15世紀から始まる。ユーラシアの文明は草原の騎馬民族の脅威から解放され始めるのだが、そうして生まれた余裕をどう使うかで、文明の消長が決まってくる。近代の始期に中国とインドは圧倒的なGDPシェアを誇っていたが、工業化と植民地支配の果実をいち早く得たのは欧州だった。広い国土を中央集権的な王朝が支配する中国と、複数の国に分かれて競争を続ける欧州。競争には軍事力だけでなく経済力の側面もあり、商業利権を巡る争いがいつの間にか砂糖、茶、綿といった世界的な産業システムに結びつき、軍事力と経済力が正のフィードバックを繰り返しながら欧州はアジアを支配する。特にイギリスは欧州諸国の王位継承戦争への介入を通じて植民地利権の確保に腐心し、インド、マラッカ、ジブラルタルと要衝を押さえていく。 筆者はアジアのリーダーの中では18世紀の清朝乾隆帝とムガール帝国アウラングゼーブ帝に批判的だが、彼らが時間を無駄にしたことが欧亜逆転の直接のきっかけになったことは間違いない。 この本は20世紀以降の歴史も語り続けるが、どちらかと言えば淡々とした言及に終始している。本の眼目がパワーシフトの解明にあるのであれば、欧州からアメリカ、そしてアジアへと続くパワーシフトについてももう少し丁寧に扱う余地があった。欧州型の分立競争モデルが両大戦期に臨界点に達した後、超大国支配と多極化の時代がやってくるのだけど、近い歴史であればあるほど、単一の要因に帰してパワーシフトを語るのは難しいということなのだろう。
Posted by