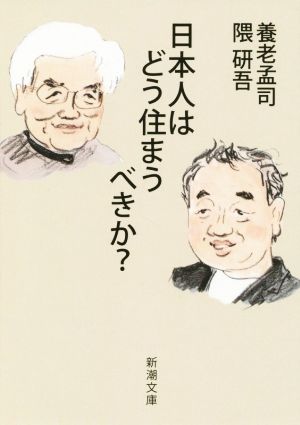日本人はどう住まうべきか? の商品レビュー
養老さんは、物知りだなぁと思う。が、勘違いもありそうなので騙されない様にしたい。良く、原理主義に陥らないためにってテーマが出るが、全ては諸行無常と意識し、意固地にならない様に常に新しい知識を入れるのが大事だと思う。
Posted by
栄光の先輩後輩の2人による対談。 震災を受け、これまでの反省をしつつ、これからよ日本人はどう住まえばいいか、というのが全体のテーマ。 全般的に批判的すぎる感じも受けるが、ところどころ勉強になる視点や共感できる考え方が散りばめられており面白く読めた。 ・「場当たり的日本」とサラリ...
栄光の先輩後輩の2人による対談。 震災を受け、これまでの反省をしつつ、これからよ日本人はどう住まえばいいか、というのが全体のテーマ。 全般的に批判的すぎる感じも受けるが、ところどころ勉強になる視点や共感できる考え方が散りばめられており面白く読めた。 ・「場当たり的日本」とサラリーマン批判 今の日本は場当たり的。江戸時代は「家制度」があったから、もっと長い時間軸でものごとを薦められていた。ヨーロッパでは貴族がそれを担っていた。今の日本にはそれがない。みなサラリーマンなので、年度の予算にとらわれ長期的視点に立てない。 ・コルビジェのサヴォア邸批判 サヴォア邸のピロティは、緑豊かな周りに調和してないいまいちなもの。だが、建物だけで完結するので、だからこそどんな場所でも一応作れる。ある種のユニバーサルデザインであり、世界でヒットした。マーケティングとしては素晴らしい。(個人的には鎌倉の近代美術館はピロティのおかげで建物の存在が軽やかになり、周りの蓮池ともうまく調和していると思うのだが、、) ・超高層ビル批判とスラムのおもしろさ インドのムンバイで大企業が高層ビルを作ろうとすると労働者が必要になるが、インドではその労働者に企業が住居を提供しなければならない。なのでほったて小屋を建て、そこにインド人は家族ぐるみでやってくる。すると周りに物を売るお店ができ、そうして5年くらいかけて建ててると、出来上がるころにはビルのまわりがスラム化している。だが、往々にして周りにできた自然発生的なコミュニティの方が面白い。大手デベが作る超高層ビルは均一的でつまらないし、テナントも数年で入れ替わることが前提のお店ばかり。
Posted by
「建築家、走る」と主張は変わってない。引用されるエピソードは半分以上同じなので、同じ本を2回読んだかのようである笑 以下、自分宛てのコメントに。(入力間違い)
Posted by
大局的にものを見る二人の対談、すごく面白く読めた。 こんな風に、俯瞰して物事を見たり判断できる人になりたいと思った。
Posted by
だましだましの現場主義とユートピア主義が融け合うように間をぬうことで日本人固有の住み方が生まれるかも。建築に興味がある人以外にもおすすめ。
Posted by
養老さんと漫画家の宮崎駿さんとの対談を収録した『虫眼とアニ眼』と主張が非常によく似ています。 対談の内容には賛同すべき点が多くあって、頷きながら読み進めました。 理想論が中心で、「どうなっても知らないけど」みないな投げやりな発言も散見され、実際に何をどうする“べきか?”という表...
養老さんと漫画家の宮崎駿さんとの対談を収録した『虫眼とアニ眼』と主張が非常によく似ています。 対談の内容には賛同すべき点が多くあって、頷きながら読み進めました。 理想論が中心で、「どうなっても知らないけど」みないな投げやりな発言も散見され、実際に何をどうする“べきか?”という表題の問いに対する解はそれほど明確には提示されていません。しかし、こんな指摘に対する著者のお二人の答えは「統一的な答えはない」ということでしょう。 全体の論旨としては大いに賛成できます。 しかし、お二人がすでに60歳を超えており、ところどころに「戦後の日本人はそうやってきた」というような表現もあって、懐古主義的に聞こえてしまう点が残念です。もっと若い論者からこういう指摘がなされればいいと思いました。 批判の対象は次のとおりです。 原子力発電所、建設業界、文系脳、コンクリート、ル・コルビュジエ、マンション、高層建築物、石油、アメリカ、サラリーマン、一律、法制、私有、コンピュータ・・・。 読み進めるごとに、なんだかもう現代が獲得してきたあらゆるものを否定しているような印象をもってしまい、そのあたりも惜しいと思います。「だましだまし」という態度を是として主張されているので、もう少し今のこの国の有り様を下敷きにした、実現可能性の高い提案が聞かれたらよかったと思います。 本書で批判に晒されている文系のサラリーマン建築屋の張本人としては、これに反論するつもりは全然なくて、こういう発想を現実化できる知識と知恵を結集して、なおかつ会社組織の利益至上主義とヒエラルキーの及ばないところでなにがしかの実践ができれば素晴らしい、と妄想するのでした。 ――妄想だけではダメすよ。実際にやってみなくては。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ビルの1階に花屋があると、街路の景色になる。そのために、花屋が入居するならば1階の家賃を安くするというのが外国であるらしい。いいアイデアだと思う。
Posted by
2011年秋「日経ビジネス オンライン」掲載の対談。 キーワードは「現場主義」「だましだまし」「ともだおれ」、現場がなく責任を取らないサラリーマン化を憂え、夢のマイホームなどのこだわりを捨てて、一箇所に住まうことからもっと自由になったほうがいいという方向の対談。家や建築のことにと...
2011年秋「日経ビジネス オンライン」掲載の対談。 キーワードは「現場主義」「だましだまし」「ともだおれ」、現場がなく責任を取らないサラリーマン化を憂え、夢のマイホームなどのこだわりを捨てて、一箇所に住まうことからもっと自由になったほうがいいという方向の対談。家や建築のことにとどまらず、災害や高齢化、地域格差などのさまざまな社会問題を既成の常識にとらわれずに論じている。 細かい部分では眉唾ものやつっこみどころもあるけれど、大きな流れとしては共感できおもしろかった。でも、こういう考えの人は少数派なんだよなぁ… 本体は対談だけに浅いところを行ったり来たりの感もあるが、養老さんのまえがき、隈さんのあとがき、それに山極寿一さんの解説がよくまとまっている。
Posted by
久しぶりに書店で買ってすぐに読了。 読んでる間、ため息ばかり。 どう住まうべきか、よりよく住まうために 住人は何ができるか。。
Posted by
住まいや土地を題材に,日本人の文明観を明文化する.本来,住むべき場所を探す際に見るべきは,嘘をつかないその土地であり,上物という建築物は人と人との信頼関係でしか推し量ることができない,というのは至言である.そのような戦略になった理由も理路整然と言及されている.薄いので直ぐ読めると...
住まいや土地を題材に,日本人の文明観を明文化する.本来,住むべき場所を探す際に見るべきは,嘘をつかないその土地であり,上物という建築物は人と人との信頼関係でしか推し量ることができない,というのは至言である.そのような戦略になった理由も理路整然と言及されている.薄いので直ぐ読めると思ったが,重い良書.
Posted by
- 1
- 2