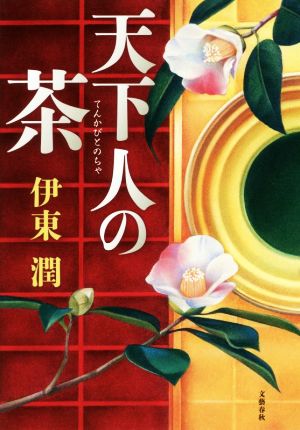天下人の茶 の商品レビュー
「へうげもの」を読んでいるなら「天下人の茶」を読みましょう。 「天下人の茶」を読んだなら「へうげもの」と読みましょう。 どちらも、己の野心そのまま生き様になり、野心に振り回されて燃え尽き、苦悩と愉悦と達観に塗れた人生を送った愛すべきスキモノたちの物語です。 いい。 「天下人の...
「へうげもの」を読んでいるなら「天下人の茶」を読みましょう。 「天下人の茶」を読んだなら「へうげもの」と読みましょう。 どちらも、己の野心そのまま生き様になり、野心に振り回されて燃え尽き、苦悩と愉悦と達観に塗れた人生を送った愛すべきスキモノたちの物語です。 いい。 「天下人の茶」の方が、黒いですけどね。野心が迸った先にある色味が。それを前提に利休好みを鑑みると、彼の持っていた業の深さを思いしれます。 『ひつみて候』の小堀遠州がいい。ぐつぐつと滾っているものを隠して、それが溢れ出す様がいい。いいねぇ。
Posted by
面白く読み通せた。へうげものと同じように利休が本能寺を画策したということになってるが、さらに秀吉までも傀儡としていたという設定。それを牧村兵部、古田織部、瀬田掃部、細川忠興などの視点から見ている。実は秀吉には数奇者の才があり、利休は黄金茶室も侘数寄の極みと気付いて他の弟子と違うよ...
面白く読み通せた。へうげものと同じように利休が本能寺を画策したということになってるが、さらに秀吉までも傀儡としていたという設定。それを牧村兵部、古田織部、瀬田掃部、細川忠興などの視点から見ている。実は秀吉には数奇者の才があり、利休は黄金茶室も侘数寄の極みと気付いて他の弟子と違うように教えていたといった見方も面白かった。
Posted by
茶がどこまで歴史に絡んでたのか気になる。 信長の褒美を土地から茶道具にするという発想が凄い! それぞれの視点で描き、最後の章にうまく繋がってる。
Posted by
http://denki.txt-nifty.com/mitamond/2016/03/post-ae62.html
Posted by
個人的に、安土桃山時代にはこれまであんまり興味を持ったことがなくて、ここに登場する、牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、細川忠興といった人物たちにも馴染みがなかった。 そもそも、千利休という人物についても然程のイメージを持ったことがない。 そういえば、自分が学生だった頃、利休ブームみ...
個人的に、安土桃山時代にはこれまであんまり興味を持ったことがなくて、ここに登場する、牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、細川忠興といった人物たちにも馴染みがなかった。 そもそも、千利休という人物についても然程のイメージを持ったことがない。 そういえば、自分が学生だった頃、利休ブームみたいな時期があったな。 映画が幾つか作られたりして。 あれは没後400年とかだったのだろうか。 そういう身からすると、本作は新鮮だった。 利休のミステリアスな存在感、茶の湯という文化に時の権力者たちが狂わされていく様が、よく表現されているように思う。 この時代に馴染みのある人から見ると、ややステロタイプなのかもしれないが。
Posted by
やはり伊東潤さんは、上手い。 利休の弟子達に利休を語らせることで、徐々に利休が浮き彫りにされていく。まずはこの描き方が良い。 また、利休が「茶の湯で世に静謐をもたらす」という考えによって、人々を動かし、時には消していく。秀吉に近付き、他の武将たちを彼に味方させ、そして、政敵らを消...
やはり伊東潤さんは、上手い。 利休の弟子達に利休を語らせることで、徐々に利休が浮き彫りにされていく。まずはこの描き方が良い。 また、利休が「茶の湯で世に静謐をもたらす」という考えによって、人々を動かし、時には消していく。秀吉に近付き、他の武将たちを彼に味方させ、そして、政敵らを消していく。本能寺の変もメインの出来事ではなく、利休にとっては必要な出来事として描かれる。その考えを手書き出して行く手法も上手い。 もちろん、作品の各所に散りばめられた伏線がラストに向けて丁寧にしかも着実に回収されていく行く手法も、まさに圧巻である。 今年の最後に、また良い本に出会えました。
Posted by
第155回「直木賞」候補作品。 茶道モノの小説といえば「利休にたずねよ」や、少し古くなりますが「本覚坊遺文」ですね。マンガだと「へうげもの」などでしょうか?いろんな主人公の視点から「茶道」を捉えているので、それぞれに面白みがあります。 本著も、同じ時代を武将や商人など、いろん...
第155回「直木賞」候補作品。 茶道モノの小説といえば「利休にたずねよ」や、少し古くなりますが「本覚坊遺文」ですね。マンガだと「へうげもの」などでしょうか?いろんな主人公の視点から「茶道」を捉えているので、それぞれに面白みがあります。 本著も、同じ時代を武将や商人など、いろんな視点で捉えて章立てされているのが特徴的ですが、それぞれが細切れになってしまっている感じがして全体感を捉えるのがすこし難しい公正だった点が残念だなあ〜と思いました。 でも、こうやって「茶道」を題材にする作品が出てくることは、とてもいいことですね!
Posted by
豊臣によって自害に追い込まれた利休。 話が進むにつれて利休と豊臣との隠された仲が明らかになっていく。 侘び茶を大成させ、美の頂点を極めた利休の裏の顔が怖かった。 これは、どこまでフィクションなのだろう。
Posted by
連作短編6編 秀吉と利休の間に何があったかを,いろんな角度,人物,出来事から推察する.お茶もうっかり飲んでられない.この本によると,小堀遠州も案外怖い人物だ.利休の切腹に新たなる視点を見せてくれたが,,本当のところはどうなんだろう?
Posted by
2016年、第155回直木賞候補作ということで、読んでみました~初読みの作家さん。 なかなかの迫力です。 茶の湯がなぜ、戦国時代の終わりに、あれほど持てはやされたのか? ふと一抹の疑問が浮かぶことがあります。 織田信長が大名を支配するための新たな方策の一つとして、意図的に盛り立...
2016年、第155回直木賞候補作ということで、読んでみました~初読みの作家さん。 なかなかの迫力です。 茶の湯がなぜ、戦国時代の終わりに、あれほど持てはやされたのか? ふと一抹の疑問が浮かぶことがあります。 織田信長が大名を支配するための新たな方策の一つとして、意図的に盛り立てたという。 戦って奪い取った土地を恩賞として分け与えるのには、限りがあったからだと。 秀吉も当初は千利休を重用しますが、しだいに葛藤が生じます。 侘び寂びを追及した利休だけれど、秀吉の派手好みは認めていたという解釈をとっています。 それは人真似でない本物の個性だから、のよう。 利休は堺の商人であり、武家と深く交わり、茶の湯という芸術を追い求めた、多面性のある人物。 多くの武家に気持ちのよりどころと安らぎを与えもした。 弟子達にとっては、難解な発言をする厳しい師匠。 牧村兵部、瀬田掃部、古田織部、細川忠興。 それぞれのやり方で、違う道を開いていく弟子達も、面白い。 利休がかなり意図的に政治を操作したというストーリー。 え、そこまで?という気もしますが~ 殺すか殺されるかという危機もある中を、何とかして生き残っていく戦国時代。 皆が将来を真剣に見据え、天下のあるべき姿を思い描いていた時代だからこそ、そういうこともあり得たかも知れない! ぞくっとする面白さがありました☆
Posted by