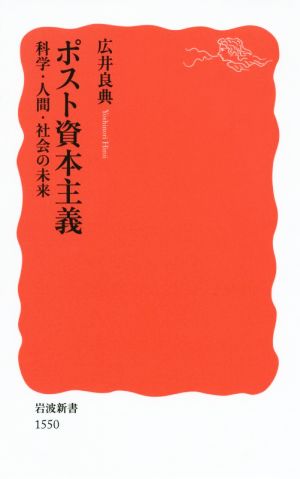ポスト資本主義 の商品レビュー
筆者自身が科学哲学専攻であることもあり、経済書というよりは思想書。 市場経済を通して限りない拡大と成長を志向する資本主義が、生産量に対する需要の限界(物があふれる社会)から定常状態にいたりつつある。なんらかの手段で限界を突破して資本主義が続く可能性もあるが、安定した定常状態を目...
筆者自身が科学哲学専攻であることもあり、経済書というよりは思想書。 市場経済を通して限りない拡大と成長を志向する資本主義が、生産量に対する需要の限界(物があふれる社会)から定常状態にいたりつつある。なんらかの手段で限界を突破して資本主義が続く可能性もあるが、安定した定常状態を目指すことも可能であり、そちらのほうが好ましいのではないか。 資本主義が進み生産性が上がりきった状態とはごく少ない労働で必要なものを生産できる状態であり、それは同時に大量失業を生む。ごく少数の人間にしか報酬が払われず、大量に生産はされど一向に消費はされない状況。この状況を打開するため、生産性のものさしを変えて、労働集約的で環境負荷の少ない産業をより評価していくべきである。社会保障と再分配の仕組みを見直しローカルなコミュニティを重視していく必要がある。 というような内容(自然の内発性の部分など結構難解な部分もあり抜けや曲解があると思いますが…)。骨太で、哲学の訓練を受けてないと十分に理解するのが難しいように思いました。 脱成長思想の中ではわりと楽観的な立場で、危機を煽るような表現も控えめで、こういう理屈からこっちの案のほうがいいんじゃない?程度の提案が多く、学者然とした態度を感じる。筆者の言う通り物質的な豊かさや富の蓄積でなく、(全員が最低限の物質的豊かさを得ている前提で)精神的な豊かさを重視し追求していく社会となっていくといいなと私も思います。
Posted by
資本主義の成り立ち、どのようなものかがわかった。これからの視点も論点として述べられており、決して、資本主義に対抗するものではない
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2015年副題として科学・人間・社会の未来。 目次として はじめにー「ポスト・ヒューマン」と電脳資本主義 序章 人類史における拡大・成長と定常化ーポスト資本主義をめぐる座標軸 第1部資本主義の進化 第1章資本主義の意味 第2章科学と資本主義 第3章電脳資本主義と超資本主義vsポスト資本主義 第Ⅱ部科学・情報・生命 第4章社会的関係性 第5章自然の内発性 第Ⅲ部緑の福祉国家/持続可能な福祉社会 第6章資本主義の現在 第7章資本主義の社会化または「ソーシャルな資本主義 第8章コミュニティ経済 終章 地球倫理の可能性―ポスト資本主義における科学と価値
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書は、現在の資本主義体制が、資源の枯渇や格差の問題などが現れている点を含めて、人類の幸福や精神的充足をもたらしているのかという現状を踏まえ、資本主義とパラレルに発展してきた科学技術が人間にとって何をもたらし、それの資本主義との関係性を探っていくものである。 . 資本主義とは何かについてまず考察しており、著者は「市場経済+限りない拡大・成長」を志向するシステム、と定義する。これは利潤の量的拡大による全体のパイの拡大が社会の利益につながるという議論が前提としてある。これを達成するために、個人が社会から独立した存在であることと、人間は自然を支配できることを思想的な出発点としている。 . このような思想を前提とした、資本主義と科学技術の発展を歴史的に概観していくと、「拡大・成長」の時代と「定常化」の時代があることがわかる。現在は第3の「定常化」の時代であり、この時代をポスト資本主義社会としている。 . この社会におけるビジョンとは、これまで考えられてきた思想(=機械的自然観・個人の独立性)が持つ外在的な考え方から、内在的な思想(=個人・コミュニティ・自然を相互依存的な観点で考えること)への変化を求めている。その上で、著者は「緑の福祉国家」または「持続可能な福祉社会」を提案している。これは、格差などの構造的な問題に対して①過剰の抑制 ②再分配の強化 ③コミュニティ経済、の方向性を持って対応する新たな社会構想として、提案し、結論としている。
Posted by
科学主義に落胆し、高度成長時代の活気を経験しながらもバブル崩壊で自信を喪失し、新自由主義的資本主義にもついていけず、グローバル都市で暮らし仕事する人が、田舎(ローカル)ののんびりした互酬互助的で自然と共存するローカル・コミュニティにノスタルジーを見出したようなお話。コミュニティの...
科学主義に落胆し、高度成長時代の活気を経験しながらもバブル崩壊で自信を喪失し、新自由主義的資本主義にもついていけず、グローバル都市で暮らし仕事する人が、田舎(ローカル)ののんびりした互酬互助的で自然と共存するローカル・コミュニティにノスタルジーを見出したようなお話。コミュニティの維持も定住者でできず、コミュニティ機能も弱まり、自立ばかりを要求され、非正規雇用で凌ぐローカルの現実はどうするんだ?
Posted by
→Xマインド:環境倫理、21レッスンズ →keynote ◯過剰による貧困(楽園のパラドックス):生産性上昇による失業ー増 ◯時間再配分 ◯時間政策inJapan:祝日増加←日本の空気 ◯市場経済と「時間」 ◯長期視座=民俗学×近代科学 ◯消費〈物質→エネルギー→情報→時間〉 ...
→Xマインド:環境倫理、21レッスンズ →keynote ◯過剰による貧困(楽園のパラドックス):生産性上昇による失業ー増 ◯時間再配分 ◯時間政策inJapan:祝日増加←日本の空気 ◯市場経済と「時間」 ◯長期視座=民俗学×近代科学 ◯消費〈物質→エネルギー→情報→時間〉 ◯未来の収奪・過去の収奪
Posted by
消費の対象は、物質からエネルギー、情報へと変化してきて、ポスト資本主義では時間になります。 それは例えばカフェなどで、あるいは自然の中で、ゆっくりとした時間を過ごす事自体への欲求や歓びだそうです
Posted by
ドラッカーの専門であるマネジメント分野よりも経済学に近い2016年の今であればコトラーのマーケティング3.0などを読んだ方がリアルに感じられる気がする。何にせよテーマが広すぎるので、ここから「一番重要」と思ったことを記載するのは非常に難しい。そこで「一番重要」ではなく「一番興味あ...
ドラッカーの専門であるマネジメント分野よりも経済学に近い2016年の今であればコトラーのマーケティング3.0などを読んだ方がリアルに感じられる気がする。何にせよテーマが広すぎるので、ここから「一番重要」と思ったことを記載するのは非常に難しい。そこで「一番重要」ではなく「一番興味ある」ことを記載する。それは「教育」だ。 超高齢化社会を迎える日本において重要なテーマはいくつかある。定年の延長。労働市場の柔軟性。それらを乗り越えるために成人後の教育の重要性が謳われている。「人は、その人生のいかなる段階にいようとも、正規の教育を受け、知識労働への資格を得ることが出来なければならない(11章より抜粋)」この点で最も進んでいるがのアメリカのようだが、それでも若いうちに基礎資格を取得していないものを知識労働に受け入れることに躊躇している。日本でも近年は定年後に資格を取得する人は増えている。事実、中小企業診断試験では定年を迎えたであろう人々が多数受験している。だが勉強には高い講義費用を払わなければ独学するしかなく、ハードルは高い。少子化が進む中、学校というシステムを改めて見直す必要性があるように思えた。 また社会セクターについても興味深い。家族だけではコミュニティとして不十分。また職場コミュニティも労働市場の柔軟性が進むと消えていくだろう。膨張する巨大都市に対して非営利組織などのコミュニティの重要性が語られていた。余談だが、先日のTVで経済学者ミルトン・フリードマンの孫(彼はGoogle技術者)が多様な社会システム、政治体制、法制度を持つ海上コミュニティの設立を進めていることを知った。今後はそういった様々なコミュニティがたちあがるのだろうか
Posted by
人間の長年にわたる営みを資本主義、科学、宗教、などなど、色んな角度で分析しながら、人間社会が目指す望ましい姿を提案している。 序章 人類史における拡大・成長と定常化 —ポスト資本主義をめぐる座標軸 第1部 資本主義の進化 第1章 資本主義の意味 第2章 科学と資本主義 ...
人間の長年にわたる営みを資本主義、科学、宗教、などなど、色んな角度で分析しながら、人間社会が目指す望ましい姿を提案している。 序章 人類史における拡大・成長と定常化 —ポスト資本主義をめぐる座標軸 第1部 資本主義の進化 第1章 資本主義の意味 第2章 科学と資本主義 第3章 電脳資本主義と超(スーパー)資本主義 vsポスト資本主義 第Ⅱ部 科学・情報・生命 第4章 社会的関係性 第5章 自然の内発性 第Ⅲ部 緑の福祉国家/持続可能な福祉社会 第6章 資本主義の現在 第7章 資本主義の社会化またはソーシャルな 資本主義 第8章 コミュニティ経済 終章 地球倫理の可能性 —ポスト資本主義における科学と価値 人類の歴史、採集狩猟社会から農耕社会、そして産業革命以来の高度情報化、人工頭脳・・・ 瞬時に情報が地球を駆け巡る時代だからこそ、人間本来の顔と顔の見えるコミュニティの原点に回帰する。 そこから、ガラガラポンでどういう価値観・思想を打ち立てれるのか、今後の人類に課せられたすごい課題です。
Posted by
評するに難しい本。資本主義が拡大・成長するという動因から、定常化へ舵を取るべき時に来た。それがポスト資本主義だという。ただ、波長が合わなかったな。 このタイトルをつけるに当たって、ドラッカーの『ポスト資本主義社会』という書籍の存在を知らなかったという。それはどうかなと思う。
Posted by
- 1
- 2