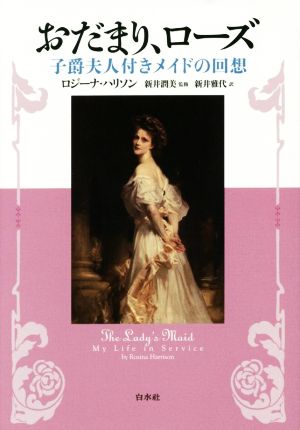おだまり、ローズ の商品レビュー
イギリスの貴族の家で働いたメイドの回顧録。 …というつもりで読み始めたが、仕えたのはイギリス初の女性の下院議員であるナンシー・アスター(レディ・アスター)で、そのことも大きなウエートを占めている。 メイドの仕事を垣間見るというだけでなく、レディ・アスターの独特のキャラクターを描く...
イギリスの貴族の家で働いたメイドの回顧録。 …というつもりで読み始めたが、仕えたのはイギリス初の女性の下院議員であるナンシー・アスター(レディ・アスター)で、そのことも大きなウエートを占めている。 メイドの仕事を垣間見るというだけでなく、レディ・アスターの独特のキャラクターを描くという側面もある。 著者は1899年生まれで、1918年からキャリアをスタートし、1928年からアスター家で働き始め、1964年にレディ・アスターが亡くなった後の1975年に本書を書いた。 ドラマ「ダウントンアビー」の時代設定が1912年から1925年というので、かなり近い。 そもそもメイドは労働者階級に属するため、本を書くような人は少ないのだという。よって、使用人の目線で貴族たちを描いたという意味で本書は希少なのだという。 レディ・アスターはアメリカ生まれであり、伝統的な淑女像とは異なる人物。歯に衣着せぬ発言で、筆者も最初は凹まされたようだが、ある時から言い返すようにしたらしっくりいったようだ(そうでなければ35年も仕えられない)。言ってみればトラッシュトークで、それを根に持たれないということだ。淑女像とは全然違う。 それだから初の下院議員が務まったのかもしれないし、選挙区(プリマス)がドイツ軍による空襲被害を受けたときにエネルギッシュに動けたのもそういうキャラクターに似つかわしい。 著者は、自身とレディ・アスターだけでなく屋敷内の人々も描いている。 なかでも特に魅力的なのが執事(家令)のエドウィン・リーだ。 「お屋敷を訪れる方々にはいつもリーまたはミスター・リーと呼ばれていて、王室の方々にさえその名を覚えられていました。当時はほかにも偉大な執事が何人もいましたが、その最高峰はリー氏だというのが、おそらくほぼ全員の一致した見方でしょう。」 随所にリー氏が登場したり逸話を語ってくれるのだが、みんなの空想上の「執事」を実際に体現する人物がいたのだなあ、という感想になる。 読後に知ったのだが、カズオ・イシグロ『日の名残り』の主人公のモデルがこのリー氏らしい。 とすると、『日の名残り』は本書より先に読んだ方がよい気がする(未読)。
Posted by
イギリスのお屋敷もの、大好物です。 トップに君臨するのはもちろん カズオ・イシグロの『日の名残り』。 こちらも楽しませて貰いました。 しかしこの分野では 日本ではいつも同じ方が 著者だったり監修だったり解説されてますよね。 人材不足なのかなぁ…
Posted by
20世紀の英国でメイドを勤めた女性の回顧録。彼女が仕えたレディアスターは、英国で2人目に庶民院議員になった女性。気まぐれで型破り。でも、人との関係を大事にしていて、それは使用人に対しても言えること。この本の中では、子爵夫人だけでなく、子爵、執事、その他の使用人がそれぞれの役割に従...
20世紀の英国でメイドを勤めた女性の回顧録。彼女が仕えたレディアスターは、英国で2人目に庶民院議員になった女性。気まぐれで型破り。でも、人との関係を大事にしていて、それは使用人に対しても言えること。この本の中では、子爵夫人だけでなく、子爵、執事、その他の使用人がそれぞれの役割に従って家を運営していく一つの部族として描かれている。個性的で面白い面々なのだが、なんと言っても子爵夫人と著者のやりとりが面白い。著者は1964年にレディアスターが死ぬまで侍女をを勤めたのだが、メイドという職業がそんなに最近まで存在したことにびっくりした。彼女が勤めている間に、二つの世界大戦があり、政治家としての活動もある中で、王家や他の貴族、著名人、外国(特にレディアスターの出身地のアメリカ)からの来客をもてなす忙しい生活をしていて、それを円滑に進める使用人たちの働きが書かれていて、貴族社会を覗き見る面白さもあった。
Posted by
19世紀のイギリス貴族の事情が事細かに描かれている。ローズと雇い主の丁々発止のやり取りが面白い。仕事に向き合う姿勢もいい。
Posted by
タイトルに目を惹かれて手に取った。読み始めてみれば、『ダウントン・アビー』そのままの世界が活字になって展開されてくる。というか、ドラマがこの本を参考にしているのでは?と思えてくる。個性的で一筋縄ではいかない貴婦人との丁々発止のやり取りは、ドラマ以上の面白さ。 時代は大戦間から戦後...
タイトルに目を惹かれて手に取った。読み始めてみれば、『ダウントン・アビー』そのままの世界が活字になって展開されてくる。というか、ドラマがこの本を参考にしているのでは?と思えてくる。個性的で一筋縄ではいかない貴婦人との丁々発止のやり取りは、ドラマ以上の面白さ。 時代は大戦間から戦後までの長きにわたり、その間に出会う人たちも又錚々たる面々。T.E.ロレンスにバーナード・ショー。チャーチルにマハトマ・ガンジーとの出会いや、プロヒューモ事件の背景になったりと、イギリス現代史と切り離せない人物や事件が出てきて、誠に「事実は小説より奇なり」 「旅行がしてみたい」と言う作者の夢を叶えるためにとった手段が主人付きメイドになること。そのためにはフランス語と婦人服の仕立てを習い戦略的にキャリアを積んだ彼女の生き方は見習うべき点が多い。そして職についた後も、敬意を持って仕事を評価してくれる場所で働くと言う哲学は見事。 折々の行事や仕事仲間、自身の政治感、宗教観まで話題は幅広く、馴染みのない世界への興味が尽きない。英国流(?)生真面目さと皮肉がないまぜになった文章は、翻訳のおかげで存分に楽しめる。
Posted by
過去に読んで面白かった記憶があるので再読。前回の感想も色々書いてあったが(メモなので非公開状態)、今回特に印章に残ったのは、この話、ダウントン・アビーより少し後、でもまあ同時代と考えて良い。 レディアスターもレディグランサム同様アメリカ人、しかし上品なレディグランサムと違って強烈...
過去に読んで面白かった記憶があるので再読。前回の感想も色々書いてあったが(メモなので非公開状態)、今回特に印章に残ったのは、この話、ダウントン・アビーより少し後、でもまあ同時代と考えて良い。 レディアスターもレディグランサム同様アメリカ人、しかし上品なレディグランサムと違って強烈な個性の持ち主、典型的な貴族夫人ではとうていありえない。 アラビアのロレンスとバイクで走り回った直後、ロレンスの事故死が伝えられた、という話は覚えていなかった。 で、アスターというとタイタニックで亡くなった富豪のことを思い出すのだが、読みながら調べてみたところ、ドイツ出身でアメリカで財を成したアスター一族は、更にイギリスに帰化して貴族に叙せられた家族、アメリカに残った家族に分かれ、タイタニックのジョン・ジェイコブ・アスター4世はアメリカ組、本書の子爵夫人の夫2代目子爵ウォルドーフ・アスターはイギリス移住組。父は初代子爵とジョン・ジェイコブ・アスター4世は従兄弟なのだとわかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
…いつだったか、リー氏が言っていました。「レディ・アスターは信心深いご婦人ではないね。いつだって永遠に見つかるはずのない導きの光を探している」と。とはいえ、クリスチャン・サイエンスは奥様のような方には好都合な宗教でした。絶対的な教義がなく、ご自分の欠点や行動を正当化するために、勝手に教えをねじ曲げることができたからです。 ――P.322 …どこかの男が戦争に勝ったのはロシアのおかげだとかなんとか叫びはじめると、今度はその男に噛みつきました。「ロシアがそんなにいいところなら、なんであっちにいかないんです? ちゃっかり自由の恩恵を受けておきながら自分の国をけなすあんたみたいな人には用はありませんよ」 ――P.333 手塚治虫のブラックジャックに『ある老婆の思い出』というエピソードがある。序盤は、それをひっきりなしに思い出させられながら読んでいた。 中盤から思うところがでてきはじめたが、ウィットに富んだただならぬ知性が生み出したこの著作に敬意を払い、明かさないことにする。 一点。当時のアメリカ南部にあって黒人の使用人がどう扱われていたかを主観で語る場面があるが、それによって主にアメリカ人による人種差別の根っこにあるものが理解できたような気がした。まさか、同じ人類であると認めていないとは思わなかった。
Posted by
イギリス初の女性庶民院議員ナンシー・アスターの使用人の回想録。使用人として身を立てながら、昇給がさほどないことに不満を抱いていた著者は、給料の高さに釣られて反感をもっていたアスター家に仕えることにした。当初は主人である夫人の怒りを買って意気消沈した彼女だったが、ある時自身の仕事が...
イギリス初の女性庶民院議員ナンシー・アスターの使用人の回想録。使用人として身を立てながら、昇給がさほどないことに不満を抱いていた著者は、給料の高さに釣られて反感をもっていたアスター家に仕えることにした。当初は主人である夫人の怒りを買って意気消沈した彼女だったが、ある時自身の仕事が全く文句のつけようのない水準のものであることを自覚し、「それ以降、わたしはやられたらやり返すようになったのです。最初は戦いだったのものは、しだいに角がとれてきて、ある種のゲームめいたものになりました。ゲームは三十五年にわたって続き、勝負は最後までつかずじまいでした。」ここから、主人の要望にはできるだけ答えつつも、おかしいと思うことには率直に意見を述べ、主人から「おだまり、ローズ」の定型句を頂戴しつつも、なおも舌戦を手を変え品を変え続けていく、世にも可笑しな主従関係が誕生したのだった。現在でも議論の種となるナンシーの政治的立場についてはさほど触れるところがないが、様々なエピソードを通じて夫人の人物像を面白おかしく描いている。
Posted by
ヴィクトリア朝の暮らしの資料として借りたつもりが、序盤のあたりで著者はヴィクトリア朝の様式を古くさいと評する時代の生まれだったと気付いたので資料にはならなかった。けれど職業婦人の自伝としてすごく面白い。 癖のある女主人の仕打ちに追い詰められて限界を迎えそうになった著者が、あると...
ヴィクトリア朝の暮らしの資料として借りたつもりが、序盤のあたりで著者はヴィクトリア朝の様式を古くさいと評する時代の生まれだったと気付いたので資料にはならなかった。けれど職業婦人の自伝としてすごく面白い。 癖のある女主人の仕打ちに追い詰められて限界を迎えそうになった著者が、あるときはっと開眼し主人に反論するようになってからの丁々発止のやりとりがなんとも小気味よい。女主人とお付きのメイド、身分差こそあれ頼りになる相棒みたいな信頼関係を築いていき、時にみなぎるパワーに圧倒され時に弱る姿を深い愛情をもって家族のように支え――という35年の日々。 正直アスター夫人はとんでもないモラハラ上司だと思うし、ほとんど休みをとれず睡眠すらも削って仕えるその働きぶりはとても真似できるものではないけれど、ただただすごいの一言。自分の仕事ぶりに自信を持っている著者の語り口調もなんとも頼もしかった。
Posted by
http://honz.jp/articles/-/40792 名古屋市図書館に予約をかけた。なんと93人待ち(@_@) 2015/3/6
Posted by