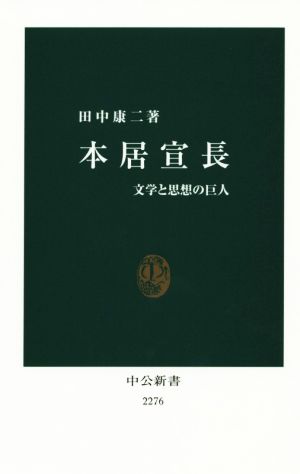本居宣長 の商品レビュー
内容(「BOOK」データベースより) 漢意を排斥して大和魂を追究し、「物のあはれを知る」説を唱えたことで知られる、江戸中期の国学者・本居宣長。伊勢松坂に生まれ、京都で医学を修めた後、賀茂真淵と運命的な出会いを果たす。以来、学問研究に身を捧げ、三十有余年の歳月を費やし『古事記伝』...
内容(「BOOK」データベースより) 漢意を排斥して大和魂を追究し、「物のあはれを知る」説を唱えたことで知られる、江戸中期の国学者・本居宣長。伊勢松坂に生まれ、京都で医学を修めた後、賀茂真淵と運命的な出会いを果たす。以来、学問研究に身を捧げ、三十有余年の歳月を費やし『古事記伝』を著した。この国学の大成者とは何者だったのか。七十年におよぶ生涯を丹念にたどりつつ、文学と思想の両分野に屹立する宣長学の全体像を描き出す。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 田中康二 1965年大阪市生まれ。94年神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)(神戸大学)。富士フェニックス短期大学助教授、神戸大学文学部助教授を経て、神戸大学大学院人文学研究科教授。日本近世文学。著書『村田春海の研究』(汲古書院、2000、日本古典文学会賞)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 目次 第1章 国学の脚本 第2章 学問の出発 第3章 人生の転機 第4章 自省の歳月 第5章 論争の季節 第6章 学問の完成 第7章 鈴屋の行方
Posted by
「はじめに」によると、本書は本居宣長の生涯をたどりながら、その学問研究を文学と思想の両面からとらえて、宣長の全体像をえがいたものです。 宣長の生涯と思想をコンパクトに解説しているバランスのよい入門書です。ただ、文学と思想の二つの側面に分裂してしまう宣長研究の現状に対する問題意識...
「はじめに」によると、本書は本居宣長の生涯をたどりながら、その学問研究を文学と思想の両面からとらえて、宣長の全体像をえがいたものです。 宣長の生涯と思想をコンパクトに解説しているバランスのよい入門書です。ただ、文学と思想の二つの側面に分裂してしまう宣長研究の現状に対する問題意識にもとづいて書かれていることを鑑みるならば、もうすこし積極的に著者自身の解釈を押し出してもよかったのではないかという気がします。
Posted by
本居宣長の功績を古道学と歌学の両面から解説。その人生は数多くの著作の概説を時系列に沿って紹介することによって概観される。 賀茂真淵に本居宣長が古風歌を批判されたために開き直って後世風の和歌を送り付けたところ和歌に関して絶交状態になったり、天照大御神が太陽そのものとの説に対する望遠...
本居宣長の功績を古道学と歌学の両面から解説。その人生は数多くの著作の概説を時系列に沿って紹介することによって概観される。 賀茂真淵に本居宣長が古風歌を批判されたために開き直って後世風の和歌を送り付けたところ和歌に関して絶交状態になったり、天照大御神が太陽そのものとの説に対する望遠鏡で見れば炎の玉でしかないという批判に記紀の記述や皇国の絶対性で押し通すなどの、やり取りが面白い。
Posted by
まず黒船の来航のこれ程前に日本のアイデンティティーを基礎づける言説を展開できたことに驚く。 一方で本居宣長の思想や事績が現代にうまく位置づけられていないような不安を感じる。平安以前のテキストの読解と読み替えを徹底的に行った本居宣長と、ファナティックに日本の独自性を主張し外来思想を...
まず黒船の来航のこれ程前に日本のアイデンティティーを基礎づける言説を展開できたことに驚く。 一方で本居宣長の思想や事績が現代にうまく位置づけられていないような不安を感じる。平安以前のテキストの読解と読み替えを徹底的に行った本居宣長と、ファナティックに日本の独自性を主張し外来思想を排する本居宣長。前者は我々が教科書的に学習する「もののあわれ」説を確立しており、平安以前の感性に幻想的なイメージやロマンティシズムを与える。契沖のようにテキストに忠実なアプローチをする先達がいたとはいえ、おそらく当時の儒教思想や仏教思想の手垢にまみれた源氏物語や古事記や万葉集に新たな息吹を吹き込むのは容易ではなかった。一方で後者は50年後の開国に始まる尊王攘夷思想と親和性が高い。時代を下れば1930年代に盛んとなった超国家主義や皇国思想の基礎となっている。 いずれにせよ、現代に連なるこの国のかたちを創った偉大なる人物であることを理解した。日本人が抱く日本のイメージの大分を本居宣長に負っているのだから。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
国学の大家である本居宣長の生涯と思想を概説した書。宣長の生涯を追いながら、彼の説いた主張や学説がどのようなものであったのかを解説する。 本書の特徴は、本居宣長の生涯を10年スパンで区切り、それぞれにテーマを設定して記述している点である。例えば第2章「学問の出発」では20代の国学・歌学との出会いを、第3章「人生の転機」では30代のターニングポイント(師である賀茂真淵との出会い、「もののあはれを知る」説の提唱)を取り上げている。その為、宣長の学問の流れがよく把握できるようになっている。また本書は宣長学を「思想」(古道学)と「文学」(国語学・歌学)の両面から捉えており、その多角的な広がりを知ることが出来る。 宣長の「日本」意識が彼の肥大化した自意識でもあるという指摘は説明不足の感があったが、全体として本居宣長の思想体系を一望できると言えるだろう。個人的に興味深かったのは宣長が和歌において「古風後世風詠み分け主義」をとっていたという点である。彼が上代のみならずそれ以降の歌風にも親しんでいたこと、またその姿勢を巡り師である真淵と対立していたということは驚きであった。
Posted by
- 1