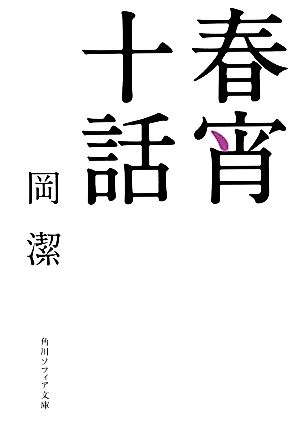春宵十話 の商品レビュー
メモ→https://x.com/nobushiromasaki/status/1832227532772372613
Posted by
「人間の建設」を読んで岡潔をもっと知りたくなって。明治は金で岡の時代を銅だと評し、同時代に警鐘を鳴らしている。そうなると果たして現代は。「人間の建設」で触れられた"世界の知力が低下してきている"の意味が分かる。金言に溢れている。
Posted by
人の中心は情緒である という書き出しで始まる 日本文化の特性がこの情緒を土台に組み立てられていることや、それがいかに美しい心情を生み出してきたかを様々な側面から論じている。 そして昨今の教育制度がいかにこの情緒的中心が失われ、それによって子供たちの創造性が阻害されてきたか警鐘を鳴...
人の中心は情緒である という書き出しで始まる 日本文化の特性がこの情緒を土台に組み立てられていることや、それがいかに美しい心情を生み出してきたかを様々な側面から論じている。 そして昨今の教育制度がいかにこの情緒的中心が失われ、それによって子供たちの創造性が阻害されてきたか警鐘を鳴らす 特に前半はあるべき日本人観のようなものが書かれていて名著。日本有数の数学者が書いている点も大変興味深い 情緒とは自然が人間に差し出してくれるもの を指していると解説にあった 人の人たる道をどんどん踏み込んでいけば宗教に到達せざるを得ない。 人の悲しみがわかること、そして自分もまた悲しいと感じることが宗教の本質ではなかろうか。キリストのいう愛も同じことを言ってると思う。 宗教の世界には自他の対立はなく、安息が得られる。しかしまた自他対立のない世界には向上もなく理想もない。だから自分は、純理性の世界だけでも、宗教的世界だけでもやっていけず、両方を兼ね備えた世界で生存し続けるであろう。 秩序を保っているのは法律ではない。それは道義心に他ならない。義務教育は、この道義的センスをつけることに尽きる。 1、2、3歳は母が愛と信とを教え、4、5、6は父が信と欲とを教えると良い。 漱石 自分の小説は少なくとも諸君の家庭に悪趣味を持ち込むことだけはしない 宇宙があるから地球があるのではなく、たった一つ奇跡の地球のために宇宙があるのかもしれない 真実美は、求めれば求めるほどわからなくなるものだと思う。わからないものだということを一般の人がわかれば、それだけでも文化水準は上がるに違いない。
Posted by
読み終え、まず思ったことは、岡先生が今生きておられたら国の行く末に絶望するほかないだろう、ということでした。 本書で明かされる岡先生の案じた日本の教育の乱れや西洋化一辺倒でアイデンティティを失いつつある日本人の在り方。数十年の時を経てその通りになっている部分もありつつ、加えて、...
読み終え、まず思ったことは、岡先生が今生きておられたら国の行く末に絶望するほかないだろう、ということでした。 本書で明かされる岡先生の案じた日本の教育の乱れや西洋化一辺倒でアイデンティティを失いつつある日本人の在り方。数十年の時を経てその通りになっている部分もありつつ、加えて、近年ではAIの普及も手伝って情緒を排したとて正解にたどり着ける選択肢が増え、成果を効率的に得るビジネスハックが隆盛していますが、岡先生はまさにこのような観念的な世相こそ危惧しておられたのではないでしょうか。 そういった国を憂う考えが展開される中、教育を扱ったトピックが非常に多く、岡先生は教育に日本再生の望みを託されていたのだと思います。特に「情緒」「情操」「道義」は本書でも重ねて使用される最も重要なキーワードだと思います。 教育への言及の中でも秀逸なのが、本書の中盤にある「道義教育の根本は悲しみがわかるということで、幼い子供には悲しみの感情が最も教えにくい。だから、小学校に入るまでは人が喜ぶからこうしなさいと教えられても、人が悲しむからこうしてはいけないとは教えられない。」(意訳)という考察でした。これは現代社会にも通ずる鋭い考察だと思います。 何事にも情緒が中心にあって学びや教育があるという岡先生のシンプルな考え方を以って現代を捉えた時、まさしく情操/道義教育をなしに悪趣味な刺激や動物的な教育に子ども達が晒された結果が、今現在の半狂乱の世相に繋がっているのではないか、と考えると裏付けがないのに妙に納得がいってしまうのは不思議なものです。 本書では一部、かなり偏った主観的な意見、データに基づかない意見も多々あり、現代の感覚では受け入れられない言葉遣いも見受けられます。しかし、それでも読者を立ち止まらせ考えさせてくれるような力を本書は大いに秘めていて、日本人とは何か知る上で今こそ読む価値のある書籍だと思いました。
Posted by
人の中心は情緒である。日本人とは何か?人間とは?この世界とは?を考えるためのヒントを沢山頂ける逸出した随筆。
Posted by
著者の考えを半分も理解出来なかった感じがする。文章などが悪いのではなく、自分の考えが及ばないところが多分にある。抽象的な部分は、繰り返し読んだり経験を重ねることで分かることがあるだろう。ただ、数学は脳みその切れ味みたいなのをフルに使う学問と思いきや、5感で感じる事、調和や美しさを...
著者の考えを半分も理解出来なかった感じがする。文章などが悪いのではなく、自分の考えが及ばないところが多分にある。抽象的な部分は、繰り返し読んだり経験を重ねることで分かることがあるだろう。ただ、数学は脳みその切れ味みたいなのをフルに使う学問と思いきや、5感で感じる事、調和や美しさを捉える感性:じょうちょが土台になっている事。百姓の例えは面白かった。
Posted by
ある先生のお薦めに従い読んでみたもの。ところどころ難しく感じる箇所があり、読みこなせた感じがしないのは、おそらく私の教養が足りないせいだろう。具体的な話は面白く読んだが、感覚的な話については表面的な言葉は理解できてもピンとこない箇所があった。数学と心の関係も、よく理解できない。で...
ある先生のお薦めに従い読んでみたもの。ところどころ難しく感じる箇所があり、読みこなせた感じがしないのは、おそらく私の教養が足りないせいだろう。具体的な話は面白く読んだが、感覚的な話については表面的な言葉は理解できてもピンとこない箇所があった。数学と心の関係も、よく理解できない。でも、上手く言葉にならないが、面白い人だなぁと思う。天才というのは凡人には理解しきれないのだと感じてしまうが、それでも知りたいという興味をそそられる。強烈なほどに自分がある人は面白い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
p131の義務教育秘話の天才教育はとても理に適っているなぁと共感できた。平等に教育の機会を与える日本の方法は悪くないけど、特別扱いする人が出るのは良くないというのが良くない考えで岡先生はそれを悪平等教育とおっしゃっていたけど、なるほど、その通りだなと思った。
Posted by
1901年生まれの著名な数学者・大学の先生のミニコラム集。岡さんの経験した青少年期は今と違って自然との触れあいが多かったのだろうなと感じられ、情緒の調和(安定)の大切さに気付かれたのかもしれないですね。スマホやパソコン漬けで、切れがちの人が増えてきている今こそ、学びが多いと感じま...
1901年生まれの著名な数学者・大学の先生のミニコラム集。岡さんの経験した青少年期は今と違って自然との触れあいが多かったのだろうなと感じられ、情緒の調和(安定)の大切さに気付かれたのかもしれないですね。スマホやパソコン漬けで、切れがちの人が増えてきている今こそ、学びが多いと感じました。数学・算数の上達論のヒントも面白かったです。
Posted by
「近頃のこの国のありさまがひどく心配」と憂う高名な数学者のエッセイ。「頭で学問をするものだという一般の観念に対して、私は本当は情緒が中心になっているといいたい。」と、学校教育のあり方について持論を述べる。 1960年前後の文章で古くさい箇所も多いが、その指摘は今の酷い学校教育の状...
「近頃のこの国のありさまがひどく心配」と憂う高名な数学者のエッセイ。「頭で学問をするものだという一般の観念に対して、私は本当は情緒が中心になっているといいたい。」と、学校教育のあり方について持論を述べる。 1960年前後の文章で古くさい箇所も多いが、その指摘は今の酷い学校教育の状況にも当てはまる内容で、こうしてみると教育問題って本当に根深いなと思わされる。著者が60年後の現在の状況を見たら何て言うのかな。 #岡潔 #春宵十話 #角川ソフィア文庫 #読書 #読書記録 #読書記録2022 #岡潔 #春宵十話 #角川ソフィア文庫 #読書 #読書記録 #読書記録2022
Posted by