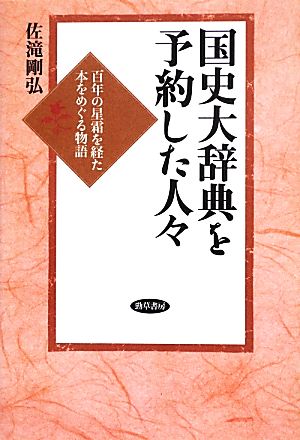国史大辞典を予約した人々 の商品レビュー
久々に胸がバクバクし、血流が駆け巡るような興奮とともに読んだ本。 タイトルだけ見るとあまり引かれない、地味なものですが、たまたま手にした幸運を噛み締めます。 これは、吉川弘文館の『国史大辞典』刊行一年前の1907年(明治40)に出版された「『国史大辞典』予約者芳名録」をもとにし...
久々に胸がバクバクし、血流が駆け巡るような興奮とともに読んだ本。 タイトルだけ見るとあまり引かれない、地味なものですが、たまたま手にした幸運を噛み締めます。 これは、吉川弘文館の『国史大辞典』刊行一年前の1907年(明治40)に出版された「『国史大辞典』予約者芳名録」をもとにしたもの。 頃は日露戦争(1904-1905)での勝利から韓国併合(1910)と向かう、日本の景気が良かった時期。 価格は20円。今の貨幣価値に換算すると、20万円程度の高級な辞書ながら、当時一万セット以上の予約があったそうです。 日本史の辞書を購入した、明治後期の知識欲に富んだ一万人近い人の名前が、そのリストには記されていました。 有名人の名前がまず紹介されます。 与謝野晶子の本名は「鳳(ほう)志(し)よう」というんだそうですね。 そちらのほうがずっとペンネームっぽい気がします。 与謝野晶子の兄は、東大教授の電気工学研究者という理系の人間でありながら、やはり注文をしていました。 その頃の有名人がどんな暮らしをしていたかの考察もされているのが興味深いところ。 高村光雲は、明治維新以降の廃仏毀釈運動の影響を受けて、当時仏師としての生活は苦しかっただろうと推察されています。 たしかに、廃仏毀釈以降、仏師の仕事は激減し、彼も時代の波に翻弄されただろうと気が付きます。 芥川龍之介は当時13歳で、牛乳販売者の実父が注文していました。 太宰治の実家もまた、注文しています。 折口信夫は10代ながら、自分で購入していました。初任給に近い金額をつぎ込んだようです。 シャトーカミヤの神谷伝兵衛や浅田飴の創業者、堀内伊太郎などの名前もあり、予約時の平均年齢は41歳と思ったよりも若いものでした。 岩崎弥之助の予約もあるものの、翌年ガンで逝去し、おそらく辞典の実物を目にすることはなかっただろうと著者は推測しています。 出版した吉川弘文館は日本最古の現役出版社。 関東大震災で建物ごと焼け、当時編纂した辞書資料がほとんど失われたため、『新版 国史大辞典』は一から作りなおしたそうです。 その大変な作業が語られます。 着手から第一巻刊行までの14年間は、一切収入がないながら、執筆者に原稿料を支払い続けてきた出版社。 長い期間お金が出て行くばかりの辞書編纂は、刊行までは会社の金食い虫だという話に、三浦しをんの『舟を編む』を思い出しました。 学校や図書館が購入しているのはわかりますが、神社が多いというのが意外でした。 神代の時代は日本の国づくりの原点であるとも言え、国史と神社は密接不可分であるからだとのこと。 また、個人で購入した辞書を、遺族が郷里の図書館に寄贈して保管しているケースも多いそうです。 増版されているながら、21世紀に入ってからもまだ第一版の購入依頼はあるそうです。 当時の社会情報を知るために研究者が求める場合があるのだとか。 著者は、かなり手間をかけて個人の消息を追っていますが、それでも芳名録の個人名の半分以上は特定できない無名の人々なのだそう。 それぞれに貧富の差はありながらも、誰もが明治期に向学の意欲を持って、安からぬ辞書を予約をしたという点では共通しています。 あとがきに、この本の編集担当者の実家にも第一版があったということが書かれていました。 購入者は担当者の曽祖父。その曾孫が出版社に勤務し、芳名録に関するこの辞書の編集を担当したということに、時代を超えた知的つながりを感じます。 職場の図書館の書庫にも、初刊の『國史大辭典』はありました。 明治期の人々が手元に置き、時折手繰った辞典がそばにあることを知って、嬉しくなりました。
Posted by
2013 11/26読了。Amazonで購入。 図書館系界隈で話題になっていたので手にとった本。 国史大辞典初版を出版当時、予約購入していた人々の芳名録をひょんなことから手に入れた著者が、芳名録中の人物について調べて行ったり、国史大辞典自体について調べたりする。 明治大正の知識人...
2013 11/26読了。Amazonで購入。 図書館系界隈で話題になっていたので手にとった本。 国史大辞典初版を出版当時、予約購入していた人々の芳名録をひょんなことから手に入れた著者が、芳名録中の人物について調べて行ったり、国史大辞典自体について調べたりする。 明治大正の知識人伝、といった体をなしていて、当時の知識人階級の雰囲気とか知るのに良い。 それにしてもワンアイディアというか一点突破で本にしていて潔いな、実に・・・。
Posted by
明治時代に国史大辞典が刊行された際、それを「予約」して買った人たちがいた。その人たちのリストを手に入れた著者が、なぜか取り付かれたようにその人たちの素性と、購入された辞典の行方を調べたものです。 今までにない試みだと思うし、作者の執念も伝わってきて「凄いなあ」と思うけど、読了後...
明治時代に国史大辞典が刊行された際、それを「予約」して買った人たちがいた。その人たちのリストを手に入れた著者が、なぜか取り付かれたようにその人たちの素性と、購入された辞典の行方を調べたものです。 今までにない試みだと思うし、作者の執念も伝わってきて「凄いなあ」と思うけど、読了後「で?」という気持ちにならなくもない、そんな一冊でした。
Posted by
日本史をちょっと熱心に学んだことのある人ならお世話になったであろう、国史大辞典。1908年に出版された国史大辞典の初版の予約者名簿から、この辞典をどんな人たちが手に入れたかを調べた本です。 新聞の書評で興味を持って読みました。予約した人を丁寧に説明するのが主で、あとはこちらで意味...
日本史をちょっと熱心に学んだことのある人ならお世話になったであろう、国史大辞典。1908年に出版された国史大辞典の初版の予約者名簿から、この辞典をどんな人たちが手に入れたかを調べた本です。 新聞の書評で興味を持って読みました。予約した人を丁寧に説明するのが主で、あとはこちらで意味を考える必要があるんだろうな、というのが率直な感想でした。ただ、初任給くらいする辞典を、金銭に余裕がある人をばかりでなく、多くの市井の人が予約までして手に入れた、その姿勢には感じるところがありました。そうやって人々の手にわたった辞典が今どこに行っているかという調査も興味深かったです。
Posted by
近代史や近代文学についてある程度の知識があると楽しく読めると思う。 ただ芳名録、という特性上仕方ないのかもしれないが、どうしても人名・施設名の伝記的列挙になってしまっている。 筆者の多方面に亘る取材には最大限の敬意を表するものであるが、中盤以降に変化球を織り交ぜた投球が見たか...
近代史や近代文学についてある程度の知識があると楽しく読めると思う。 ただ芳名録、という特性上仕方ないのかもしれないが、どうしても人名・施設名の伝記的列挙になってしまっている。 筆者の多方面に亘る取材には最大限の敬意を表するものであるが、中盤以降に変化球を織り交ぜた投球が見たかったかもしれない。 ともあれ、開化期の日本史を回顧した書として、非常に面白く読ませていただきました。
Posted by
明治も末の1908年(明治41)、吉川弘文館から『国史大辞典』の初版が出た。定価20円。予約全額払いだと8円。当時の教員の初任給が12~15円だったというから、20万は今で言えば25万くらいに相当する。佐滝さんは、2008年、群馬県の藤岡市の老舗旅館で食事をした際、宿の女将からた...
明治も末の1908年(明治41)、吉川弘文館から『国史大辞典』の初版が出た。定価20円。予約全額払いだと8円。当時の教員の初任給が12~15円だったというから、20万は今で言えば25万くらいに相当する。佐滝さんは、2008年、群馬県の藤岡市の老舗旅館で食事をした際、宿の女将からたまたま、『国史大辞典芳名録』を見せられた。それは、ただ地域と名前だけが並んでいるだけの無機質なものである。しかも、誤植も少なくない。また、作家などだと、実名であるがゆえにすぐに誰だかわからない人も多い。佐滝さんは、この名前だけがならんだ名簿をたよりに、5年にわたりこれを購入した人々を調べ上げて本書を書いた。そこには、当時の著名人がつぎつぎと現れてくるだけでなく、華族、群馬の製糸工場主たち、大学から小学校までの学校、商店、企業、銀行、官公庁、出版社、書店、図書館等があがっている。こうした調査をするのは、たいへんではあるが、佐滝さんは、きっと楽しくて、夢中になってやったことだろう。この本を読みながら、ぼくは明治の前、文久2年に200冊あまり印刷されたという、日本初の本格的英和辞典、『英和対訳袖珍辞書』(1862)が現在どれだけ残っているかを追いかけた、堀孝彦・遠藤『『英和対訳袖珍辞書』の遍歴 現存初版15冊』のことを思い出した。この書は、この英和辞書がどのような人の手を経て現在に至ったかを追究したもので、日本の英学史の一班をそこに見ることができた。それに対し、本書はむしろ、当時の日本の知識層と社会を生き生きと描いてくれたと言える。地元のことを言えば、名古屋大学の農学部には、東大の農科大学の重複本がまわってきているらしい。ぼくは、ロプシャイトの英華字典(1866-69)を最初、名大の農学部で見せてもらったが、それもあるいは、そうした流れだったのかもしれない。もう一つ、地元豊橋にある藤ノ花女子高等学校の前身である豊橋裁縫女学校でも本書を購入していたという。
Posted by
- 1