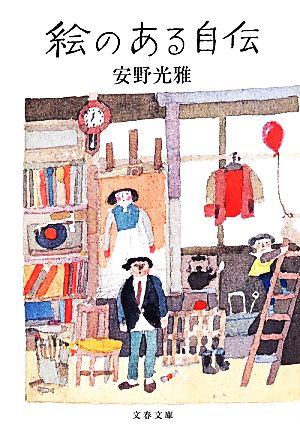絵のある自伝 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2024年、北九州市立美術館に安野光雅展を見に行って、グッズショップで購入しました。子どものころから安野光雅さんの絵本に親しんできたので、私が夢中になっていたあの絵本は、このようにして作られたんだなとか、こんな秘密があったのね、なんて発見もあり、読んで良かったです。絵は一つのエッセイにつき1つ、ささやかに添えてある感じです。 印象深いエピソードがたくさん載っている。戦時中のエピソード、子ども時代のことも興味深い。 私が一番好きな安野光雅さんの絵本、「旅の絵本」シリーズがいかにつくられたかのエピソードもあって、読めて良かった。一冊目の中部ヨーロッパ編に脱獄犯が描かれていること。これはよく覚えているし、子どもの頃の私も気になってしょうがなかった。脱獄犯が他のページにもいるらしいと編集者が目を皿のようにして調べたと聞いて、しまった、描いておけばよかったと思ったらしい(笑)。で、6冊目のデンマーク編で、逃げている脱獄犯がいるらしい。(確認しなきゃ笑)。 旅の絵本シリーズは文字は全くなくて、批判もされたらしい。しかし、安野氏いわく「絵や音楽をことばの説明を仲立ちにして見たり聞いたりしようとするのは、ことばに頼りすぎた者の悪い癖である。その癖が長じると『この絵は何なにを表している』とか、『何を意味している』というように、ことばで整理して判じ物を見るような目で見るようになる。そして、絵とはそういうものだと思いはじめるだろう」とのこと。 そう考えると、姉と二人でほおを寄せ合って、「旅の絵本」を飽きもせず眺めていた幼い頃の私の、絵本の鑑賞の仕方は、本当に純粋で、それ以上ないくら正しいやりかただったのではないかと思う。 最後の方は、親しい人たちとの別れのエピソードが多くなって、読むのが少し切なかったです。
Posted by
安野さんの絵を意識してみていたかと言われれば、そうでなかったように思う。風景のイメージが強いのもなぜだろう。。 「昭和を生きた著者の人生」が突き刺さる。自分はそれを祖父に見ていただろうか。
Posted by
具体的なことがとてもよかった。ディテールがおもしろい、興味深い。 祖父母のライフヒストリーの聞き書きをしたいと思った。
Posted by
2020年に安野さんは亡くなった。 それから3年。 かなりご長命でいられたので、もうすぐ生誕100年にもなる。 本書は80代に入って生涯を振り返ったもの。 故郷の津和野の様子。 宿屋を営んでいた家族のことなどの他、土地の人々のことも書かれている。 貧しい家に生まれたけれど、立...
2020年に安野さんは亡くなった。 それから3年。 かなりご長命でいられたので、もうすぐ生誕100年にもなる。 本書は80代に入って生涯を振り返ったもの。 故郷の津和野の様子。 宿屋を営んでいた家族のことなどの他、土地の人々のことも書かれている。 貧しい家に生まれたけれど、立派に子育てをして幸福を築いた幼馴染のつえ子さん。 「げんきでヘンヨウせいよ」という伝言を残して突然転向した山本虎雄君。 「過ぎたことはみんな、神話のような世界」と安野さん自身も言うが、しかしどこか味わい深い。 司馬遼太郎の「街道をゆく」の取材に同行したこと。 ダイアナ妃来日時のレセプションに参加したこと。 『ABCの本』が海外でも読まれ、英語圏の人々からさまざまな意見が来たこと。 そんなことが飄々とした文章でつづられていく。 昭和四十五年の年賀状の話は傑作である。 その年賀状は収録されているので、そこだけでも十分見る価値がある。 顰蹙を買う可能性もあるけれど、ユーモアのセンスがない自分には、こんなことができる人はうらやましくて仕方がない。
Posted by
感想 絵を描く人の鋭い目線。刺々しい切れ味はなく優しさに満ちている。それでいて他人が気づかない細部に気がつき大局を汲み取る。時代の空気を感じる。
Posted by
絵を描く人なのに、言葉選びも無駄がなく洗練されていると思った。私の親世代より少し上くらいだと思うけど、その時代のことが気軽に抵抗無く(固く古めかしい感じではなく)読めて良かった。大型本屋の戦争特集か何かで平積みされているなかで、読みやすそうだなと思って見つけた。大型書店はこういう...
絵を描く人なのに、言葉選びも無駄がなく洗練されていると思った。私の親世代より少し上くらいだと思うけど、その時代のことが気軽に抵抗無く(固く古めかしい感じではなく)読めて良かった。大型本屋の戦争特集か何かで平積みされているなかで、読みやすそうだなと思って見つけた。大型書店はこういう出会いがあるから本当に好き。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
今、一等になるために走るのではない、いつか大人になって一等になっても得意にならず、ビリになってもくじけないプライドを持つ日の為に走るのだ 試験というもののありかたが、教育の方向を決定づけているという変なことになりつつある。 絵は説明ではない。(略)壁に飾る絵に題名はあっても文字はない。 空想の時間 などなど、普段感じてることがさらっと書かれていて、あぁ、間違ってない、というか、自分の気持ちに肯定感を得たような。 戦中、戦後を生き抜き、沢山の絵を残し、令和の世の中まで見て逝かれたのだと思うと尊敬しかない。
Posted by
安野さんの生きた時代の息づかいを感じたのが良かった。ずっと続いているような錯覚に陥るけれど、母と父、祖父母、私と兄弟、甥っ子、それぞれを取り巻いてきた、取り巻いている時代の空気は、自分の生きた年齢に合わせてその感じ方は矢張り違うもので、それをまざまざと実感したというか。同じ時代を...
安野さんの生きた時代の息づかいを感じたのが良かった。ずっと続いているような錯覚に陥るけれど、母と父、祖父母、私と兄弟、甥っ子、それぞれを取り巻いてきた、取り巻いている時代の空気は、自分の生きた年齢に合わせてその感じ方は矢張り違うもので、それをまざまざと実感したというか。同じ時代を生きているということだけで、どうしてこう容易く「私とあなたは同じ」だなんて思ってしまえるんだろう?甘えもいいとこだ。厳密に言えば、同世代と言えども違うこともあるわけなのに。 「同じだね」って、時にぐっと人との距離を近づけてくれるけれど、同時に同じくらい「我々は違う」って、忘れないでいることって、とっても大事なんだなって、ふと思った。
Posted by
安野光雅さんの自伝。エッセイ。 絵のことはあまり書かれてなかった。絵本がすごく大好きでいろいろ読んだので、少しでも詳しいことがわかればと思ったが。ただ書き下ろしの絵が沢山で有難い。ABCの本については残念。いろいろ考えて描かれたのに駄目出しが多かったり無断で使われたりあまり良いこ...
安野光雅さんの自伝。エッセイ。 絵のことはあまり書かれてなかった。絵本がすごく大好きでいろいろ読んだので、少しでも詳しいことがわかればと思ったが。ただ書き下ろしの絵が沢山で有難い。ABCの本については残念。いろいろ考えて描かれたのに駄目出しが多かったり無断で使われたりあまり良いことがない。それでも大好きな絵のひとつ。
Posted by
1926年生まれ・・・とプロフィールをみて、ふと、かこさとしさんと同年生まれだったんだなと気づく。戦争を知っていて、その体験を絵や言葉で伝えうる大きな存在がまたひとり、いなくなってしまった。世に出された作品を、繰り返しかみしめたい。 子ども時代から少年、そして戦争の日々について...
1926年生まれ・・・とプロフィールをみて、ふと、かこさとしさんと同年生まれだったんだなと気づく。戦争を知っていて、その体験を絵や言葉で伝えうる大きな存在がまたひとり、いなくなってしまった。世に出された作品を、繰り返しかみしめたい。 子ども時代から少年、そして戦争の日々について、身の回りの小さなエピソードまでよく覚えていらして書かれている。ユーモアたっぷりで、悲惨とか厳しいといった語り口ではないのだが、それゆえに率直な気持ちがにじみ出ていると思う。 ユーモア、という点で、『農民兵士の手紙』の話がなんともいえずよかった。よかったというのもおかしいのだけど。 「わたしは戦争には反対だが、学徒と農民を差別することにはもっと反対である。徴兵猶予などと、だれが考え出したのだろうとおもう。」 徴兵された農民を思っての言葉だが、そのあとに自らの若い恋のエピソードを重ねてこう続けるのだ。 「しかし、先に書いたように、「花ある君」に手紙を出し、返事をもらった友人がいなかったら、このような公憤と私憤を混同することもなかっただろう。」 教員になり、画家として立ち、というその後の人生で出会った人との交流も興味深い。また、大上段に構えたものでなく家族など身辺のことに徹していて、ひとりごとを読んでいるような穏やかな気持ちになった。 さいごの『空想犯』もおもしろい。全くの"空想近況"を書いた年賀状を出してしまう安野さん。人柄の一端がしのばれる、たいへんユニークなエピソード。
Posted by
- 1
- 2