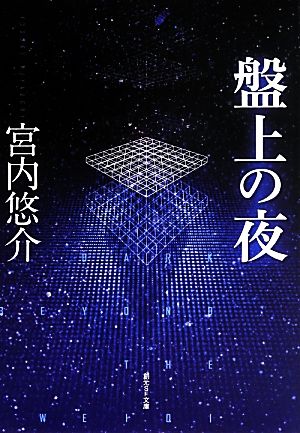盤上の夜 の商品レビュー
1作目、2作目と読んでそれぞれに短編とは思えない重厚感があり、これはじっくり間を開けながら読みすすめたほうがいいなと一旦本を閉じました。 いやでも連作短篇集なのだと思い出して、独立しているようにも思える2作がつながっていく先を思えば、読後はどんな境地に至るのかと期待が膨らみます。...
1作目、2作目と読んでそれぞれに短編とは思えない重厚感があり、これはじっくり間を開けながら読みすすめたほうがいいなと一旦本を閉じました。 いやでも連作短篇集なのだと思い出して、独立しているようにも思える2作がつながっていく先を思えば、読後はどんな境地に至るのかと期待が膨らみます。残りは一気に読んでしまいそう。 でも、今はここまで。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ボードゲームを題材とした話の構成に、おっ!と思わされました。個々のエピソードそれぞれについては、ちょっとトンデモ?な感じも含めて、しっかり読ませてくれてよかったのだけれど、最後のエピソードが若干蛇足 or 物足りない感じ。ここが、これまでのエピソードを集大成して、振り切った最高潮の盛り上がりを見せてくれたなら、忘れられない本になったのかもしれないのだけれど…。
Posted by
面白かったです。おそらく今年読んだ本の中で1番面白い一冊になると思います。 SFは初めて読みましたが、とても楽しめました。6編からなる短編集で、一気に読みたいところです。 特に2本目は実在する人物が主題の話になっており、虚構と現実の境を曖昧にする仕掛けが秀逸です。5年後にもう一度...
面白かったです。おそらく今年読んだ本の中で1番面白い一冊になると思います。 SFは初めて読みましたが、とても楽しめました。6編からなる短編集で、一気に読みたいところです。 特に2本目は実在する人物が主題の話になっており、虚構と現実の境を曖昧にする仕掛けが秀逸です。5年後にもう一度読み返したい本です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
碁、将棋、麻雀、チェス、ボードゲームを題材にした短編集。ゲームを巡る人間の執念や狂気がおもしろい。 ■盤上の夜 囲碁の話。四肢を失った女流棋士が研ぎ澄まされた感覚と純粋な勝負心から連勝を重ねるが、より感覚を研ぎ澄ますために取り組んだのが外国語という点が面白い。一つの事象や感情も言語によって表現の仕方は多様で、宇宙にも例えられる囲碁の魅力とのつながりがオカルトちっくでありSFっぽくもある。 ■人間の王 チェッカーの話。半世紀負け知らずの人間と機械の闘い、そして数学による完全解が証明されてしまったゲームにおいて、人間の王者は何を見たのか。 計算上は完全解明されたゲームであっても、人間がプレイするときには考える楽しさや負けたくないという思いは変わらないのだな。 ■清められた卓 麻雀の話。麻雀は運の要素が非常に強く、プロであっても交通事故のような負けに遭ってしまう。何かを賭ければ必然と狂気じみたものになる。 オカルトと数理と度胸がぶつかり合う勝負が面白い。 ■象を飛ばした王子 チェスや将棋のルーツとも言われる古代インドのチャトランガの話。教えは易しく、時とともに変遷し、底知れなさがあることで伝承されるという一説に納得。 ■千年の虚空 将棋の話。実務派の兄のAIと天才派の弟の頭脳の対決、その間にいるのは魔性の女。データ処理で歴史を正しい一本の道にする量子歴史学というエセ学問に魅力を感じた。 ■原爆の局 囲碁の話。他の話のスピンオフのようにもなっている。 碁とは何か、五割の抽象と五割の具体か、九割の意志と一割の天命か。
Posted by
2012年の第33回SF大賞受賞作品ではあるが、内容は一般的なSFとは少し異質な印象。このような作品でもジャンルの作品として受け入れ、評価できるのがSFの強み。
Posted by
囲碁、将棋、チェス、麻雀などのボードゲームを題材にしたSF短編集なのですが、史実に基づいた描写も多く、いわゆる「SF要素」が薄めな作品も多いです。 ただこの「史実」と「フィクション」の織り交ぜ方や、独自の解釈が非常に読ませる作者さんで、ゲームのルーツや歴史についても飽きずに読め...
囲碁、将棋、チェス、麻雀などのボードゲームを題材にしたSF短編集なのですが、史実に基づいた描写も多く、いわゆる「SF要素」が薄めな作品も多いです。 ただこの「史実」と「フィクション」の織り交ぜ方や、独自の解釈が非常に読ませる作者さんで、ゲームのルーツや歴史についても飽きずに読めます。 人間プレイヤーVSコンピューターの視点はやはり、現代の観点からボードゲームを見るに当たっては、避けられない話題なのでしょうか。 麻雀を題材にした「清められた卓」なんかは麻雀のルールを知らずとも引き込まれてしまったし、「三角関係」という表現では生ぬるい、倒錯した性関係・愛情関係がもつれる「千年の虚空」も良かったです。
Posted by
囲碁、麻雀、将棋などのボードーゲームを題材にした短編集。 特殊な過去や設定を持つ登場人物達のストーリーにワクワクしたし、共通のテーマである「なぜそのゲームをプレイするのか」という部分もそれぞれ違っていて面白かった。 架空の話に現実の事件や歴史を混ぜてあるのも上手い。
Posted by
’「由宇は、外国語を勉強したのです」と相田が言った。「由宇が、囲碁の盤面を触覚として感知できる能力を持っていた、というお話はしたと思います。この力そのものは、中国時代から身につけていたようです。ただ、最初はまだ洗練されていなかった。感覚でしかないものを、まず言葉に分類する必要があ...
’「由宇は、外国語を勉強したのです」と相田が言った。「由宇が、囲碁の盤面を触覚として感知できる能力を持っていた、というお話はしたと思います。この力そのものは、中国時代から身につけていたようです。ただ、最初はまだ洗練されていなかった。感覚でしかないものを、まず言葉に分類する必要があったのです。痛い、痒い、熱い、固い、…最初は、そうした日本語だけでも勝つことができた。しかし、徐々に、それでは不十分になってきたのです。痛い、痒い、熱い、そんなお馴染みの言葉だけでは、トッププロに勝てないことがわかってきた」 ここで由宇が着目したのが、外国語だったのだという。相田によれば、たとえば英語では、明るい青も暗い青も、基本的にはブルーと呼ぶ。ところがロシア語では、明るい青と暗い青とを呼び分ける。必然的に、知覚できる青色の種類は増えてくる。そこで由宇は、世界各国の触覚に関する単語を集め、自分のなかに蓄えていった。強くなるため、言葉を殖やしていくーかつて、そのような棋士がありえただろうか。こうしたプロセスを経て、由宇は自分の感覚を磨き、より精密なものへと育てあげたということだ’ 人は、言葉を通して現実を見る。現実が、言葉を規定するのではない。ー言語こそが、現実を規定する。 (サピア・ウォーフ仮設) 「現実」という範囲を引き寄せている感覚という実体。現実という実体が先にあって、それに当て嵌める言葉を見出していく。この成り立ちはある部分では事実となるが、それ以外の部分ではまるでそうではないという事実が大きく広がっているということを、考える。現実という幅を捉えるのに、言葉とい幅がそのままに折り重なって世界を規定しているという姿は、世界というものが立ち上がってくる様子によって、それこそが現実になるということをこちらに明示してくれている。 その「幅」という概念がないままに、物事を繰り広げ、それ自体によってもまた制約され定められていく周囲の振る舞いを見ることで、その意味をいつも教えられることになる。 感覚、覚醒、自覚、覚悟。覚えるという言葉のもつ意味を通して、自分自身、そして自分以外を捉えようとする。 自分がもちえている幅を覚えているのか。自分の幅によって映し出されるものがあることを覚えているのか。自分の幅が引き寄せている範囲があることを覚えているのか。自分の幅を覚えることによってしか自分の幅は掴まえられないし、その幅を動かすことはできない。自分の幅というものと自分に投影される自分の世界が合同でしか手に入らないことを、それこそ覚えているのか。 自覚はあるのか。 その覚悟はあるのか。 それだけが世界を現出させる。このことをあなたはぼくと共有できるのか。 幅というものが固定されるものではなく、自由に繰り広げていくものだと、そのためにする過程が、生きるということの自由を手に入れることと同じだと、言葉は存在するだろうか。
Posted by
盤上遊戯が、世界を、歴史を、人を変える。見たことない世界を見せてもらった。 個人的ベストは「人間の王」 半世紀の間無敗のチェッカー王者、ティンズリーは機械に敗れたとき、そしてチェッカーが滅ぶとき、何を思うのか。 次いで「象を飛ばした王子」、「千年の虚空」などなど。前作とも素晴らし...
盤上遊戯が、世界を、歴史を、人を変える。見たことない世界を見せてもらった。 個人的ベストは「人間の王」 半世紀の間無敗のチェッカー王者、ティンズリーは機械に敗れたとき、そしてチェッカーが滅ぶとき、何を思うのか。 次いで「象を飛ばした王子」、「千年の虚空」などなど。前作とも素晴らしかった。
Posted by
一冊の本で、こんなにも満たされるとは思いもしませんでした。 6つの話で構成されているのですが、どの話も違った魅力があって最後まで夢中で読むことができました。 ルールや用語がわからないものばかりだったのですが、それでも読んでいて惹き込まれ、盤上の美しさにうっとりしました。 滅多...
一冊の本で、こんなにも満たされるとは思いもしませんでした。 6つの話で構成されているのですが、どの話も違った魅力があって最後まで夢中で読むことができました。 ルールや用語がわからないものばかりだったのですが、それでも読んでいて惹き込まれ、盤上の美しさにうっとりしました。 滅多に出会うことのできない素晴らしい作品に出会えたことが嬉しいです。
Posted by