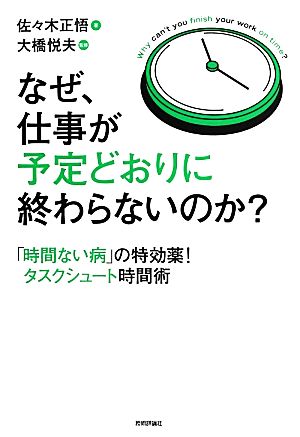なぜ、仕事が予定どおりに終わらないのか? の商品レビュー
これを読む前までは自分の時間管理に対しての認識がふわっとしてましたが、読んでからは今まで意識していなかった時間のレシピに気付きました。 1日の仕事をシュミレーションする時に、休憩、トイレ、割込み仕事、その他ルーティンの仕事を加味して割り出す。 それをする事によって、今までより...
これを読む前までは自分の時間管理に対しての認識がふわっとしてましたが、読んでからは今まで意識していなかった時間のレシピに気付きました。 1日の仕事をシュミレーションする時に、休憩、トイレ、割込み仕事、その他ルーティンの仕事を加味して割り出す。 それをする事によって、今までよりも具体的にシュミレーションできるようになりました。 1日は思っていたより時間がない。 それに気付けただけでも、儲けものです。 とゆー事で、早速1日のtodoを細分化しました。 見えていなかったものが見えるようになるって面白いですね。
Posted by
さらっと読む本ですか、結局人は感覚でなく記録して振り返ると自分の仕事の仕方や時間の使い方に気づくことができるんだよね
Posted by
「期日まで余裕があったはずなのに…?!」 気付いたら仕事が遅れている、って よくありますよね。 予定より時間がかかってしまうのは、 なぜでしょうか。 電話などの割り込みが多い、 業務を詰め込みすぎた、 時間の見積もりが誤っていた。 さまざまな要因はありますが、 以下を気をつけ...
「期日まで余裕があったはずなのに…?!」 気付いたら仕事が遅れている、って よくありますよね。 予定より時間がかかってしまうのは、 なぜでしょうか。 電話などの割り込みが多い、 業務を詰め込みすぎた、 時間の見積もりが誤っていた。 さまざまな要因はありますが、 以下を気をつけてみてはいかがでしょうか。 ➀休憩を確保 ➁実際にかかった時間を記録する ➂先送りにしない
Posted by
仕事ではタスクシュート(無料版)、プライベートではたすくまを使用しています。 自分の使い方が正しいのか模索しながら使っていたもので、使い方(タスクシュートの設計思想)を再確認する意味で読みました。 使っていないひとにはピンときづらいかもしれません。無料版を少し触ってみるとわかるか...
仕事ではタスクシュート(無料版)、プライベートではたすくまを使用しています。 自分の使い方が正しいのか模索しながら使っていたもので、使い方(タスクシュートの設計思想)を再確認する意味で読みました。 使っていないひとにはピンときづらいかもしれません。無料版を少し触ってみるとわかるかも…? 使い方は概ねずれていないなということを確認できました。 本文中に「こんな細かく時間管理したら窮屈じゃないか?」みたいな問いかけがあり、そんなことはないと筆者は書かれていますが、この気持ちはタスクシュート(たすくま)を使っているとすごく頷けます。 時間を忘れて集中できるし(たすくまの場合規定時間がきたらアラームが鳴る)、その通りにやれば終わると、安心できるからかもしれません。 仕事でタスクシュート使い始めて3年くらいたってると思いますが、ある日突然なくなると路頭に迷う自信がありますw帰宅時間が見える安心感は、(なんとなくの)残業が多くなりがちな自分の職業にうってつけだと感じています。 (本ではなくタスクシュートのことを語る文章になってしまった;) 以下、自分用の読書メモ。 ・脱線は時間の無駄、調べ物の途中のネットサーフィンなど。これは仕事してるつもりでやるので休憩にもならず、仕事も進まないしで極めて非生産的な行動 ・夏休みの宿題を先送りする理由→人間は緊張が高まりすぎると行動を起こせなくなるから ・人は疲れてくると、大事な問題でもかなり安直な判断を下すもの ・朝にはなるべく大物を、いつやってもいいものはなるべく夕方に
Posted by
タスクシュートの考え方を解説してくれている本。 タスクシュートに対する批判にも丁寧に答えくれている。タスクシュートしていて迷ったら、戻ってこようと思う。
Posted by
時間はもともと足りない→強く自覚する方法が必要 締切時間が来る前に締切時間は存在している フライト→その前のチェックイン→空港着→移動 朝食 日頃から繰り返していることを優先→時間がなくなる 生理的時間(生きるために必要な時間)を分かっていないとどんどん予定を入れてしまう。 ...
時間はもともと足りない→強く自覚する方法が必要 締切時間が来る前に締切時間は存在している フライト→その前のチェックイン→空港着→移動 朝食 日頃から繰り返していることを優先→時間がなくなる 生理的時間(生きるために必要な時間)を分かっていないとどんどん予定を入れてしまう。 ×スキマ時間を活用しよう→スキマ時間はない 飽きっぽい人→ドラマティックな状況に身を置いた自分の姿に酔いたい 割り込み 集中するために要した時間、再び集中するのに必要な時間を奪う。 ネットサーフィン 人は緊張が高まりすぎると行動を起こせなくなる。 恐怖の仕事は、朝、最初に取り掛かる→不安が解消 手塚治虫 アイデアが浮かべば直したがる。より良いものを時間の許す限り追求 2:8の法則 完璧を求めすぎない タスクシュート式の基本的なルール ①本日1日分の仕事を1シートで管理 ②これからやる仕事 これまでにやった仕事 を管理 ③1分以上かかる仕事は管理 ④見積時間を出しておく ⑤終る時間をリアルタイムに把握 優先順位は付けない→1分以上かかるものをすべて見積もる→ズレを把握 病的に細かい予測 カーナビの通過予測時間 計画→仕事に取り組みたいという気持ちが膨らむ ×時間が無駄になるからとりあえずメールチェック、頼まれ仕事→時間を失っている。 見積と実測のセットを繰り返す 上司からの割り込み仕事→記録→記録を付けないと割り込みが入ったという事実すら示せない(精神論に頼らずに脱線を防ぐのに有効) 今何をしているのか?を明らかにすることなしにタスクシュート式は成立せず 割り込み仕事があることを前提に先取りタスク化 自分への割り込み ①脱線系(ネット)②仕事を増やす系(完璧主義)③先送り系 朝にメール、SNS→広い部屋を小物でいっぱいにしている 睡眠中にしか補給できないエネルギーの無駄使い 単なる習慣(ネット、新聞)をやめる 休憩→仕事に決定的に重要な影響をもたらす。人は疲れてくると安直な判断 イスラエルの調査 仮釈放判定人→疲れてくると仮釈放の申請を却下(安易な判断) 小物をたくさんこなしても意味がない 朝はなるべく大物 レシピはそのままマニュアルになる。 完璧主義者のくせにどうして遅刻するのか?→化粧に長時間 仕事の質にこだわる 難しい仕事を急に頼まれたとき ①きちんと計画 ②課題の把握(作業量、自分の作業スピード、進捗報告の手間を最小限にする) 予定表 実績表 進捗管理表 =REPT() REPT("*-", 3) *- を 3 回表示 *-*-*- かかった時間の記録 今日はどこまでやるのか?何時に退社できるか?全体としていつ終わるか?
Posted by
仕事やタスクだけでなく、1分以上かかる全ての行動を書き出し、開始・終了時間を記録し、ルーチン化、シミュレーションできるようにしていく。先送りとは自分への割り込み。ナビで到着予定時間を見るように、常に終了時刻を知る。 エクセラーじゃないと難しそうです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
紹介されていたタスクシートを視覚的にわかりやすくするため、開始から終了を時刻ではなく、線にして、1日つけてみた。 見積もり時間と実際の時間の差は思ったほど出なかったけれど、割り込み仕事の多さとそれに割く時間が思った以上に多かった。 著者の言うとおり、仕事を振り返るためにも役立つ。 ただ、これを毎日つけるのは、しんどい。急かされて仕事をしている感覚。 まあ、それが働くってことなんだろうけど、そんな調子でやってると壊れる気がする。 ただのTODOリストよりは時間を意識するようになり、優先度も、割り込みされる前にしていた仕事の状況も、見積もりからどの程度遅れているのかも、視覚でパッとわかるので、無駄な時間が生じにくい。 時々は、自分の仕事ぶりを振り返るためにつけてみるのもいいかもしれない。
Posted by
これもGTDなんだろう。GTDは行為を洗い出して、どう処理するかに注目していたが、タスクシュートでは行為を抽出した後に、どのくらい時間がかかるか、かかったかに注目している点で異なる。
Posted by
んー。仕事が遅い自分を認めて、それを前提として時間を配分しような本。ちょっと期待してた内容と違うな。 著者は真面目だが時間効率を上げる方法論を知らない。 家計簿と一緒で時間簿を付けることで何にどれくらい時間がかかっているかを把握するという以前読んだ本に似てるかな。 繰り返し...
んー。仕事が遅い自分を認めて、それを前提として時間を配分しような本。ちょっと期待してた内容と違うな。 著者は真面目だが時間効率を上げる方法論を知らない。 家計簿と一緒で時間簿を付けることで何にどれくらい時間がかかっているかを把握するという以前読んだ本に似てるかな。 繰り返しやっていることは、やりやすいから、優先順位を考えないままつい取り組んでしまう。 「とりあえず片付くこと」ばかり片付けているうちに、時間がなくなる。 恐怖の仕事は朝、最初に取りかかる。 朝にメールチェックをしたり、SNSをやってしまうのは、広い部屋を小物でいっぱいにしてしまうようなもの。認知リソースには限界がある。使い切ったら睡眠で回復するしかない。 人は単純に休憩を取らずに仕事をしていると、怪しげな判断を下してしまう。従って、難しく時間のかかる仕事をするなら、そもそもメンタルが疲れてない時間帯を先に確保し、そこで確実にやる。朝の早い段階では認知リソースがたくさんある。 自分の時間がいかに限られているかを肝に銘じる。
Posted by