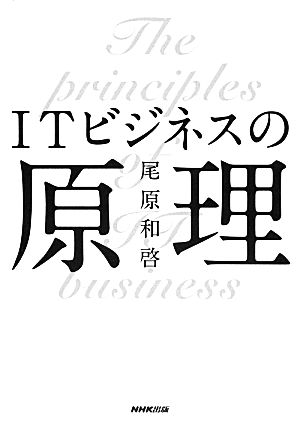ITビジネスの原理 の商品レビュー
点在する情報を一箇所に集めるのがインターネットの得意な所 ユーザーを獲得するために払っているコスト(=TAC)をゼロに近づけるのがビジネスの課題。ゼロに近づけることはつまりユーザーが勝手に集まってきてくれること 1.ユーザーのインテンションを正しく把握する、2.インテンションに基...
点在する情報を一箇所に集めるのがインターネットの得意な所 ユーザーを獲得するために払っているコスト(=TAC)をゼロに近づけるのがビジネスの課題。ゼロに近づけることはつまりユーザーが勝手に集まってきてくれること 1.ユーザーのインテンションを正しく把握する、2.インテンションに基いて最適な物を表示する仕組みをきちんと回ることがインターネットビジネスでは重要 ネット印刷通販会社ラクスル=各印刷所の印刷機の空き時間を使って印刷を行い、通常より安く印刷物を提供する。日本の印刷機の稼働率は45%程度。 ITにより情報を細切れにして配ることでプライバシーの問題にも対処している
Posted by
点在する情報を1箇所に集めるという作業はインターネットが非常に得意とするところ インターネット以前のビジネス モノを安く仕入れて高く売る インタネットのビジネスはユーザを安く仕入れて高く売る 世界中に散財しているユーザを1箇所に集めて、そのユーザを金を出しても欲しいと思ってい...
点在する情報を1箇所に集めるという作業はインターネットが非常に得意とするところ インターネット以前のビジネス モノを安く仕入れて高く売る インタネットのビジネスはユーザを安く仕入れて高く売る 世界中に散財しているユーザを1箇所に集めて、そのユーザを金を出しても欲しいと思っている企業や人と結びつける、マッチングするのが、インターネットビジネス ソーシャルゲームの原型はポケットモンスター ポケモンを作ったのは田尻智さん 「新ゲームデザイン」 ゲームの主要な要素 交換、収集、育成、対戦 クラウドソーシングの究極 ネット通販印刷会社ラクスル 全国の印刷会社の空き時間を使う ITやインターネットは仕事を細切れにすることで価値を生み出すだけでなく、その細切れを集めることによって新しい価値を生み出し、普段使われていない部分を有効活用することができる タスクの細分化 レイヤーバンドル レイヤーバンドルによるオランダの農業革命 マズロー 欲求五段階説 生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求 目的型情報発信、非目的型情報発信 ハイコンテクストのコミュニケーションの歴史が日本にはあった 日本というハイコンテクストな国は、こうした言葉ではない部分を楽しむ、隙間を楽しめるという文化がある appleのコンテンツの市場 2012年4500億円 日本のモバイルコンテンツは2007年ですでに超えている アメリカ人はローコンテクストだから言わないとわからない。でも日本人はハイコンテクストなので、言わなくても分かる アメリカ的なものでつくられた無駄なき社会から人間を取り戻せるのは、日本的なもの アメリカという国家、社会の成立事情から仕方のないことであるが、阿吽の呼吸が成立しないので、コニュニケーションを楽しむというところまでいかない。余剰の部分まで到達しないのです。この余剰に生まれるのがコミュニケーションの消費なので、だからアメリカではコミュニケーション消費が起きにくいのではないかというのが私の仮説 英語を母国語とするアメリカで生まれたインターネットは、英語が世界共通語であるとする雰囲気の中で、英語という言語に縛られてしまった。そのため、ほぼ強制的にローコンテクストにならざるをえなかったといえる ハイコンテクストなコニュニケーションを加速するのがウェラブルであり、ギガビットインターネットなんです
Posted by
最近Webサービスについて考える事が多かったので、まさにぴったりの内容で、すっと理解が出来るコンテンツだった。米国と日本の文化的な特徴とITによって影響される部分、Googleから楽天への転職の意味するところ、今後日本が強く押し出して行くべき強く・価値について訴求されている。
Posted by
名だたる企業を10社も渡り歩いて最後に選んだ会社が楽天。その理由を、ITビジネスの変化と共に説明している。筆者の言うハイコンテクストはこれからのキーワードであろう。
Posted by
この本の中心的に言われていたことは、要するに、誤解を恐れずに言えば、「他者への敬意」がこれから大事になるということだと思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
書いてある理論も非常におもしろく、具体例も付随しているからわかりやすい。あーあれは○○っていうんだ。という具合に。 人の欲求からどのようなことが生じるのか、そしてどのようなことが起きて今これが流行っている、など基本から学べる。 個人的にはリーンフォーワードとリーンバックがお気に入り。
Posted by
ネットビジネスの話。収益構造、細分化、フローとストックのゆらぎ、コミュニケーション消費、ハイコンテキスト。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【文章】 読み易い 【気付き】 ★★★・・ 【ハマり】 ★★★・・ 【共感度】 ★★★・・ マッキンゼー、NTT、リクルート、google、楽天等の大手企業を渡り歩いた著者が語るITビジネスについて。 マッチングビジネス、ソーシャルゲーム、SNS、クラウドソーシング、ショッピングサイト、ウェアラブルデバイス ・ユーザが情報に対して支払うコストは、 情報そのもののコストだけでなく、その情報にたどり着くまでの手間や、支払いまでに掛かる時間や手間を総合したもの 情報そのもの価格が安くても、検索されにくかったり、購入手続きが煩雑すぎては売れない。 ・インフォメーションとコミュニケーション 受け手にとって利益をもたらすデータがインフォメーション ハイコンテクストなコミュニケーションを好む日本では、インフォメーションコンテンツよりも、コミュニケーションコンテンツの方がお金になる。 ・一昔前のインターネットは上り速度が貧弱だったために、個人の情報発信が進まなかった ・amazon:どのショップでも商品ページには同じフレームを使い、合理的かつ効率的に”物”を売る事に特化している。ローコンテクストでありアメリカ的 楽天:ショップ毎に商品ページが異なっていて、”物語”を売っている。ハイコンテクストであり、日本的
Posted by
何で稼いだのか。インターネットは点在する情報を1箇所に集める作業が得意。商売の基本は安く仕入れて高く売る。ユーザーそのものが商品。Googleは、六本木でコーヒーを飲もうとしているユーザーをただで仕入れて、15円で売る。なので、いかにユーザーを安く仕入れられるかが勝負。Googl...
何で稼いだのか。インターネットは点在する情報を1箇所に集める作業が得意。商売の基本は安く仕入れて高く売る。ユーザーそのものが商品。Googleは、六本木でコーヒーを飲もうとしているユーザーをただで仕入れて、15円で売る。なので、いかにユーザーを安く仕入れられるかが勝負。Googleは、いかに勝手にユーザーが集まるのかを力を入れる。リクルートは、いかに高く売るのかが強み。いかに安く仕入れるのかに力を入れるべき。 Googleの強みは、カスタマーニーズを直接の打ち込みによって完全に把握すること。Facebookは、そこが弱いからマネタイズに苦労している。Googleのすごいところは、クライアント側も束ねるアドセンスを持っているところ。Webページの運営者がアドセンスを利用すると、そのページの内容が解析されて、関連広告が出される。 課金ビジネスがなかなか上手く行かなかったのは、その情報そのもののコスト、情報を探索するコスト、情報を手に入れるためのコストがある。支払いの手間がこれまで大変すぎた。 発展の背景。 掲示板。テキストデータ。フロー情報。箱で分けて入れようが、スレッド。その後、写真などもアップされているWebブラウザ。ハードディスクも安くなり、ストックへ。ハイパーリンクの発明。 通信インフラが整い、ユーザーからもFB出来るweb2.0へ。そして不特定多数の情報アップを、貯めるサイト、CGMの登場。人間関係の強化から、情報取得へ、 SNS。そしてTwitterなどは、フロー情報化にサイドなった為に、それをまとめるキュレーションサービスの登場。リーンフォワードとリーンバックの姿勢の違いによって、情報に求めるレベルは変わる。iモードの思想は、24時間、7日間、30センチいない。 日本のハイコンテクストだから出来るコミュニケーション市場。待受画面、着うた、アバターなど。本当に小さな違いをお互い認め合える。コミュニケーションでその違いがわかることこそが価値。こんな着メロにしたよなど。 次のインターネットはハイコンテクスト化? 物語を売る。共通語から、多言語化、そして、非言語化へ。デバイスはウェアラブルで、さらに一心同体。情報取得コストの最小化へ。 当たり前のことを、わかりやすくまとめてくれたので、大変整理出来た。一度読んでおくと良い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルどおり、インターネットがもたらしたこと、本質的な原理について、記載された本。良著である。 <メモ> ・インターネット以前:ものを安く仕入れて高く売る インターネット以後:ユーザを安く集めて高く売る ・ソーシャルゲームのビジネスモデル。 北風から太陽へ。お金を払わないと・・からお金を払わないでもできるが、払った方がなおよし・・ ・インターネットは時間、報酬、作業、役割を細切れにするものである。 ・グーグルによってディレクトリ検索からキーワード検索へ。サイト単位ではなく、ページ単位、記事単位と粒度が細かくなった。 ・リアクティブな受信技術が重要に。しょうもないのを受け流す力。これがないと発信もしづらい社会になってしまう。重要。 ・日本はハイコンテキストな社会であるため、隙間や機微をわかりあうことができる。そうした背景の上でコミュニケーション消費が大ヒットする。 また前提をはしょりがちなのもまさに同質性の高いハイコンテキストな社会であるためである。 ・ハイコンテキストとローコンテキストとの比較で後半語られておりおもしろい。 合理化と背景を大事にする複雑性を捉える社会との違いにも思える。(感想) ・グーグルグラスにより、日常の検索コスト、情報収集コストがさらに下がり、コンテキストを共有しやすい、機微がわかりやすい社会がくるはずとのこと。 ・日本はハイコンテキストな国、コミュニケーション消費先進国であり、どんどん新しいものをつくっていってもらいたい。
Posted by