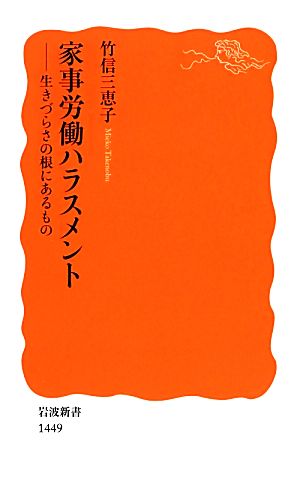家事労働ハラスメント の商品レビュー
ワーキングマザー的な話題の中で、あるブログで紹介されていた本。3歳男子の子育て真っ最中、仕事・家事・育児をどう両立するかが自分自身の課題であるとともに、それって自分ひとりの問題じゃなくて、世の中の問題じゃないの?と常々思っているのですが、そのあたりをしっかりまとめてくれている一冊...
ワーキングマザー的な話題の中で、あるブログで紹介されていた本。3歳男子の子育て真っ最中、仕事・家事・育児をどう両立するかが自分自身の課題であるとともに、それって自分ひとりの問題じゃなくて、世の中の問題じゃないの?と常々思っているのですが、そのあたりをしっかりまとめてくれている一冊。なぜ家事労働が軽視されているのか、もしくは美化されて(家事は尊いものだから)無償であるべきとされているのかの理由を追いかけるとともに、問題提起しています。 長年取材してきた内容も踏まえつつ、現在の法制度の背景や、なぜ日本はこういう社会なのか、ということに向き合っていく。自分が漠然と感じていた違和感のようなものを、ちゃんと説明してくれた…というか。 ただ、タイトルをキャッチ―にしたかったのは分かるのですが、「ハラスメント」というのは内容とズレがあると思っています。ハラスメントというと個人から個人へのいやがらせのように受け取れてしまうのですが、これはあくまでも単純に個人的な「ダンナが奥さんの家事を軽視している」という問題ではなくて、社会として「家事労働を軽視する仕組みになっている」という問題だ、ということを訴えています。ワーキングマザーに限らず、パパ達も、むしろ子育て世代じゃない人たち、管理職の人たちとか社会や会社の仕組みを動かす・作る立場にある人たちにも是非一読して欲しいですね。
Posted by
内容に興味はあったものの、文書が読みづらい。 岩波新書なので仕方ないかもしれないが、かたい。 実際の体験談やインタビューも度々はいるが、どうもテンポが崩れて読みづらい。 以下メモ---> 避難所でも家事労働は女性の仕事にされた 復興支援の就職口も肉体労働ばかりで女性の就...
内容に興味はあったものの、文書が読みづらい。 岩波新書なので仕方ないかもしれないが、かたい。 実際の体験談やインタビューも度々はいるが、どうもテンポが崩れて読みづらい。 以下メモ---> 避難所でも家事労働は女性の仕事にされた 復興支援の就職口も肉体労働ばかりで女性の就職の壁になった 貧困3つの理由 ①男女雇用機会均等法 男性と同じ労働を求められる 「総合職」「一般職」が生まれる ②労働者派遣法の制定 ③第3号被保険者制度「主婦年金」 年収を130万円に抑える 何故女の子はピンクで、男の子はブルーなんでしょうか うちのなかで家事をしても誰もほめてくれない。外に行ったらゴミ箱を片付けただけでお礼を言われて、お金までもらえた。 カネの若者離れ 欲望のダウンサイジング 専業主婦回帰の罠 貧困主婦 ⇒保育を頼むほど賃金が期待できない(低賃金 ⇒家事労働を外部に出すコストの方が高い 家庭内の就業者 妻の賃金は自営業主と一緒で経費にならない という原則があり、自営妻の賃金は認めれつつも税務署長の裁量次第 ニート支援の対象 若い女性の「家事手伝い」を対象にするか ブラック化するケア労働 ・家事(無償)のイメージが強い 最低賃金だけが歯止め ・「労働者」としてではなく「嫁労働」の延長として見られる 女性風俗問題 若者の供給は減らないので強気 指名が少ないと賃金以上の罰金を取る オランダ かつて「専業主婦大国」だった 保育所が圧倒的に足りないので、働き手が合わせる。 同じ労働なら正社員でもパートでも賃金は同じ 労働日数なども柔軟 スウェーデン フルタイム復帰 1+1=2 オランダ 女性のパート率60% →0.75+0.75=1.5を目指す
Posted by
働き出してからずっと感じていた働きにくさや違和感の原因がやっとわかってスッキリした。選挙の時などはこの違和感の原因を大切にして候補者を選びたいと思う。仕事中もこの違和感を内に込めずはっきりと声に出していきたいと思う。そういう気持ちになれたのでこの本に出会えてよかった。
Posted by
レビューはここに書きました http://kobeni.hatenablog.jp/entry/2014/01/23/145827
Posted by
家事労働について、例えば男性一人暮らしは食事の材料を買う、作る、後片付け、というのを社会(コンビニなど)に委託していることになるが、社会に委託しているという意識がないために、家事労働がなかったことになっている、という視点。 著者の思いが強すぎて文章にそれが感じられるためか、多分い...
家事労働について、例えば男性一人暮らしは食事の材料を買う、作る、後片付け、というのを社会(コンビニなど)に委託していることになるが、社会に委託しているという意識がないために、家事労働がなかったことになっている、という視点。 著者の思いが強すぎて文章にそれが感じられるためか、多分いい内容なんだけどなかなか頭に入ってこなかった。
Posted by
国を挙げてのハラスメントだから根が深い。 ハラスメントって受けてきた人が他の人に回さぬよう努力しなきゃ連鎖してしまうから。 生きていきたくなる世にしていきましょう。
Posted by
読んでいて、今までもやもやしていた感情が整理でき、怒りというかなんというか、「こんなにひどい状況をよく放置してきたものだ!」と言いたくなった。 データは説得力がある。家事や仕事、子育てと性別をかけ合わせると、感情論や慣習が大きく影響する問題になるので、扱いが難しいのも併せて実感...
読んでいて、今までもやもやしていた感情が整理でき、怒りというかなんというか、「こんなにひどい状況をよく放置してきたものだ!」と言いたくなった。 データは説得力がある。家事や仕事、子育てと性別をかけ合わせると、感情論や慣習が大きく影響する問題になるので、扱いが難しいのも併せて実感した。
Posted by
家事、育児、介護などの家庭内での労働(そもそも貨幣変換できそうな概念を用いるのが根本的に間違っているとは思うが)を家族内ケアと呼ぶとわかりやすいと思う。 あらゆる方面から検証がなされていて、とてもわかりやすい。 結論としても「再分配」を挙げているので、中途半端な提案でもない。 た...
家事、育児、介護などの家庭内での労働(そもそも貨幣変換できそうな概念を用いるのが根本的に間違っているとは思うが)を家族内ケアと呼ぶとわかりやすいと思う。 あらゆる方面から検証がなされていて、とてもわかりやすい。 結論としても「再分配」を挙げているので、中途半端な提案でもない。 ただ、「ケア」という概念をもっと掘り下げてほしい思う。 すべてのケアが対価に相当するとも思えず、ケアには個性があり、深みがあり・・・と思うのですが。
Posted by