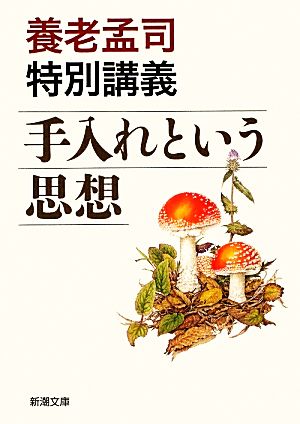手入れという思想 の商品レビュー
98-99年あたりに行われた養老先生の講演会をまとめたもの。先日読んだ小島慶子さんとの対談本で、小島さんが推していたので読んでみた。 根本にあるのは、そもそも日本の近代化とは都市化であって、人間がコントロールできない自然を排除する傾向にあるとの論。ウィルスとの関連では、交通事故...
98-99年あたりに行われた養老先生の講演会をまとめたもの。先日読んだ小島慶子さんとの対談本で、小島さんが推していたので読んでみた。 根本にあるのは、そもそも日本の近代化とは都市化であって、人間がコントロールできない自然を排除する傾向にあるとの論。ウィルスとの関連では、交通事故死の数とウィルスによる死亡者数が同じであっても、コントロールできないウィルスの方を異常に脅威と感じるというところが、昨今の流れに合致していてしっくり来た。言われてみれば、自分で発明した自動車に殺されることの方がキミが悪いのに、対処法がわかっていれば安心してしまう不思議な人間心理を指摘されたよう。 小島さんが感銘を受けたと言う子育てについては、子供=自然である、という発想(思うままにならない子供を育てる人が減る→少子化)。言い換えればマニュアル化なのかもしれないが、「これを入力すればこういう結果が出る」ということを求めてしまう現代人の性を指摘されて、なるほどと思ってしまった。子育ても月齢別マニュアルから、「自分の子供が育てにくいと思ったら読む本」云々まで実にさまざまあり、無意識のうちに「子供は親の力で抑制できる/正しい方向に育てられる」と思い込んでいることが育児ストレスを生み出しているのかもと思った。 知識と自分との乖離。当時はサリン事件が騒がれていたこともあり、どうしてそういう若者が生まれたのかと、若者に接する教授としての養老先生の思考が垣間見れて面白かった。
Posted by
大学などの講義録 いささか内容等古い( 当然だが…) ただし、昔からこの人の発言にはブレがないことがよくわかる
Posted by
養老孟司先生の講義録。 日本人特有の「手入れ」という思想から、 「言葉」というものの再定義、人類が行ってきた「都市化」という行動がもたらすもの、「死」というものについて… 意表をついた切り口が鮮やかで、霧がぱっと晴れたようにものごとが分かった気がします。で、IQが10くらいは上が...
養老孟司先生の講義録。 日本人特有の「手入れ」という思想から、 「言葉」というものの再定義、人類が行ってきた「都市化」という行動がもたらすもの、「死」というものについて… 意表をついた切り口が鮮やかで、霧がぱっと晴れたようにものごとが分かった気がします。で、IQが10くらいは上がったような気になりますが、後で人に説明しようとしてもうまく伝えられない。とても難解なことを語っていたのだなと、後で気がつくのです。これは読み返してしまいますね。
Posted by
手入れとは何か。養老さんがいう。手入れとは、日本的な文化で、自然という、どうにもならないものに対して、少しでも人間の側に寄せるために手を入れることなのだと。日本人は、自然を相手と認め、折り合うために手を尽くした。神道などの宗教とは違った、別の切り口から考えさせられました。
Posted by
養老さんの講演を収めたもの。全部で八つの講演が収録されていて、都市と自然について触れている部分がとても多いです。 この本でとりあげられている都市の象徴は天王洲とみなとみらい。とことん人工的で、地べたからすべて人間が設計して作りあげた、養老さん式に言うと「ああすれば、こうなる」が形...
養老さんの講演を収めたもの。全部で八つの講演が収録されていて、都市と自然について触れている部分がとても多いです。 この本でとりあげられている都市の象徴は天王洲とみなとみらい。とことん人工的で、地べたからすべて人間が設計して作りあげた、養老さん式に言うと「ああすれば、こうなる」が形になったところ。その対極にある自然の象徴は屋久島と白神山地。ここを養老さんは「人間とできるだけかかわりのないところ」で「使いようがありません」と言います。 そしてその中間にあるのが里山。これは自分が作ったものではない、自分の思いどおりにならない自然を素直に認め、「それをできるだけ自分の意に沿うように動かしていこうと」する人々の働きかけによってできたものです。そしてその働きかけこそが「手入れ」なのです。 里山風景というのは、決してそれを作ろうという意識が作り出したものではなくて、こうやったら農作業がしやすいとか作物がうまく作れるとか、そういうことを考えて人々が努力して工夫してきた結果できたもの。そしてそれは人にとって使い勝手がよく、目で見ても美しい。 これを養老さんは子育てやお化粧に例えます。子育てには「こうやれば大丈夫」ということは一つもない。こうやれば永遠に美しく若くいられる、という魔法もない。到達点は見えないけれど、それでもよりよくしようと日々努力してきちんと整えていこうとする、それが「手入れ」で、それをやっていれば出来上がりが大きく間違うことはないだろうと。とても共感できました。生きていると思いどおりにならないことばかりありますが、結局は日々よくなろうと努力するしかないのだから。 死んだ時に心がなくなるとしたら、人が死ぬ時に体重を計ったら心の重さが分かるだろうと、それをやってみた人がいる、という話。死は具体的なある瞬間ではなくて、人はそれぞれの器官がバラバラに死んでいくのだという話。言葉と音楽と絵は人間の「表現」の典型で、本来これらは同じものであり、それを別物と区別しているのは人間の意識であるという話。とても挙げきれないくらい面白い話がたくさん出てきます。 養老さんのお父さんの死について語られる部分では、きっと彼らしく飄々と話されたのでしょうが(実際彼の講演に行ったことがあるので、声が聞こえる気がしました)涙が出ました。 養老さんはブレなくて、どの講演でも基本的に同じことを繰り返し言っています。でも、講演をする場所、語る相手によって切り口が違う。それが面白いと思います。
Posted by
里山の話は他の本で読んだが、 あらためて話を読むと、ふんふんなるほどと思う。 子育てにしてもお化粧にしても、せっせと手入れをするのだ。 自然のままにしておけば、いったいどうなるか空恐ろしい。 死に対するはなし、脳死について、 ああそうかと腑に落ちる。 帯にある通り、この本は日本...
里山の話は他の本で読んだが、 あらためて話を読むと、ふんふんなるほどと思う。 子育てにしてもお化粧にしても、せっせと手入れをするのだ。 自然のままにしておけば、いったいどうなるか空恐ろしい。 死に対するはなし、脳死について、 ああそうかと腑に落ちる。 帯にある通り、この本は日本人論だ。
Posted by
「バカの壁」の著者として有名な養老孟司氏の講演会の書き起こしをいくつか集めた本。著者は解剖学者であり、趣味が昆虫採集(虫を捕るために海外まで出かけてしまう猛者)ということで、生き物の「生」と「死」、あるいは「変わるもの」と「変わらないもの」という観点での考察がとても鋭い。自然とは...
「バカの壁」の著者として有名な養老孟司氏の講演会の書き起こしをいくつか集めた本。著者は解剖学者であり、趣味が昆虫採集(虫を捕るために海外まで出かけてしまう猛者)ということで、生き物の「生」と「死」、あるいは「変わるもの」と「変わらないもの」という観点での考察がとても鋭い。自然とは、人の手が入っておらず「変わり続ける」のが本質であるのに対して、人による都市化とは、あらゆるものを「変わらない(ように見える)」人工物で覆い尽くしてしまう営みであると看破している。そして、都市化の象徴として、人間の「四苦=生老病死」を、すべて「病院」という人工物に押し込んでしまっていることを挙げている。日本でも、一昔前までは、ほとんどの人が家で「自然に」生まれ、家で「自然に」死んだものであるが、現代ではそれらの機能がすべて病院に移ってしまった。すなわち、日常生活から「生」と「死」が消えてしまうことが都市化の最大の特徴であり、現代社会の様々な不具合の病巣になっているという指摘は、まことに愁眉である。 著者は、また、「知ることは変わること」だとも主張する。膨大な知識を蓄えていても、それで自分が変わらないのであれば「知っている」ことにはならないし、逆に、本当に何かを「知る」ということは、(特に、現状維持を良とする封建的な共同体においては)非常に危険なことなのだと指摘している。 不治の病にかかって、医師に「余命半年」と宣告されたら、誰もがそれまでの生き方を変えるはずである。それが「知る」ということである。「生きること」と「死ぬこと」、「変わること」と「変わらないこと」、「知ること」と「変わること」、これらの関係が人間として生きることの本質なのだと教えてくれる良書であった。
Posted by
「今日の自分と明日の自分はもはや違う人間である」、「今日の自分が少しずつ死んでいき、新しい自分になっている」という感覚が現代人にはない。それはおそらく自我が強くなってきたことと相関があるのだと思う。自分自身が変化しているという感覚。中世には「人は変わるもの」という感覚があったよう...
「今日の自分と明日の自分はもはや違う人間である」、「今日の自分が少しずつ死んでいき、新しい自分になっている」という感覚が現代人にはない。それはおそらく自我が強くなってきたことと相関があるのだと思う。自分自身が変化しているという感覚。中世には「人は変わるもの」という感覚があったようで、だからこそ約束を絶対とする「武士に二言はない」ということが言われたと記憶している。常日頃思うのは、よくもまあみんな「自分」という曖昧模糊なものに根拠もなく確信を持って生きられるなぁと感心する次第。養老先生の『感覚』に大変共感した。
Posted by
複数の講演録が収録されています。 宗教について、都市について、育児について・・今が悪くて昔がよかったと言っているわけでもないと思うのですが、現在おこっていること・身の回りのことをどうやって理解するかについてヒントが多く示されていると思いました。 とくに都市化というキーワードは...
複数の講演録が収録されています。 宗教について、都市について、育児について・・今が悪くて昔がよかったと言っているわけでもないと思うのですが、現在おこっていること・身の回りのことをどうやって理解するかについてヒントが多く示されていると思いました。 とくに都市化というキーワードは繰り返し出てきます。そのことが自分たちの心性に与える影響のことはあまり考えないで都市化がすすめられてきたんだなーと思います。 再読しての感想。 都市化をキーワードに、人がいかに、周りのものを制御可能になるよう努力してきたか、その結果制御できない自然なもの(たとえば子供)を受け付けない状況になってるか、(結果としての少子化)などの視点が提供されてました。多少飛躍してると感じたところもありましたが、説明や制御できないものもあって普通である、という視点を(当たり前なのですが忘れそうになっていた)改めて得られました。 タイトルの示すように、そうやって説明や制御ができないものに対し、その場その場で良いと思う対応をこまめにしていくことが「手入れ」であるとして、その貴重さが説かれていました。
Posted by
他のレビュアーさんも指摘しているように、内容の重複がだいぶ見られます。 講演をベースにしているためだと思われます。 ですが、各講演ごとに扱われているテーマが異なりますので、興味のある部分だけでも、読む価値はあります。読みやすいですしね。 個人的には、「子どもと現代社会」「手入れ...
他のレビュアーさんも指摘しているように、内容の重複がだいぶ見られます。 講演をベースにしているためだと思われます。 ですが、各講演ごとに扱われているテーマが異なりますので、興味のある部分だけでも、読む価値はあります。読みやすいですしね。 個人的には、「子どもと現代社会」「手入れ文化と日本」がお気に入りです。前者は、知ることは変わることである、という指摘にグッときました。後者は、養老先生の都市論と宗教論が詰まっていて、文系脳が刺激されました。
Posted by
- 1
- 2