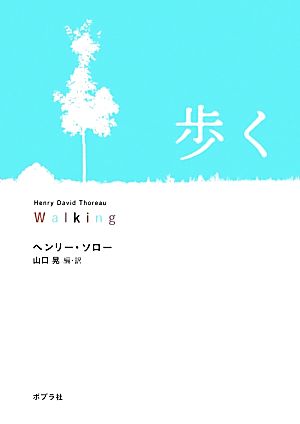歩く の商品レビュー
難解だが一気に読んだ。ソローは長生きしたと思い込んでいたが、自分より若く亡くなったことを知って驚いた。
Posted by
『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』から本書に収められたエッセイ「歩く」を知り読みたくなった。 本文のエッセイ「歩く」のほか、冒頭のフォトブック形式のパート、ソローの伝記的な解説の三要素からなる、変則的な構成をとっている。 冒頭30ページほどは、ソローのさまざまな著...
『ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした』から本書に収められたエッセイ「歩く」を知り読みたくなった。 本文のエッセイ「歩く」のほか、冒頭のフォトブック形式のパート、ソローの伝記的な解説の三要素からなる、変則的な構成をとっている。 冒頭30ページほどは、ソローのさまざまな著作と手紙からの短い抜粋文を集成したもの。20世紀初頭にソロー生前の足跡をたどった際に撮影された写真が添えられ、ここまでは詩的なフォトブックのような趣向となっている。以降が本文にあたり、亡くなる二か月前に推敲を終えた講演原稿「歩く」を収録(講演そのものは約十年前に行われていた)。遺言ともいうべきエッセイで、ソロー全集からの訳出。この本書の核となるエッセイ「歩く」だけなら90ページほどと、かなり短い。本文に続く約百ページは「歩く人ソローについての覚書」となっており、ソローの文章を引用しながらソローの人生を解説する。本文よりもこちらの解説部のほうがページ数としては多い。巻末には訳者あとがき、ソロー略年譜、参考文献が掲載される。 エッセイのキーワードは「野生」である。ソローにとって希望であり、惹きつけられるものは野生的なるものだけだ。そして善いものはすべて野生的で自由だという。反対から見ると、"飼い慣らされた"ものへの否定ということになる。主張そのものは『ウォールデン 森の生活』にあるものと変わらず、その一部をエッセイとしてコンパクトにまとめたものという印象だ。ちなみに、ソローは一日四、五時間、距離にして二、三十キロ、自然の中を歩くことを習慣としていたらしい。 個人的にはエッセイ本文よりも、ソローの生涯や人となりを振り返った後半部の「歩く人ソローについての覚書」のほうが新鮮だった。ソローの著述、日記、友人への手紙だけでなく、関係者からみたソローの姿の証言を含む。とりわけソローに強い影響を与えたエマソンについては多くが費やされる。公人としてのソローの影響力を示す出来事ととしては人頭税拒否の顛末について詳細が語られており、ガンジーがソローの著作に影響を受けるまでを伝える。ほか、若き日の失恋のようなプライベートなエピソードも少なくない。著作と講演だけで生計を立てたいソローが、食うために選んだ測量の仕事を離れられずに悩むあたりは現代人の抱える理想と現実と近しいものを感じる。 ある意味もっとも意外だったのは、一般人の目から見れば奇異にも映ったであろうソローが、少なからぬ人々に慕われていたらしいことだった。逃亡する黒人奴隷への継続的な救済活動と政府への働きかけも印象的だ。ソローが亡くなった際のエマソンの言葉は、ソローが深く愛されていたことを伺わせる。 「エマソンは顔をそむけ、彼は美しい魂をもっていた、本当に美しい魂をもっていた、とつぶやいた」
Posted by
「ウォールデン 森の生活」で知られるヘンリー・デビット・ソローの歩くこと、散歩についての考察。 思索家は、ただ歩く。 そして、彼の思考はその歩きとともに拡がる。 本書は、彼の講演録と編者によるソロー研究の二本立てで成り立っている。 私は研究者ではなくただの読み手なので、後半は読...
「ウォールデン 森の生活」で知られるヘンリー・デビット・ソローの歩くこと、散歩についての考察。 思索家は、ただ歩く。 そして、彼の思考はその歩きとともに拡がる。 本書は、彼の講演録と編者によるソロー研究の二本立てで成り立っている。 私は研究者ではなくただの読み手なので、後半は読み飛ばした。 ソローは、森の生活の中で、多くのものを手放した生活をしている。 彼の講演の中でも、彼は多くの思索の上に、その思索を手放している。 一度はちゃんと研究しなきゃだめなのね。 断捨離の前に、いろいろなグッズを集めてる自分が少し正当化できるような気がした。
Posted by
「森と生活」著者 ヘンリー・ソローの講演をまとめたものと、著者の人となりとその時代背景の二本立てで構成されていました。 「森の生活」が生まれた時代、背景、著者の人となりがわかって改めて良さを再認識しました。
Posted by
読み始めてすぐに違和感を覚える... もしかしたら翻訳者の何か(思いのようなもの...?)が少しまとわりついているように感じてしまう。 気のせいだったのかもしれない...と思いながら読み進み、読み終える。 最後の訳者あとがき を読んで腑に落ちる。 ある思いを込めてこの本を「つ...
読み始めてすぐに違和感を覚える... もしかしたら翻訳者の何か(思いのようなもの...?)が少しまとわりついているように感じてしまう。 気のせいだったのかもしれない...と思いながら読み進み、読み終える。 最後の訳者あとがき を読んで腑に落ちる。 ある思いを込めてこの本を「つくった」ようである...。 それでも最後まで読めたのは翻訳プラス訳者の思いがあったからかもしれない... けれどやっぱり 「素」のソローの言葉が知りたかったかも… ただやっぱり 注釈一覧や参考文献は見ても興味深い... もう少し...ヘンリー・ソローを読んで見たい。
Posted by
散歩が好きなので買ってみた。毎日何キロも歩くというソローの独特の感性や考え方を素敵だと思った。そして、なぜか日常生活が少し楽になった気がした。(散歩の本ではなかった)最後にソローが100年もあとの人たちに影響を与えたことを知り、またその偉人たちのラインナップに驚愕した。
Posted by
おおよそ160年前、H.ソローが「歩く、あるいは野生」と題して講演した記録だ。 エッセイとして推敲されているが、話し言葉で書かれているためか、本の世界に集中できない。本の半ばまで読み進めたが、もう読むのをやめようかと思ったころ、タイトルの「歩く」は終わった。 続くのはH.ソロー...
おおよそ160年前、H.ソローが「歩く、あるいは野生」と題して講演した記録だ。 エッセイとして推敲されているが、話し言葉で書かれているためか、本の世界に集中できない。本の半ばまで読み進めたが、もう読むのをやめようかと思ったころ、タイトルの「歩く」は終わった。 続くのはH.ソローについての覚書だ。 周囲の人がソローについて語ったことを覚書されている。そこで思うのは、・・・私は彼に似ている・・・。偉大な思想家でもあるソローに似ているというのはおこがましいので、書き換えると、非常に共感できる。 静かに歩く。ウオールデンの湖を前にし、穏やかにたたずむ。ゆっくりと時間を過ごすことが、160年前にすでに価値を持っていたことにも驚くが、2016年を生きる私にも十分魅力的な『あり方』が書かれている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
H・ソロー『歩く』ポプラ社、読了。家を出て、ただ自然の音に耳をすまし、たんたんと歩いてみよう。自然への集中は自分の存在への集中となる。あえて俗事を考えずに歩け!が世に流されない自由な自分になる。本書は非暴力不服従の端緒となった『森の生活』のソロー晩年の講演エッセイ集。☆5 無関心を決め込んでエコロジーという話でもないし、所謂「24時間意識高くあれ」でもない。そこには本当の自分は存在しない。自然と向き合うことで自分と対面する。そのことで虚構を自覚する私のNOが立ち上がる。その眼差しが市民的不服従を招来か。正にパワーゲームを超克する「私」が立ち上がる。
Posted by
嬉しい本を手に取って胸がいっぱい。自然の子、歩く人ソローと繋がる感覚。本にふさわしいウェンデル・グリースンのモノクロの風景写真が挿入されている。まさにソロー好きな訳者が作った、手作り感覚が伝わる。紙質も、活字、装丁どれをとっても、この本をおざなりに作ったのでない事が知れる。e-b...
嬉しい本を手に取って胸がいっぱい。自然の子、歩く人ソローと繋がる感覚。本にふさわしいウェンデル・グリースンのモノクロの風景写真が挿入されている。まさにソロー好きな訳者が作った、手作り感覚が伝わる。紙質も、活字、装丁どれをとっても、この本をおざなりに作ったのでない事が知れる。e-book ではない、紙の本を手にする嬉しさを久しぶりに味わう。今時珍しくしおりが付いている。勿論、内容が一番。「歩く」と、敢えて能動的な訳にしてあるのに着目。walking を従来風に「散歩」としなかった思い入れを感じる。訳注もあるし、ソローについての覚書では、ソローの人となりを語る。最期の日々についての記述があって、小生は初めて読んだ。ソローの魂が、益々近くに寄ってきた感じがして、読書の秋に相応しい贈り物を得た気がした。訳者、ポプラ社に有難うと言いたい。
Posted by
- 1