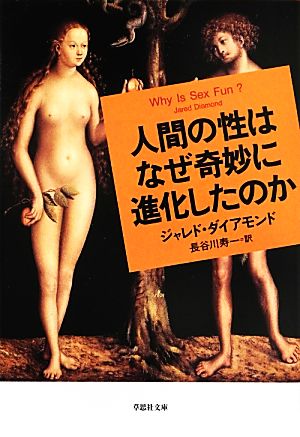人間の性はなぜ奇妙に進化したのか の商品レビュー
本書によると、人類の進化は、その経済的合理性によってほぼ説明できるのだという。人間の性(単にセックスという狭い意味を表すものではない)が他の動物に比べてひどく奇妙である点について驚きを禁じ得ないが、更にその理由が、生存し、種を保存していくうえでの経済合理性に関係しているという説明...
本書によると、人類の進化は、その経済的合理性によってほぼ説明できるのだという。人間の性(単にセックスという狭い意味を表すものではない)が他の動物に比べてひどく奇妙である点について驚きを禁じ得ないが、更にその理由が、生存し、種を保存していくうえでの経済合理性に関係しているという説明は、とても新鮮で興味深いものに感じた。
Posted by
以前から読みたかった本。空港で文庫を見つけたので購入。確かに人間と他の動物を比べると特異さが際立つ。よいし視点。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フーコーの「性の歴史」の世界にやや凝り固まってきた頭をほぐすために、進化生物学や人類学の知見を参照してみる。ひとつの問題を違った角度から眺めてみるよい勉強だが、とりわけ多様なアプローチを取り得るセクシャリティに関しては興味のもっていきかたに際限がなく、それぞれの説得力を整理するのがたいへんである。医学、心理学が基本概念とする生物=心理=社会モデルを振り返ってみると、もうセックスとジェンダーを区別した思考はナンセンスなのかなと思えてきた。
Posted by
期待しすぎたためか、つまらない内容に辟易しながら読み進めた。 まわりくどく、他の事例の引用が長々しい。 演繹法的な説明ではなく、陳腐な帰納法での説明なので、まどろっこしくてたまらない。 結局何が言いたいのか?とそれでも我慢して読み進めていくが、結局陳腐な誰でも知っているような事柄...
期待しすぎたためか、つまらない内容に辟易しながら読み進めた。 まわりくどく、他の事例の引用が長々しい。 演繹法的な説明ではなく、陳腐な帰納法での説明なので、まどろっこしくてたまらない。 結局何が言いたいのか?とそれでも我慢して読み進めていくが、結局陳腐な誰でも知っているような事柄の紹介に終わる。 あまり薦められない本である。
Posted by
面白い観点だと思うし、興味深い点も幾つかあったが、まだまだ未解決の部分も多いのだと分かった。(著者自身がそのようにコメントしているが)
Posted by
原著のタイトルは非常にエキセントリックである。人種・性別などの倫理的な差別問題を超えながら、私たち人間そのものへの理解を行うことに私自身非常に興味がある。内容は生物学的な記述が多く、初学者にとっては少し読みにくいサイエンスエッセイであった。 私たちは、私たちが関わっていること=...
原著のタイトルは非常にエキセントリックである。人種・性別などの倫理的な差別問題を超えながら、私たち人間そのものへの理解を行うことに私自身非常に興味がある。内容は生物学的な記述が多く、初学者にとっては少し読みにくいサイエンスエッセイであった。 私たちは、私たちが関わっていること=人間というものに一番関心があるのだと改めて感じた。
Posted by
大変読みやすい啓蒙書。「ダーウィンが来た」などの動物番組を見ていて、さまざまな動物が繁殖のためにそれぞれ独自の行動を取っていて、おかしな進化をするものだなあと思っているが、実は人間こそ最も奇妙なのではないかと気づかされる。(まあ、ぼくは以前からこの手の本をたくさん読んでいるので、...
大変読みやすい啓蒙書。「ダーウィンが来た」などの動物番組を見ていて、さまざまな動物が繁殖のためにそれぞれ独自の行動を取っていて、おかしな進化をするものだなあと思っているが、実は人間こそ最も奇妙なのではないかと気づかされる。(まあ、ぼくは以前からこの手の本をたくさん読んでいるので、その辺に気づいてはいたんだけど、改めて。) また、「男が力仕事をして女を守り、女は男に守られて子を産み、育てる」というのもどうやら怪しいことが分かってくる。この辺も面白い。 ニューギニアの狩人たちは、大きな獲物を狙って何日も野山を駆け回るが、苦労して倒した獲物は男たちだけで食べてしまい、家族には与えないという。以前に見たNHKのドキュメンタリーで、太平洋でウミガメ漁をしている男たちも全く同じだった。何日も苦労してウミガメを追って手漕ぎのカヌーで海を旅して、やっと捕まえたと思ったら男たちだけで食べてしまう。実際に家族を養っているのは、女たちが採集する植物性の食べ物だ。 人間の男の行動をよく見ると、いかにも大事な仕事をしているようでいて、実は男たちだけの楽しみのための行動であったり、浮気の機会を増やすための行動であったりするようだ。どうも先進国の都市生活でも、似たようなことは行われている気がする。
Posted by
Posted by
この本の初版では、タイトルは直訳で「セックスはなぜ楽しいか」だったそうですから、確かにそのタイトルでは中身を誤解され、手に取ることをはばかる人が多そうです。またはその逆で、HOWTOものと思って期待して読む方もあるかもしれません。 著者はかのジャレド・ダイアモンド氏ですから、そん...
この本の初版では、タイトルは直訳で「セックスはなぜ楽しいか」だったそうですから、確かにそのタイトルでは中身を誤解され、手に取ることをはばかる人が多そうです。またはその逆で、HOWTOものと思って期待して読む方もあるかもしれません。 著者はかのジャレド・ダイアモンド氏ですから、そんなわけはある筈もなく、今回の内容も彼が疑問に思った人間の生殖の仕組みや性行動・男女の役割などに焦点をあてて、色々な研究や仮説を取り上げてきっちり検証するという学術的な中身になっています。彼の疑問は、人間固有の性行動として往々にして繁殖のためではなく、楽しむためにセックスするのはなぜなのか、女性がいつ排卵しているのかわからなくしたのはなぜか、女性が50歳前後で閉経するようになったのはなぜか等、大抵の人があたり前に思っていることを解き明かしていきます。そのために、他の動物の例を取り上げて人間の方こそ奇妙だと、人間中心の考え方が視野を狭くさせていることを指摘しています。 この中で、女性の出産、授乳、子育てなど重要な役割に対して男性の役割の低さが取り上げられているのも興味ある部分でした。「男はなんの役に立つか」というタイトルの章は、著者自身男性として微妙な気持ちだろうと思いました(彼は双子のお父さんでした) その他、文字をもたない社会での老人の役割の重要性が述べてありましたが、現代の高齢社会での老人の役割にも通用するところがあるのではと興味深く読みました。
Posted by
この方面の本はいろいろ読んでいるので、目からウロコ的なものはあまりなかったけどね。で、政府が少子化対策のために婚活に予算をつけるこの国は、もう全然違う方向に進化しちゃってるってことでいいのかね?
Posted by