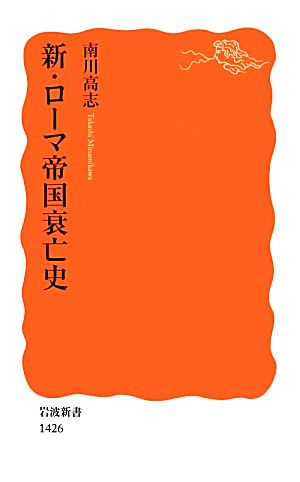新・ローマ帝国衰亡史 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ローマ帝国(西ローマ帝国)の崩壊は、世に言う「ゲルマン人の大移動」が主因ではなく、ローマ帝国自体が時代とともに変容していき、ローマ市民自体の弱体化(権利は主張するが義務は果たさない)、異民族に対する狭量な排斥運動、皇帝(軍隊)間の内紛といったことが重なり自壊したという話。読んでいると今のアメリカを映しているようで、パクスアメリカーナも風前の灯火に思えてきて少々怖い。
Posted by
ローマ帝国が当初、民族の捉え方がフレキシブルで融通性に富み、帝国を発展させる力の一つであったが、東西の分裂、東方民族の侵入への対処に狭小な考え方が入りはじめ、フレキシブルさを失った帝国の未来は暗澹たるものになってしまった。
Posted by
ローマ帝国の崩壊を、人々が「ローマ人である」という誇りを持ったアイデンティの衰退から説明している、と思われる。 人物名が多く、地理に馴染みがなかったので読むのに時間がかかり、理解できた自信はないが、物語の核はとても分かりやすかった。 トップの政策の失敗、汚職により体制が綻び始め、...
ローマ帝国の崩壊を、人々が「ローマ人である」という誇りを持ったアイデンティの衰退から説明している、と思われる。 人物名が多く、地理に馴染みがなかったので読むのに時間がかかり、理解できた自信はないが、物語の核はとても分かりやすかった。 トップの政策の失敗、汚職により体制が綻び始め、人々の生活が立ち行かなくなると「仮想敵」がいると呼びかけて団結を図ろうとする流れは、現代でも見られるだろう。 ローマ帝国の存続は、まさに人の流れに制限がほとんどなく、有能であれば徴用されて、出世ができたという文化にあり、それを自ら狭めてしまったのは生存可能性を自ら低くしてしまう行いであった。 この点は、組織論でも指摘がなされそうな箇所であり、面白かった。
Posted by
地図や系譜図がふんだんに用いられ、年表も付けられているので慣れない人名や地名も混乱せずに読める。さらに欲を言えば、これだけよくまとまった内容なだけに、索引があるとうれしいところ。
Posted by
ローマ史は大好きなテーマの一つなので、大変面白く読めました。まだまだ学問的にこの分野は進んでいきそうで今後の展開が楽しみです。
Posted by
ローマ帝国衰亡の原因を歴史的展開から眺めたら、「ローマ人としてのアイデンティティを失った」ということだそうです。新書を読むような人間にはこれぐらいの説明と結論がちょうどいい、みたいな感じですかね?
Posted by
ギボンのローマ帝国衰亡史も読んでいないし、ローマ帝国の歴史に詳しいわけでもないため、消化不良気味。 ローマ帝国がこんなに広大だったことに驚いた。また、最初は、外れの方は境界が曖昧というかゆるかった、民族という意識がなく、「ローマ人である」という意識で繋がっていた。帝国崩壊の原因は...
ギボンのローマ帝国衰亡史も読んでいないし、ローマ帝国の歴史に詳しいわけでもないため、消化不良気味。 ローマ帝国がこんなに広大だったことに驚いた。また、最初は、外れの方は境界が曖昧というかゆるかった、民族という意識がなく、「ローマ人である」という意識で繋がっていた。帝国崩壊の原因はそのような意識でいたはずの「第3のローマ人」達を排外主義により帝国の中心部から排除しようという動きのせい、など。 現在の日本は大丈夫かな、とつい考えてしまった。 巻末に簡単な年表がついていて、先に気づいていれば、もう少し頭がついていけてたかもしれない、と思いました
Posted by
『ローマ帝国衰亡史』といえばギボンのものが本家本元。その向こうを張って21世紀の衰亡史を書こうというもの。歴史学はその同時代の影響を必ず受けるものだと。もっとも本家は文庫本で全10巻。手軽なところが21世紀的という訳ではなかろうが。 カエサルの時代(前1世紀)、五賢帝時代(2世...
『ローマ帝国衰亡史』といえばギボンのものが本家本元。その向こうを張って21世紀の衰亡史を書こうというもの。歴史学はその同時代の影響を必ず受けるものだと。もっとも本家は文庫本で全10巻。手軽なところが21世紀的という訳ではなかろうが。 カエサルの時代(前1世紀)、五賢帝時代(2世紀)、軍人皇帝時代(3世紀)からまず概観して、コンスタンティヌス大帝、ウァレンティニアヌス朝、東西ローマ帝国分裂(4世紀)、西ローマ皇帝廃位(5世紀)までを扱う。ローマの歴史に詳しくないので、ざっと掴むのにはありがたい記述の分量。 ・ローマ帝国の国境は出入りのルーズな「ゾーン」であった。→昔だしそんなものか。一方、ハドリアヌスの長城なんてあったが。 ・複数の皇帝による分割統治は東西分裂以前、ディオクレティアヌスの治世からあった。→版図が広くなりすぎとはいえ「帝国」のイメージとなんか違う。当時の通信手段は何があったのだろう?駅伝とか狼煙とか。 ・「ローマ人」の概念は版図拡大とともに広がった。ローマの外にいるローマ市民もローマの特定地区に本籍みたいなものを持っていたが次第に名目化した。生粋のローマ人が「第一のローマ人」、植民市生まれが「第二のローマ人」、蛮族出身が「第三のローマ人」。今のような「民族」概念は持っていなかったとされる。ただ服装をローマ風にすることが要求されたりした。 ・蛮族出身者にとってローマ軍への入隊が帝国内の社会階層を上がる典型的なルートであった。ほかに官僚への登用なども。「第三のローマ人」の存在は時の皇帝の重用によるものであり、皇帝権力と密接に結びついていた。→100年以上たっても同化しなかったわけだし、蛮族出身のアイデンティティは保たれていたようだ。 ・ゲルマン民族の大移動が、これまで言われてきたように破壊的なものであったか、それともよりマイルドなものであったかは議論がある。しかし、特定の時期にローマの城砦などが破壊されていることは発掘により明らかになっている。 ・混乱期は皇帝や一族郎党がよく処刑される。北朝鮮か。 著者の主張は、ローマ人アイデンティティの崩壊=偏狭な排外主義がローマ帝国衰亡につながったと読める(あまり因果関係を明示的に主張してはいないが)。しかし因果は逆で、帝国の勢力衰退が排外主義台頭につながったと考えるほうが素直では。
Posted by
・ローマ帝国を実体あるものとしたのは「ローマ人」であるというアイデンティティ。このアイデンティティのもと、外部からの人材を受け入れてきた。しかし、四世紀以降の経過の中で徐々に変質し、内なる他者を排除するようになった。政治もそうした思潮に押し流されて動くことによって、その行動は視野...
・ローマ帝国を実体あるものとしたのは「ローマ人」であるというアイデンティティ。このアイデンティティのもと、外部からの人材を受け入れてきた。しかし、四世紀以降の経過の中で徐々に変質し、内なる他者を排除するようになった。政治もそうした思潮に押し流されて動くことによって、その行動は視野狭窄で世界大国に相応しくないものとなり、結果としてローマ国家は政治・軍隊で敗退するだけでなく、「帝国」としての魅力も威信も失っていった
Posted by
ローマ帝国の拡大路線を支えていたものは、ローマ人ではなく、ローマ市民という意識。 逆にこれが、排他的な意識となり、帝国の衰亡を招いた。
Posted by