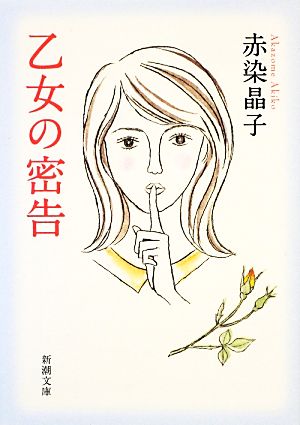乙女の密告 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
テンポがよくユーモアにあふれた文体で書かれている。 人種差別や被差別者のアイデンティティー、何が「他者」を作るのか、「他者になりたい」と思わせる気持ち、噂話や密告を止められない構造、奪われた名前など、短い小説ではあるがいろいろと考えさせられた。 ある外語大では毎年スピーチコンテストが行われる。 みか子ら女子学生「乙女」たちとバッハマン教授は、暗唱の練習を通して『アンネの日記』について学んでいく。 このゼミでは、女子学生たちは「乙女」と呼ばれる。乙女たちはすみれ組と黒ばら組にグループ分けされる。 「乙女」という呼び名やグループ分けそのものにはたいした意味はない。 ひとつの集団に名前がつけられ、さらにグループ分けされることで、彼女たちは「自分たち」の外に「他者たち」を作る。 よそのグループに対する攻撃性をためらうと仲間から排除される。 だから、噂話を聞いたら面白がって同意の意思表示をしなければならない。噂話の拡散、密告といった行動も余儀なくされる。 実際に信じているかどうかは関係ない。そうやって差別や偏見、嘘は大きくふくらみ、行動につながっていく。 人はどんな状況になると差別や噂話に乗ってしまうのか。人の命を奪うとわかっているのに、なぜ密告できてしまうのか。 コミカルに書かれてはいるが、自分は世の中の縮図としてこの部分を読んだ。 第一次大戦ではアンネの父と秘密警察のジルバーバウアーは同じドイツ兵として戦った。 にもかかわらず、ナチの台頭によってユダヤ人たちは「他者」にされ、差別され、密告の対象にもされていく。 ドイツ人やドイツに占領された国の人々は、「他者」になったユダヤ人を密告する。 ジルバーバウアーも「他者」になったアンネたちを逮捕し連行した。 みか子は暗唱の練習をしていて、いつも同じ一文を忘れてしまう。 「今、わたしが一番望むことは、戦争が終わったらオランダ人になることです!」 ペーターは戦争が終わったらキリスト教徒になりたいと言う。アンネも戦争が終わったらオランダ人になりたいと言う。 アンネたちの言葉に対して、安全な立場にいる人が「戦争が終わればなりたいものになれる」と返答することの残酷さを考える。 アンネはオランダが好きだが、ユダヤ人としての自分を捨てたいわけではない。 「他者」になりたいと思わせてしまう何かがあることに敏感でなければならない。 これは21世紀のいまにもいえる。 さまざまな経緯で他国に移住してきた人たちに対して、「国籍を変えればいい」「名前を変えればいい」と簡単に言ってしまう思慮の浅さを考える。 人が「何かになりたい」と言うときに、その言葉の裏には何があるのか。 自発的にそう思っているのか、それとも構造的な何かがあって、そう思うように仕向けられているのか。 このスピーチコンテストでは暗唱するときのルールがある。 暗唱の最後には必ずアンネの名前を言わなければならない。文章を忘れてしまって途中で棄権する場合でも、必ずアンネの名前だけは言わなければならない。 『アンネの日記』は手紙形式で書かれている。そのほとんどが最後に差出人としてアンネの名前が記されている。 ホロコーストによって奪われたのは人命や財産だけではない。名前も奪われた。 異質な存在は「他者」としてひとくくりにされ、一人ひとりは名前を奪われる。 『アンネの日記』は、名もなき人たち全てに名前があったことを後世に伝えた。
Posted by
タイトルの乙女という言葉から、つい少女小説や恋愛小説なのかと推測してしまうが、さにあらず。 学生たちに“メンチ”を切り、怒って教室を立ち去るときは「あたくし、実家に帰らせて頂きます!」と言い放つドイツ人教授や、指にストップウォッチだこができている麗子様などなど、強烈なキャラとそ...
タイトルの乙女という言葉から、つい少女小説や恋愛小説なのかと推測してしまうが、さにあらず。 学生たちに“メンチ”を切り、怒って教室を立ち去るときは「あたくし、実家に帰らせて頂きます!」と言い放つドイツ人教授や、指にストップウォッチだこができている麗子様などなど、強烈なキャラとその言動にゲラゲラ笑ってしまうのだが、読み進めていくと作者の《さあ、ここからが本番やで》という声が聞こえてくるかのように、作者の冷徹な目をもって《真実をみつめよ》と言葉が紡がれていく。 素晴らしい音楽を聴き終えた瞬間、人は深い溜息が出るものであるが、この本を読み終えたとき、同じように深い溜息が出た。 この作者は鬼才である。早世が本当に悔やまれてならない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
舞台は外国語大学。アンネの日記を題材とするスピーチコンテストに向けての、変わり者の教授と女学生たちのドタバタがユーモラスに描かれる。ある事件が起き、自分に関しての悪い噂が飛び交っていることを感じながらコンテストの準備を続ける女学生が追い込まれてゆく状況がアンネ・フランクを想起させる仕掛けになっている。ユーモアとシリアスが重なり合い、サラッと読むとコメディだが丁寧に読むと怖い小説。
Posted by
#12奈良県立図書情報館ビブリオバトル「告白」で紹介された本です。 2012.2.18 http://eventinformation.blog116.fc2.com/blog-entry-748.html?sp
Posted by
初めから真実を知ろうともせずに、皆がやっているから、世間に蔓延っているから、自らは何の疑いも持たず、信念を持たない姿勢に対して、アンネの日記と現代を交錯させて鋭いまなざしで描かれている。 アンネの日記は小学生のころに伝記漫画で読んだのが懐かしく、衝撃が凄かったのを強く覚えている。
Posted by
外大生のスピーチコンテストまでの日々と、アンネの日記に綴られた日々。 忘れてはならないことが何か、真実の追求。
Posted by
⚫︎受け取ったメッセージ 「真実とは乙女にとって禁断の果実だった。」 ⚫︎あらすじ(本概要より転載) ある外国語大学で流れた教授と女学生にまつわる黒い噂。乙女達が騒然とするなか、みか子はスピーチコンテストの課題『アンネの日記』のドイツ語のテキストの暗記に懸命になる。そこには、少...
⚫︎受け取ったメッセージ 「真実とは乙女にとって禁断の果実だった。」 ⚫︎あらすじ(本概要より転載) ある外国語大学で流れた教授と女学生にまつわる黒い噂。乙女達が騒然とするなか、みか子はスピーチコンテストの課題『アンネの日記』のドイツ語のテキストの暗記に懸命になる。そこには、少女時代に読んだときは気づかなかったアンネの心の叫びが記されていた。やがて噂の真相も明らかとなり……。悲劇の少女アンネ・フランクと現代女性の奇跡の邂逅を描く、感動の芥川賞受賞作。 ⚫︎感想 すごい短編小説だった。ユーモアとシリアスをこのように巧みにブレンドし、密告する側とされる側という葛藤と統合を描く。深刻なホロコーストというテーマを自分たちの生活に引きつけて考えることは、普段の生活ではなかなかできない。それを「乙女」な女子大生という「清純」を密告者側とと置きかえ描かれた作品。いつ誰が「乙女」と見なされなくなるか、わからない。 真実は多くの人が夢見ていたい中で隠されなくてはならないものである。 人は同じ美しいと思える幻想をみんなで信じて安心したがる生き物だということを改めて思った。 面白く読ませてくれる漫画風なところがありながら、実はメタファーを盛り込み深いテーマを描いている。ぜひ再読したい。
Posted by
微妙に張り巡らせられた緊迫感と、平の文でたまに登場するおふざけのギャップがとても良かった。読みながら笑ってしまった。 物事を自分の見みたい一側面だけで判断するのは良くないな
Posted by
なんということだろう。 「じゃむパンの日」でファンになり手に取った、赤染さんの数少ない著書。ユダヤ人であることを否定され短い人生を生きた、アンネ・フランクの日記を読み解く女子学生の話だ。 彼女を美化してはいけない。彼女の人生を悲劇だとひと言で済ませてはいけない。ユダヤ人として生き...
なんということだろう。 「じゃむパンの日」でファンになり手に取った、赤染さんの数少ない著書。ユダヤ人であることを否定され短い人生を生きた、アンネ・フランクの日記を読み解く女子学生の話だ。 彼女を美化してはいけない。彼女の人生を悲劇だとひと言で済ませてはいけない。ユダヤ人として生きることを許されなかった人たちの名前。みか子の葛藤はわたしたちが抱えなければならないものでもある。なぜかわたしも、彼女たちと同じ壇上にひとりで立っている。忘れてしまう恐怖を突きつけられて身動きひとつできないでいる。 まばたきも邪魔になるほど物語に入り込んでしまった。 何気なく選んだ本に、こうして現実の目の前に放り出されることがある。 赤染さんは今の世界、戦争をみて、どんな思いでいるだろう。
Posted by
ちょっと特殊の日本語と思います。ドイツ語の特性がミックスされそうです。あらすじより、文字の流れが好きです。
Posted by