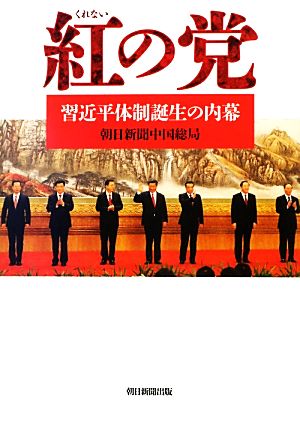紅の党 の商品レビュー
朝日の記者による中国共産党の要人に関する新聞連載をまとめたもの。新聞記事とあって情報が新しく、時宜を得た参考になる内容であった。もちろん内容は、取材から得られた、記者の主観的なものと言えるが、短時間に丁寧に取材されており、中国共産党の一面を理解できた。 「(ワシントンポスト)中...
朝日の記者による中国共産党の要人に関する新聞連載をまとめたもの。新聞記事とあって情報が新しく、時宜を得た参考になる内容であった。もちろん内容は、取材から得られた、記者の主観的なものと言えるが、短時間に丁寧に取材されており、中国共産党の一面を理解できた。 「(ワシントンポスト)中国共産党最高指導部の常任委員9人のうち、少なくとも5人の子供か孫が米国に留学している。習近平の娘、習明沢もハーバード大学に在籍中だ」p84 「不正が発覚しそうになった「裸官」本人が、海外へと逃亡するケースも絶えない。中国社会科学院の調べでは、2008年までの10年余りに海外へ逃れた政府や国有企業などの幹部は1万6000~1万8000人に上り、流出資産は8000億元(約10兆円)に達するという」p85 「オックスフォード大学職員によると、中国政府職員は同大幹部に「中国人学生がもっと勉強するよう指導してほしい」と求めた」p88 「父の重慶市の書記としての年収は、約2万元(約160万円)とされる」p106 「中央から地方に派遣された党高官候補が、地元実力者らを味方にしようとすれば、腐敗や派閥争いに巻き込まれやすい。逆に押さえ込もうとすれば反発を生む。いずれも地方で実績を残そうとする高官候補が陥りがちな落とし穴だった」p179 「中国の最高指導者となって10年間、胡錦濤は江沢民を筆頭とする長老らの影響力に悩まされてきた。乾坤一擲、完全引退という最大の政治カードを切ることによって、胡錦濤は江沢民を道連れにした。現役の最高指導者が、あえて全退という政治カードを切らなければ追い込めないほど、江沢民の影響力が大きかったともいえる」p212
Posted by
中華人民共和国の、というより中国共産党の最近の政治闘争のノンフィクションネタ。特に薄煕来事件を主軸におきながら、現体制と前体制のVIPのエピソードなどを集約している。中国ネタに強い朝日新聞出版なので、独自の切り口・ソースを期待したが、他メディアで知り得た内容のみだったので、残念感...
中華人民共和国の、というより中国共産党の最近の政治闘争のノンフィクションネタ。特に薄煕来事件を主軸におきながら、現体制と前体制のVIPのエピソードなどを集約している。中国ネタに強い朝日新聞出版なので、独自の切り口・ソースを期待したが、他メディアで知り得た内容のみだったので、残念感が残った。ただ、まとめて当該知識を入れたい方にはオススメです。
Posted by
朝日新聞で2012年に三回に分けて特集された中国の新体制(習近平体制)の立ち上げに対する取材結果を一冊にまとめた本。中国ネタに興味がある方であれ既知の情報が多く、とりたてて新しいネタはない(とはいってもこの取材が行われたのは2012年で、僕が読んだのは2014年であるからこういっ...
朝日新聞で2012年に三回に分けて特集された中国の新体制(習近平体制)の立ち上げに対する取材結果を一冊にまとめた本。中国ネタに興味がある方であれ既知の情報が多く、とりたてて新しいネタはない(とはいってもこの取材が行われたのは2012年で、僕が読んだのは2014年であるからこういった評価はフェアではないかもしれない) この本が書かれたきっかけになるであろう薄熙来は日本ではそれほど報道はされていなったかもしれないが、中国では2010年ぐらいからかなり注目をされていたので、正直なところ中国総局といっても現地で報道されている情報とあまり変わらないな・・というのが率直な感想。 現指導者体制がどのようにして出来あがったか・・・ということをコンパクトに把握するには向いていると思う一冊。
Posted by
中国の政治腐敗ジャーナル記事をまとめたもの。 政治腐敗のことはニュース等でよく見るが、特に真新しくも、驚きの話も無く、「うんうんそう言われているよね」と思う。
Posted by
中国も「情報化社会」の中にあるためなのだろうか。かつて「神秘の奥の院」であった中南海の中国指導部の動向が、真偽はともかくだいぶ伝わってきている。 本書は、中国の最高指導部である「習近平体制誕生の内幕」をかなり詳しく伝えている。 しかし、中国の同種情報についての「遠藤誉氏」の...
中国も「情報化社会」の中にあるためなのだろうか。かつて「神秘の奥の院」であった中南海の中国指導部の動向が、真偽はともかくだいぶ伝わってきている。 本書は、中国の最高指導部である「習近平体制誕生の内幕」をかなり詳しく伝えている。 しかし、中国の同種情報についての「遠藤誉氏」の秀逸な考察に比べるとやや不満が残る内容に思えた。 「中国情勢」は連立方程式のように複雑な因子を考察しなければ事実を捉えることは困難であると思う。 本書は「薄熙来」「赤い貴族」「指導者たち」と「人事」を中心として構成しているが、中国においては、「経済」と「政治」を抜きにしては風景が歪むのではないのかとの懸念を持った。 しかし、本書が新聞連載記事が元であることを思うと、新聞で他国の内情についてよくここまでかけたものだとの感想を持った。 やはり、中国は日本にとって、良くも悪くも特別の国なのだろうか。 本書は、中国共産党の内幕の一面を知るという意味で興味深いが、同時に中国をこの一面のみで捉えることはちょっと無理があるのではないかとも思った。
Posted by
習近平体制誕生の内幕との副題ではあるが、その内実までは踏み込まれてはいない。 本書から何となく伝わるイメージは従来より感じているものと大差はない。共産党独裁、一部上層部の腐敗など。
Posted by
薄熙来失脚から習近平体制確立までの経過が分かる本。中国共産党幹部の不正蓄財についても触れられている。良書だと思うが、この本では最近の出来事にしか触れられていない為、中国共産党について知識のない人は『中国共産党 支配者たちの秘密の世界』などを読んでから読むと尚良い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
朝日新聞で連載していた記事をまとめたものだそうで、薄熙来の事件から習近平が総書記に選ばれるまでがリアルタイムで描かれている。 新聞等で断片的にしか読んでいなかったことがまとまるという意味で、よい内容。日本の10倍の人口の国で、トップ7人に入るということがどういう力を持つのか、よく分かる。 やはり腐敗は進んでおり、中国国内でも「裸官」ということがよく言われている。わいろなどで財を成した官僚が、告発を恐れて家族を順次国外に出し、最後は自分一人が国に残る様をいうそうだ。ハーバードやオックスフォードなど、英米の有名校にはこうして国外に先乗りさせられた高級官僚の子弟が多いらしい。
Posted by
朝日新聞中国総局がまとめた本。中国総局長は坂尻信義さん、47歳。若くして総局長なんだなぁ。 先日、中国に出張して、改めてこの国について知らないなと思いなおし、書店で手にした本。概略を知るのにはとてもよかった。薄熙来(Bó Xīlái)、習近平(Xí Jìnpíng)、胡錦濤(H...
朝日新聞中国総局がまとめた本。中国総局長は坂尻信義さん、47歳。若くして総局長なんだなぁ。 先日、中国に出張して、改めてこの国について知らないなと思いなおし、書店で手にした本。概略を知るのにはとてもよかった。薄熙来(Bó Xīlái)、習近平(Xí Jìnpíng)、胡錦濤(Hú Jǐntāo)、温家宝(Wēn Jiābǎo)などの基本的な関係がよく分かった。そして、日本でもそうなのかもしれないが、必ずしも合理的な関係だけで政治が成り立っていないことも理解できた。 薄熙来は重慶で打黒(マフィア撲滅運動)を展開し、市民から支持を得た。薄熙来が政治局常務委員(常委)になって、中国全体の舵取りに加わることを期待した人も多いようだ。ただ、一方では「重慶を支配していたのは、一切の批判を許さぬファシズムだった」とも言われる。「文化大革命が戻ってきた」と感じた人も多い。毛沢東が進めた文化大革命では、儒教もブルジョア的だとされ批判の対象だった。この理由で、現在の中国では道徳面が廃れたと言われるが、薄熙来は文革をモデルにした。文革時代のマイナス面を肌身で覚えている胡錦濤、温家宝は眉をしかめたといわれる。 結局、政治は人がやっていることだ。だから、そこには思惑が絡む。それぞれの国には成り立ちには歴史と文脈があるが、そこに必ずしも合理性があるわけではない。いろいろな関係性から、あるシステムが出来上がって成り立っているに過ぎない。もちろん、中国も例外ではなく、それを理解したうえで、今の中国に興味を持つことが大切なのだと思った。
Posted by
- 1