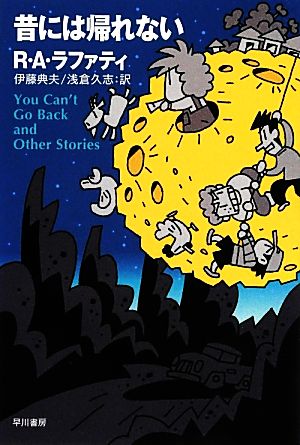昔には帰れない の商品レビュー
「SF界きってのホラ吹きおじさん」ラファティの中短編集。 初期のころに邦訳された品々に比べると、若干インパクトは弱い気がするが、相変わらず気軽に楽しくちょっとヘンな世界に誘ってくれる楽しい作家であることは間違いない。 話の本筋がちょっとヘンなのは勿論、登場人物のモノの考え方や喋り...
「SF界きってのホラ吹きおじさん」ラファティの中短編集。 初期のころに邦訳された品々に比べると、若干インパクトは弱い気がするが、相変わらず気軽に楽しくちょっとヘンな世界に誘ってくれる楽しい作家であることは間違いない。 話の本筋がちょっとヘンなのは勿論、登場人物のモノの考え方や喋り方、あだ名に至るまで、何もかもちょっとヘンなのにそれをさも当たり前のように話を続けちゃうのがラファティ独特のテンポの源泉であるような気がする。 以下、いくつか印象に残った作品について。 『素顔のユリーマ』 世界で随一のポンコツ男性が、己のポンコツゆえに様々な便利品を発明していく。「愚鈍は発明の母」という皮肉の利いたユニークな一品。 『パイン・キャッスル』 怖いね。うん、怖い。 『小石はどこから』 身近な不思議を想像力で膨らませた、何だか牧歌的な一品。作中の「なぜなぜはてな大百科」に載せる珍説もおかしいのに大真面目に取り扱っているシュールな感じが良い。 『そして、わが名は』 もしかしたらあり得たかもしれない創世記。 『大河の千の岸辺』 これは結構正統派の、きれいな流れの短編。蒐集癖のある主人公に妙な共感を覚える。 『すべての陸地ふたたび溢れいずるとき』 ラファティに特徴的な、聖書モチーフのお話。 『行間からはみ出すものを読め』 記録されなかった歴史の、無視できない質量。
Posted by
横田順彌が古典SF研究家として、またハチャハチャSFの書き手として登場してきた頃、彼がはじめてアメリカのSF大会に行った旅行記がSFマガジンに掲載された。その中に、酒に酔って会場を徘徊し、人にぶつかっては「ばーん」といっている、変なぶつかりおじさんの記述があった。それがR・A・...
横田順彌が古典SF研究家として、またハチャハチャSFの書き手として登場してきた頃、彼がはじめてアメリカのSF大会に行った旅行記がSFマガジンに掲載された。その中に、酒に酔って会場を徘徊し、人にぶつかっては「ばーん」といっている、変なぶつかりおじさんの記述があった。それがR・A・ラファティである。(このエピソードは伊藤典夫も記していて、『つぎの岩につづく』のあとがきに再録されている) よく「SFほら吹きおじさん」などと形容され、確かにアメリカのほら話の伝統に乗っているのかも知れないが、しばしばSFかどうかはわからない話で、ときに深遠だったりする。 じゃ、ラファティが好きかといわれると、一歩引く。話がよくわからなかったりするのだ。でも、訳者の伊藤典夫もラファティにはわからないのもあるというのでちょっと安心。 さて、日本オリジナルの短編集である。伊藤典夫が折々に訳したものと、故・浅倉久志が訳したものをまとめて1冊にした。第1部は伊藤典夫が気に入ったもので比較的シンプルな作品。 探検隊がエデンの園そっくりの惑星を見つける。これはすごい観光資源だ、むしり尽くしてやるとビジネスの話になる。他方、「エデン」側、やってくるであろう大量の観光客から略奪してやろうと画策。探検隊側も騙されていない。武装護衛隊をつけよう。ところがオチは「ある意味では、あれは楽園だったよな」。まるで落語なその理由。「楽園にて」。 「昔には帰れない」、これは表紙イラストの通り。子どもの頃、小さな月を笛で呼び寄せて、そこに渡って遊んだ仲間が大人になってから再訪する話。顛末はみんな知っている通り。 冒頭の「素顔のユリーマ」はヒューゴー賞受賞作品としてラファティのバイオグラフィによく出てくる作品だ。 第2部は伊藤曰く「ちょっとこじれているかなあと思う作品」と浅倉訳の長めのもの。 むかしアメリカではサーカスなどに「世界一長い絵」という見世物が展示されたらしい。そんなものがネタにされる時点で、日本の読者にはもうちょっと入りこみがたい「大河の千の岸辺」。その絵を集める男。そしてその川の絵を拡大するとどこまでも拡大可能で細部が見えてくる。ただの絵じゃない。これは何だ。(オチはネットで「蹄状紋と渦状紋」を検索しなければわからなかった……) 伊藤典夫の理解にあまるという「1873年のテレビドラマ」。ドイツでテレビが発明される前、アメリカでテレビを発明し、テレビ放送までしていたオーレリアン・ベントリーという男がいる。彼には13本のテレビドラマがある。彼の受像機を入手したが、セレンの発光を利用したこの機械は、セレンの発光の遅さから、スロー・ライトという特性があり、受像機にはこのため13本のテレビドラマが残存しており、再生を繰り返すたびに鮮明化し、さらになかったはずの音声までスロー・サウンドとして入ってくる。ではその13作を順に紹介しよう。 ということで、13編のテレビドラマの筋が述べられていくが、そこに劇外のベントリーと主演女優の痴話が混ざり込んでくる。で、何なの?という感想になるけれど、それを言ったらラファティなんて多かれ少なかれそんなもん。
Posted by
ほら吹き爺さんラファティの日本オリジナル短編集。伊藤典夫のあとがきもあるけれど、キリスト教に疎い人間にはわかりにくい作品もある。でも、それでもあのとぼけた感じの語り口は好きだなあ。「素顔のユリーマ」「ぴかぴかコインの湧きでる泉」「大河の千の岸辺」「一八七三年のテレビドラマ」が特に...
ほら吹き爺さんラファティの日本オリジナル短編集。伊藤典夫のあとがきもあるけれど、キリスト教に疎い人間にはわかりにくい作品もある。でも、それでもあのとぼけた感じの語り口は好きだなあ。「素顔のユリーマ」「ぴかぴかコインの湧きでる泉」「大河の千の岸辺」「一八七三年のテレビドラマ」が特にお気に入り。
Posted by
『素顔のユリーマ』が一番笑った。あとは、うーん・・・? 面白くなくはないんだけど、とらえきれなかった。
Posted by
「素顔のユリーマ」、「月の裏側」、「楽園にて」、「パイン・キャッスル」、「ぴかぴかコインの湧きでる泉」、「崖を登る」、「小石はどこから」、「昔には帰れない」、「忘れた偽足」、「ゴールデン・トラバント」、「そして、わが名は」、「大河の千の岸辺」、「すべての陸地ふたたび溢れいづるとき...
「素顔のユリーマ」、「月の裏側」、「楽園にて」、「パイン・キャッスル」、「ぴかぴかコインの湧きでる泉」、「崖を登る」、「小石はどこから」、「昔には帰れない」、「忘れた偽足」、「ゴールデン・トラバント」、「そして、わが名は」、「大河の千の岸辺」、「すべての陸地ふたたび溢れいづるとき」、「廃品置き場の裏面史」、「行間からはみだすものを読め」、「一八七三年のテレビドラマ」 そこまで印象に残るものがなかった。 表題作の「昔には帰れない」は、幼い頃の空想かと思いきやそこはラファティなんだなあ、と思った。よりどうしようもない感覚。 「小石はどこから」がどう考えても小粒な話なんだけど、なぜか記憶に残っている。ほんとにタイトル通りの話。
Posted by
SFホラ吹きオジさんの短篇集。あとがきにあるように伊藤訳の作品群は比較的わかりやすいものが多く、浅倉訳のそれらには難解で衒学的で理解不能な傾向がありました。想像力がおいてけぼりを食らう酩酊感はラファティならではの醍醐味だと思います。
Posted by
SFというより、話の上手なお祖父ちゃんが、孫を寝かしつけるために語ったお伽話のよう。 そんな印象を抱くのは、小話のところどころに、どこか不可思議なワクワク感と秘かな道徳的側面を感じるからかもしれません。 (なかには読者を突き放したような作品もありますが…それもまた味を感じさせます...
SFというより、話の上手なお祖父ちゃんが、孫を寝かしつけるために語ったお伽話のよう。 そんな印象を抱くのは、小話のところどころに、どこか不可思議なワクワク感と秘かな道徳的側面を感じるからかもしれません。 (なかには読者を突き放したような作品もありますが…それもまた味を感じさせます) だからかどうかは定かではありませんが、伊藤典夫氏が本書を詩的に表した次の一文に得心の一言。 「望遠鏡を逆さまにのぞくようなもので、たいした収穫はないだろうが、レンズの向こうになにやら別の世界があることは納得できるはずだ」 本書は2部構成になっています。 伊藤氏曰く、1部は彼が気に入るシンプルな小品で、2部はちょっとこじれた作品群。 たしかに1部のほうが読みやすいですね。 「素顔のユリーマ」とか「月の裏側」、「小石はどこから」、「昔には帰れない」といった本書でもお気に入りの作品はこちらに分類。 2部では、「忘れた義足」、「そして、わが名は」、「大河の千の岸辺」、「廃品置き場の裏面史」あたりがおすすめ。 「笛の音によって空に浮かぶ不思議な”月”。その”月”にときめいた子供時代の日々は遠く……」 表題だけでノスタルジアを覚える「昔には帰れない」は、上述の裏面の紹介文も良い感じ。 そして、本作最後の一文に、ふと考えさせられる素敵な作品です。 大きな感動も感心する結末もありせんが、心のどこかを刺激する本書は、これもまた読書の楽しみだと、悦に浸ることができるかもしれません。
Posted by
滅茶苦茶面白い。前半のみじかめのお話はわりとわかりやすい。「崖を登る」「小石はどこから」「昔には帰れない」あたり大好き。 後半は少しながめのお話。「忘れた偽足」「大河の千の岸辺」「1873年のテレビドラマ」はわかりやすく面白い。私は「すべての〜」「行間から〜」がちょいわかりづらく...
滅茶苦茶面白い。前半のみじかめのお話はわりとわかりやすい。「崖を登る」「小石はどこから」「昔には帰れない」あたり大好き。 後半は少しながめのお話。「忘れた偽足」「大河の千の岸辺」「1873年のテレビドラマ」はわかりやすく面白い。私は「すべての〜」「行間から〜」がちょいわかりづらくて、「廃品置き場の裏面史」はこの読みでいいのかな〜 結末はわざと曖昧なのかな〜 と悩みます。 みなさんどう読んだのかな〜?
Posted by
十数年ぶりに出たラファティの短編集.第II部は難解だけど,これがラファティの本質かもしれない.「大河の千の岸辺」や「全ての陸地ふたたび溢れいづるとき」なんかの奇妙な風合いは,ラファティ以外の何者でも無い.帯の「抱腹絶倒」というコピーに惹かれて買った人は,戸惑うんじゃ無いかな.
Posted by
- 1
- 2