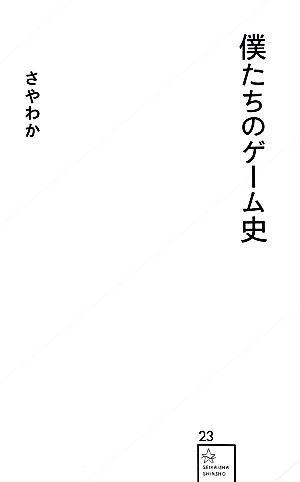僕たちのゲーム史 の商品レビュー
読み終わりました。本当にゲーム史という題名に恥じず、70年台後半から現在まで語られています。こういった物では省かれやすい美少女ゲームもノベルゲームとしてトゥーハート、月姫、ひぐらし、そしてYU-NOと取り上げてくれていたのが好印象でした。もちろんスト2やドラクエ、beatmani...
読み終わりました。本当にゲーム史という題名に恥じず、70年台後半から現在まで語られています。こういった物では省かれやすい美少女ゲームもノベルゲームとしてトゥーハート、月姫、ひぐらし、そしてYU-NOと取り上げてくれていたのが好印象でした。もちろんスト2やドラクエ、beatmaniaとその他のジャンルも抜かりなくとりあげています。 作者の主観は極力省いて昔の開発陣のインタビューから抜粋していく書き方なので非常にフラットに読むことができます。 もし次作があるなら作者自らからの開発陣へのインタビューなどが入っているともっと楽しめそうですね。
Posted by
びっくりするほど著者の感情を捨ててゲーム史を書き抜いた本。 扱っている範囲は主にスーパーマリオ発売(1985年)から現代までがメインストーリー。ただ70年代後半と80年代前半のことも結構書かれています。 発売当時のゲーム雑誌のレビューや作者へのインタビューの引用が多く、どうい...
びっくりするほど著者の感情を捨ててゲーム史を書き抜いた本。 扱っている範囲は主にスーパーマリオ発売(1985年)から現代までがメインストーリー。ただ70年代後半と80年代前半のことも結構書かれています。 発売当時のゲーム雑誌のレビューや作者へのインタビューの引用が多く、どういったことを考えてゲームが開発され、プレイヤーに受け入れられていったのか?ということが追体験できます。 たとえば、スーパーマリオはアクションとしてではなく、アドベンチャー、世界に隠された謎を暴くというゲーム性が売りでした。どういった時代背景でそのように売りだされたのか?今ではなぜ考えが変わってしまったのか?ということがよく分かります。 なお、家庭用ゲームだけでなく、アーケードゲームやパソコン用ゲーム(戦略SLGからギャルゲー、MODや同人ゲまでかなり横断的です)、日本と海外の事情など、できるだけ網羅的にゲーム史を語ろうとしている著者のこだわりには脱帽しました。 かなり内容を削ったそうですが、それでも330ページほどあります。ゲーム史は歴史が浅く、ほとんどの文献もゲームそのものも手に入りますし、自身で体験していることも多いのでここまでのボリュームになったのですね。 ゲームはもうやってないけど、昔はよかったなあという懐古主義に浸るのにも最適です。 これからも、みんなが疎み軽んじるようなところにスポットを当てることで、ゲーム業界は発展していくのでしょうね。30年前、信長の野望が史実を無視する内容でもヒットしたように、15年前、音楽をやらない人でもビートマニアはプレイしたように、今、モバゲーGREEが携帯を使うことで学生を取り込んだように。
Posted by
コンピューターゲームについて、「ボタンを押すと反応する」「物語をどのように扱うか」というポイントから、過去30年くらいの流れを書いたもの。懐かしいゲーム名がたくさん出てきた。懐かしい人物名もたくさん出てきた。
Posted by
ページ全面ギリギリまで組まれていて,とても読みづらい。 文は平易なんだけど,読みづらい。 わざとこういう風に組んだのかなー。 内容はおもしろかったです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ゲーム史ときいて百科事典的な網羅性を求める人には物足りないのだろうけど、「ボタンを押すと反応するもの」という定義と「物語をどのように扱うか」という2つを軸に海外の事情も含めてテレビゲームがどのように変遷してきたのかを見る、という独自性の高い考察が展開されていました。結論非常に面白かったですし、さらにもっと広く深く読ませてほしいと思ったぐらいです。
Posted by
面白かった。続きが読みたくて現代に近づくのが物足りなく感じた。ただゲームをやっているだけでは知らなかったゲーム開発側の意図や戦略、それが実際にどういう評価を得たり、後続作に影響を与えたりしたかなど。
Posted by
すごく面白かったけど、もう少し人物に焦点を当ててあると個人的には読んでて楽しかったのかも。でも、それだと「僕たち」のゲーム史的には外れることになるのかも知れないけど。「僕たち」とタイトルに謳ってあるからには、主観的な思い入れの深い、ゲーム史が語られるのかと思いきや案外と冷静な文章...
すごく面白かったけど、もう少し人物に焦点を当ててあると個人的には読んでて楽しかったのかも。でも、それだと「僕たち」のゲーム史的には外れることになるのかも知れないけど。「僕たち」とタイトルに謳ってあるからには、主観的な思い入れの深い、ゲーム史が語られるのかと思いきや案外と冷静な文章。
Posted by
"僕たちのゲーム史"さやわか著 星海社新書(2012/09/25発売) ・・・1980年前後からのゲーム史。ゲームの拡張期、アドベンチャー・RPGの成り立ち、シュミレーションゲームの成り立ち、ゲームセンターの遷移、CDロム戦争、物語の扱い、コミュニケーション要...
"僕たちのゲーム史"さやわか著 星海社新書(2012/09/25発売) ・・・1980年前後からのゲーム史。ゲームの拡張期、アドベンチャー・RPGの成り立ち、シュミレーションゲームの成り立ち、ゲームセンターの遷移、CDロム戦争、物語の扱い、コミュニケーション要素、海外・ネトゲ、ソーシャル・カジュアルゲームの台頭、そして未来。 個々のゲームについての語りはわずかでどちらかというと、ゲーム業界全体について・ゲーム会社・製作者の志向性などについて重点が置かれているように感じました。 ・・・ゲームの歴史を認識したい方や、80年代・90年代を懐かしみたい方におすすめかと。
Posted by
大きな流れがあった97年に僕は高校一年ぐらいで確かFF7はジャンプの懸賞で当たって発売日とかに来たんだけどプレイしてもどうものれなくて友達に売ってしまった記憶がある。僕が家庭用ゲームから離れたのはその頃だった。 実際に新しいハードを買ったのは『MOTHER3』がやりたかったから...
大きな流れがあった97年に僕は高校一年ぐらいで確かFF7はジャンプの懸賞で当たって発売日とかに来たんだけどプレイしてもどうものれなくて友達に売ってしまった記憶がある。僕が家庭用ゲームから離れたのはその頃だった。 実際に新しいハードを買ったのは『MOTHER3』がやりたかったからで、それ以外に新しいソフトも買った記憶はない。ただ十年前の状況時にゲーセンでバイトしてて格ゲーやったり出たばかりのWCCFが賑わっていてサッカー好きじゃないけど対戦とカード集めでかなり熱中したのを思い出す。 数年前に小学生時代にやったファミコンソフトを懐かしんで買ってプレイしたのは懐古からだが正直ゲームとして楽しかった。今のゲームのグラフィックとか映画的なムービーに乗れないのは97年当時から映画館で映画を観るようになったからというものあったのかもしれない。 ゲームはゲームとしての面白さが、映画は映画としてのみたいな。ゲームがゲームという部分よりも他の部分に凝り始めて去って行った人間としてはこの本に書かれている97年以降のことは身近でありながら体験しなかったことなので新鮮でもあった。 格ゲーにしろWCCFのようなアーケードゲームは他者とのコミュニケーションがあったからまだハマったのだろう、そこでの人との関わりにゲームが介在していたから。 この新書は今までゲームをしてなくても問題なく読めるように書かれている。このゲームに置ける歴史は他の分野とも呼応している。僕らが生きてきた時代の中でそれは社会の変化や経済や新しいテクノロジーと共に移りゆくから。 ゲームから遠く離れているけど読む事でいろんなジャンルの事を考えるきっかけにもなる。こういうある特定のジャンルについてきちんと書かれている本が様々なジャンルであるともっと多角的に総合的にものごとを見る目ができるのだろう。 僕が次に新しいハードを買う時はやっぱり『MOTHER4』が出るときぐらいかなw
Posted by