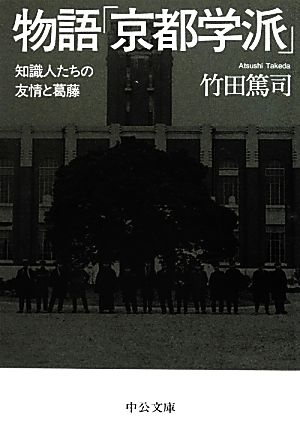物語「京都学派」 の商品レビュー
西田幾多郎を中心とする京都学派の解説書や研究書は数え切れないほどあるが、彼らの哲学や思想そのものではなく、その人間関係にスポットを当てた書物は意外に少ない。本書は西田の高弟である下村寅太郎の書簡を中心に、これまで紹介されることのなかった興味深いエピソードを交えて、日本哲学史上極め...
西田幾多郎を中心とする京都学派の解説書や研究書は数え切れないほどあるが、彼らの哲学や思想そのものではなく、その人間関係にスポットを当てた書物は意外に少ない。本書は西田の高弟である下村寅太郎の書簡を中心に、これまで紹介されることのなかった興味深いエピソードを交えて、日本哲学史上極めてユニークな思想山脈を形成した哲学徒達のドラマを綴ったものである。 京都学派の形成にあたって西田の強烈な個性の果たした役割は言うまでもないが、中でも著者は西田の人事の「妙」を強調する。波多野精一やのちの田辺元のような自己の批判者を迎え入れ、和辻哲郎や九鬼周造といった東大出の異色の人材を主要ポストに抜擢するとともに、一方で卒業生の俊秀を内部に送り込むという配慮を怠らなかった。外部の批判や異質性への開かれた風土と、師弟関係を軸とした濃密な人間的結び付きを両立させたところは、あらゆる組織に通じる成功の秘訣でもあるだろう。学派というとボス教授を中心としたムラ社会的なイメージが先行するが、西田と田辺の熾烈な論争や、弟子の下村寅太郎や西谷啓治が師の西田に与えた学問的影響をみれば、それが京都学派と無縁であったことが分かるだろう。 京都学派と言えば西田と田辺の学問的対立が注目されがちだが、見逃せないのは、西田に代表されるSelbstdenken=「自己自身の哲学」を重んじる狭義の京都学派(当然田辺もその一員である)と、波多野精一、山内得立、田中美知太郎といった古典文献学の伝統に忠実なグループとの、思想的というより方法論上あるいはスタイルの対立である。波多野は「西田君のような学問は一夜漬けが出来るが、僕のはそうはいかない」と言い放ち、田中は「ハイデガーによって示唆された時間の問題」を「私の立場で考え」「私の言葉で語った」梅原猛の卒業論文を「心境小説だね」と酷評した。戦後西田の高弟達が公職追放された後、京大哲学科を再建した山内得立はあくまで地味な哲学史研究を重視した。それが厳密な原典研究の成果を着実にもたらす一方で、思想的な華々しさではむしろ東大にお株を奪われた感があり、評者のような西田びいきの素人哲学ファンは一抹の寂しさを禁じ得ない。 本書で紹介されるエピソードの中で個人的に最も興味深かったのは、西田の最大の批判者であった田辺が、最後の病床で弟子の大島康正にやっぱり自分が間違っていたと告白したという話である。大橋良介は全ての西田批判は基本的には田辺の批判で言い尽くされていると言っているが、その田辺が最後に兜を脱いだということだ。田辺の西田批判の上っ面をなぞった議論が今も横行しているだけにこの事実は重要だ。西田哲学は決して「乗り越えられた」過去の哲学などではないと思う。
Posted by
たくさんのエピソードを集めて紹介してくれる労作。ここに出てくる人たちの学問への情熱の高さが、読んでるこちらにもうつってくる。自分ももっと勉強しようという気持ちになれる。(2015年4月12日読了)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2012年(底本2001年)刊行。既に逝去された著者は元明治大学教授。 15年戦争期、京都大学には西田幾多郎を頭に戴く哲学研究の花が咲いていた。本書は、西田とその後継たる田辺元を軸に、戦前昭和~戦後直後の京都大学哲学科に関わった研究者の合従と相克、そしてその生臭い人間的な裏面を解読しようと試みる人物評伝である。 余り関心を持っていない領域であるが、少なくとも彼等の著作の字面からは見えてこない内なる声と、彼らの関係性を上手く拾い上げているので、評伝としては抜群に出来栄えの良い作と感じられる。 ここで書かれるように、研究者間の蜜なる関係性が京都大学の学風を作り上げ、それは東大とは異質なもの、という観点からも、かの大学の独自性を感じ取れる一書とも言えそう。
Posted by
西田幾多郎を中心として戦前の京都帝大に集った知識人・学徒たちのドラマを描く。京都帝大の成り立ち、西田が京大に招かれるまでの経緯、西田とその周りに集う個性豊かな哲学徒たちの活躍、戦争とのかかわり、戦後の田辺元と野上弥生子の関係などに論及し、最後に京都学派を成立させた要因が考察される...
西田幾多郎を中心として戦前の京都帝大に集った知識人・学徒たちのドラマを描く。京都帝大の成り立ち、西田が京大に招かれるまでの経緯、西田とその周りに集う個性豊かな哲学徒たちの活躍、戦争とのかかわり、戦後の田辺元と野上弥生子の関係などに論及し、最後に京都学派を成立させた要因が考察される。 いくつか確認しておこう。まず、本書は西田を中心とした哲学系の動向を論述の中心としている。京大東洋学に言及する箇所は一応あるが主題ではなく、その他の領域も対象としていない。戦後のいわゆる「新京都学派」についても同様である。次に、本書タイトルに「物語」とあるが、小説の類ではなく、事実にもとづいて構成される。とはいっても、登場人物たちの研究内容に踏み込んだ記述がなされるわけではなく、あくまでも彼らの人間関係・ドラマを扱うものなので、読み通すのに特別な知識は必要としないだろう。 様々なエピソードで彩られた本書は、漫然と読んでいるだけでも十分面白い。ただ、本書は現代に対して重要な問いを発してもいる。それは、人文的な知を成立させる「場」とは何か、という問いである。著者・竹田は本書のエピローグ「『ネットワーク』としての『京都学派』」で、「京都学派」の成立・持続の動因として、1.西田ら中心メンバーの世代的特殊性、2.西田・朝永三十郎による「人事の妙」、に加え、3.当時の京都の空間的狭さおよび大学における学生数の僅少、そしてそこから生まれる濃密な人間関係、を挙げる。今日の人文知の困難を考える時、重要なのは3点目、一言に集約するなら「場」の問題であろう。今日、大学は大衆化して久しい。教授や講師は遠隔地から「通勤」するのが当たり前。濃密な人間関係は望むべくもないし、そもそも新自由主義の波にあらわれて、文学部の存立自体が危うい時代である。大学における人文知の存続・発展は困難に直面している。では、我々はどの「場」にそれを求めればいいのだろうか……。 それにしても、91~92頁に引用される唐木順三の文章、「読者諸君、こころみにこういう情景を頭に浮べてみたまえ。」と始まる、西田が定年退官間近だった時期の京大哲学科の風景の活写は圧巻である。講義に臨むべく西田が錚々たる助教授陣を引き連れ教室に入っていく。それに合わせ京都の各大学で活躍する新進気鋭の学者たち、いずれ名を馳せるであろう学生たちが教室に詰めかける。逐一名前が挙げられていくその面々の豪華さと言ったら。 すでに遠い過去の話である。だが、かつてこの国でこのような光景が繰り広げられていたことを、我々は記憶しておくべきだろう。
Posted by
竹田篤司『物語「京都学派」 知識人たちの友情と葛藤』中公文庫、読了。京都学派の哲学者たち五〇余人人間模様を膨大な資料から描き出す労作。近代知性の師友や人間関係の葛藤と友誼の足跡を生き生きと伝えてくれる。期待せず読んだためか、その息吹は面白かった。叢書の文庫収録化。 筆者は学派の...
竹田篤司『物語「京都学派」 知識人たちの友情と葛藤』中公文庫、読了。京都学派の哲学者たち五〇余人人間模様を膨大な資料から描き出す労作。近代知性の師友や人間関係の葛藤と友誼の足跡を生き生きと伝えてくれる。期待せず読んだためか、その息吹は面白かった。叢書の文庫収録化。 筆者は学派の成立しなかった東大と対比的に描きながら、京都学派の成立与件に言及するが、京都という学的空間の濃密さには驚いた。また以外にも本書の主人公は田辺元。本書で初めて知るエピソードも多い。 近代国民国家は所与の関係を分断することで成立する。全国から集まった世界視野の英才が、しかしながら狭い人間関係の中で……つまり反都市的……生成されたことはアイロニカル。物語風一書ながら考えさせられる。
Posted by
- 1