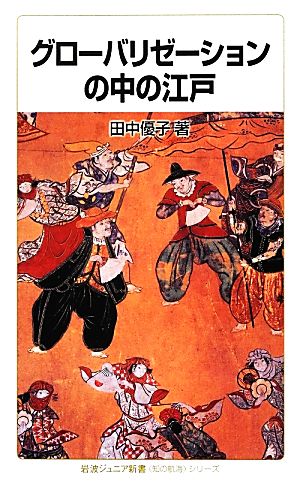グローバリゼーションの中の江戸 の商品レビュー
読みやすかったけど内容がつまらなかった 江戸時代の物流とか交易の話 今のグローバリゼーションはここが原点だったんだなって感じ
Posted by
面白かった。 同じジュニア新書の砂糖の世界史と対になっている。 銀、鉄砲、砂糖、木綿、磁器、これらがいかに世界をかえたのかよく分かる。 ものの本、呉服の由来もはじめて知った。 明治以降の日本のやり方への批判も。 秀吉が東アジアにやったことも大きさよ、、、。 日本が東アジアの...
面白かった。 同じジュニア新書の砂糖の世界史と対になっている。 銀、鉄砲、砂糖、木綿、磁器、これらがいかに世界をかえたのかよく分かる。 ものの本、呉服の由来もはじめて知った。 明治以降の日本のやり方への批判も。 秀吉が東アジアにやったことも大きさよ、、、。 日本が東アジアの一員であることを今後も考えながらいかなくては。
Posted by
江戸時代を多少賛美し過ぎているきらいはあったが全体に面白かったと思う。個人的には、本の中で取り上げられた「江戸時代のファッション」「浮世絵」などが、初めて知る知識が多かったこと、それと教科書で見たことのある写真をふんだんに使われつつ教科書とは全く異なるアングルから書かれていたため...
江戸時代を多少賛美し過ぎているきらいはあったが全体に面白かったと思う。個人的には、本の中で取り上げられた「江戸時代のファッション」「浮世絵」などが、初めて知る知識が多かったこと、それと教科書で見たことのある写真をふんだんに使われつつ教科書とは全く異なるアングルから書かれていたため、とても興味惹かれた。 一番の良かったのは江戸時代に限らず広い観点から「グローバル化」「グローバリゼーション」を考え直すきっかけになったことだったのでないかと思う。 「グローバリズム」とはどういった概念なのか?から始まり、ジュニアにもわかる言葉で簡潔に説明した上で、良い点悪い点をハッキリ掲げている。 江戸文化をグローバル化の観点から見直すことで、「グローバル化」そのものが、曖昧模糊としたものから少しずつ形が見えてきた感覚だった。 日本はアジアをはじめ世界各国と繋がっており、どうしたって相互に影響し合っているのだろう。 歴史の勉強を始めたばかりの方や、ジュニアの方には良い本ではないかと思う。教科書に書かれた歴史とは違う観点を知る意味で。歴史は多角的に捉えられるということ・多角的に捉えるとひとつの歴史的事実の認識がもともとあったものとは異なってきたり、より深みを増してくるという事を知る、という意味で。
Posted by
江戸時代は世界のグローバリゼーションの中で出現した。また、「江戸時代は庶民も外国の文物に触れる機会も多く、それによって江戸文化も成熟していった」という考え。 前半は退屈だか、後半の3章、4章は秀逸だと思う。後半だけでも読んでみるては?
Posted by
前半は目からウロコの連続。縞模様の語源は「島=インド」の模様だとか、八重洲の由来はヤン・ヨーステンだとか、人に話したくなるウンチクが満載で。 後半はいまいち読むのがつらかったな。「鎖国」という言い方がいかに的をはずしているのかはよくわかったけど、秀吉への評価は一方的で一面的だと思...
前半は目からウロコの連続。縞模様の語源は「島=インド」の模様だとか、八重洲の由来はヤン・ヨーステンだとか、人に話したくなるウンチクが満載で。 後半はいまいち読むのがつらかったな。「鎖国」という言い方がいかに的をはずしているのかはよくわかったけど、秀吉への評価は一方的で一面的だと思うし、朝鮮出兵への断罪の仕方も近視眼的であるように感じた。いや断罪はいいんだけど、あれを断罪するなら、元寇はどうなんだとか、もうちょっと広い視野からの批判が必要であるように思う。 あと明らかに経済を敵視しちゃってるところも引いちゃう。経済を重視するってのは「贅沢を尊ぶ」みたいなのとは別次元のはずなんだけど、その辺の批判の仕方が荒い。 ま、とはいうものの、全体的には「読んでよかったな」と思います。レンズの語源はレンズマメってことが知れたし。
Posted by
田中優子著『グローバリゼーションの中の江戸』. 大航海時代を経て、我が国は世界史と接触をもつ時代がはじまる. 科学技術の発展は、航海術など諸科学の機能のうえに、アジアとヨーロッパが<海洋>でつながる時代にはいる. グローバリゼーション.地理的空間を圧縮する...
田中優子著『グローバリゼーションの中の江戸』. 大航海時代を経て、我が国は世界史と接触をもつ時代がはじまる. 科学技術の発展は、航海術など諸科学の機能のうえに、アジアとヨーロッパが<海洋>でつながる時代にはいる. グローバリゼーション.地理的空間を圧縮する.そのために異なる文化、利用不可能が活用可能となる. 資することもあればと利点をあげ、かえす論理で競争、不幸、植民地化、アメリカ化と不平等を示す. グローバリゼーションは、生活・文化・習慣にも変革をもたらし、受容のうえに<主体性>を試される. 変革と受容に政権と庶民.どちらが利点の恩恵に浴し、どちらが利益を提供する役割を担うか. そこを緻密に問い直そうとするかの感が、行間にうかがわれる. グローバリゼーションは必然.その時代に生きることを否応なく求められている若者に、試金石を示すということのようだ.(岩波書店 2012年)
Posted by
岩波ジュニアー文庫という洗脳教科書では 見ることのできない角度から 若者に向けた世界史の中のニホンを浮き彫りにする 特に《鎖国》と呼ばれている江戸前後を解剖する 鎖国はむしろ江戸以前であって 江戸は自主的に管理しながら 海外情報と貿易を庶民の目線で広めていることを 独特の視点か...
岩波ジュニアー文庫という洗脳教科書では 見ることのできない角度から 若者に向けた世界史の中のニホンを浮き彫りにする 特に《鎖国》と呼ばれている江戸前後を解剖する 鎖国はむしろ江戸以前であって 江戸は自主的に管理しながら 海外情報と貿易を庶民の目線で広めていることを 独特の視点から解き明かしている その証拠として現代のお祭りでも ポルトガル人や挑戦や琉球からの使節団に扮した 仮装行列がアチラコチラで行われているというし 浮世絵やファッションや食器やメガネなどの技術を通して あるいは政治や経済や侵略戦争を通して 人間の悪行と成長を紐解いて行く 経済を江戸では《経世済民》と呼び 世を営むことで全ての人や自然を救済することを 意味したという GDPとは無関係に暮らしを過不足なく豊かにする グローバルに生きるということは 力尽くの大国に従って真似することでなく 地域ごとの特色を活かしながらも 世界の中から可能性を選び出して補い合うということだと
Posted by
グローバリゼーションの功罪を問う。 リサイクル時代江戸を賛美しすぎるきらいはあるが世界中が消費社会と化した現代に一言物申した本であり青少年のみならず大人も読むべきである。
Posted by
江戸時代、日本はみずから「鎖国」の道を選び、長崎の出島でのみ細々とオランダ、中国と貿易を行っていたとするのが、従来一般の江戸幕府に対する外交観だろう。1492年にコロンブスがアメリカに到達し、その後の南アメリカでの銀山開発、鉄砲の伝来と国内生産、秀吉の朝鮮侵略、そして家康の江戸幕...
江戸時代、日本はみずから「鎖国」の道を選び、長崎の出島でのみ細々とオランダ、中国と貿易を行っていたとするのが、従来一般の江戸幕府に対する外交観だろう。1492年にコロンブスがアメリカに到達し、その後の南アメリカでの銀山開発、鉄砲の伝来と国内生産、秀吉の朝鮮侵略、そして家康の江戸幕府。こうした一連の流れの中で、16世紀以降の日本はグローバリゼーションに巻き込まれ、やがてそのことを自覚し、転換していった歴史だと捉え直す。しかも、本書の目的は現代の日本が真にグローバルであることの意味を問いかけることにあった。
Posted by
江戸時代は鎖国の時代? なぜ、「鎖国をしていた」「開国した」ということになったのか。教科書で習ったことを、疑わないまま、それを常識として知識にしている。それが危険だな、と思った。学校で習ったことが、すべて本当ではない。江戸の文化についても、なかなか面白かったけど、それに加えて、...
江戸時代は鎖国の時代? なぜ、「鎖国をしていた」「開国した」ということになったのか。教科書で習ったことを、疑わないまま、それを常識として知識にしている。それが危険だな、と思った。学校で習ったことが、すべて本当ではない。江戸の文化についても、なかなか面白かったけど、それに加えて、「鎖国」「開国」「日本」などのことばをどういう立場で使うのか、という視点でも面白かった。 グローバル、ということばを、世界均質化、と捉えてはいけない。どこか大きくて強い(と思われる)国を真似すればいいってもんじゃない。
Posted by
- 1
- 2