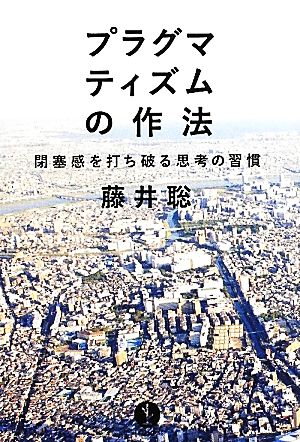プラグマティズムの作法 の商品レビュー
工学系の筆者が描く一風変わった哲学書であるが、例も分かりやすく、論旨が掴みやすい(語り口調でもある)。 プラグマティズムとは、道具主義、実用主義と訳される。ジェームズによると、その格率とは、対象物の概念をとらえるにあたり、その及ぼす効果について考えよ、と。 またプラグマティズム...
工学系の筆者が描く一風変わった哲学書であるが、例も分かりやすく、論旨が掴みやすい(語り口調でもある)。 プラグマティズムとは、道具主義、実用主義と訳される。ジェームズによると、その格率とは、対象物の概念をとらえるにあたり、その及ぼす効果について考えよ、と。 またプラグマティズムの作法を持つには、①何かに取り組む際に、その取り組みの目的について考え、②その取り組みが”お天道様”に恥ずかしくないものであるか常に意識せよ、と。 以後、話は経済論、都市工学論と続いていく。 それにしても、三方良しの精神が欠如しているとマックに対する批判は強烈だった。マックを食べ続けたらどうなるか、なんて映画もあったのか・・・
Posted by
アメリカの学者、パース、ジェームス、デューイのプラグマティズムを平易に説明している。 そして、ウィットゲンシュタインの説との同一性を論じ、プラグマティズムというものさしでもって現今の日本の閉塞感を打破しようと著者は訴える。 要は、「人間、何をやるにしても、それが一体何の目的や...
アメリカの学者、パース、ジェームス、デューイのプラグマティズムを平易に説明している。 そして、ウィットゲンシュタインの説との同一性を論じ、プラグマティズムというものさしでもって現今の日本の閉塞感を打破しようと著者は訴える。 要は、「人間、何をやるにしても、それが一体何の目的や意味があるのかを見失わないようにしましょう」という取り組み方を著者は、プラグマティズムの作法を熟知すればいいという。 ウィットゲンシュタインの命題7 語り詰めたものについては、ひとは沈黙せねばならない。 また、生きるとは恐ろしいほど真剣なことだ。 という教えは、心に重くのしかかります。 お天道様が見ているので、姿勢を正し、ことにあたらねばならないという言い方も日本人には解りやすくていい言い回しだと思いました。
Posted by
プラグマティズムの真髄が理解できたような気がする。 著者の主張はもっともである。しかし,一部の記述は思い込みが激しすぎるような気がしないでもない。 2012/12/15図書館から借用;12/27朝の通勤電車から読み始め;2013/01/08夕方の通勤電車で読了
Posted by
この世の中は、もうこの本でいうところの「プラグマティズムの作法」を行う人と無作法の人との戦いなのです。 純度100%の無作法な人も滅多にいないし、その逆の人もそういないでしょう。 この世のほとんどを占める、どっちでもない人、どっちにでも転ぶ人の割合が時代によって変るのではないかと...
この世の中は、もうこの本でいうところの「プラグマティズムの作法」を行う人と無作法の人との戦いなのです。 純度100%の無作法な人も滅多にいないし、その逆の人もそういないでしょう。 この世のほとんどを占める、どっちでもない人、どっちにでも転ぶ人の割合が時代によって変るのではないかと思います。 下弦の時代は、無作法に偏っているんですね。 私も長らく無作法と戦ってきましたが、とりあえず負けましたし、今はどっちでもないでしょう。 それでも、無作法にならないように、こころがけていくこと。少しでも「おせっかいゲーム」をして増やしていくことしかできないのだとも思います。 真剣に生きること、よりよく生きること なんだかとても難しそうで、いいかっこうしいのように聞こえるかもしれませんが私はいつも真剣なので、背中を押してもらったようで嬉しい本でもありました。 まず自らが、より良く生きる、目的を間違えないことから始めるということですね。 少し絵空事のように感じるけど、その絵空ごとに感じる部分は私が無作法に汚染されたからなのかもしれません。 この人も世の中も下賤になりさがる時代に生まれて、真剣に、真摯によりよく行き続けること。これさえ出来たら、価値があるのではないかと思うのです。 だからこそ、自分を恥じないでいられるとも思えました。
Posted by
本書では、何を為すにも「お天道様」に対して恥ずかしくないことであるか否かを問い続けるようにしましょう。而して人としての真っ当な生き方は、極々当たり前であることとして、ヒジョーに解り易く述べられています。若し解らなければ「プラグマティズム」が足りていません。 ボク自身はキリスト者な...
本書では、何を為すにも「お天道様」に対して恥ずかしくないことであるか否かを問い続けるようにしましょう。而して人としての真っ当な生き方は、極々当たり前であることとして、ヒジョーに解り易く述べられています。若し解らなければ「プラグマティズム」が足りていません。 ボク自身はキリスト者なので、本書で使われている「お天道様」と言葉を置き換えることなく、然り、然りと一気に読みました。 凡てを真面目に生きるべし。
Posted by
プラグマティズムの考え方、その実践と効用についての解説はわかりやすい。それを踏まえて後半は日本社会への批判・提言となる。そこの主張が若干寄ってることに留意すれば得られるものはたくさんあると思う。
Posted by
最初にプラグマティズムと言う考え方の説明がある。 哲学とは言っても、小難しい事ではない。 学校で習ってきた「道徳」の様なものだ。 ただ、道徳や倫理を実践するのが意外と難しいように、プラグマティズムの実践もそんなに簡単なことではなさそうである。 この本は特に、地方の疲弊した商店街...
最初にプラグマティズムと言う考え方の説明がある。 哲学とは言っても、小難しい事ではない。 学校で習ってきた「道徳」の様なものだ。 ただ、道徳や倫理を実践するのが意外と難しいように、プラグマティズムの実践もそんなに簡単なことではなさそうである。 この本は特に、地方の疲弊した商店街の復興を願う方々や、地域の活性化を目指す人達に読んでもらうと実際に役立つのではないかと思う。 地域の有識者とか、政治家さんとかも巻き込んでの勉強会などで、ネタ本として使うには実践的でとてもいいと思う。 出来れば、マイケル・サンダルの「これからの正義の話をしよう」と言う本も一緒につかうと、より具体的に議論が進められるのではないかと思う。 地域で大量に買って、配るのもとても良いかもしれない。
Posted by
元日本マクドナルド社長藤田田による価格競争が長期にわたるデフレトレンドのトリガーを引いた愚かしさ・井上勝による小岩井農場創設の経緯の話題など実例を引き合いに出した内容でわかりやすい。 構造改革路線がそれ自体自己目的化しているというのはその通りで、プラグマティズムというととかく誤...
元日本マクドナルド社長藤田田による価格競争が長期にわたるデフレトレンドのトリガーを引いた愚かしさ・井上勝による小岩井農場創設の経緯の話題など実例を引き合いに出した内容でわかりやすい。 構造改革路線がそれ自体自己目的化しているというのはその通りで、プラグマティズムというととかく誤解されがちだが、合成の誤謬の愚かしさを時間軸を取り入れて考察しているところが秀逸。
Posted by
プラグマティズムがキリスト教的精神の前提の上にあったということを踏まえて、プラグマティズムの作法として、目的を確認することと、目的が「お天道さまに対して」恥ずべきことではないかを確認することを提起する、前半については示唆されるところがある。しかし、キリスト教的倫理観はやはりプラグ...
プラグマティズムがキリスト教的精神の前提の上にあったということを踏まえて、プラグマティズムの作法として、目的を確認することと、目的が「お天道さまに対して」恥ずべきことではないかを確認することを提起する、前半については示唆されるところがある。しかし、キリスト教的倫理観はやはりプラグマティズムの思想家の持っていた精神土壌であって、プラグマティズムそのものの持つものではないのではないか。そうでなければ、それをそのまま「お天道さま」の下に移植することはできない。キリスト教的プラグマティズム、イスラム教的プラグマティズム、資本主義プラグマティズムとかも可能なのであって、技術としてのプラグマティズムを何に使うかを制御する精神はプラグマティズムからは導けないのでは、とも思わせる。その点で後半の説得力は、僕にとっては弱く感じた。
Posted by
プラグマティズムとは「常に今している行為の目的を忘れないこと」と「その目的がお天道様に見せても恥ずかしいものでないか」の二つを持ちながら生きること。 言うてることには共感するし、この考え方は徹底できたらいいなあと思う。 ただ、「プラグマティズムをこの社会に生きる人たちにも持ってほ...
プラグマティズムとは「常に今している行為の目的を忘れないこと」と「その目的がお天道様に見せても恥ずかしいものでないか」の二つを持ちながら生きること。 言うてることには共感するし、この考え方は徹底できたらいいなあと思う。 ただ、「プラグマティズムをこの社会に生きる人たちにも持ってほしい!」というような、押しがもうひとつ弱い気がする。魅力をもっと惜しみなく伝えられたらよりいい本になるかと。 でも、この著者のことは気になったので、ほかの本も読んでみたい。
Posted by