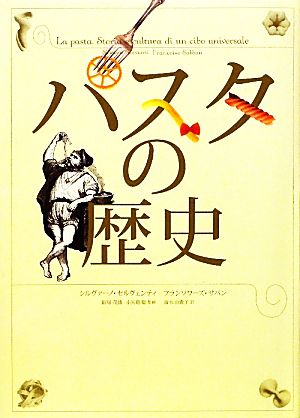パスタの歴史 の商品レビュー
パスタの奥深い歴史を多面的に詳述し、バイブル的な存在として、世界で高く評価されている一冊。古代から中世にかけて“パスタ”の基本概念が形成される過程の解説から始まり、原料、種類、調理法、生産技術、企業動向、社会情勢、国際情勢、中国の麺文化との比較などが、細かく解説されています。様々...
パスタの奥深い歴史を多面的に詳述し、バイブル的な存在として、世界で高く評価されている一冊。古代から中世にかけて“パスタ”の基本概念が形成される過程の解説から始まり、原料、種類、調理法、生産技術、企業動向、社会情勢、国際情勢、中国の麺文化との比較などが、細かく解説されています。様々な発見がありました。
Posted by
帯文:"世界が愛する「食」の秘密" "古代小麦からはじまる深遠な物語―1冊に収められた画期的な歴史" 目次:序文 アンティパス・タ、プロローグ はじめに小麦ありき、第1章 パスタの誕生、第2章 先駆者の時代、第3章 手づくりパスタから機...
帯文:"世界が愛する「食」の秘密" "古代小麦からはじまる深遠な物語―1冊に収められた画期的な歴史" 目次:序文 アンティパス・タ、プロローグ はじめに小麦ありき、第1章 パスタの誕生、第2章 先駆者の時代、第3章 手づくりパスタから機械生産へ、第4章 手工業による黄金時代、第5章 工業生産の時代、第6章 国境なきパスタ、第7章 飽食の時代、…他
Posted by
パン種がキリストの魂を表わし、無酵母は純粋を、油は神の恩寵を表わしている。 聖書が書かれた時代に、パンがどのように調理されていたかは、それから一千年も後世の注釈書では決して知ることができない。
Posted by
今では、すっかり日本人になじみの深い食べ物になったパスタ。カップメンならぬカップパスタまで登場するくらい人気者になって、パスタ自身が一番驚いているはずだ。 歴史の長さを物語るがごとく、今回の本は300ページ以上ある。パスタが古代から人類の歴史とともに歩んできたのがよく分かる...
今では、すっかり日本人になじみの深い食べ物になったパスタ。カップメンならぬカップパスタまで登場するくらい人気者になって、パスタ自身が一番驚いているはずだ。 歴史の長さを物語るがごとく、今回の本は300ページ以上ある。パスタが古代から人類の歴史とともに歩んできたのがよく分かる。手でパスタを作っていた時代や工業化されて機械で作られるようになった時代のパスタ、乾燥パスタ、生パスタなどパスタ好きにはたまらない話が載っている。 アッと驚いたのがアメリカでパスタが根付くきっかけを与えた人物だ。その名は、第3代アメリカ大統領トーマス・ジェファーソン(1743-1826)だ。ジェファーソンがヨーロッパからはじめてパスタを作る機械を輸入したと書かれている。好奇心の塊なのがよく分かる。こういう人がいたからこそイノベーション好きなアメリカがあるといる。 第9章には中国 もうひとつのパスタの祖国として、中国を取り上げている。麺の世界では長い歴史を持っている中国だけに取り上げたのだろう。中国にも長い歴史があるのが読んでいてよく分かる。ただ、訳者もあとがきで書いているが、日本のパスタの歴史も取り上げてほしかった。これだけパスタが普及していった過程を筆者流に料理してほしかった。 パスタは、これからどんなふうになっていくのか。日本では、たらこスパゲッティ―のような変化形も続々登場してきているので、どんなものが出てくるか注目してきたい。
Posted by
世界中で愛されている小麦粉をこねて茹でたやつの歴史。 ヨーロッパ(主にイタリア)での発祥、道具や味の発展、工業化や食べられ方などの歴史と、アジア代表の中国もついでに少々。 あまり整理された文章ではない。 話が飛ぶし、ふたりで執筆しているせいか無駄な重複が気になる。 どこを誰が書...
世界中で愛されている小麦粉をこねて茹でたやつの歴史。 ヨーロッパ(主にイタリア)での発祥、道具や味の発展、工業化や食べられ方などの歴史と、アジア代表の中国もついでに少々。 あまり整理された文章ではない。 話が飛ぶし、ふたりで執筆しているせいか無駄な重複が気になる。 どこを誰が書いているのか明記されていないのでどちらが(あるいは両方が)原因かわからないが、しばしば上から目線。 内容のわかりにくさを訳が強化する。 「つまり」の後につづく文が全然「つまり」じゃない。 この本の中の「パスタ」は日本語でイメージする「パスタ(小麦粉を練って茹でる西洋由来の主食系食品)」ではなく、「練り粉系料理」くらいの意味。 wikiによるとイタリア語の「pasta」には日本語で言うところの「パスタ」の他に「粉物系」、「(食品以外も含めた)ペースト状のもの」等の意味があり、日本語的な意味での「パスタ」を区別して「pasta alimentare(パスタ・アリメンターレ:食用のパスタ」と呼ぶこともあるらしい。 ロゼットパスタのパスタはそういうことか。 という知識なしに読み始めたから違和感が甚だしい。 「食用パスタ」という日本語を見たときは、食用じゃないパスタってなんだよ?ってなった。 単語を日本語に置きかえて、難しい部分は無理せず原語のまま(せいぜいカタカナ表記)文法だけを整えたような直訳風の部分が多い。 翻訳というよりは変換といいたい。 ひとかたまりの文章として読むとなにが言いたいのかわからない。 中国関係にいたっては伝言ゲームを見るようなもどかしさ。 中国経由の麺文化に親しむアジア人としてはアジアのパスタという言い方は受けいれがたい。 「西洋風中華レストランの数少ないメニュー」である「マメ科植物の澱粉でつくった透きとおるようなヴェルミチェッリ」(p4)ってなんだ?……春雨か!わかりにくい! 麺はまだしも餃子や焼売までパスタと表現されるとすごい違和感。 おおくの自動翻訳は、英語を触媒にして色んな言語を翻訳する。 日中変換も実は日→中ではなく日→英→中らしい。 全然知らない言語をわずかでもたどれるんだからとても便利ではあるけれど、英語を経由することで正確さが失われてしまうときもある。 たとえば日中には「姉」という概念があるから「姉」は「姉」になるけれど、間に「sister」が入ると上下は失われ「姉」も「妹」も「姉妹」になってしまう。 そういう、失われたものがうっすら見える。なにが失われているのかを想像で補いながら読むのはとても疲れる。 そのうえ漢語圏同士のまぎらわしさが加わって混乱することこの上ない。 「餅」は「ビン」と読む中国の食べ物(月餅などの小麦系)だけど、私の頭はこの文字をつい「もち」と読んでしまう。 餃子や麺とおぼしきものを「餅というタルト」などと書かれるともうなにがなにやら。 ストレートに中国名で書くなり日本で通じやすい言葉に変えるなりほしかった。 読まれる場所の事情も勘案して失われる部分をカバーしてこそ「変換」ではない人間の「訳」なんだけどな。 ただでさえ著者と文化が違うから前提を共有できなくて手探りで読んでるのに、文章でさらに理解しにくさが増している。 説明なしではわからないことが多すぎる…… 監修後書きもこれ本当に内容を読んだ上での感想なのか?と思うようなものだった。 訳者あとがきともども、この本における「パスタ」ではなく日本語でイメージするパスタの当たり障りない現状しか書いてない。 印刷はきれい。最近解像度を間違えて保存しちゃったようなぼやけた図画をのせる本が多いから、この本のために描かれたわけじゃない絵をきれいにのせてくれてるのが嬉しい。
Posted by
- 1