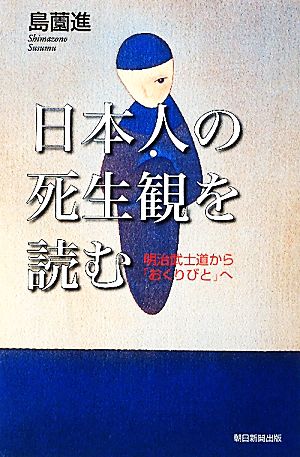日本人の死生観を読む の商品レビュー
宮沢賢治が描く死の場面 向こう側の世界を垣間見る 大局的な死生観の併存 死生観を物語で表す 1章 「おくりびと」と二一世紀初頭の死生観 死に向き合うことの勧め 死を超える力はいずこから 欧米からの移入と日本の死生学 第2章 死生観という語と死生観言説の始まり 死生観という語が優勢...
宮沢賢治が描く死の場面 向こう側の世界を垣間見る 大局的な死生観の併存 死生観を物語で表す 1章 「おくりびと」と二一世紀初頭の死生観 死に向き合うことの勧め 死を超える力はいずこから 欧米からの移入と日本の死生学 第2章 死生観という語と死生観言説の始まり 死生観という語が優勢になった敬意 武士道的死生観 死生観はなぜ必要か 死生観論述の時代背景 第3章 死生観を通しての自己確立 教養成年の死生観 志賀直哉の自己確立 死生観を描く教養小説 死生観文学の系譜 第4章 「常民」の死生観を求めて 死生観を問う民俗学 固有信仰論に世代間連帯の思想を見る 近代人の孤独から死の意識を透視する 第5章 無惨な死を超えて 戦中派の死生観の内実 内なる虚無との対面 協働行為としての戦争の意味・無意味 死生観と倫理 他者に即して戦争の死を捉え返す 第6章 がんに直面して生きる 死生観の類型型 死に向かう旅路
Posted by
死生観を集めてくる対象範囲にやや偏りがあるように思いました。もう少しこの分野を広く捉えて読んでいきたい。
Posted by
●日本についてもっと知りたいという思いから、本書を手に取った。日本独自の死生観に触れることはできるかと期待したが、何ともよくわからなかった。 ●映画『おくりびと』に象徴されるシーンとして、納棺夫となった主人公の妻が、彼に向かって「穢らわしい。近づかないで」と言い放つシーンがある。...
●日本についてもっと知りたいという思いから、本書を手に取った。日本独自の死生観に触れることはできるかと期待したが、何ともよくわからなかった。 ●映画『おくりびと』に象徴されるシーンとして、納棺夫となった主人公の妻が、彼に向かって「穢らわしい。近づかないで」と言い放つシーンがある。しかし、なぜ「死=穢れ」となるのだろう? もちろん、「死」が恐怖や遠ざけたいもの、否定したいものといった感情を喚起するものだということは何となくわかるが、なぜ「穢れ」と結びつくのだろう? そもそも「穢れ」とは何か? さらなる知的好奇心が湧いた。
Posted by
『本書の「日本人の死生観を読む」の意味はもっとすなおなもので、「死生観」を表現した日本人の書物やテクストを読むというものだ。』(p236) 死生観の入門書だと思う。死生観の概要ないしは日本人の思想、仏教、哲学、文学など、様々な観点から、死生学を紹介している。あーしかしこういう本難...
『本書の「日本人の死生観を読む」の意味はもっとすなおなもので、「死生観」を表現した日本人の書物やテクストを読むというものだ。』(p236) 死生観の入門書だと思う。死生観の概要ないしは日本人の思想、仏教、哲学、文学など、様々な観点から、死生学を紹介している。あーしかしこういう本難しーわw
Posted by
神道や仏教を始めとした日本人の中にある様々な宗教観に基づく死生観や、キリスト教や西洋哲学に軸足を置いたそれなど、様々な切り口で日本的死生観が語られ興味深い。けれど「近代日本絞った」とは言うものの、僕にはそれでも散漫な感じがした。 多くを語っているが断片の集まりという感が否めず、著...
神道や仏教を始めとした日本人の中にある様々な宗教観に基づく死生観や、キリスト教や西洋哲学に軸足を置いたそれなど、様々な切り口で日本的死生観が語られ興味深い。けれど「近代日本絞った」とは言うものの、僕にはそれでも散漫な感じがした。 多くを語っているが断片の集まりという感が否めず、著者が何を一番伝えたかったのかが掴みきれなかった。 そんな一冊だったけれど、読んでみて心に浮かんだことは「日本人にとって死生観とは生き様に於いて使う言葉ではなく、死に様に於いて語られるべき言葉である」ということだ。 「いかに生きるか」が西洋哲学に源流を持つ死生観だとしたら、「いかに死ぬか」が日本人の死生観なのではないだろうか。
Posted by
創造力なき日本 からのリファレンス。タイトルのとおり、日本人が死というものをどのように定義しようとしてきたかが学べる一冊。 武士道のように、明治期において定義されたイデオロギーとしての死、志賀直哉の世界観を通じて見る哲学としての死、そして日本に古来より土着する、ご先祖さまの世界...
創造力なき日本 からのリファレンス。タイトルのとおり、日本人が死というものをどのように定義しようとしてきたかが学べる一冊。 武士道のように、明治期において定義されたイデオロギーとしての死、志賀直哉の世界観を通じて見る哲学としての死、そして日本に古来より土着する、ご先祖さまの世界へと繋がる死。 死は門のようなものだとは、映画おくりびとの中のセリフだそうですが、その向こうが見えない、あるいは、それを通じてこそ本当の生が映し出されるという意味で、死は神殿に祀られる鏡のようなものではないかと考えさせられました。
Posted by
宗教学界隈では最近「死生学」なるものが流行っており、授業の課題にも取り上げられたので手にとってみた次第。流行っているのには、やはり高齢化が強く関係しているのだろう。先の大震災関連のこともそれに拍車をかけたと思われる。 さて、普段あまり「死」を意識しない自分にとってはこのように「...
宗教学界隈では最近「死生学」なるものが流行っており、授業の課題にも取り上げられたので手にとってみた次第。流行っているのには、やはり高齢化が強く関係しているのだろう。先の大震災関連のこともそれに拍車をかけたと思われる。 さて、普段あまり「死」を意識しない自分にとってはこのように「死」を考えてみるというのはなかなかどうして不思議な体験だった。とくに感傷的になったのは最終章あたりの死についての詩や戦争に赴く者の手記に関するところで、自分は死ぬ前には何を思うのだろうか? 「死」を意識せよ、とハイデガーが言っていたことを思い出す。死生観を考えることはそのまま、生きるという意味を考えることになり、それはうまくいけば生命を研ぎ澄ませることになる。エポケーしまくって据え置いていくのも一つの手だけども、自分の最後の着地点のことぐらいはちゃんと考えて生きることにしようと思う。
Posted by
烏兎の庭 第四部 書評 3.17.02 http://www5e.biglobe.ne.jp/~utouto/uto04/diary/d1203.html#0317
Posted by
- 1