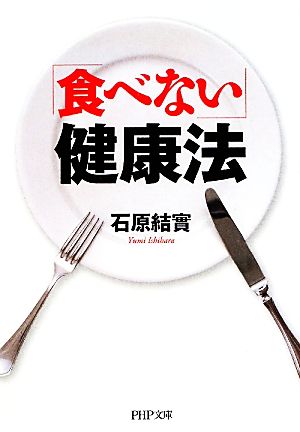「食べない」健康法 の商品レビュー
断食をすることの良さをひたすら記載している本。 断食は実践して良いと思った。 体を冷やす食べ物、温める食べ物は色によって分類できるとあるが、なんだかこじつけに過ぎないような気がする。 理屈づけたがる著者なのだろうと思い、その点はあまり参考にしないようにする。
Posted by
「食べない」ことが体にいいのは知っていた。アンドルー・ワイル著『癒す心、治る力 自発的治癒とはなにか』(上野圭一訳、角川文庫ソフィア、1998年)に絶食の効用が書かれていた。週に一度の絶食を勧めている。ただし古本屋を侮っては困る。アンドルー・ワイルや石原結實に科学性を認めることは...
「食べない」ことが体にいいのは知っていた。アンドルー・ワイル著『癒す心、治る力 自発的治癒とはなにか』(上野圭一訳、角川文庫ソフィア、1998年)に絶食の効用が書かれていた。週に一度の絶食を勧めている。ただし古本屋を侮っては困る。アンドルー・ワイルや石原結實に科学性を認めることはできない。 http://sessendo.blogspot.jp/2015/07/blog-post_21.html
Posted by
自然療法の内容。 ①体を温める食べ物、赤・黒・橙(チーズ・根菜・紅茶など)の物を摂る事を推奨。逆に青・白・緑(牛乳・葉菜・緑茶・珈琲・カレー・白身)の体を冷やす食べ物の多食を控える。※珈琲やカレーにトマトは産地が熱帯地域なので。また熱や塩加えたものになると、温める物に変化、緑茶→...
自然療法の内容。 ①体を温める食べ物、赤・黒・橙(チーズ・根菜・紅茶など)の物を摂る事を推奨。逆に青・白・緑(牛乳・葉菜・緑茶・珈琲・カレー・白身)の体を冷やす食べ物の多食を控える。※珈琲やカレーにトマトは産地が熱帯地域なので。また熱や塩加えたものになると、温める物に変化、緑茶→紅茶、牛乳→チーズ、大根→たくあん。 ②朝→黒砂糖or蜂蜜入り生姜紅茶1〜2杯か、人参リンゴジュース1〜2杯。昼→そばにネギと七味をしっかりかけたもの。夜→何を食べても可。 生姜はやる気UPに漢方の基本薬で多岐の効能。黒砂糖はミネラルの宝庫。 日月神示に記載されている、粗食、昔ながらの食事を推奨している点など、感覚的に納得できる内容である。動物は病になると免疫力を高めるため食欲がなくなるように出来ているなど、解釈の仕方が東洋的で面白い。
Posted by
最近は東洋医学を取り入れている医師が独自の考え方を語った本がとても多い。西洋医学的な手法で科学的数字を出されるとなんとなく納得してしまうが、漢方やらツボなどといった概念を取り上げた説明は眉唾もの…という人も多いだろう。しかし考えてみると、取り上げた数字は一定の手法においてはじき...
最近は東洋医学を取り入れている医師が独自の考え方を語った本がとても多い。西洋医学的な手法で科学的数字を出されるとなんとなく納得してしまうが、漢方やらツボなどといった概念を取り上げた説明は眉唾もの…という人も多いだろう。しかし考えてみると、取り上げた数字は一定の手法においてはじき出された「事実」といえるだろうが、そこから先の説明には多くの「仮説」が含まれている。ここにおける事実は「数字」である必要はなく「気」や「経絡」といった概念で置き換えれば「仮説」で語られている部分にそれほどの違いはないのではないか。著者の石原先生は従来の西洋医学に東洋医学、特に漢方の手法を取り入れ、一時しのぎではない根治を目指した治療法を提唱している。石原先生は「プチ断食」も推奨しているが、本書の「少食主義」はそれをより発展させた、さらなる本質的方法論である。 1日3食という習慣はいかにして形成されていったのか。たしかに肉体労働者やアスリート、あるいは成長期の若い人には1日3食でも足りないかもしれない。しかしわざわざ会費を支払ってまで運動を強引に生活習慣に取り入れているような生活をしている人にとって必要な食事量はそれほど多いとはいえないのではないか。また、ほとんどの人は身体が欲していなくても「健康のための習慣」として決まった時間に食事をとる。こうした風潮はいつから始まったのか。それがすべて間違いとはいえないが、少なくとも疑ってみるだけの価値はある。 著者は食事を減らすことについて具体的にいろいろやかましいことは言わない。1日2食でも1食でもよい。石原先生は「一番調子がよいと感じられる少食」を提唱されているが、問題はこの「調子がよいと感じる」能力を発揮することが極めて難しいことのように思う。多くの人は空腹を感じなくても「食事の時間」だから食べる。これは「朝食抜きはよくない」といった既成の習慣に従っているということもあるが、おそらく職場をはじめとした社会的環境が強く影響しているはずである。すなわち、時間だからという理由で空腹でもないのに食事をしてしまうのは「今食べなければしばらく食べられない」という状況があるのではないか。時間が比較的自由になる環境の人はそうではないかもしれないが、いわゆる「昼休み」が決まっている職場の人は昼休みに食事しなければ少なくとも夕方5時以降になるまでまともな食事ができない。腹囲何センチ以上がどうこう言う前に一部のヒトのエゴがそれに従わざるを得ない人の身体を蝕んでいることを認識すべきである。 こうした思想が語られるのはいかに今の世の中に「不必要」なものが多いか、ということを示しているように思う。「食べない」ということもそうだが「デトックス」や「断捨離」といった「マイナス」の考え方を持てず、必要性が疑わしいものを常に「プラス」することしか能がない人間が今の世の中を動かしているように思えてならない。その結果「不要なものを押し付けられる」あるいは「不要なものを必要なものとして認識させられる」という事態が蔓延っているように思える。
Posted by
自分の食生活を見直してみて、お昼は食べ過ぎだな、と思うので、量を減らしてみようと思った。朝については、黒砂糖入りの生姜紅茶のみに切り替えた。それが吉と出るか、凶と出るか。しばらく様子を見てみようと思う。夜は、和食中心の食事に切り替えたいが、これがなかなかできない。
Posted by
体を空腹状態にして白血球を活発にして体の免疫力を高めることを、改めて言葉で伺って納得。確かに断食中は体が軽い。医学的に説明されており、安心して手軽に実行できる。
Posted by
常々、1日3食は多くないか?と思ってもいたので「ああ、やっぱそうなんだ…」と淡々と読んでいたらいつの間にか終わってました。人間、活動する分のエネルギー分食事すれば十分。それが確認できる本です。 よく「ラクして痩せたい!」とぽっちゃり通り越した肥満体の人がぼやいている様子が見られる...
常々、1日3食は多くないか?と思ってもいたので「ああ、やっぱそうなんだ…」と淡々と読んでいたらいつの間にか終わってました。人間、活動する分のエネルギー分食事すれば十分。それが確認できる本です。 よく「ラクして痩せたい!」とぽっちゃり通り越した肥満体の人がぼやいている様子が見られるのは全国どこでもいっしょの現象なんでしょう。が、ラクしてダイエットなど心底くだらないことに甘ったれる前に、自分の食事や生活ぶりを見直すのがいいと思います。キツイ・腹が立つ言い方だと感じるかもしれませんが、事実なんですよ…。
Posted by
石原先生の本は、いろいろ読んでいますが、これは、とても実践しやすく、何度も読んでいます。 そして、食べないと力が出ないだとか、一日三食きっちり食べるのが健康にいいと思っている方には、ぜひ読んでいただきたいと思います。 少食が、いかに病気を防げるかが、わかりやすく書かれている。少食...
石原先生の本は、いろいろ読んでいますが、これは、とても実践しやすく、何度も読んでいます。 そして、食べないと力が出ないだとか、一日三食きっちり食べるのが健康にいいと思っている方には、ぜひ読んでいただきたいと思います。 少食が、いかに病気を防げるかが、わかりやすく書かれている。少食が体に良い根拠、具体的な実践法、読書のみなさんがいだかれるであろう疑問まで、書かれている。 国民に、1人一冊配布してほしい本です。きっと病気で苦しむ人が減るでしょう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「少食療法」を著者自身の体験談や、体の機能から導かれる根拠に基いて述べた1冊。 同様に少食を勧める人に、「空腹が人を健康にする」等数多くの書物の 著者でもある南雲吉則さんがいるが、本書の著書である石原結實さんの ほうが納得がいく論拠を示しているように思う。 「体験手記」の引用が多すぎたことが難点。具体的な患者の実例を示すことで、読者の右脳を刺激しイメージを換気する効果はあるのかもしれないが, 個人的にはあまり好ましくなく感じた。 今印象に残っている箇所はいくつかあるが、具体的なレビューは再度読みなおした際に載せることにする。
Posted by
共感できる部分、目から鱗の部分が多々あり、実践してみようと思うが。。。実際にできるかは?でも、1週間のうち数日は実践してみよう。
Posted by
- 1
- 2