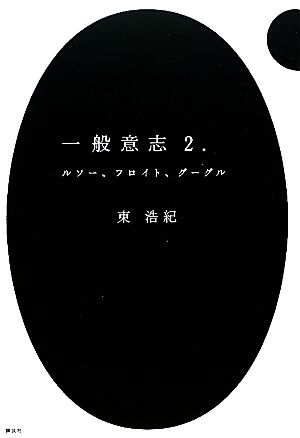一般意志2.0 の商品レビュー
成田悠輔による『22世紀の民主主義』を思い出しながら読んだ。ルソーの社会契約論を基礎に、独自の論理を展開していく。頭の体験というか、心地良い脳の疲労感が知的充足感を齎す良い読書体験。 スコットペイジの多様性予測定理。集団の多様性が高ければ高いほど、集合知の精度が上がる。一般意志...
成田悠輔による『22世紀の民主主義』を思い出しながら読んだ。ルソーの社会契約論を基礎に、独自の論理を展開していく。頭の体験というか、心地良い脳の疲労感が知的充足感を齎す良い読書体験。 スコットペイジの多様性予測定理。集団の多様性が高ければ高いほど、集合知の精度が上がる。一般意志についてのルソーの主張はその定理と全く同じことだという。三人寄れば文殊の知恵、と言えばピンと来るが、問題は議論の展開方法、結論の絞り込み方だ。叩き台があるかどうか。あるいは、多数決、熟議。それらをアナログかデジタルで処理するかという話だ。論点はボンヤリ分かる。しかし、データベースを活用したとて、アナログな手法との違いは規模感と処理速度の差異程度。ルソーが社会契約論で述べる立法者とは、一般意志を掴み、制作や制度として具体化可能な一部の天才。独裁者がその役目を務めること。他方、データベースとアルゴリズムであれば人は不要と著者は言う。成田悠輔に発想が近い。しかし、両者とも、では実務的にアルゴリズム開発に人が介入する点に触れていない。自動生成したアルゴリズムを多数決というアルゴリズムで自動選択し決定するという事だろうか。無理がある。 結局、政治とは境界、属性ごとに利害調整を行う場合に必要となる意思決定、決定事項の渉外代表機能だ。つまり、内政と外交が政治機能に求められるわけだが、その一般意思反映に民主主義が取り入れられ、選挙制度がある。しかし、データは内政にはある程度活用できても、外交は難しいだろう。実務想定をするなら、例えば、外国と相互にデータベース間で利害調整をする場合、領土問題をどう解決するのか。自国優位にアルゴリズムを調整したくもなるし、それだから、境界単位が異なれば、別の論理、別のアルゴリズム、纏まらない一般意思という事なのだ。その点では、カールシュミットの政治論の方が地に足が着いているし、データベースに夢を求めるには、まだ、論理薄弱ではないのか。
Posted by
「一般意志2.0」東浩紀著、講談社、2011.11.25 262p ¥1,890 C0095 (2021.07.31読了)(2016.01.04購入)(2011.12.06/2刷) 副題「ルソー、フロイト、グーグル」 【目次】 序文 1 第一章 第二章 第三章 2 第四章 第五...
「一般意志2.0」東浩紀著、講談社、2011.11.25 262p ¥1,890 C0095 (2021.07.31読了)(2016.01.04購入)(2011.12.06/2刷) 副題「ルソー、フロイト、グーグル」 【目次】 序文 1 第一章 第二章 第三章 2 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第一〇章 3 第一一章 第一二章 第一三章 第一四章 第一五章 参考文献 固有名索引 謝辞 ☆今後読む本 「市民政府論」ロック著・鵜飼信成訳、岩波文庫、1968.11.16 「夢判断(上)」フロイト著・高橋義孝訳、新潮文庫、1969.11.10 「夢判断(下)」フロイト著・高橋義孝訳、新潮文庫、1969.11.10 「グーグル革命の衝撃」NHKスペシャル取材班著、新潮文庫、2009.09.01 「ノイマンの夢・近代の欲望」佐藤俊樹著、講談社選書、1996.09.10 ☆関連図書(既読) 「動物化するポストモダン」東浩紀著、講談社現代新書、2001.11.20 「社会契約論」ルソー著・桑原武夫訳、岩波文庫、1954.12.25 「エミール(上)」ルソー著・今野一雄訳、岩波文庫、1962.05.16 「エミール(中)」ルソー著・今野一雄訳、岩波文庫、1963.07.16 「エミール(下)」ルソー著・今野一雄訳、岩波文庫、1964.07.16 「孤独な散歩者の夢想」ルソー著・今野一雄訳、ワイド版岩波文庫、1991.01.24 「ルソー」桑原武夫編、岩波新書、1962.12.20 「ルソー『エミール』」西研著、NHK出版、2016.06.01 「読書の学校・ルソー『社会契約論』」苫野一徳著、NHK出版、2020.12.30 「ハンナ・アーレント」矢野久美子著、中公新書、2014.03.25 「ウェブ進化論」梅田望夫著、ちくま新書、2006.02.10 「Twitter社会論」津田大介著、洋泉社新書y、2009.11.21 (アマゾンより) 18世紀のルソーの見た夢が現代社会で実現する! グーグルやツイッターなど、人々の無意識を可視化する情報技術を使い民主主義の組み替えへ──。政治の新たな可能性を拓く大胆な構想。 「一般意志」。フランスのみならず世界を代表する思想家J・J・ルソーが18世紀半ばに『社会契約論』の中で唱えた言葉です。しかしその意味するものの難解さから、これまで、さまざまな解釈がなされてきました。 東さんが本書で展開するのは、このルソーの唱えた「一般意志」は、21世紀のいまこそ実現し得るという大胆かつ斬新な論。ルソーの一般意志をあえてベタに読み込み、それを現代に適用するとはどういうことか、探求します。そして、「人々の無意識を現代の情報技術を駆使することで可視化し、それを政治に反映することこそが、一般意志の実現につながる」と述べるにいたるのです。 そしてそのアイデアは、いまやさまざまな局面で行き詰まっている、いまの民主主義、政治を突破する可能性に満ちています。 私たちの多くは「何か問題があれば、議論を尽くしたほうが民主主義的でうまくいく」と思っていないでしょうか? でもそれは本当のことなのでしょうか? 昨今の政治の機能不全を見ていると、私たちが信じてきた民主主義の形はすでに賞味期限を過ぎているような気さえします。 本書では情報技術を実装した新しい民主主義、政治の道を提示することで、日本の社会に新たな一石を投じるものなのです。 雑誌連載時から大きな反響を呼んだ注目書、待望の刊行です!!
Posted by
思いもよらない視点だった。ルソーの精緻な読み取りから一般意志の正確な概念を描き出し、無意識的民主主義を提唱する。 星5つにできなかったのは、肝であるにもかかわらず、情報技術の変容(発表からたった8年しか経っていないにま関わらず、ニコニコ動画は下火だ)があることと、無意識すら、そ...
思いもよらない視点だった。ルソーの精緻な読み取りから一般意志の正確な概念を描き出し、無意識的民主主義を提唱する。 星5つにできなかったのは、肝であるにもかかわらず、情報技術の変容(発表からたった8年しか経っていないにま関わらず、ニコニコ動画は下火だ)があることと、無意識すら、それが政治に結びつのならば介入する恣意的な動きが予想されるからだ。 熟議の限界を指摘したのは見事。 全体的に荒っぽさは目立つが読んでいて刺激を受けた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
◆感想 読みやすい。実生活のシーンに合わせて該当箇所を何度もつまみ読みしたくなる一冊。 ◆内容 ソーシャルサービスのようなデータベースが国民の無意識を可視化する今、民主主義国家や我々の生活がどうなっていくのか?の問いに迫る。 小さな政府となり、経済や文化などのレイヤーは政府から切り離され、国民の安全を守るための暴力を抑制するシステムに徹するようになる。 経済面は功利主義、リバタリアンのレンズで市場に委ねられているという。 また現在の議会にあたる熟議空間をUstで中継するような流れで異なる意志クラスタから代表者が論点を抽出して熟議の源泉とする民主国家のあり方を提案。
Posted by
著者はネットが民主主義そのものを変容させる可能性について論じている。 そこで再考されるのは19Cの思想家「ルソー」だ。 彼は、多作な著作からうかがえる彼は自発性を重んじる「近代的な自我」が発露した「エロイーズ」や「エミール」等を発表する一方、「社会契約論」等、個人の全体(一般意思...
著者はネットが民主主義そのものを変容させる可能性について論じている。 そこで再考されるのは19Cの思想家「ルソー」だ。 彼は、多作な著作からうかがえる彼は自発性を重んじる「近代的な自我」が発露した「エロイーズ」や「エミール」等を発表する一方、「社会契約論」等、個人の全体(一般意思)への絶対服従を説いたとされる著作も見られ、全体主義者ととらえられることも多かった。 だが、ここで改めて「全体意思」ではなく彼の説いた「一般意思」を改めてみてみる。 著者は「一般意思」は単純な欲望の和ではなく、個々の欲望をすべて合わせ、相殺しあうものを除いた、いわば「ベクトル」としている。 それは恣意的なものではなく数学的な存在である。 振り返って、ネットが発達した現代において、かつては机上の空論でしかなかった「一般意思」が現実のものとして立ち上がろうとしている。その母体は「ネットの履歴」である。これが、「集合知」を生み出すとともに「大衆の無意識」となり、民意を生み出すだろう。 しかし、「大衆の無意識」に我々の政治を任せるのは危険ではないか。 だが、現代の一般意思、いわばネットに支えられた「一般意思 2.0」は可視化と双方向の交流が可能である。端的なのはニコ動だろう。そこでは、会議が行われている場にそれを視聴する者のコメントが書き入れられ、即時にフィードバックと双方向性が可能である。すべての省庁会議もそうすることで、今まで専門家が密室で「熟議」の上、運営していたため、参加のコストが跳ね上がっていた民主主義のコストが激減する。 そうなると、国家の役割も変わり、人間の物理的、身体的安全の確保のみとなる。 それ以外の人間的な性の自由は市場が提供する世界となるだろう。 P227 「熟議で閉じた島宇宙。その間をランダムにつなぐ感情の糸。熱量の暴走を外部から抑制するネットワーク」
Posted by
【由来】 ・ルソーの「社会契約論」をhontoで検索していて。ってか、今まで登録してなかったんだな。ちょうど「多数決を疑う」を読み、「一般意志」について知ったところだったのでタイミングもよかった。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、...
【由来】 ・ルソーの「社会契約論」をhontoで検索していて。ってか、今まで登録してなかったんだな。ちょうど「多数決を疑う」を読み、「一般意志」について知ったところだったのでタイミングもよかった。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
Posted by
期待値が100点だとすると読後の印象は40点。著者の提案は面白い。ルソーの枠組みを使って新しい政治の形を提示している。言葉の解釈や引用など丁寧にされているし誠実に書かれているのはよくわかる。が、終盤、まとめがはじまるとがっくり来る。言っていることはわかるのだけれどただし、とか、前...
期待値が100点だとすると読後の印象は40点。著者の提案は面白い。ルソーの枠組みを使って新しい政治の形を提示している。言葉の解釈や引用など丁寧にされているし誠実に書かれているのはよくわかる。が、終盤、まとめがはじまるとがっくり来る。言っていることはわかるのだけれどただし、とか、前提が多い。夢を語ると言っているので仕方がないのだけれど世の中の流れからいえばここに書いてあることはある程度的を得ているのかもしれないが直観的には限界を感じるし、その可能性を不相応に大きく飛躍させているので読み終わると少し肩すかしな気分に。ルソーの枠組みを使っているがルソーを読んだ時のような共感がなかったのが印象的かもしれない。
Posted by
選挙は、国政について自らの意志を示す唯一の機会だ。 ずっと思っていたけど、 今は、ツイッターやSNSによって、意志が様々な形で公開されているじゃないか。 その意志を生かさないで、国のことをいつまで議員だけで話し合ってるの?という主張に、目から鱗が落ちた。 政治は国民の為のもの...
選挙は、国政について自らの意志を示す唯一の機会だ。 ずっと思っていたけど、 今は、ツイッターやSNSによって、意志が様々な形で公開されているじゃないか。 その意志を生かさないで、国のことをいつまで議員だけで話し合ってるの?という主張に、目から鱗が落ちた。 政治は国民の為のもの。 社会は社会の構成員の意志の集合。 しかし、政治家への陳情には利害が絡み、必ずしも無意識の一般意志とは合致しない。 政治家がすべきことは、一般意志を集め、その中から無意識の一般意志を見極め、それを元に政策を立案すること。 そういう動きをする議員は、世の中にどれだけいるのだろう。 一般意志2.0の考え方は、政治に限らない。 一般意志を集めることを恐れず、本物を見極め、それを正しく理解し実行すること。 社会の役に立つ仕事をする為の重要な考え方を学んだ。
Posted by
ルソーの理想とした一般意志に基づく政治を、現代のウェブを用いて実現できないか、その可能性を探る内容です。そしてそれが実現したとき、ウェブが政治的なものの定義を変える可能性を示唆しています。 著者はルソーの思想を、敵味方をつくるカールシュミット的全体主義とは別だといいます。一般意志...
ルソーの理想とした一般意志に基づく政治を、現代のウェブを用いて実現できないか、その可能性を探る内容です。そしてそれが実現したとき、ウェブが政治的なものの定義を変える可能性を示唆しています。 著者はルソーの思想を、敵味方をつくるカールシュミット的全体主義とは別だといいます。一般意志はコミニュケーションレスな数理的なものだと。また、当然コミニュケーションを排する点でハーバマス的な熟議民主主義も否定します。ここにジャン・ジャック・ルソー問題が解消されます。そのうえで、グーグルによる検索、ツイッターによるつぶやきの発信など、無意識に近いかたちで人々が行ウェブ上の操作を一般意志の形成に役立てようというのです。 この思考の根底にあるのは既存の政治的常識を超えた価値一般の否定です。人はいくら議論しようが分かり合えない、理性は利害を乗り越えられない、市民が高い意識によって政治に関与することはない。そういった19世紀から20世紀にかけ隆盛した価値観の否定を受け入れられるか受け入れられないかで、本書の評価が分かれているように見えます。そして、ネットツールの話などが大変今時で目立っていますが、そんな手段の追求は枝葉のはなしであり、既存の価値観を変える選択を我々が決断するか否か、またするとしたらいかに政治的なものを再構築していくかを考えなければなりません。ツールがあるから乗っかろうではなく、論じる順番こそ重要だと思いました。
Posted by
以前はグーグル化する世界も怖いと思ったが、こういう考え方もあるのだと興味深く読めた。 「ハシズム」も別に怖いことではなく(氏は「自分がなるほど」と思う意見ならなんでも取り入れると聴いたし)、それも時代の流れなのかもしれない。 それよりも寧ろ… そんな時代の流れを全然汲みもせず...
以前はグーグル化する世界も怖いと思ったが、こういう考え方もあるのだと興味深く読めた。 「ハシズム」も別に怖いことではなく(氏は「自分がなるほど」と思う意見ならなんでも取り入れると聴いたし)、それも時代の流れなのかもしれない。 それよりも寧ろ… そんな時代の流れを全然汲みもせず「党離脱」云々で喧々囂々しているオジサン達が滑稽に見えてならない。
Posted by