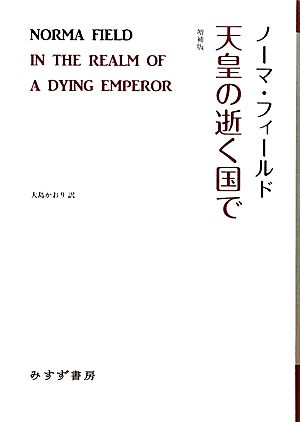天皇の逝く国で 増補版 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
とても有名な本であるのに読んだことがなかったような気がする。目次は沖縄、山口、長崎である。沖縄については戦争中のことであると推測はされた。山口は全く予想がつかず、自衛隊合祀を訴えたことについてであることは読んでいくうちにわかった。しかし、この合祀の出来事もマスコミが書かないので忘れられる。長崎は原爆投下のことかと思っていたら、本島市長の天皇の戦争責任発言についてであった。筆者は本島市長をはじめ、これらの関係者に直接インタビューをしてその発言を書いている。たぶんそれがほかの評論と異なることであろう。
Posted by
「原爆を、日本の侵略戦争の背景のなかでどう位置づけるか」 この問いが本島長崎市長に投げかけられたのが1989年。BTSメンバーの着用したTシャツのことが2018年にあれほどの問題となったのも、この問いと向き合うことを30年近く避け続けてきたからこそだったのではないか。 日本の『...
「原爆を、日本の侵略戦争の背景のなかでどう位置づけるか」 この問いが本島長崎市長に投げかけられたのが1989年。BTSメンバーの着用したTシャツのことが2018年にあれほどの問題となったのも、この問いと向き合うことを30年近く避け続けてきたからこそだったのではないか。 日本の『内』において棚上げにしてきた問題を『外』からやって来たポップカルチャーによって突きつけられた衝撃は日本人である自分ですら戸惑うほどの大きさだったと記憶している。 原爆を投下した側であるアメリカで育った人が原爆投下を肯定的に捉えるのと、植民地支配されていた韓国で育った人が肯定的に捉えるのは、当然ながら意味は異なる。原爆投下はそれが為された文脈抜きに語られるべきではないし、それを日本の侵略戦争の背景のなかで位置づけることなしに語るのもまた歴史をお座なりにしているだろう。唯一の被爆国であるからこそ、日本は被害の面だけを見ていてはいけない。 また、本作では日本及び日本人が多層で多義性を持つものであることが時に鳥瞰的、時に虫瞰的に描き出されており、面白かった。
Posted by
【この惨めな輪廻をどうかしてぬけでる道はないものか。あるはずはない。としたら,私たちは折々,この責任回避の繰りかえしに歯止めをかける工夫を執拗に繰りかえさなければならない】(文中より引用) アメリカ人を父に,日本人を母に持つ著者が,昭和天皇の崩御の直前に訪れた日本での経験をもと...
【この惨めな輪廻をどうかしてぬけでる道はないものか。あるはずはない。としたら,私たちは折々,この責任回避の繰りかえしに歯止めをかける工夫を執拗に繰りかえさなければならない】(文中より引用) アメリカ人を父に,日本人を母に持つ著者が,昭和天皇の崩御の直前に訪れた日本での経験をもとに綴るエッセイ。いわゆる「少数派」の視点から日本社会,そして天皇制についての新たな視点を投げかける全米図書賞受賞作です。著者は,小林多喜二の研究でも知られるシカゴ大学教授のノーマ・フィールド。訳者は,ハンナ・アーレントの作品の翻訳も手がけた大島かおり。原題は,"In the Realm of a Dying Emperor"。 本書の初版が出たのは1994年なのですが,この約20年あまりで,ずいぶんと本書を受容する世界が変質したのではないかということを感じました。著者は歴史を紡ぐという意味での物語,特に「弱者」にとっての物語を大切にしているのですが,もはやその「弱者」に対置する日本そのものが(特に国際社会における物語を作り上げるアクターとして)必ずしも「強者」ではないという点が特筆すべき変化なのではないかと。「日本が〜〜すべき」という議論を大上段からかかげられるところに,良い意味でも悪い意味でも,日本が「強者」であった時代があったんだなと強く感じました。 議論に花が咲くタイプの一冊です☆5つ
Posted by
アメリカ人の父、日本人の母を持つ著者が、昭和末期の日本で「天皇制」に関係する言動を起こした3人の人々を訪ねて記した本。 沖縄国体で日の丸を燃やした知花昌一、自衛隊だった亡夫の靖国神社合祀に対して訴訟を起こした中谷康子、天皇の戦争責任に言及した長崎市長本島等。3人へのインタビューだ...
アメリカ人の父、日本人の母を持つ著者が、昭和末期の日本で「天皇制」に関係する言動を起こした3人の人々を訪ねて記した本。 沖縄国体で日の丸を燃やした知花昌一、自衛隊だった亡夫の靖国神社合祀に対して訴訟を起こした中谷康子、天皇の戦争責任に言及した長崎市長本島等。3人へのインタビューだけでなく、道中の様子や筆者自身の生い立ちや思想、そして昭和天皇が病に倒れてからの日本の空気感も丁寧に描かれています。 3人の言葉に共通するのは、世間からの注目とは似つかわしくない「普通の人」らしさと細やかさ。そして、そういう人が己の主張を述べた途端、良くも悪くも─多くは悪い方へ─甚大な注目を集めてしまう、裏を返せば声をあげる人の少ない、日本の様子。それは二十余年経った現在でも、さして変わらないように感じられます。 3人、そして筆者の考えに全面的に賛同するものではないけれど、何を賭しても声をあげ続けることの難しさと尊さに、上手く言えないけど感じるものがたくさんありました。 時間をおいてもう一度読みたい一冊です。
Posted by
回送先:府中市立新町図書館 94年に刊行された同名書籍の増補分を含めて「始まりの書」シリーズの一冊として刊行。事実上の復刊に当たる。 89年に死去したヒロヒトと「過ぎ去らない戦後(あるいは過ぎ去らない記憶)」の問題について論じる書籍はたくさんあるが、本書が復刊までにいたったの...
回送先:府中市立新町図書館 94年に刊行された同名書籍の増補分を含めて「始まりの書」シリーズの一冊として刊行。事実上の復刊に当たる。 89年に死去したヒロヒトと「過ぎ去らない戦後(あるいは過ぎ去らない記憶)」の問題について論じる書籍はたくさんあるが、本書が復刊までにいたったのは、その出発点が「祖母のくに(=祖母の郷里)」と「日本という国民国家」との同一化をしなければならないのかという個人的でありつつも公共的でもある問いだからであろう。確かに増補箇所であるように「表面的にしか知らなかった」がために、その表面さから自らが投げかける「質問」の文言にあとから「顔から火が出る」のもわからなくはないが、しかし「原因はこれだ」(あるいは「これによってこうなった」という幼稚なルサンチマンの表明)と断定するだけの書籍と見比べて、本書は「顔から火が出てしまったこと」を率直に認め、それから何を得たのかについてもキチンと加筆されている。書きっぱなしで終わったのではなかったのである。 「権威」や「同意」によって翻弄された格好の言の葉のみを選り好みするのではなく、単語(あるいは文字ひとつひとつ)を真摯に紡ぐことの責任を、さりげなく投げかけられたような読後感をもっている。
Posted by
- 1