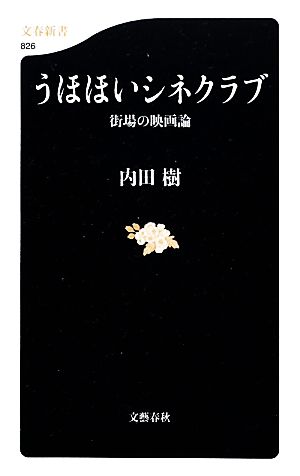うほほいシネクラブ の商品レビュー
著者がこれまで鑑賞してきた映画作品を批評し、それらを1冊にまとめた本。多くの映画作品を取り扱うが、どの箇所を読んでも目から鱗が落ちるが、なかでも小津安二郎作品の批評は興味深い。著者曰く、小津作品は、大人としての振る舞い方を学べるという。具体的には、話し方、酒の頼み方などと、成熟...
著者がこれまで鑑賞してきた映画作品を批評し、それらを1冊にまとめた本。多くの映画作品を取り扱うが、どの箇所を読んでも目から鱗が落ちるが、なかでも小津安二郎作品の批評は興味深い。著者曰く、小津作品は、大人としての振る舞い方を学べるという。具体的には、話し方、酒の頼み方などと、成熟した男として、どのような行動を取るべきかを学べるらしい。また、宮崎駿作品の身体性や女性像に関しても、本書は言及する。空を飛ぶということと、大人でも子供でもない時期が、宮崎作品においてどうやら重要らしい。
Posted by
うほほいシネクラブ 街場の映画論 (小津安二郎の『お早う』の感想も含め) 同僚の勧めもあり、『お早う』をやっと見た。内田翁が何度も言っていたメタメッセージということがよくわかり、さらに大人というものが常套句がうまい人であると言うことにも理解できた。子供は、大人が常套句ばかりいっ...
うほほいシネクラブ 街場の映画論 (小津安二郎の『お早う』の感想も含め) 同僚の勧めもあり、『お早う』をやっと見た。内田翁が何度も言っていたメタメッセージということがよくわかり、さらに大人というものが常套句がうまい人であると言うことにも理解できた。子供は、大人が常套句ばかりいって、何も意味のない会話ばかりすることに憤慨する。しかしながら、まさに大人の社会を形作っているのが、何でもない常套句ばかりの会話なのである。「おはよう」「おはよう」という何の意味のなさないような言葉の交換が、実はメタメッセージとして「あなたの存在を私は認めています」という根本的な親愛の表現として提示しているというカラクリというか、人間社会のミソのようなものがわかった時に、人は大人になるのかもしれない。メタメッセージという重層的な観点でメッセージを捉えるということに、大人の端緒があるのかもしれない。そんなことに気づかせてくれる映画であった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
私の求めている映画評論本でなかったので私的☆は低めだが(著者自身が前説に映画のあらすじや背景に言及するものではないと書いているので著者のせいではないんです)、今回読んだ中のなるほどなあ文↓ 『エターナル・サンシャイン』について 人間というのは不思議なもので、確定したはずの過去に「別の解釈の可能性」があり、そのとき「別の選択肢を取った場合の私」というものがありえたと思うと、なぜか他人に優しくなって、生きる勇気がわいてくるんです。 『グラン・トリノ』について 自分が何ものであるか、何ものに生まれついたのか、といったことは副次的な条件にすぎない。人間は自分を造形し、自分で演じるのである。私たちが「ほんとうの自分は何ものであるのか」といったことは問う必要のないことである。それよりは与えられた状況の中で、「自分がそうありたい人間」として、語るべきことを語り、なすべきことをなせ。ただし、どんなときもそれが虚構であることを忘れるな。
Posted by
素直な映画評って訳ではないから、特に何かがオススメされていたり、っていう本ではない。でも作者のファンとして、その目(フィルター)を通して見た映画観はいろいろ刺激的で、映画と全然関係なく思えるところに含蓄あるひとことが放たれていたりとか、主題とは関係ないところで気になる映画があった...
素直な映画評って訳ではないから、特に何かがオススメされていたり、っていう本ではない。でも作者のファンとして、その目(フィルター)を通して見た映画観はいろいろ刺激的で、映画と全然関係なく思えるところに含蓄あるひとことが放たれていたりとか、主題とは関係ないところで気になる映画があったりとか、自分的には、これで十分に鑑賞欲を刺激される読み物でした。まずはやっぱり、黒澤・小津からですね。
Posted by
見ていない映画のレビューはやっぱり読みたくないので、とばし読み。そうなると、流れがわからなくて・・・。 ブラックレインの松田優作の演技についてと、ライフ・イズ・ビューティフルの解説はゾクッとしました。 改めて読みたいと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
知らない映画の評も読ませる、というのが、文筆で印税を得ることができるか否かの違いであろう。『ホテル・ルワンダ』と品川プリンス日教組拒否事件とをリンクさせたのは秀逸としか言いようが無い。
Posted by
映画とは自身について語られることを欲望しているジャンル いはやは内田節全開。元大学教授で、専門はフランス現代思想ともなれば語り口はほほ〜んという感じで、あの時代の空気に触れ、エクリチュールに身を任せた人間なら楽しめると思います。 かくいう私も前世紀から内田樹のブログの読者ですの...
映画とは自身について語られることを欲望しているジャンル いはやは内田節全開。元大学教授で、専門はフランス現代思想ともなれば語り口はほほ〜んという感じで、あの時代の空気に触れ、エクリチュールに身を任せた人間なら楽しめると思います。 かくいう私も前世紀から内田樹のブログの読者ですので、本書にも当時の「おとぼけ映画批評」で拝見した記事もいくつかあったような。 一応、解説、評論、批評の形を取っていますが、これらは映画へのオマージュ、愛の表明に他なりません。満ち溢れたエネルギーは言葉の洪水となります。筆者自身、「言語によって映画の本質に肉迫することができるかもしれない。そんな期待を抱かせてくれる芸術ジャンルは他にありません。たぶん、僕たちが映画について語り止めることができないのは、そのせいだろうとぼくは思います」とあとがきで書いているんですから。 映画は数多くの才能を引き寄せる磁場として、複数の作り手(「フィルムメイカー」)の夢見る糠床となる。いろんな手合いがそこに手を突っ込み引っ掻き捏ね繰り回すものだから、もはや誰のtasteであるのか分からないし、決めようがない。昔、角川春樹のメディアミックスという戦略で、“読んでから観るか、観てから読むか”というようなキャッチコピーがあったけど、読むのは原作本だけでなく「その映画について語られた無数の言葉」もまたその資格を持っているのではないか。 筆者の言うように、僕たちのような「映画について語るもの」もまた「フィルメイカー」の一員として、その映画の構成要素の一つとして組み込まれている。だとしたらそれについてどこまでも知りたいと思うのは当たり前でしょ。なぜって、映画とは他ならぬ僕自身(=自己)なんだから。
Posted by
見たことがある映画+ちょっと興味ある映画のところだけつまみ読み。 読了としてよいものかとも思うが一応読了。 それにしても、この人はなんでこんなタイトルにするんだろう。
Posted by
映画大好き人間の私ですが、あんまり他人の書評などは読みません 映画の本はほぼ初めて位の一冊です 著者が冒頭前書きでとんでもない頁数の新書になってしまったとおっしゃっている通 り 新書にしては二冊分のボリュームがあると思います それぞれの作品にナルホドな意見がたくさ...
映画大好き人間の私ですが、あんまり他人の書評などは読みません 映画の本はほぼ初めて位の一冊です 著者が冒頭前書きでとんでもない頁数の新書になってしまったとおっしゃっている通 り 新書にしては二冊分のボリュームがあると思います それぞれの作品にナルホドな意見がたくさんあって面白かったです あの映画はこの映画とストーリーが一緒だったのね とか このシーンはあの映画のオマージュだったのね とか ただ、見てない作品も多数あり、特に小津安二郎監督と黒沢明監督の作品がお好きな ようですが これに関してはちんぷんかんぷん ついでに韓国映画もほとんど見ていないのでよくわかりませんでした 特に興味深かったのはアメリカの学園ドラマに関する考察です アメリカの学園ドラマ特融カースト制度について Jocks & Queens 男はアメフト選手 女はチアリーダーで金髪 The Brains ガリ勉君 上昇志向は強いけど筋肉なし The Greeks 故郷脱出志向はある 多少の上昇志向はあるものの向上心はナシ The Goth 最下層 将来性ゼロ キレると自動小銃を乱射する なんだかわかるわかるぅ っていう感じです
Posted by
ウチダタツルさん、読書に加えて映画まで。 どうやったらこんなに大量のインプット・アウトプットが できるのだろう? で、映画評もひと味違っていて その映画からこんなことを考えるか? と意表をつくものばかり。 西部劇からアメリカのジェンダー論を説くなど 圧巻の映画論。 映画を3...
ウチダタツルさん、読書に加えて映画まで。 どうやったらこんなに大量のインプット・アウトプットが できるのだろう? で、映画評もひと味違っていて その映画からこんなことを考えるか? と意表をつくものばかり。 西部劇からアメリカのジェンダー論を説くなど 圧巻の映画論。 映画を30分くらいで観られたらいいのに。
Posted by