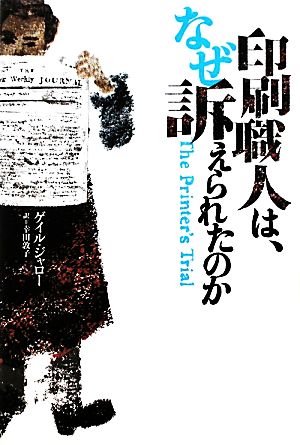印刷職人は、なぜ訴えられたのか の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
図書館の子どもコーナーで見つけた本。 アメリカ植民地時代に実際にあった話。言論・出版の力で悪徳政治家を打ち倒す。言論の自由にとって、歴史的に重要な出来事だったみたい。 争いに巻き込まれた平凡な一市民である印刷職人と、政争の主役である政治家や活動家たちとのギャップが面白い。印刷職人は正義のためにがんばった。でも、それ以上の視野はない。釈放後は有名になって天狗になってるあたり、大きな展望がないとそうなるよなぁとしんみりする。 悪徳政治家を懲らしめる話としてエンタメ的に面白いし、言論の自由の大切さが分かって良い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
〇その場に立っているような高揚感とリアル感 “言論の自由”と“政治”について考える コスビーのむちゃくちゃな政治は、彼やイギリスにとって当時当たり前のものだったのか? また、当時の世界についても学びたく思った ・政府御用達新聞(総督コスビー)VS ニューヨーク・ウィークリー・ジャーナル(反コスビー) イギリス既得権者VSニューヨーク市民 ◎1730年代ニューヨーク、イギリス植民地にやってきた新総督コスビー。アメリカ独立につながっていった、「言論・報道の自由」に関する騒動 アメリカの夜明け前の物語 ・金と汚職にまみれた搾取する気まんまんのコスビー ・有色人にも低所得層にもあらゆる女性にも権利のない時代にあっての“市民”の話 ・ニューヨーク・ジャーナルの執筆者がはっきりと分からず逮捕出来なかったコスビーは、印刷元の職人兼代表のゼンガーを逮捕する ←ジャーナルは出版され続けた「獄中より」も掲載 ・三ヶ月後、大陪審で不起訴決定。が、コスビー派の検事総長により略式起訴に持ち込まれる ←このような職権乱用がまかり通るならば、自分たち一般市民には防ぎようがない ・ゼンガーの2人の弁護人は法廷で判事2人の資格を問う。 →反対に免職され、ゼンガーの弁護人がいなくなった →ゼンガーは絶望し疲れ果てていたが、決して執筆者の名前を口にしなかった。 ・陪審員の選任 コスビー派ばかりが選ばれる ゼンガーの新しい弁護人が抗議する …コスビー派だが法の僕だった …元弁護人たちも、信頼出来る弁護人ハミルトンに依頼する ・1753/8/4 陪審員、検察はほぼコルビー派 傍聴席は、ほぼゼンガーの味方 ハミルトン弁護士 「起訴事実の通り、ジャーナルを発行したことをみとめる。ただし、そのことはなんの罪を犯したことにもならない」 「起訴状の通り『虚偽の、悪意に満ちた、扇動的』な内容を検察側が証明せよ」 ある時代のある場所にいて優れた法であっても、ほかの時代、ほかの土地では悪法ともなる 報道の自由こそが、腐敗した総督たちから植民地人を守り抜く唯一のすべである 「新聞の記事は虚偽ではなく真である。従って・ゼンガーは扇動的文書毀罪には問われない。」 …ゼンガー氏の裁判を自由への闘争とした ←陪審員の判決…無罪 ←しかし、ゼンガー氏を交えずに祝いの宴を催す “印刷職人の自由”ではなく、“われらモリス派”が政敵を打ち負かした ・それから 『ニューヨーク・ウィークリー・ジャーナル紙印刷発行人ジョン・ピーター・ゼンガーの法廷闘争覚書』…ゼンガーではなくジェームズ・アレクサンダーの執筆 ←イギリス植民地支配からの脱却に向けての気運を高めた 立役者たちのその後 アメリカ独立革命へ 報道の自由 「政府の基盤は“民の声”だ」
Posted by
YA向けブックガイドから。小説様のノンフ作品。アメリカ成立前の微妙な時期、こんな問題があったんですね。ここでは良心が勝利しているけど、涙を飲んだその他大勢の物語もありそう。そんなことまで含め、いろいろ考えさせられる一冊でした。
Posted by
昔のアメリカであった出版・表現の自由を求めて怒っていた争いについての本。 一応のところ自由が勝利したわけだが、いまいち釈然としない話だった。
Posted by
1932年ニューヨークのイギリス植民地に新しい総督がやってきました。その名はウィリアム・コスビー。この人物は総督という権利を使い、自分の私腹を肥やすことしか考えない、こんな横暴な人がいたのか!と驚くほどの人物だったのです。そんな総督の行いを世間に知らせようと、当時はまだ特殊な技術...
1932年ニューヨークのイギリス植民地に新しい総督がやってきました。その名はウィリアム・コスビー。この人物は総督という権利を使い、自分の私腹を肥やすことしか考えない、こんな横暴な人がいたのか!と驚くほどの人物だったのです。そんな総督の行いを世間に知らせようと、当時はまだ特殊な技術だった印刷技術職人を求め、新聞をつくらせます。しかしコスビーはこれを政府批判という罪で裁判にかけてしまうのです。アメリカで実際にあった事件です。報道の自由について考えさせられる一冊。
Posted by
300年もの昔の、アメリカがまだイギリスの植民地だった頃の話。ノンフィクション。 歴史的な事実を子どもに読みやすいように解き明かしている。 内容は、我々日本人にとっては遠い昔のとある事件、といったところだ。 しかし、アメリカ国民にとっては独立運動の前進となる、大きな一歩を踏み出...
300年もの昔の、アメリカがまだイギリスの植民地だった頃の話。ノンフィクション。 歴史的な事実を子どもに読みやすいように解き明かしている。 内容は、我々日本人にとっては遠い昔のとある事件、といったところだ。 しかし、アメリカ国民にとっては独立運動の前進となる、大きな一歩を踏み出した瞬間だ。 なんというか、地元の小学校の社会の教科書なんかに載っていそうな話。 小学校高学年からオススメ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1730年代のニューヨーク。イギリスの植民地だった時代、アメリカの「言論・報道の自由」をめぐる闘いの記録。そしてその事件はアメリカ独立へと繋がってゆくのだった。 発端はイギリス本国から植民地の総督としてやってきたウィリアム・コズビーが 私腹を肥やし、職権乱用をすることなどに反対し、それを糾弾する新聞が発行されたこと。 当時、ニューヨークには二人の印刷職人しかいなかった。一人はコズビー総督派の新聞を発行していた。だがコズビーに反対する有志の者たちは、コズビー批判を掲載する新聞を新しく発刊した。ニューヨークのもう一人の印刷職人ゼンガーは、沢山の子を養ってゆくために、その新聞の印刷を引き受ける。 二つの新聞は 政治の2大勢力の闘いに巻き込まれてゆく。 936
Posted by
アメリカが、まだイギリスの植民地だった1730年代の話。イギリス本国から赴任してきたウィリアム・コスビー総督は、私腹を肥やす事しか考えず、都合が悪ければ法さえも曲げる独裁者だった。権力を持つコスビーに対抗するため、最高裁主席判事のルイス・モリスらの反総督派の人々は、世論に訴えるた...
アメリカが、まだイギリスの植民地だった1730年代の話。イギリス本国から赴任してきたウィリアム・コスビー総督は、私腹を肥やす事しか考えず、都合が悪ければ法さえも曲げる独裁者だった。権力を持つコスビーに対抗するため、最高裁主席判事のルイス・モリスらの反総督派の人々は、世論に訴えるために、コスビーの暴挙の数々を大衆に報じる週刊新聞を発行する。それに怒ったコスビーは、新聞を取り締まろうとするが、記事は偽名で書かれているため、執筆者は明白なものの証拠にならずに逮捕できない。そこで新聞を印刷していた職人を逮捕してしまう。 権力者と戦うためにはペンの力が武器になること、そして、それゆえに「言論の自由」は独裁者には都合が悪く、民主国家には絶対に必要なものであるということを、歴史的事実から教えてくれる。この事件がアメリカを植民地からの独立へと動かすことになる。 ページ数も少なく、淡々と事実を述べている大変読み易い本だが、その内容は重い。
Posted by
アメリカの自由の始まりは、植民地時代に端を発していたのかー 圧政に耐えかねて、言論によって立ち上がるが、それは、当時は違法行為だというのには驚いた。 ここで陪審員制が生きてくる。本当に正しいことはなにか、を陪審員は考えようとするところが興味深い。法律が間違っていたら直せる、という...
アメリカの自由の始まりは、植民地時代に端を発していたのかー 圧政に耐えかねて、言論によって立ち上がるが、それは、当時は違法行為だというのには驚いた。 ここで陪審員制が生きてくる。本当に正しいことはなにか、を陪審員は考えようとするところが興味深い。法律が間違っていたら直せる、というのがおもしろい。しかし人に委ねられてしまうと、常に買収の危機にさらされる。日本の裁判員にはこのようなバックボーンがないために、根付きにくいのでは、ともおもった。 なぜ執筆者ではなく、印刷者が訴えられたのか。 責任表示は大事だけど、印刷所にそれを課すのは変。しかし結社の一員として訴えられているなら仕方ない? しかし、自由について1730年代に考えていたアメリカはすごいやー 日本はそういう意識が薄いのでは。損なわれてしまう不安や、勝ち取ってきた気概は感じられない。
Posted by
言論の自由を巡るノンフィクション。 たしかにアメリカではこの手の権利についての意識は建国以前から高かったんだろう。だってそういう権利を守ることをかかげて独立したんだから。 でも、よくわからないうちに矢面に立たされて、投獄されてつらい目にあわされた印刷職人があわれ。今でもいそうだ。...
言論の自由を巡るノンフィクション。 たしかにアメリカではこの手の権利についての意識は建国以前から高かったんだろう。だってそういう権利を守ることをかかげて独立したんだから。 でも、よくわからないうちに矢面に立たされて、投獄されてつらい目にあわされた印刷職人があわれ。今でもいそうだ。教養高く、志操堅固な方々にそそのかされて(または影響されて)、旗を振っていたらとんでもない目にあってしまったというナイーブな人が。
Posted by
- 1
- 2