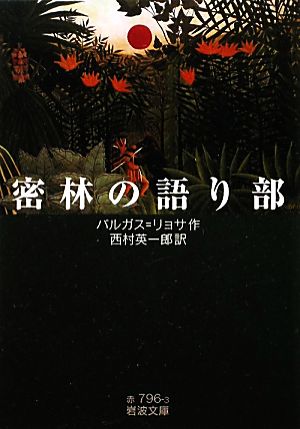密林の語り部 の商品レビュー
”《大切なことは、焦らず、起こるべきことが起こるに任せることだよ》と、彼は言った。《もし人間が苛々せずに、静かに生きていたら、迷走し、考える余裕ができる》そうすれば、人間は運命と出遭うだろう。”(p.259) 日本の遥か彼方、ペルーの密林で語られる人生の構え方にこうして聞き入る...
”《大切なことは、焦らず、起こるべきことが起こるに任せることだよ》と、彼は言った。《もし人間が苛々せずに、静かに生きていたら、迷走し、考える余裕ができる》そうすれば、人間は運命と出遭うだろう。”(p.259) 日本の遥か彼方、ペルーの密林で語られる人生の構え方にこうして聞き入ることが出来ること、それが、私にとって翻訳文学を楽しむ理由の一つである。 ”文明(≒西欧的、キリスト教世界的進化)”と切り離されたアマゾンの先住民の世界に身を投げ出したユダヤ人の友人を探すというストーリーをベースに、マチゲンガ族の神話がたっぷりと語られる本作。神話の部分、最初は多少読みづらさを感じるかもしれないが、すぐさま、自分がまるでアマゾンを歩いているような感覚に襲われることは確実である。
Posted by
真に他者、異文化を理解することと、それと同化することの間に大きな隔たりがある。理解は対象を分析し自身のコードに合わせて再構築すること。同化は自身がそれまでに得た世界観を捨て、生まれ変わること。同化には完全な理解は必要ないのかもしれない。サウルはマチゲンガ族が不具の子供を殺す理由を...
真に他者、異文化を理解することと、それと同化することの間に大きな隔たりがある。理解は対象を分析し自身のコードに合わせて再構築すること。同化は自身がそれまでに得た世界観を捨て、生まれ変わること。同化には完全な理解は必要ないのかもしれない。サウルはマチゲンガ族が不具の子供を殺す理由を理解できなかった。 サウルは西洋的な価値観は捨てたが物語は捨てなかった。カフカやユダヤ教、キリスト教の物語。サウルは密林の物語の中に自身の物語を自然に織り交ぜて同化した。これは宣教師や学者の理解とは違う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ひとつの文化に魅せられ、回心してその内部へと踏み込み"語り部"となるサウルと、文化を外側から物語にしようと試みる筆者(?)の2人の物語が交互に折り重ねられている。 初め語り部の物語が始まった時、なれない情景や言葉に戸惑いつつも引き込まれている自分がいた。
Posted by
ルソーの絵がまた良い。ふと、池澤夏樹のマシアス・ギリの失脚を思い出した。リョサの、楽園への道もおすすめ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アマゾンの密林に暮らす原住民に溶け込んで「語り部」として、民族の日常や伝説や神話を語り聞かせるユダヤ人青年のことを回想する部分と、語り部が聞かせる物語が交互に展開する。 物語部分では、民族独自の世界認識が、奇想天外ではあるが生き生きと語られる。あまりにも荒唐無稽で面食らったが、これが彼らなりの原始的な世界認識なのだと理解し、坦々と読み進めた。 回想部分はずっとリアルで、ユダヤ人青年が都会を捨てて語り部となった経緯に迫っていく。そこには自分の顔の痣とキリスト教社会でのユダヤ人という二つの意味でのマイノリティとしての苦悩が発端となっている。そこから、原住民を強制的に文明社会へと取り込むことへの反感が生まれたようだ。ペルーの国内事情としては、広大なアマゾンを原住民だけのものにするのではなく、原住民を取り込んでアマゾンを開発しようという方向なので当然対立することになる。ユダヤ人青年は対立運動などを起こすのではなく、原住民に溶け込むことを選んだが、もはや原住民と運命を共にする以外に自分にできることはないと思ったのかもしれない。 一つの国の中にこれだけ文化の違う人間が存在しているということは、日本で言えば群馬の山奥に文明に接触したことのない民族がいるようなものなので、ちょっと想像することが難しい。
Posted by
南米文学の「普通」に慣れるにはまだまだ読書量が足りません。。南米文学自体がもはや密林。歩き回ってぐるぐる迷っているような、濁流に豪快に流されるような。
Posted by
2012.7記。 「チボの狂宴」の著者バルガス・リョサ再読。ペルーの少数民族マチゲンガ族の「語り部」が伝える神話的記憶と、人類学者の考察やドキュメンタリー制作の描写が交互に描かれる。 「木が血を流した時代」と語り部が呼ぶ、白人の過酷なゴムプランテーション経営による人口の激減、...
2012.7記。 「チボの狂宴」の著者バルガス・リョサ再読。ペルーの少数民族マチゲンガ族の「語り部」が伝える神話的記憶と、人類学者の考察やドキュメンタリー制作の描写が交互に描かれる。 「木が血を流した時代」と語り部が呼ぶ、白人の過酷なゴムプランテーション経営による人口の激減、乱開発から滅び行く民族を守ろうと努力する同じ白人の人類学者たち。定住し農耕することを教え、人口維持に貢献する学者たちは、しかし同時に境界なく森を行き来する民族の誇りと文化を破壊したのだろうか?こうした問題を考えさせられながら、めくるめく神話の数々にも圧倒される。 ところで、本作のハイライトである「大地の揺れ、怒りを鎮めるため突如姿を消す」マチゲンガの家族のシーンは、僕に村上春樹の「神の子どもたちはみな踊る」の冒頭部分を思い起こさせた。阪神淡路大震災の報道を一時もテレビの前を離れずに無言で見続けていた「妻」が、突然姿を消すところからこの小説は始まる。発想の源泉が偶々似ているのか、村上がリョサを読んでインスピレーションを受けたのか、とにかくいずれもとても印象的なシーンであった。
Posted by
現代の私が語る章と、密林の語り部が部族の神話を語る章とが折り重なるように繰り返す。語り部の章が断然よい。アマゾンに生きる少数民族の、いまを生きる神話が、まさに風前の灯の絶唱の如き生々しい生命力を感じさせる。 解説によると、リョサの半生にまたがるテーマを具現化したものだそうだ。物...
現代の私が語る章と、密林の語り部が部族の神話を語る章とが折り重なるように繰り返す。語り部の章が断然よい。アマゾンに生きる少数民族の、いまを生きる神話が、まさに風前の灯の絶唱の如き生々しい生命力を感じさせる。 解説によると、リョサの半生にまたがるテーマを具現化したものだそうだ。物語の出来上がりのレベルで考えれば、同じテーマの「緑の家」の方を上と見る読者が大半を占めると思われる。それでも、作者の思い入れが強い作品は別にある、ということは往々にしてある。 リョサの作品としては読みやすい、入門の書として絶好。
Posted by
命題は 「宗教やイデオロギーを超える精神的糧、刺激、人生の理由づけ、責務は あるか」 率直な感想は 「面白かったが、それを伝えるのに 330ページ必要か?220ページまで テーマが 全くわからなかった」 時間、場所、ストーリーテラーが 章ごと 変わる。視点を変えられるのに ...
命題は 「宗教やイデオロギーを超える精神的糧、刺激、人生の理由づけ、責務は あるか」 率直な感想は 「面白かったが、それを伝えるのに 330ページ必要か?220ページまで テーマが 全くわからなかった」 時間、場所、ストーリーテラーが 章ごと 変わる。視点を変えられるのに 慣れてくると、語り部が 密林で 物語る章は 本の中に異空間を演出している 著者の意図が 見えてくる
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ノーベル文学賞を取ったバルガス・リョサ氏の作品「密林の語り部」を読了。南米ペルーのウルバンバ川流域に住むマチゲンカ族のジャングルでの放浪の生活の物語が話の大筋かのように書かれてはいるが、いつは主人公の友人であるペールに住むユダヤ人であり、生まれながらに顔に大きな痣があるという聡明な青年の語り部の口を通して繰り広げられる、彼らの転生・放浪の物語が巧妙に織り込まれている。途中で読んでいて語りの主人公が変わっている事に気付き、それがああやはりペールから消えたと言われていた友人だということに気付く事ができる仕組みになっている。その仕組みをはっきりと意識し読み込みたかったので、本当に久しぶりに続けて二度読んだ。だから難解な本という事ではない。グローバル化の中での自国の文化をいかに守るのかという事に関しても考えさせてくれる内容だ。そんな骨太の南米文学を読むBGMに選んだのはMiles Davisの"The compete Live at the Pluged Nickel"。5枚組でライブの全容が聞けるのがすごい。疲れるけど。"Four and More"もいいけど。僕はこちらの方がより高いテンションのグループが聞けるから好きだ。https://www.youtube.com/watch?v=nyAO3twW_Mk
Posted by