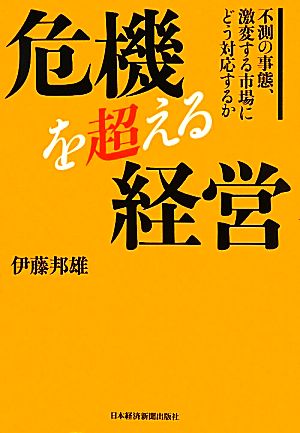危機を超える経営 の商品レビュー
危機を超えるには? →危機耐性力を支える行動原理は、PDCA+3Sであり、情報力を媒介として感知力、高速回転、危機意識 差異恒常化モデルとは、顧客認識価値の逓減問題を克服する手段であり、差異化再創出型である差異化の機能を付け加える方法と技術、認識価値連動型として、参入障壁や技術...
危機を超えるには? →危機耐性力を支える行動原理は、PDCA+3Sであり、情報力を媒介として感知力、高速回転、危機意識 差異恒常化モデルとは、顧客認識価値の逓減問題を克服する手段であり、差異化再創出型である差異化の機能を付け加える方法と技術、認識価値連動型として、参入障壁や技術優位性を築く方法がある 競争優位を構築する力として、顧客洞察力、技術融合力、文化発信力、他社資産活用力の4つ PDCAサイクルは見える化しておく
Posted by
リーマンショック、311といった危機を乗り越え、そして克服した企業の戦略・行動を分析した本。 さまざまな企業の事例を紹介しつつ、その中から日本企業再飛躍のための条件を導き出しています。 本書では、その危機を克服するための力として ・危機耐性力 ・危機進化力 と分析しています。...
リーマンショック、311といった危機を乗り越え、そして克服した企業の戦略・行動を分析した本。 さまざまな企業の事例を紹介しつつ、その中から日本企業再飛躍のための条件を導き出しています。 本書では、その危機を克服するための力として ・危機耐性力 ・危機進化力 と分析しています。 危機耐性力では3つの行動原理として 危機をすばやく感知する(Sensor) 高速回転する(Speed) 危機意識を熟成する(Sense of urgency) といった行動原理を分析し、スズキ、日本電産、キヤノン電子の事例を紹介しています。 さらに危機進化力としては3つの戦略を示し 高付加価値モデル 新興国最適化モデル 差異恒常化モデル として、3つの戦略について、多くの企業の事例を紹介しています。 そして、危機突破の行動原則として7つの試練と10の行動原則を導き出しています。 最終章では、311にとった各企業の対応をドキュメントタッチで紹介しています。311での各企業の行動は本当にすばらしいものだったと思いました。 本書でぜひ参考にしたいものが 新興国最適化モデル 差異恒常化モデル の戦略。 とりわけ、差異恒常化モデルとして、コモディティ化にどう対処するかというところはしっかり分析する必要がありそうです。 筆者によれば、コモディティ化に対応するには2つの戦略型があり、差異を付加するか参入障壁を築くかとのこと。 私たちのビジネスで考えると、ある程度参入障壁が築けてはいるものの、その中でもコモディティ化が進んでいるので、やはり差異を付加するしかなさそうです。 では何で差異を付加するかがポイントとなりますが、本書では、ユニチャーム、コマツ、ファーストリテイリング、シマノ、島精機といった企業の事例を紹介しています。自分たちのビジネス分野で何かしらのヒントにならないかなって思います。 250ページに各戦略モデルとそれに必要な力が分析されている図があってこれがとてもわかりやすいです。 これだけ、各企業の事例を分析し、わかりやすくまとめているのはとてもありがたい本です。 お勧めの一冊です。
Posted by
2012年10月末読了。 2011年末の本で、リーマンショック・東日本大震災という危機に対し、さまざまな企業がとったactionを取り上げ、そこに共通する力を、大きく情報・行動・恒常化の3点にまとめ論じた本。具体的な企業の具体的な対応が次々と数多く取り上げられている。ここまで多数...
2012年10月末読了。 2011年末の本で、リーマンショック・東日本大震災という危機に対し、さまざまな企業がとったactionを取り上げ、そこに共通する力を、大きく情報・行動・恒常化の3点にまとめ論じた本。具体的な企業の具体的な対応が次々と数多く取り上げられている。ここまで多数の企業の具体的なactionがまとめられている本はなかなか貴重だ(…と思う)。自分はメーカー勤務だから、読むのはビジネス本はメーカー関連のものが中心だけど、この本に取り上げられている企業の取り組みを読み、流通・金融にも企業経営には共通点が予想以上に多かった。 最終章に書いてあった震災直後の企業の団結力、人々のつながりに少し涙してしまった。本としての構成もさまざまな話題も取り上げながら本題は決してぶれることがなく、最後のまとめも美しかった(美しすぎ?)。良本でした。
Posted by
2011年9月という比較的早い時期にここまでまとめることができたのはさすが、という書籍。とくに震災後の企業の対応がまとめられている第12章の事例が読み応えあり。東京海上日動、日産、ローソンなど。
Posted by
リーマンショックを中心に、企業の対応事例をあげて一般化しようという内容。 表現はあまり好きではなかったが、エピソード本としては面白かった。 普段の仕事に活かせそうなこと。 ●ユニ・チャームの週次SAPS ●原因自分論
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著者は伊藤邦雄先生。 ケース分析の中からエッセンスをまとめ、帯びにもあるが「再飛躍の条件」を探る内容。 読んでて思うが、新興国最適化モデルなるものとか、自分が読んだ中だと『未来をつくる資本主義』の内容と酷似。BOPの成功ケースだとこの辺りしかないのか。 読んでて思うが、ケースに触れるほど、根本的には『人の力』だと。『知恵』だと。あと『人の力』を具現化できる、実行できる組織力だな。 備忘録。 ・そもそもだけど、リーマンショックのダメージが一番深刻なのは日本だという著者の主張。確かに鉱工業生産指数だとそうだ。メーカーだからか。確かにコスト削減余地が限られた中での一気な需要減は大変だ。 ・イノベーションは研究開発費の額とは関係ないbyジョブズ ・日本メーカーの危機→技術的差別化効果の減少と、新興国市場の台頭(日本が世界二位のマーケットではなくなったという意味で) ・ファブレスの強みと弱みと対策法の整理はわかりやすい。弱み→製造現場でのカイゼンを自前で出来ない。対策法→委託先にうまく競争原理を働かせる。 ・ネスレの現地化いい→ブランド階層を構築。コーポレートブランド→世界戦略ブランド→地域戦略ブランド→ローカルブランドとする。 ・色々と、○○力として整理していただけているが頭に入らないので、とりあえず、分析力が大事で、成功体験のそのままゴリ押しはダメ、と理解しておく。 そんなとこ。
Posted by
まさに、この本のタイトルが、経営者の悩み。 地震、タイの洪水、円高。。。何をそこまで、日本人に試練をあたえるのか? 危機耐性力には、感知力、高速回転(PDCA)、危機意識のキーワードが あるという。 感知力の源泉は、TOPと現場のつながりがベース。 日本電産の永守社...
まさに、この本のタイトルが、経営者の悩み。 地震、タイの洪水、円高。。。何をそこまで、日本人に試練をあたえるのか? 危機耐性力には、感知力、高速回転(PDCA)、危機意識のキーワードが あるという。 感知力の源泉は、TOPと現場のつながりがベース。 日本電産の永守社長は、「新幹線は渡廊下、飛行機はかけはし」といい 一年のほとんどを、現場ですごす。おそらく、ブレーンがしっかりしているから 外に出れるというのもあるだろうが、現場を大事にする姿勢はすごい!! 新聞にも出ていたが、図書館に通い、1929年の大恐慌を勉強し 経営に生かしているという。 ライチョウは、環境の変化に対応せず、ただ、高地に逃げたため 進化するのではなく、数が少なくなっていったそうだ。 変化をしなければ、どんな会社もライチョウになってしまう。 スズキは、車を生産していない国にいけば、100台でもTOPになれると はっぱをかけているという。このアグレッシブな姿勢が、生き残りにつながって いる。さあ、どうやって危機を乗り越えるか。。。
Posted by
日本の企業は、創意工夫と品質の良さ、コストで世界に存在感を示してきたが、新興国のキャッチアップと部品のモジュール化で、すでに日本企業の優位性は喪失した。それでもなお経営者の多くが,モノづくりへの考え方が転換できないところに、今の閉塞感があると著者は、指摘している。その後、今なお元...
日本の企業は、創意工夫と品質の良さ、コストで世界に存在感を示してきたが、新興国のキャッチアップと部品のモジュール化で、すでに日本企業の優位性は喪失した。それでもなお経営者の多くが,モノづくりへの考え方が転換できないところに、今の閉塞感があると著者は、指摘している。その後、今なお元気な企業の戦略や、東日本大震災で企業が見せた多様な対応力を示し、日本企業の目指すべき方向性を示唆している。
Posted by
危機を乗り越えることのできる体質を持つ(と、日経の読者なら普通に知っている)会社をいくつかピックアップしているが、「元気そうに見える」数社の、たまたま「目につく」活動だけから、経済雑誌の解説風の「柔軟たれ」「経営者の判断と社員にスピードを求める」「正確な情報を収集し駆使せよ」とい...
危機を乗り越えることのできる体質を持つ(と、日経の読者なら普通に知っている)会社をいくつかピックアップしているが、「元気そうに見える」数社の、たまたま「目につく」活動だけから、経済雑誌の解説風の「柔軟たれ」「経営者の判断と社員にスピードを求める」「正確な情報を収集し駆使せよ」という「別に言われなくてもわかってるんだけどね。実施するのはそりゃ難しいんだけど・・・」という処方箋を、日本アカデミック経営学の頂点に君臨する伊藤先生の権威で、むりやり本にしているだけだね、こりゃ。
Posted by
- 1