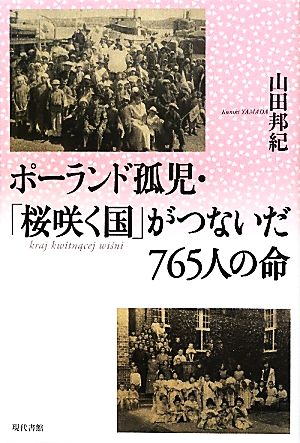ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ765人の命 の商品レビュー
『また, 桜の国で』(須賀しのぶ 著) を読み、1920年~22年の日本のポ-ランド孤児救済の経緯を探ってみました。▷日本政府・外務省はポーランドを追われたシベリア孤児の存在に深い同情を示すも、日本軍のシベリア出兵による戦費捻出に喘いでおり、孤児救済の予算的余裕がなかった。▷シベ...
『また, 桜の国で』(須賀しのぶ 著) を読み、1920年~22年の日本のポ-ランド孤児救済の経緯を探ってみました。▷日本政府・外務省はポーランドを追われたシベリア孤児の存在に深い同情を示すも、日本軍のシベリア出兵による戦費捻出に喘いでおり、孤児救済の予算的余裕がなかった。▷シベリア出兵に対する内外の批判をかわすため、日本赤十字社に救援事業を委嘱した。▷コルベ神父が長崎で布教のため来日(1930年~36年)したきっかけは、ポ-ランド孤児救済の報恩にあった。▷元孤児たちは、ナチス占領軍と果敢に戦っている。
Posted by
ポーランド孤児・「桜咲く国」がつないだ765人の命。山田邦紀先生。第1次世界大戦後に日本が当時のポーランド孤児に救いの手を差し伸べていただなんて知りませんでした。このような孤児を生み出す戦争は絶対になくさなくてはいけません。
Posted by
今から約九十年前、ロシアでの戦争のさなか孤児となったポーランドの子供たちがいた。自国民を助けようと立ち上がったポーランド救済委員会は孤児となった子供たちの救済のを各国に求めたがその要請に応じたのは日本だけだった。 1920年~22年にかけて700余名の在ロシアポーランド孤児が日...
今から約九十年前、ロシアでの戦争のさなか孤児となったポーランドの子供たちがいた。自国民を助けようと立ち上がったポーランド救済委員会は孤児となった子供たちの救済のを各国に求めたがその要請に応じたのは日本だけだった。 1920年~22年にかけて700余名の在ロシアポーランド孤児が日本を経由して祖国へと旅立っていった。この日本ではほとんど知られていない史実を描いています。 冒頭からのしばらくはロシアでポーランド孤児が生まれた歴史的背景が細かすぎるぐらいに描かれているので少々冗長な感じと思えるが、孤児を理解するためには必要だと思う。 その後本題である孤児の救済の状況へと移り、ロシアからの輸送、日本滞在中の国民諸氏の手厚いもてなしの様子などがえがかれてくる。 後半は孤児たちが過ごしたその後の人生へと進んでくるのだが、最後、高齢となった孤児の代表の方々がポーランドを訪問した天皇陛下と謁見する話のところは涙をこらえきれないものがある。 本書は戦災孤児救出ということでつながった日本とポーランド両国間の絆をその歴史的要因から救済の実態、その後の孤児たちと日本との関わりまでも精緻に描ききったこれ以上ない秀作だと思います。
Posted by
敦賀は天使が舞い降りた町、イスラエルは何百年も敦賀を忘れない。 ポーランド孤児院は日本大使館が面倒を見ていた。ゲシュタポが家宅捜査に来たら、日本大使館が助けに行った。身元は日本が保障する、君らに迷惑をかけないといって、堂々とした態度にゲシュタポも身をひいた。 95年の神戸大震...
敦賀は天使が舞い降りた町、イスラエルは何百年も敦賀を忘れない。 ポーランド孤児院は日本大使館が面倒を見ていた。ゲシュタポが家宅捜査に来たら、日本大使館が助けに行った。身元は日本が保障する、君らに迷惑をかけないといって、堂々とした態度にゲシュタポも身をひいた。 95年の神戸大震災の時には被災した孤児をポーランドに招いてくれた。
Posted by
第一次世界大戦後の1920年と1922年の二度、酷寒のシベリアからポーランド人孤児たち合計765人が日本赤十字社の手で救出された。孤児たちは日本国民の同情が集まる中、東京・大阪で保護されたあと、無事祖国へと帰還する。 生き延び、成長した孤児たちは第二次世界大戦下の時代を、ある者は...
第一次世界大戦後の1920年と1922年の二度、酷寒のシベリアからポーランド人孤児たち合計765人が日本赤十字社の手で救出された。孤児たちは日本国民の同情が集まる中、東京・大阪で保護されたあと、無事祖国へと帰還する。 生き延び、成長した孤児たちは第二次世界大戦下の時代を、ある者はドイツとソ連に再び引き裂かれたポーランドを取り戻すために戦い、ある者はナチスの迫害からユダヤ人を匿い、斃れ、または生き延び、そして、日本を忘れなかった。 なぜ、ポーランドから遠く離れたシベリアに多くの孤児が取り残される事態となったのか。なぜ、孤児たちは日本赤十字社の手にゆだねられたのか。 日本で保護され、祖国へと帰った孤児たちを待ち受けていた数奇な運命を主軸に、ポーランドとその周辺国の近代史を交えて記す歴史秘話。 読んでいる間中、『ジェノサイドの丘』下巻にある「政府とはつまりお医者さんと同じで、殺す時もある、助けられない時もある、助ける時もある。」という台詞を思い出さずにはいられませんでした。 数百人を救い出そうと、色々な国や機関が奔走し、民間の善意が寄せられるかたわらで、別の国や民族の手で数万人が殺されていく。 国とはそういうもの。人間とはそういうもの。ということを痛感する。「助けることもある。でも殺すこともある」。 日本とポーランドは「助けることもある」という国や人々の善意が通じ、第二次世界大戦では互いの地政学的理由から敵対してしまったにもかかわらず、深い関係を築くことができた良い例だと思います。「桜咲く国」とは、ポーランドが日本に対してつけてくれた美しい別称。
Posted by
- 1