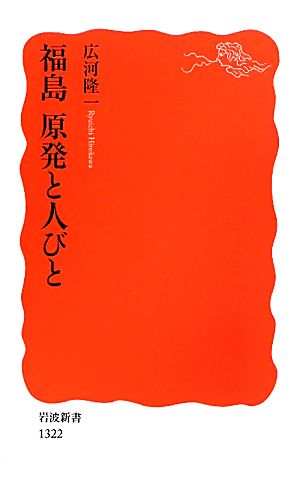福島 原発と人びと の商品レビュー
根拠のない安全神話は実際自分も疑うことはなかった。この話については結果論ではあるけど、著者の言う様に事故は起きないに越したことはないが、万が一起きた場合の対処が、人命救助よりも保身が強く働いた事は本当に人災だと思う。
Posted by
カテゴリ:図書館企画展示 2016年度第9回図書館企画展示 「災害を識る」 展示中の図書は借りることができますので、どうぞお早めにご来館ください。 開催期間:2017年3月1日(水) ~ 2017年4月15日(金) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペー...
カテゴリ:図書館企画展示 2016年度第9回図書館企画展示 「災害を識る」 展示中の図書は借りることができますので、どうぞお早めにご来館ください。 開催期間:2017年3月1日(水) ~ 2017年4月15日(金) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース
Posted by
東日本大震災から五ヶ月後に書かれた新書。福島第一原発のメルトダウン事故後、地元住民、事故処理作業員、避難した人々、子供たちの声を丁寧に拾いあげている。政府と東電が何を隠したのか、現在の進展状況と比較しても大差がないように感じました。
Posted by
3.11後、すぐに現地に入ったジャーナリスト、広河隆一氏のルポ。 直後の現場の状況やいかに現地で情報制御されていたかがよくわかる。 避難時の対応などチェルノブイリとも比較し、政府・東電が後手後手に回っているさまがよくわかる。 さきに読んだ原発収束作業日記では原発現場の内側からの...
3.11後、すぐに現地に入ったジャーナリスト、広河隆一氏のルポ。 直後の現場の状況やいかに現地で情報制御されていたかがよくわかる。 避難時の対応などチェルノブイリとも比較し、政府・東電が後手後手に回っているさまがよくわかる。 さきに読んだ原発収束作業日記では原発現場の内側からの状況が分かったが、外ではどうだったか。 合わせて読むと、全体が見えてくる。
Posted by
目をそむけずに知ってほしい声 先日、福島へ除染ボランティアに行ってきた これまで、暗い気持ちになることがいやで意図的に避けてきた現実 そこから一歩踏み出すことができたということに私はなんとなく満足していた しかし、本書によって改めて事故の深刻さを実感した 地元住人、原発作...
目をそむけずに知ってほしい声 先日、福島へ除染ボランティアに行ってきた これまで、暗い気持ちになることがいやで意図的に避けてきた現実 そこから一歩踏み出すことができたということに私はなんとなく満足していた しかし、本書によって改めて事故の深刻さを実感した 地元住人、原発作業員、避難してきた人々、そしてチェルノブイリの被害者達への丁寧な取材 事故の被災者達の声が切々と伝わってくる 同じ過ちを二度と繰り返さないように 私達が真剣に考える問題が本書にあると思う
Posted by
この本の中身をすべて信用することはできないが(他のメディアと同じ、という意味で)、どうしても東電や政府の対応は、被害者への賠償やその他のコストを抑えようとして動いているとしか思えない。チェルノブイリと同様、30km圏ないし放射能汚染がひどい地域は立ち入り不可とし、住民は集団移転さ...
この本の中身をすべて信用することはできないが(他のメディアと同じ、という意味で)、どうしても東電や政府の対応は、被害者への賠償やその他のコストを抑えようとして動いているとしか思えない。チェルノブイリと同様、30km圏ないし放射能汚染がひどい地域は立ち入り不可とし、住民は集団移転させて十分な賠償と生活保護をする方が、効果の現れにくい除染に大量の資金を投入するより被害者を直接支援できるので効果的であると思うのだが。私はアウトサイダーなので心情までは完全に汲み取れないという前提で。 こういう対応があるので、原発運営は外側からちゃんと管理・チェックができないという推定をしてしまう。 ストレスになるほど福島を支援するとか、福島を拒否するとかしない方が良い。原発事故での収入減は賠償されてしかるべきであるのだから。 どうしても、「福島の人たちはかわいそう、助けてあげたいけど自分のコストは支払いたくない」というのが政財界の主流意見なのだろう。管理できない危険な原発は止めて、コストが上がっても火力その他の発電をすべき、というのが私の今の意見。原発事故の被害者は、原発周辺の住民が過度にかぶるのに対し、発電コスト増は受益者全体が負担するのであるから、平等性がより高いと思われる。コストを支払いたくない人は、リスクを原発周辺住民に負わせる方が良いので原発稼働を支持するのだろう。周辺住民も雇用なり補助金なりで受益していたが、リスクとリターンは見合ってるのか? パニックをあおるから報道をしない、発表をしないとはどういうことだ?パニックになって逃げ出した方が被害が大きくなったと思っているのだろうか。何も知らないまま周辺住民を被曝させておいたほうが日本全体では利益が大きい、という判断か。知って不安になる方が知らずに不安でいることより精神衛生上ベター(少なくとも私にとっては)。
Posted by
真実。受け身であったらマスコミの報道しか入ってこない。それに洗脳され、安全だと思い込む。真実を知るには自らが情報を得ようとしなくてはならない。こうやって真実を告げるメディアはたくさん出て来ているのだから。そして、反原発はもちろんではあるのだが、最悪の事態にどうするか、原発を無くす...
真実。受け身であったらマスコミの報道しか入ってこない。それに洗脳され、安全だと思い込む。真実を知るには自らが情報を得ようとしなくてはならない。こうやって真実を告げるメディアはたくさん出て来ているのだから。そして、反原発はもちろんではあるのだが、最悪の事態にどうするか、原発を無くすのはなかなか難しいので、備えた様々な逃げ道を知恵を絞って用意しておくべきなのではないかと感じた。 原発って日本にとっては自爆装置だと思うんだけど。
Posted by
フォトジャーナリストにより執筆された、福島県での原発事故について書かれた本。 原発の被害によって苦しめられた人々を主に取材しているため、原発問題の概要を知りたいかたは他の本も参照したほうが良いかもしれない。 震災後の補正予算で、「ネット上の不正確情報の監視」のために予算が計...
フォトジャーナリストにより執筆された、福島県での原発事故について書かれた本。 原発の被害によって苦しめられた人々を主に取材しているため、原発問題の概要を知りたいかたは他の本も参照したほうが良いかもしれない。 震災後の補正予算で、「ネット上の不正確情報の監視」のために予算が計上されていたと知り驚いた。確かにあからさまなデマや風評被害を防ぐという効果も果たしてはいるのだろうが、政府にとって不都合な情報が隠蔽されるということが起こりえないだろうか。 これまでにも何度となく悲しい「風評被害」が報じられてきたが、この本に書かれている話も悲惨だ。安全宣言が出ているいわき出身の方が輸血を拒否され(厚生省の基準から見ても不当なものであった)、かつ遺伝子や被爆状態を検査する場所もない。さらにはその事をネットに書くとバッシングを受けたという例や、子供たちを安全な場所に避難させようとすると「逃げるのか」「卑怯者」と罵られる。マスクをするといじめられる子供の出現、洗濯物を干す場所でさえ気軽に話すことがままならない。校庭の使用する際の安全性を問いただすと「ここに来ている以上学校の方針を受け入れろ」と質問を遮り拍手が起きるという、不安を表に出すことすらままならない雰囲気。ギスギスした空気であることが否が応にも伝わってくる。 チェルノブイリ事故の写真、特に事故で苦しむ方の写真は見ていて胸が痛くなった。この事故でもデータを隠蔽し、責任逃れをしようとしていた事が分かっている。 あとがきも含めると全体で213ページ、見開きの写真も含んでこのページ数であるが、内容は決して薄くはない。 無責任な言葉を垂れ流す御用学者山下俊一・関村直人・長瀧重信・高村昇らがいる一方で、小佐古敏荘・小出裕章氏といった比較的信用できる学者がいる。自分たちで何が正しいのかを見極めなければいけない。
Posted by
(2012.07.14読了)(2012.07.12借入) 【東日本大震災関連・その98】 チェルノブイリの原発事故の取材をしたことのある著者による、福島第一原発事故に関するルポです。写真もたくさん収録されています。 地元住民、事故処理に携わる作業員、避難した人々、等の声の報告です...
(2012.07.14読了)(2012.07.12借入) 【東日本大震災関連・その98】 チェルノブイリの原発事故の取材をしたことのある著者による、福島第一原発事故に関するルポです。写真もたくさん収録されています。 地元住民、事故処理に携わる作業員、避難した人々、等の声の報告です。 【目次】 第1章 地震、そして事故発生 第2章 原発作業員は何を見たか 第3章 避難した人びと 第4章 事故の隠蔽とメディア 第5章 広がる放射能被害 第6章 子どもと学校 第7章 チェルノブイリから何を学ぶか 第8章 これからのこと あとがき ●念のための避難(17頁) 避難のために街を出るときも、数千円しか持たない人が多かったという。 みんなすぐに公民館などに集められ、数日の避難だと告げられてバスに乗せられた。避難生活も三日目を迎えると、ある人は預金通帳を取りに、ある人はペットに餌を与えに戻ってきていた。 ●原発復旧作業(36頁) そのうち「赤紙」つまり戻れという連絡が来た。それを見て彼は「人海戦術の海になる」ことを覚悟した。戻ることにしたのだ。その時の気持ちは「ああ、おそらくこれから死ぬんだろうな」というものだった。 ●自衛隊が姿を消した(40頁) 自衛隊がなぜ姿を消したのかはすぐに分かった。3号機の爆発のときに、東京電力は「絶対爆発はしないから大丈夫」と言うので、自衛隊は装甲車ではなくジープのような車で現場に行った。車が3号機のそばに着くのと爆発はほとんど同時だった。車は吹き飛ばされた。「隊員のけがは打撲程度」とメディアには発表されたが、実際は打撲どころか下半身不随になった隊員もいたという噂が作業員作業員の間で流れていた。 ●東京も(61頁) 地震と津波に襲われた後、家族の誰一人、原発が危ないなんて思わなかった。しかし爆発したと聞いて久美さんは「ありえない」と思った。昔から周りでは、原発が爆発するときには東京の人もみんな死んでしまうんだと話していた。 ●戦争と原子力(80頁) 戦争と原子力災害に共通なのは、「加害者は市民の被害を隠す」ということである。そして今回、この〝原則〟にマスコミが乗り、巨大な「記者クラブ」が出来上がった。 ●原発産業(84頁) チェルノブイリ事故の後、原発産業とは、まず国民を欺くものであるという認識が世界中に広まっていった。 他の産業とは異なり、ひとたび事故を起こすと巨大な規模の被害を生み出すからである。しかし、「安全」のために必要な資金を投入すると、赤字になる。そのため事故が起きても、それをなかったことにし、安全だと言い続け、隠蔽し、犠牲者が出ても見捨てることになる。さらに放射能と病気の関連を実証するのは困難であることをいいことに、保障もしない。 ●子どもは産みません(137頁) 「友達の娘さんは高校生なんですけど、チェルノブイリの話や放射能の危険について聞かせて、一応本人に「疎開する?」って聞いたら「友達から離れるのは嫌だし、友達置いて自分だけ逃げるのも嫌だ」って。そして最後に「私は将来結婚するとしても、子どもは産みません。そういう覚悟でここに残る」って言ったんですって。 ●放射線防護服(174頁) 今、福島第一原発で作業員が着用している白い服はなんだろう。正確な言い方ではあれは「放射線防護服」ではない。放射性物質が付着したときなどに脱いで捨てるための衣類だ。危険な場所に行くには、放射線を防ぐ手段はないから、結局作業時間を短く制限して、交代するほかない。 ☆広河隆一の本(既読) 「パレスチナ」広河隆一著、岩波新書、1987.08.20 「パレスチナ 瓦礫の中のこどもたち」広河隆一著、徳間文庫、2001.02.15 「チェルノブイリ報告」広河隆一著、岩波新書、1991.04.19 (2012年7月16日・記)
Posted by
事故発生から作業員のルポ、周辺に暮らす人びとのルポ、彼らの見聞きし感じるものとのギャップが大きいメディアや政府、東電の発表や情報。そして周辺にとどまらず広がる放射能被害を、チェルノブイリも引用しながら伝えてくれている。暮らしや望みを奪われた人たちと「これから」一緒に生きていく方法...
事故発生から作業員のルポ、周辺に暮らす人びとのルポ、彼らの見聞きし感じるものとのギャップが大きいメディアや政府、東電の発表や情報。そして周辺にとどまらず広がる放射能被害を、チェルノブイリも引用しながら伝えてくれている。暮らしや望みを奪われた人たちと「これから」一緒に生きていく方法を探していきたいと思う。これ以上の犠牲はもういらない。 12/07/20再読 チェルノブイリ支援してるNGOでのインタビューを深めるため。 今ふくしまに生きる人の姿。 根本的に変えたいのは、ライフスタイルとコミュニティのre-desighne
Posted by