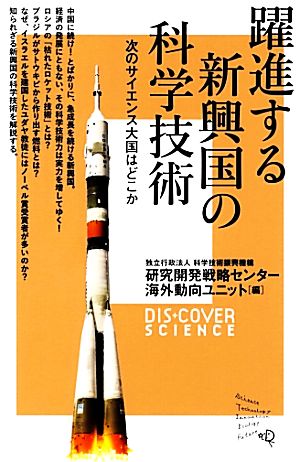躍進する新興国の科学技術 の商品レビュー
新興国の科学技術はどちらかというと産業と密接な分野が中心のような気がするが、いずれにせよ、多くの振興国が得意分野に集中投資している様子がうかがえ興味深い。
Posted by
中国を除くBRICS・東南アジア諸国における科学技術政策について、コンパクトに報告されている。今後、情報収集する際に必要な、自分自身の指向性アンテナを調整することができるだろう。JSTによるものなので、台湾に対する記述に過剰な配慮が見られた。同国の李遠哲氏がかかわった政策について...
中国を除くBRICS・東南アジア諸国における科学技術政策について、コンパクトに報告されている。今後、情報収集する際に必要な、自分自身の指向性アンテナを調整することができるだろう。JSTによるものなので、台湾に対する記述に過剰な配慮が見られた。同国の李遠哲氏がかかわった政策については以下を参照。 http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Topics/pdf/51_09.pdf
Posted by
JST研究開発戦略センターってところが、中国以外の新興国科学技術政策についてまとめた本。IT系では滅茶苦茶存在感があるイスラエルの章が興味深かった。イスラエルの教育レベルが高いのは言わずもながなんだけど、ソ連崩壊時に優秀な研究者が大量に流入し、西欧と東欧の科学の融合により、新たな...
JST研究開発戦略センターってところが、中国以外の新興国科学技術政策についてまとめた本。IT系では滅茶苦茶存在感があるイスラエルの章が興味深かった。イスラエルの教育レベルが高いのは言わずもながなんだけど、ソ連崩壊時に優秀な研究者が大量に流入し、西欧と東欧の科学の融合により、新たな科学技術が発展したとか。起業国家とも呼ばれる礎を作ったヨズマプロジェクトとか。
Posted by
中国やアジアあたりの情報は他の書籍でも見ていたが,ロシア,ブラジル,南ア,イスラエル,あたりの状況は目新しかった.
Posted by
ロシアのプーチンリストは8項目ある。 ・安全保障とテロが含まれている。 ロシアはソ連時代の1957年に世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げている。 ロシアでもイノベーションが流行語になっており、ロシア版シリコンバレーのスコルコヴォ・イノベーションセンターの創設が進んでいる。...
ロシアのプーチンリストは8項目ある。 ・安全保障とテロが含まれている。 ロシアはソ連時代の1957年に世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げている。 ロシアでもイノベーションが流行語になっており、ロシア版シリコンバレーのスコルコヴォ・イノベーションセンターの創設が進んでいる。欧米の企業も積極的な関心を示している。ロシアは世界最大の資源大国であり、エネルギーを梃子に国益を追求する姿勢は明白。ロシアがイノベーション路線を放棄して、今以上に資源外交をついきゅすれば天然ガスで首根っこを押さえられている応手は深刻なエネルギー問題に直面する。 インド人の英語はきれいになってきた。コールセンターのおかげであろう。インド人の英語がわかりにくいなんていっているようではだめ。 イスラエルは世界最高の技術力を持っていることは疑いない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ジュンクでたまたま目に留まり購入。 チャンギ国際空港@シンガポールで一夜を明かすために持って行った。無事、読了。 この本のちょうど前に読んだ、「ハーバードのなんちゃら授業」と扱っている国が近く、その対比で読めたのでよかった。が、科学技術振興機構の編にもかかわらず、文体が結構ユルいのが気になる。。 ロシア、インド、ブラジル、南アフリカ、韓国、イスラエル、東南アジア、台湾、のそれぞれについての科学技術の動向や科学技術政策について解説している。しかし、単なる事例紹介の感は否めない。本全体の構造やストーリーが見えず。 (この本に限らず、日本の科学技術政策研究・書籍などは世界標準の科学技術政策研究に則っているのか、正直疑問を感じることが多くある。。) 主に各国の科学技術政策について記述が充実。各国における教育事情もそれなりに詳しいが、産業との連携に関してはあまり重きを置かれていない様子。 ブラジルとイスラエルの科学技術については勉強になった。各国の歴史から、その国に特徴的な科学技術の発展が導かれている点。国の発展の経路依存性を強く感じる。
Posted by
中国以外の「新興国」の科学技術について紹介している本。 なお、中国に関しては別途刊行予定とのこと。 あくまで「多くの国を紹介する」という内容なので、出来れば次は例えば「ブラジルの科学技術」みたいに個別の国に絞った内容の本の刊行を期待したい。
Posted by
各新興国の技術や研究活動について記されていて、BRICsやイスラエルや南アへの興味以上の好奇心を呼び起こさない程度の本だった。基本的には各国の政府なり企業なりの研究や開発への投資活動について細かく説明されてはいるが、そのそれぞれがどれほど将来への影響力があるか未知数であり筆者はそ...
各新興国の技術や研究活動について記されていて、BRICsやイスラエルや南アへの興味以上の好奇心を呼び起こさない程度の本だった。基本的には各国の政府なり企業なりの研究や開発への投資活動について細かく説明されてはいるが、そのそれぞれがどれほど将来への影響力があるか未知数であり筆者はそのどれをも「すごい!」と思わせんばかりの描き方をしており、少々誇張がすぎる。すごいかどうかはこちらご決める。金額ベースでみたらアメリカや日本のほうがR&Dでは上なので依然すごいと思える 本のタイトルほどすごい内容があるわけでもない、そんな図書です
Posted by
ロシア、インド、ブラジル、南ア、韓国、イスラエル、東南アジア、台湾の科学技術について、研究開発の概況や、それぞれの国で発達している技術分野について簡単に説明している。 それほど厚い本でもないのに、8カ国も詰め込んである為、一カ国あたりの情報量はそれほど多くなく、新興国全体の動向...
ロシア、インド、ブラジル、南ア、韓国、イスラエル、東南アジア、台湾の科学技術について、研究開発の概況や、それぞれの国で発達している技術分野について簡単に説明している。 それほど厚い本でもないのに、8カ国も詰め込んである為、一カ国あたりの情報量はそれほど多くなく、新興国全体の動向を概括するようなこともしていない。タイトルに興味をひかれた人が軽い気持ちで読むというのが正解だろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本に出てくる新興国のうち、ロシアとイスラエルを除けば、公文式が進出している国ばかり(インド、ブラジル、南アフリカ、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、台湾)。 科学技術をテコに躍進しようとしている国だからこそ、教育も熱心なんだろうな…。
Posted by
- 1