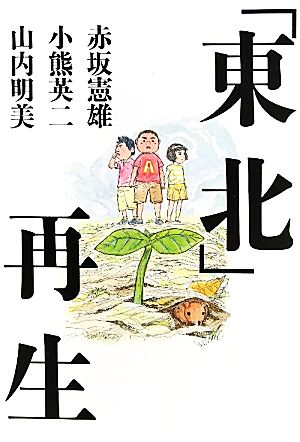「東北」再生 の商品レビュー
東北学の赤坂憲雄、社会学の小熊英二、そして三陸出身の若き論客山内明美の3者によるアピールと提言。「東北は東京の植民地」―これまでもそうだったし今もなおそうなのだ。労働力と食糧とエネルギーを供給し、原発の危険をも引き受けて。したがって、東北が復興したところで、それが繰り返されるだけ...
東北学の赤坂憲雄、社会学の小熊英二、そして三陸出身の若き論客山内明美の3者によるアピールと提言。「東北は東京の植民地」―これまでもそうだったし今もなおそうなのだ。労働力と食糧とエネルギーを供給し、原発の危険をも引き受けて。したがって、東北が復興したところで、それが繰り返されるだけだ。今こそ東北の真の再生を、すなわちパラダイムシフトを図らなければならない。「福島をエネルギー特区に」との赤坂の提言は一聴に値する。今こそ本当の意味での構造的な改革のチャンスであるのかもしれない。いや、そうしなければならないのだ。
Posted by
タイトルで、購入。 震災直後の5月の対談。復興構想会議のメンバーだった赤坂さんなどが対談。 復興構想会議ってなんだったんだろうな。 3人とも興奮していて、今時点でよむとちょっと混乱気味。 気になったコメント。 (1)山内:私個人としては、東北はどんなに低開発と...
タイトルで、購入。 震災直後の5月の対談。復興構想会議のメンバーだった赤坂さんなどが対談。 復興構想会議ってなんだったんだろうな。 3人とも興奮していて、今時点でよむとちょっと混乱気味。 気になったコメント。 (1)山内:私個人としては、東北はどんなに低開発と呼ばれようとも、一次産業で立っていける場所にしたいのです。(p46) (2)小熊:よほどプランをきちんと考えて、これからのトレンドがどこに向いているのかも考えて、新しい産業をおこす方向で公共投資を使わないと、被災地の未来は高齢者と財政赤字だけが残る新築の過疎地です。(p60) 新しい産業でなくても、とにかく生業、かせぎを確保するという観点が今求められていると思う。済む場所は、一応、問題はあるけど、仮設住宅、災害公営と対応ができているが、復興まちづくりのなかで、かせぎをどう確保するか、地元の産業をどう復興の目処をつけるかについての配慮がかけているのが気になる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
終章、小熊英二の「近代日本を超える構想力」が小論ながら、戦前・戦後史を踏まえた、食糧と労働力の供給地としての東北、さらには電力供給地としての東北、への分析・論考が説得力あるものとなっている。
Posted by
『こども東北学』のあと、この本を借りてきた。昨年の5月1日、3月11日から51日目に、半ば公開のかたちでおこなわれた赤坂憲雄+小熊英二+山内明美の鼎談を「I」に、山内と小熊の既発表のテキストをもとに書かれた2つの文章を「II」に、それぞれ収録した本。 「最後[ケガヅ]の場所か...
『こども東北学』のあと、この本を借りてきた。昨年の5月1日、3月11日から51日目に、半ば公開のかたちでおこなわれた赤坂憲雄+小熊英二+山内明美の鼎談を「I」に、山内と小熊の既発表のテキストをもとに書かれた2つの文章を「II」に、それぞれ収録した本。 「最後[ケガヅ]の場所からの思想」の末尾で、山内はこう書いている。 ▼…未来の東北を奪還する手だてがあるとすれば、それはたぶん、「ほんたうの農業と漁業」のあり方を模索することだろうと思う。その道のりは、これまでとは比較にならないほど過酷だろうと思う。それでも、東北ならできると思う。ここは、地獄絵図のような生き死にの紡がれた歴史の中で、くり返し死の淵から再生をとげてきた場所だからだ。 巨大な樹木が倒れたあと、無数の蘖[ひこばえ]があらわれるように、「東北」は、きっと再生する。(pp.122-123) 鼎談のなかで、山内はこう語ってもいた。 ▼私個人としては、東北がどんなに低開発と呼ばれようとも、一次産業で立っていける場所にしたいのです。今回被災した地域は、「ケガチ」と呼ばれる飢饉の頻発地帯です。そこに暮らす日とは「ケガヅ」と言いますが、いずれにしても、文字どおり「ケ」、つまり日常の、ことに食料が欠けがちな場所なのです。地震も津波も冷害もある。陸で生きるのも浜で生きるのも過酷な場所です。過去の歴史のなかでどれほど津波が起きてきたのか、私たちはあらためて知りましたが、それでも、漁師が漁をやめたことはありませんでした。過酷な自然に対峙しながら、ここまで続いてきたのです。いま、私たちは、この深刻な汚染を発端として、将来へ向けてどんな「生のあり方」が可能なのか、未来への責任とともに考える時期にあるのだと思います。(p.46) 3人は、東北はどのような場所としてこれまであったのかと共に、この先どんな「生のあり方」が可能なのか、新しい社会をどのように構想していくのか、と語りあう。 赤坂は、自分たちが学問としてやってきたことのなかに、社会の批判は山ほどあったけれど、どんな世界をつくっていったらいいのか、これからの社会のあり方を大きな構想力をもって提示することはしてこなかったと振り返る。 小熊は、ナショナリズムに関して、「がんばれ日本」や「日本の転機」といった論調が東京のマスメディアを中心として出てきたが、阪神大震災のときを思い出しても、あのときは「がんばれ日本」という形にはならなかったし、例えば同じ規模の地震が沖縄で起きたとしても「がんばれ沖縄」にはなっても「がんばれ日本」にはならないのではと書く。それは、東京の政治家やビジネスマンやマスメディア関連の人も揺れて、放射能のキケンを感じたからではないかと。 ▼メディアを中心として人口の三割が集まっている東京圏が危機に陥らないと、そういう形にはならないというのが正直な印象です。(pp.90-91) 3人の語りは、またあるのかもしれない。時間が経つにつれて、変わっていくこともたくさんあるだろうと思う。けれど、この51日目の語りを読んで、私自身のなかにもやもやと残る"感じ"を、ときどきこれを読みかえして、自分でしっかり感じたいと思った。 そこのところで、赤坂の「現場の声」と「よそ者」の思考についてのこの一節は、遠くにいる私にとって、そうなのかもしれない、と思えた。 ▼今回本当に僕は、現場ってなんだろうなって思いました。現場の声が正しいなんて本当に思えない。でも現場の声を大事にしたい。常に引き裂かれて、知らん顔したり、寄り添った顔したり、自分でも実にいい加減だと思いながら、それしかできないのかもしれないと思っています。(p.103) (1/18了)
Posted by
東日本大震災によってあらわになった、東北の問題、原発の問題、日本の歴史、経済、政治の問題、ここに今生きている僕たちの問題。 しっかりと現実を見つめ、なんとか希望を語ろうと問いかける鼎談。 少なくとも僕が見聞した中では今回の災害に関してもっとも正直な問いかけがちりばめられている本だ...
東日本大震災によってあらわになった、東北の問題、原発の問題、日本の歴史、経済、政治の問題、ここに今生きている僕たちの問題。 しっかりと現実を見つめ、なんとか希望を語ろうと問いかける鼎談。 少なくとも僕が見聞した中では今回の災害に関してもっとも正直な問いかけがちりばめられている本だと思う。引用を参照のこと。
Posted by
福島県立博物館長である赤坂憲雄氏と小熊英二氏,そしてまだ学生(と言っても博士課程)の山内明美氏との鼎談集です。 赤坂さんが原発事故を引き合いに出して,「東北はまだ植民地だったんだ」と言った言葉が頭から離れません。それまで原発に対して曖昧な態度だったという赤坂さんは,今回の事故...
福島県立博物館長である赤坂憲雄氏と小熊英二氏,そしてまだ学生(と言っても博士課程)の山内明美氏との鼎談集です。 赤坂さんが原発事故を引き合いに出して,「東北はまだ植民地だったんだ」と言った言葉が頭から離れません。それまで原発に対して曖昧な態度だったという赤坂さんは,今回の事故で立場をはっきりさせて行動しています。「いわなくてはならない」「行動しなくてはならない」と思ったそうです。 わたしのすんでいる能登半島も「大都市の植民地」なのじゃないかと思います。 小熊氏が,「今回の震災がもし沖縄にあったても,やはり「がんばれ日本」って言っただろうか…」と疑問を投げかけます。わたしは,言わないような気がします。その違いはなんでしょうか。そんな新たな視点も与えてくれる本です。
Posted by
「東北学」とかで有名な赤坂憲雄さんを含む3人の講演等をベースにした一冊。東北が抱えてきた構造的な問題をそのままにして、既存の公共投資を引き込む復興モデルを繰り返しても意味がない、という趣旨は大いに共感するが…「じゃあどうするんだ?」という部分がなんか軽い。問題が大きいからどうしよ...
「東北学」とかで有名な赤坂憲雄さんを含む3人の講演等をベースにした一冊。東北が抱えてきた構造的な問題をそのままにして、既存の公共投資を引き込む復興モデルを繰り返しても意味がない、という趣旨は大いに共感するが…「じゃあどうするんだ?」という部分がなんか軽い。問題が大きいからどうしようもないのはわかるんだけど…独特の徒労感が読了後に漂う一冊だった。悪い本じゃないんだけどね。
Posted by
- 1