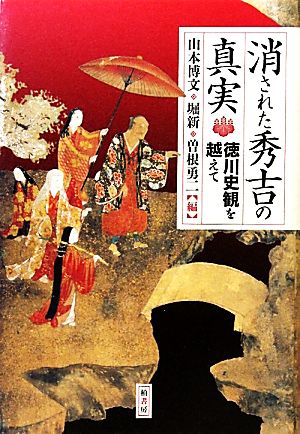消された秀吉の真実 の商品レビュー
まあ良いんですけどね。 日本は、鬼でさえ徹底的な悪としないというのは、そうなんですけど、古事記も聖書も神話も、権力者にによって「作られたもの」というのは忘れてはいけない。 それらにばかり論拠を求めているのはちょっとね。
Posted by
豊臣政権の盤石ぶりとその弱点について、とくに徳川家の取り扱いという点で再検討、という感じか。 豊臣政権の位置づけを中世と近世の二つの視点からもっと大きく解説してくれた方が素人としては読みやすかった気もするんだけども。奉公衆や同朋衆など、室町時代から続く個人商店的、もっと言えば近...
豊臣政権の盤石ぶりとその弱点について、とくに徳川家の取り扱いという点で再検討、という感じか。 豊臣政権の位置づけを中世と近世の二つの視点からもっと大きく解説してくれた方が素人としては読みやすかった気もするんだけども。奉公衆や同朋衆など、室町時代から続く個人商店的、もっと言えば近代のカリスマ型指導者に近い組織運営と、より官僚的な組織運営と、秀吉政権と徳川政権、足利政権の政治過程を比較すると現代史っぽい切り口もあり得るんじゃないかなというのが読後の直観。
Posted by
元和から始まる徹底した徳川の神格化によって、歪められた豊臣の歴史や功績を検証する、という内容。 だからといって、徳川家を糾弾しているわけでもありません。 古文書の対訳も分かりやすく説明されています。 ●長久手の戦い ●豊臣政権の大名統制と取次 ●刀狩令に見る秀吉法令の特質 ●秀...
元和から始まる徹底した徳川の神格化によって、歪められた豊臣の歴史や功績を検証する、という内容。 だからといって、徳川家を糾弾しているわけでもありません。 古文書の対訳も分かりやすく説明されています。 ●長久手の戦い ●豊臣政権の大名統制と取次 ●刀狩令に見る秀吉法令の特質 ●秀吉の右筆 ●豊臣秀吉と「豊臣」家康 ●人掃令を読みなおす ●秀吉と情報 ●太閤秀吉と関白秀次 ●秀次事件と血判起請文・「掟書」の諸問題 ●秀吉の遺言と「五大老」・「五奉行」
Posted by
家康は、豊臣家康を名乗らされていた。秀吉政権下 の複雑な人間関係に切り込み、最も新しい秀吉像と 豊臣政権の姿を描く。10本の論文を収録。 まずは、装丁が素晴らしい。カバー図版は醍醐の花 見図屏風からとられている。 次に、秀吉文書の原本の写真が掲げられているのが 良い...
家康は、豊臣家康を名乗らされていた。秀吉政権下 の複雑な人間関係に切り込み、最も新しい秀吉像と 豊臣政権の姿を描く。10本の論文を収録。 まずは、装丁が素晴らしい。カバー図版は醍醐の花 見図屏風からとられている。 次に、秀吉文書の原本の写真が掲げられているのが 良い。ハードカバーならではと言える。 さて内容であるが、本書の論文が通説となるかどう かは、今後、さらに研究者達によって練られていく 必要があるのだろう。内容的には、従来の説に対し 問題点の提示にとどまっているだけのものもあり、 やや物足りない気もするが、本書の内容は十分刺激 的である。 秀吉は征夷大将軍を望んでいたが、源氏ではないた め、次善の策として関白となったという話がある。 本書によると、この話は江戸時代に作られたもので あり、秀吉時代の史料には、天皇に将軍任官を勧め られて断ったという記録があるという。 よく考えてみれば、関白になる方が難しく、藤原氏 の内紛に乗じて、たなぼた式に関白になったのが実 態だという。(信長も三職推任を受けているので、 源氏でなければ将軍になれないという話には疑問符 がつく) 太閤検地、刀狩り、朝鮮出兵という事柄は有名であ るが、秀吉政権というものがどの様に運営されてい たのかがわからないが、取次や右筆の役割から一端 を窺い知ることが出来て面白い。 本書では、山本博文と三鬼清一郎の論争にも触れら ている。本書が新たな「たたき台」として生かされ れば、大変有意義であろう。
Posted by
誤解を恐れずに言えば、市民大学での古文書講義といった趣の論文集。 豊臣関連古文書というお題にて、10人の研究者がそれぞれ選んだ古文書を徹底的に掘り下げるという内容である。一般向けを意識したためか、丁寧語表現?の文章なのと、古文書の写真に加えて釈文と現代語解釈が併記されていてとても...
誤解を恐れずに言えば、市民大学での古文書講義といった趣の論文集。 豊臣関連古文書というお題にて、10人の研究者がそれぞれ選んだ古文書を徹底的に掘り下げるという内容である。一般向けを意識したためか、丁寧語表現?の文章なのと、古文書の写真に加えて釈文と現代語解釈が併記されていてとてもわかりやすくなっているのが好印象だ。そして、古文書の解釈を踏まえて研究史とともに議論を展開するというスタイルは、歴史学研究の醍醐味を十分に味わえると思われる。反面、限られた紙幅の中で字数が取られてしまうという制限もあり、ページ数に対する論者数から考えても、説明不足すぎるのでは?これは研究ノート段階でまとまりに欠けるのでは?、本テーマに沿っているの?(「徳川史観を越えて」という副題が付いている)、唐突な議論展開などといった残念な箇所は次回の反省点としてもらいたい。 本書の統一テーマである脱徳川史観の観点でいえば、笠谷和比古の「二重公儀」論に対し、徳川家康は一貫して源姓だったのではなく、「羽柴」名字を受けていた関係上、一時期、豊臣姓だった可能性があり、潜在的な「将軍」として「二重公儀」構造ではなかったという論は面白かった。 他にも秀吉遺言や小牧・長久手の戦いの評価、朝鮮での情報伝達など興味深い論も多かったのだが、自分としては豊臣関連古文書を読むキーワードとして、自敬表現と書札礼の話はなかなか興味深かった。 今後も、このようなコンセプトでの出版を期待します。
Posted by
- 1