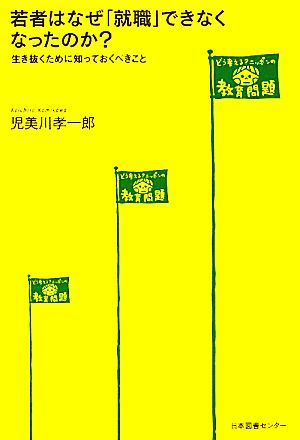若者はなぜ「就職」できなくなったのか? の商品レビュー
終身雇用、年功序列は崩壊していく構造。会社の中の立ち位置でなく、世界を含む社会全体で何が求められるのかを強く意識していかないと、生きることもできない。日本社会の教育、就職、労働モデルへの危機感を感じさせる。
Posted by
法政大学の就職専門(キャリアデザイン学部)の教授による研究成果が本書です。 高度成長時代に形成された「新規学卒一括採用」による「日本的雇用(長期雇用・年功序列型賃金など)」に、すなわち、学校から仕事へという接続構造に、低成長の続いた近年、大企業が正社員枠を減らすという構造的変化が...
法政大学の就職専門(キャリアデザイン学部)の教授による研究成果が本書です。 高度成長時代に形成された「新規学卒一括採用」による「日本的雇用(長期雇用・年功序列型賃金など)」に、すなわち、学校から仕事へという接続構造に、低成長の続いた近年、大企業が正社員枠を減らすという構造的変化が生じたことによる影響を説明しています。 これが本書の表題である「若者がなぜ『就職』できなくなったのか?」の説明です。 この問題に対する政府の対策および学校側の対応などについて、状況評価と、中・長期的な著者の提案が述べられています。 読後の感想として、就職に直面している若者には、参考となる記述は少なく、保護者・父兄には、すでに断片的に知っているこの社会問題を整理して理解できます。
Posted by
採用枠が狭くなってるので、新卒があぶれるのは当たりまえ。要は、そのあぶれた人たちが落ちこぼれ意識を持たず、長いスパンで就活できる環境を作ることが必要だと思った。
Posted by
(「BOOK」データベースより) 「日本的雇用」、「新規学卒就職」モデルの崩壊!悪化する「就職内定率」、燃え尽きる「正社員」、使い捨てられる「非正規労働者」、付け焼刃の「学校教育」。ルールなき時代を漕ぎ渡るキャリアとは?無防備なままに若者を社会に放り出すな。
Posted by
本書は、「若者の就職問題」を大学の側からの視点でとらえた本であるが、わかりにくい上に、問題のとらえ方が甘く、理解しにくく、あまり評価できないと思った。 本書によれば、大学3年の後期に実質的な「就活」がはじまることにより大学教育は実質2年半となっているというが、そんなことは一般...
本書は、「若者の就職問題」を大学の側からの視点でとらえた本であるが、わかりにくい上に、問題のとらえ方が甘く、理解しにくく、あまり評価できないと思った。 本書によれば、大学3年の後期に実質的な「就活」がはじまることにより大学教育は実質2年半となっているというが、そんなことは一般常識であり、もっと詳細な実情が聞きたいと思った。「エンプロビリティ(雇用されるための能力)」や「学歴代替」などの説明はあるが、現状についての記載も多くはなく、学生達がおかれた実情がわかりにくいものとなっている。著者は学校内部の人間であるのだから、もっと詳細な報告を期待したのだが、物足りない。 本書には「新規学歴一括採用」「日本的雇用システム」などの記載はあるが、この程度では全体像はよくわからない。本として著するのであれば、学校関係者としての詳細なデータや、より専門的な認識を期待するものである。 また、現状をどうすればよいかの結論についても、説得力がなく、夢ももてないものとなっているように思える。 本書の主張する「学校制度改革」。そのようなもので、学生の置かれた現状が改善できるのだろうかという疑問は当然出てくる。また、「学校教育の職業的レリバランスの強化」「格差的労働市場の改革」「職業能力開発に資する生涯学習社会の構築」を三種の神器としているが、これも説得力が薄い。 若者が就職できなくなった理由は、グローバル経済の進展による歴史的な経済状況の変化によるものと思われる以上、個人の心構えや、短期的な政策対応では手に負えない課題であることは明らかである。これへの対処には、もっと広範かつ深い考察が必要であると思えるが、本書にはそれがあるようには思えない。書名からも、学校関係者からの「学生の置かれた過酷な現状の赤裸々な実態」と「歴史的な日本資本主義の現状や労働事情の学術的な深い考察」を期待したが、ちょっと期待はずれの1冊であった。
Posted by
自分の息子が大学生なので、若者の「就職問題」は直近の問題です。 この本を読むと、若者を取り巻く状況が大きく変化しているので、昭和世代の感覚で就職を考えていてもダメだということが分かりました。 高卒の求人数は、1992年3月末 167万6000件。 2010年3月末 19万80...
自分の息子が大学生なので、若者の「就職問題」は直近の問題です。 この本を読むと、若者を取り巻く状況が大きく変化しているので、昭和世代の感覚で就職を考えていてもダメだということが分かりました。 高卒の求人数は、1992年3月末 167万6000件。 2010年3月末 19万8000件。 87%減なのです。 それ故、大学進学希望が増えたのです。 しかし、大学の受け入れ人数も増えているため、大学間で競争がおこり、現在のキャリア教育が盛んになる、という構図なようです。 『就職の代替としての進学というルートが存在していることが、日本においては、高卒後「無業」のままの若者たちが、大量に街にあふれ出るといった事態を不正でいるのです。この意味では、今日の大学や専門学校という存在は、冷徹に観察すれば、若年層における「潜在的な失業人口」をプールする場所として機能しているということができるのかもしれません」と著者は述べています。 これが、現在の大学で「キャリア教育科目」が盛んになった理由です。 大学3年生から就職活動が始まり、本格的に就活する4年生では卒論に割く時間もなくなるとか。 この現状が引きおこす、知的損失は大きいと僕は思う。 さらに「キャリア教育科目」で時間が割かれ、大学本来の目的である研究の時間を取れなくなっているのだから、何がどうなっているのやら、という感じです。 学校間の競争は、『ライバル校との競争に負けて、自校の生徒・学生のレベルが低下したり、受験生確保ができなくなったりしたら、どうするのか』という論理を引きおこし、学校間の競争を加速させていくのです。 著者は、まとめとして ・新たな「学校から仕事への移行」に目配りすること ・「自分探し」に埋没するキャリアガイダンスを改善すること ・労働者の権利と働く場のルールを学習できる機会の提供 を挙げています。 さいごに、この大きな転換期だからこそ『旧来の世代に属するものには想像もできなかったような生き方や働き方をしていくことも、これからの若い世代には可能性として開かれているのです』と、若者にエールを送っています。 この部分がなければ、暗い話しで終わってしまうところでした(^^) この本のお陰で、現在の学生がおかれている状況が見えてきました。 学生たちの就職状況は決して安心はできない。 でも、彼らが社会をどのように変化させていくのかを見守っていきたいと思います。
Posted by
ゼミ生にキャリアセンターが就職活動に役に立ったか、と聞いてみたら、12人中0人だった(笑)一度も利用したことがない学生は自分も含めて5人。なぜ若者は就職できなくなったのか、という問題に対する筆者の答えは、やはり企業が採用を抑制しているから、というもの。法政大学の、しかもキャリアを...
ゼミ生にキャリアセンターが就職活動に役に立ったか、と聞いてみたら、12人中0人だった(笑)一度も利用したことがない学生は自分も含めて5人。なぜ若者は就職できなくなったのか、という問題に対する筆者の答えは、やはり企業が採用を抑制しているから、というもの。法政大学の、しかもキャリアを専門に教えている教授がこんなことを堂々と言うのは正直驚き。
Posted by
大学がキャリア教育花盛りになってしまっていることは嘆かわしい。 キャリア教育とかキャリア支援とか言うが、就職できればそれでいいのか? 大学が教えるのは教養と学問であって、就職予備校ではないはず。
Posted by
昨今のキャリア教育は「いびつ」である、と、大学でのキャリア教育に携わる著者はいう。その要因の一つとして、従来の終身雇用モデルを想定し教育の目標として「正社員採用」を掲げていることを著者は指摘している。現在のキャリア教育では、非正規雇用、あるいは、職なしで大学から社会に出た大卒者に...
昨今のキャリア教育は「いびつ」である、と、大学でのキャリア教育に携わる著者はいう。その要因の一つとして、従来の終身雇用モデルを想定し教育の目標として「正社員採用」を掲げていることを著者は指摘している。現在のキャリア教育では、非正規雇用、あるいは、職なしで大学から社会に出た大卒者には何の指針も与えられない。現在の雇用情勢では、構造上、一定の非正規雇用者数が生み出される現状で有るにもかかわらず。。。。 著者が提案するキャリア教育改善策の一つに、労働者の権利を守る法律や様々な仕組みの一つがあり、これには、ポンと膝をうつものがあった。 なるほどね、終身雇用モデルは崩壊しつつあるんだし、自分の権利は自分でまもらなきゃね。そして、現在の雇用情勢は、会社にキャリアをデザインしてもらうものではなく、したたかに、自分で切り開いて行くものなのだと実感させられる1冊でした。
Posted by
- 1
- 2