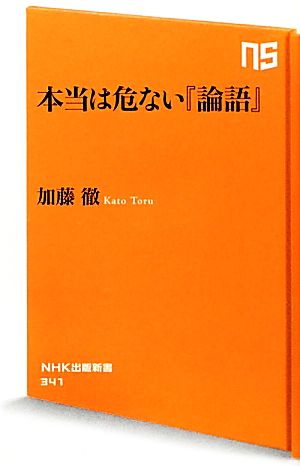本当は危ない『論語』 の商品レビュー
論語の成り立ち、孔子の生涯、日本における論語について書かれている。 副読本に過ぎなかった論語が、江戸時代には、天下を支配するための「漢文の思想の力」として利用されたが、幕府は、論語が革命の起爆剤となりうるため、儒教徒化は規制するという「日本化した水割りの儒教」にとどめた。信長は...
論語の成り立ち、孔子の生涯、日本における論語について書かれている。 副読本に過ぎなかった論語が、江戸時代には、天下を支配するための「漢文の思想の力」として利用されたが、幕府は、論語が革命の起爆剤となりうるため、儒教徒化は規制するという「日本化した水割りの儒教」にとどめた。信長は武力で、秀吉は金の力で天下を支配しようとしたが、思想の力を利用したのが家康だという。 論語は、支配する側の道具としても、教養として読むこともできるが、革命のエネルギーとして利用したのが、松下村塾という志縁集団の志士であり、論語は読み方によっては「危ない」という所以である。 孔子自身は地味な人生であり、論語は孔子が書いたものではなく、聖典でもなかった。漢文の解釈の仕方によって意味も変わってくること、論語が古くから日本に入ってきてはいたが、思想として定着するのも江戸以降だとすると、それまでの日本の思想は何を規範にしていたのか疑問に思うと共に、論語を真面目に読む意味があるのだろうかと疑問を思ってしまった。
Posted by
コロナ巣ごもりで再読する。 高島俊男師が鬼籍に入られた今、加藤徹先生を中国古典の水先案内人と頼んでいる。 巻末に諸星大二郎『孔子暗黒伝』への言及があるのは嬉しい。
Posted by
孔子の生涯と『論語』という書物の成立過程について解説するとともに、とくに日本において孔子の思想がどのように受容されてきたのかということを、わかりやすく説明している本です。 『論語』という書物の成立過程とその読まれかたについて、興味深い実例を紹介している本として、おもしろく読めま...
孔子の生涯と『論語』という書物の成立過程について解説するとともに、とくに日本において孔子の思想がどのように受容されてきたのかということを、わかりやすく説明している本です。 『論語』という書物の成立過程とその読まれかたについて、興味深い実例を紹介している本として、おもしろく読めました。ただ、とくに日本文化に対する孔子の思想の影響については、じゅうぶんに説明されていないような印象もあります。とくに本書のタイトルになっている『論語』の「危ない」側面にかんしては、孔子がその後の東洋文明のかたちをきめた「志縁集団」の創始者であるということや、かつての日本人がそうした孔子の思想の「危ない」側面を熟知しており、それに対してある程度距離を置いてきたといったことなどがとりあげられているのですが、もうすこしていねいな説明がほしかったように思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
論語を多角的な視点から見ることができる。但し、表題の「危なさ」については、創造以上の展開がなかったのが残念。貝と羊の中国人が素晴らしかっただけに。
Posted by
論語には句読点の打ち方で何通りにも解釈できる部分があるというのが面白かった。 徳川幕府が儒学を奨励して安定を保つ道具としたというのを初めて知って、社会の安定には教育が大事と改めて思った。織田信長、豊臣秀吉の布石もあったとは思うが、国の思想の均一化に儒学を使い、儒教は禁じたというの...
論語には句読点の打ち方で何通りにも解釈できる部分があるというのが面白かった。 徳川幕府が儒学を奨励して安定を保つ道具としたというのを初めて知って、社会の安定には教育が大事と改めて思った。織田信長、豊臣秀吉の布石もあったとは思うが、国の思想の均一化に儒学を使い、儒教は禁じたというのは徳川家康という人は全体や先を見る力がすごくあったんだなと思う。著者が書いていらっしゃるように論語は使い方によって毒にも薬にもなるということが、徳川の時代のことからよく分かった。 日本で初めてしっかり論語を読んだ武将が加藤清正だということで、機会があれば加藤清正についてもっと知りたいと思った。
Posted by
一般の解説書は、孔子を聖人君子、論語を聖典的にとらえ、 非の打ち所のないもののように書かれていることが多いが、 本書は、歴史的な背景を踏まえつつ、淡々と推測される事実 を書いている。 従来のイメージからかけ離れた部分も多いが、それにより論語の 価値を貶めるものではなく、より深く読...
一般の解説書は、孔子を聖人君子、論語を聖典的にとらえ、 非の打ち所のないもののように書かれていることが多いが、 本書は、歴史的な背景を踏まえつつ、淡々と推測される事実 を書いている。 従来のイメージからかけ離れた部分も多いが、それにより論語の 価値を貶めるものではなく、より深く読むための参考になる。 孔子についても、論語についても歴史的な資料が少なく、本当の 事実は誰にもわからないが、本書のような考え方も大変おもしろく、 興味深く読めた。 孔子のいうように、バランスのとれた考え方を持つためには、 いろいろな考え方に触れておくことが必要であり、本書の存在は 価値あるものである。
Posted by
論語の多面性と、面白い読み方を探っていく。書いた弟子達のパワーバランスだったり、間違いだったり、擬音感だったりと、論語および周辺書籍を読みたい、と思わせる素敵な本。日本人と中国人、どちらが粗野で仁を持っていないか、論語の捉え方から考えてみると面白いですね。 歴史や古典の授業では、...
論語の多面性と、面白い読み方を探っていく。書いた弟子達のパワーバランスだったり、間違いだったり、擬音感だったりと、論語および周辺書籍を読みたい、と思わせる素敵な本。日本人と中国人、どちらが粗野で仁を持っていないか、論語の捉え方から考えてみると面白いですね。 歴史や古典の授業では、誰が何年に何をした、なんてことより、こういうことを教えたほうがいいと思うなあ。
Posted by
挑発的なタイトルですが、論語の成り立ち、孔子の人物像、発音、日本の歴史に与えた影響等を博識を以て分かりやすく解説。素読教育についても興味を持てました。
Posted by
タイトルは奇抜だが、中身は論語の出処や歴史的背景、日本での浸透の仕方などを細かなソースをつけて説明している良書。これだけの論語知識があれば、道を外さず論語を読めるようになるでしょう。
Posted by
タイトルは煽りが効いているけれど、まっとうな内容の本。論語の誕生・成立から発展に至るまでの歴史的経緯と、孔子の人となりの推測、そして、論語と日本のかかわりについて、既存の論語研究の成果を数多く引用しながら説明している。タイトルにある「危ない」とは、次の3点の意味での「危なっかしさ...
タイトルは煽りが効いているけれど、まっとうな内容の本。論語の誕生・成立から発展に至るまでの歴史的経緯と、孔子の人となりの推測、そして、論語と日本のかかわりについて、既存の論語研究の成果を数多く引用しながら説明している。タイトルにある「危ない」とは、次の3点の意味での「危なっかしさ」を指していると私は理解した。 1.成立の経緯が不明なところがあり、孔子一門とは関係ない別の書物の言論が混じっていたり、孔子の弟子達による学閥の主導権争いの結果、孔子の言が歪められている可能性がある。実際、荀子の言と思しき文章が論語に紛れ込んでいるという指摘もある。 2.古典ゆえに表現技法が未発達で、読み方に曖昧性が発生している。文の区切りの入れ方により正反対の意味に解釈できることもあり、専門家同士でも意見が対立している。したがって、片方の解釈のみを信じることは避け、両論を吟味する必要がある。 3.孔子の思想はラディカルなため、論語の内容を盲信する勢力が力を持つと、国家が転覆しかねない。徳川家康は論語の怖さを熟知しており、国家秩序の形成のために論語の教えを「儒学」として利用したものの、論語を盲信する「儒教」については(キリスト教と同様かそれ以上に)徹底的に弾圧した。
Posted by
- 1
- 2