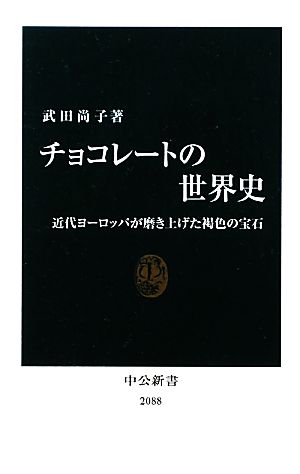チョコレートの世界史 の商品レビュー
チョコレートの原料はカカオ豆です。 中南米では昔から薬として摂取されていたそうです。 それが、ココアとしてヨーロッパに伝わり、チョコレートができました。 キットカットのロウントリー社の歴史が書かれていて、この会社は社員のための学校や住宅街などを作ったりととても誠実な経営をしていた...
チョコレートの原料はカカオ豆です。 中南米では昔から薬として摂取されていたそうです。 それが、ココアとしてヨーロッパに伝わり、チョコレートができました。 キットカットのロウントリー社の歴史が書かれていて、この会社は社員のための学校や住宅街などを作ったりととても誠実な経営をしていたようです。 その誠実さの表れが、キットカットの包装紙に、今は戦時下なので、キットカット本来の原料では作れないけど、できるだけ近い味にしてあります、というような但し書きが書かれていたそうです。 この話を読んで、前よりももっとキットカットが好きになりました。 Have a Break, Have a KitKat!
Posted by
お菓子の代表格、チョコレートがどのように食べられるようになり普及していったかの歴史を書く。世界的に食べられている赤と白の袋の「キットカット」の誕生や生産体制、宣伝方法などを通して、イギリスを中心とする労働者の働き方にも目をむける。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
私達にも身近なチョコレートは近代化の産物です。特にイギリスの産業革命によってチョコレートはそれまでとは大きく違った意味を持ち始めます。その流れを知れる本書は非常に刺激的です。 また、本記事のタイトルにも書きましたが私達もよく知るキットカットの歴史もこの本では知ることができます。 本書を読めばこうしたチョコ菓子が人気になっていくのもまさに近代化の影響だったということがよくわかります。 私達の身近な生活にも直結するチョコレートの成り立ちを知るのにこの本はとてもおすすめです。前回紹介した『チョコレートの歴史』とセットで読めばさらに理解が深まること間違いなしです。
Posted by
『チョコレートの世界史』 マヤやアステカで滋養強壮の薬品として嗜好されていた中南米原産のカカオが、いかにして世界中に普及してココアやチョコレートとして利用されるようになったか。そこには奴隷貿易とキリスト教が大きく絡んでいる。 カカオを発見したスペインやポルトガルは、現地インデ...
『チョコレートの世界史』 マヤやアステカで滋養強壮の薬品として嗜好されていた中南米原産のカカオが、いかにして世界中に普及してココアやチョコレートとして利用されるようになったか。そこには奴隷貿易とキリスト教が大きく絡んでいる。 カカオを発見したスペインやポルトガルは、現地インディオが人口減少するに伴って、アフリカから奴隷を連れてくるようになる。さらにカカオは西アフリカに移植され、大規模なプランテーションで生産されるようになる。後発のオランダやイギリスは、プロテスタント的な戒律から奴隷制を批判し、工業生産へと舵を切っていく。 主に薬品として王侯貴族の嗜好品に使われてきたカカオは、オランダやイギリスにおいて庶民が楽しめる甘味としての普及品となっていく。ココアパウダーからチョコレートへ、バンホーテンやキットカットといったブランドもその流れから誕生していった。 田園都市構想や従業員の福利厚生といった労働者の生活水準を上げることにも熱心だったチョコレート工場の経営者たちは、消費者を増やすことが自らの事業に繋がることを発見する。そしてヨーロッパから世界各国へとチョコレートは輸出されるようになり、日本においても好まれるようになっていった。
Posted by
序章 スイーツ・ロード旅支度 1章 カカオ・ロードの拡大 2章 すてきな飲み物ココア 3章 チョコレートの誕生 4章 イギリスのココア・ネットワーク 5章 理想のチョコレート工場 6章 戦争とチョコレート 7章 チョコレートのグローバル・マーケット 終章 スイーツと社会
Posted by
武田尚子氏が2010年に刊行した歴史書。 『砂糖の世界史』や『茶の世界史』と同様にチョコレート(カカオ)というモノからみた歴史書である。 チョコレートも砂糖も茶もやはり大航海時代から世界に広まり、各時代や地域によってさまざまな使われ方をしてきた。 物流からの経済史からの視点...
武田尚子氏が2010年に刊行した歴史書。 『砂糖の世界史』や『茶の世界史』と同様にチョコレート(カカオ)というモノからみた歴史書である。 チョコレートも砂糖も茶もやはり大航海時代から世界に広まり、各時代や地域によってさまざまな使われ方をしてきた。 物流からの経済史からの視点や労働者からみた歴史などチョコレートに秘められた歴史は奥深く面白いです。
Posted by
くっ、読み終わったらキットカットが無性に食べたくなった罠。 あんまりチョコレート菓子は好きじゃないのだけど。 王侯貴族の薬的なドリンクから始まったチョコレートが庶民の労働者の手軽な栄養補給に至るまで。 そして今のチョコレート事情など。 もうちょっと最近のことまで書くなら、気候変動...
くっ、読み終わったらキットカットが無性に食べたくなった罠。 あんまりチョコレート菓子は好きじゃないのだけど。 王侯貴族の薬的なドリンクから始まったチョコレートが庶民の労働者の手軽な栄養補給に至るまで。 そして今のチョコレート事情など。 もうちょっと最近のことまで書くなら、気候変動と病気によるカカオの絶滅の危機まで入ったかなぁ。 砂糖と乳製品も値上がってるし、今年も高級チョコレートは小粒化の一途だそうですよ。 というか、イギリスの奴隷制度廃止の発端は人道とかそういう話ではなかったんですね。 まぁそんなもんかなと思ったりしつつ。甘いだけじゃないビターなエピソードも多かったです。
Posted by
チョコレートの元になるカカオの原種は2つあり、今ではその二つの遺伝子が混ざったものがあるため三通りになっている。一つはアマゾン川を中心とした南米産フォラステロ種で、もう一つは、グアテマラあたりの中米産クリオロ種である。南米のは脂肪分が多くかつ苦味が強い 一方中米のはチョコレートに...
チョコレートの元になるカカオの原種は2つあり、今ではその二つの遺伝子が混ざったものがあるため三通りになっている。一つはアマゾン川を中心とした南米産フォラステロ種で、もう一つは、グアテマラあたりの中米産クリオロ種である。南米のは脂肪分が多くかつ苦味が強い 一方中米のはチョコレートにした際に苦味がそれほど無い。しかしこちらは病気に弱いらしく、現在のカカオの10%ぐらいしかない。南米産は味は劣るが耐病性が強かった。19世紀に植民地を支配していた白人がこれらを勾配してガーナに移植したのでガーナのチョコレートは有名となり、今ではこの品種が最も多い。 こんな歴史を紐解きながら、ヨーロッパ、特にイギリスの産業構図、クエーカーが果たした役割、さらには大工場化と労働者保護まで、いろいろな角度からチョコレートについて語っている。 チョコレート面白い!調べてみるとチョコレート検定まであるではないか。
Posted by
たまたま図書館のバレンタインデー特集コーナーで目に留まり、読んでみた1冊。そしてたまたま、少し前に、砂糖のプランテーションに関する本、近代世界システムの中でのイギリスの勃興と衰退に関する本などなどを読んでいたので、歴史の本として、本書をとても楽しむことができた。
Posted by
チョコレートの歴史。 珈琲と同様な歴史を辿っている。 チョコレートって最初は食事だったのかとか、 キットカットって最初の名前がちがうのかとか、 初めて知ることが多くて、楽しい読み物だった。
Posted by