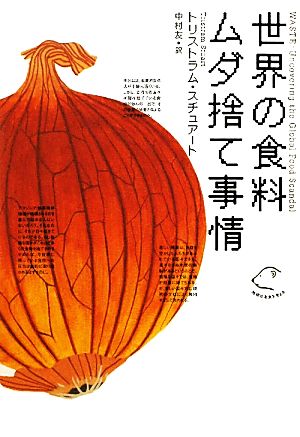世界の食料ムダ捨て事情 の商品レビュー
何回かに分けて内容を紹介してきました。 著者がおおいに問題視している食料廃棄は家庭で食べられなくなって捨てられるものの他に、保管設備のインフラが整っていない途上国の事情(害虫やカビによる損失、輸送中の損壊など)、漁における混獲(網に引っ掛かった目的外の魚の遺棄)などがあります。こ...
何回かに分けて内容を紹介してきました。 著者がおおいに問題視している食料廃棄は家庭で食べられなくなって捨てられるものの他に、保管設備のインフラが整っていない途上国の事情(害虫やカビによる損失、輸送中の損壊など)、漁における混獲(網に引っ掛かった目的外の魚の遺棄)などがあります。こうした廃棄量を分かりやすい数字として換算しているのが本書の特徴でもあります。 例えば スリランカでは青果の損失率が年に30~40%(1億ドル分)、 インドでは120億ドル分と言われます。 アメリカでは一人当たり1日3900kcal分の食料が食され、これは必要エネルギーの200%(ちなみに日本では150%)という計算。世界の食料供給の19.6%を節約すれば、これにより解放された土地をエネルギー算出に利用でき、1億6400万テラジュールに相当=18億軒のヨーロッパスタイルの家を暖房できる といった具合。 とはいえ、捨てるのはもったいからエネルギーに回しましょうというのは何の解決策にもなっておらず、単に埋立地に直行よりマシであるというだけなので、根本的には無駄なものを買わず、残さず食べるのがベストだという主張は最後まで一貫して書かれていました。 そしてそうすることが飢饉の問題のみならず、地球の環境保全にもつながり、豊かな自然を残す運動(何も車に乗らないという運動だけでなく)になるのだという発想です。「もったいない」から「環境運動へ」という広い視野。CO2排出規制だけが環境保全に役立つとクローズアップされがちですが、農業もCO2排出に大いに影響を与えており、無駄なものを作らないようにするだけでそのインパクトは強いようです。 さらに余ったものを足りてない人々に分け与えることで、彼らは食料に使うお金を他に回すことができ、社会的弱者から立ち直れる機会が増えるということも。 こうした大きな問題は個人個人が小さく取り組むだけで(たった捨てる量を減らすだけ)解決できるのですが、著者が日本を評価している例として、食品会社に対して廃棄物の扱い方を規制している点を挙げていました。やはり家庭で出る食料廃棄物より企業が出す量の方が圧倒的に多いので、ここを改善するだけでも違うということです。そしてこれら廃棄物は家畜飼料として利用されていることも評価されていました。ヨーロッパではこれが許されておらず、そのため家畜飼料のための栽培がおこなわれている結果、余剰生産に拍車をかけていると問題指摘しています。 だらだらと紹介してきましたが、するべきことは単純です。買い過ぎない、残さない。
Posted by
食料廃棄について、世界の現場を取材した貴重な本。消費者が自分たちで食料を生産したり、ファーマーズマーケットを利用するのは理想的解決法だとしながら、食料廃棄の方法を探る。 食料廃棄を減らせば、世界の食糧不足を減らすことができるというのは物事を単純化しすぎた考え方だと思うが、論理的に...
食料廃棄について、世界の現場を取材した貴重な本。消費者が自分たちで食料を生産したり、ファーマーズマーケットを利用するのは理想的解決法だとしながら、食料廃棄の方法を探る。 食料廃棄を減らせば、世界の食糧不足を減らすことができるというのは物事を単純化しすぎた考え方だと思うが、論理的にそれが実証できれば、食料を無駄にしない世界的な流れが生まれるのではないだろうか。少し前にFAOも食料廃棄で報告書を発表しており、徐々にその道筋ができあがってきたところだろう。 内容は良いのだが、邦訳すると中々すんなり読めず、読むのに苦労した。各章には、中見出しが一つもない。。。
Posted by
読み終わるまでに数年を費やした作品。 …読み出して直ぐに内容で数値の比較などの部分で自己に都合の良い数値、測定方法を持ち出して比較して論じているのに半分くらいまで読んで正直放置してました(^^; 不可抗力で時間が出来たので再度挑戦したわけですが…どうにも自己の主張ばかりを押し付け...
読み終わるまでに数年を費やした作品。 …読み出して直ぐに内容で数値の比較などの部分で自己に都合の良い数値、測定方法を持ち出して比較して論じているのに半分くらいまで読んで正直放置してました(^^; 不可抗力で時間が出来たので再度挑戦したわけですが…どうにも自己の主張ばかりを押し付けるような感じが好きになれませんでした。 啓発的にあえてこのような書き方をされているのでしょうが…おいらはスキクナイ。 食べ物を無駄にしてよいという訳ではなくて、ご飯は残さず食べる。食べれる以上にはとらない。それは基本として守っていかないとねぇ… ご飯を食べ終わった後に茶碗にお茶や白湯を注いで飲む。自分にとっては普通の習慣なんやけどなぁ(^^;
Posted by
消費者を含め、サプライチェーン上で食品廃棄物の削減に取り組んでいるが、まだまだやれることはたくさんある。 これまでの購買行動・習慣・商慣行を見直すべきことを見落としていないだろうか。 レストランや居酒屋では "Don't take more than yo...
消費者を含め、サプライチェーン上で食品廃棄物の削減に取り組んでいるが、まだまだやれることはたくさんある。 これまでの購買行動・習慣・商慣行を見直すべきことを見落としていないだろうか。 レストランや居酒屋では "Don't take more than you can eat!" と自分に投げかけようっと。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
一応は農学をかじった身の上であるので、規格によって大量の農作物がはじかれたり、インフラや保存施設の不足によって無駄に腐っていくことは知っていた。これほどの割合とは思っていなかったけれど。打ち捨てられた作物の画像はかなり破壊力あったわぁ。 流通からテーブルに載るまでの過程で、小売が廃棄物を大量に出しているというのも既知。ただ一番驚いたのが生産者が大量に捨てているということ。スーパーの圧力に応えるための処置というのも大きいのだろうけど、何の問題もない製品をばっさばっさ捨てるのは他業種では考えられないと思う。 作者が本書で繰り返し述べる、食べ物のムダを出すことは他者の食べ物を奪うこと、無駄をなくすことで生産に使われる労力と土地を節減しようという考え。これにはちょっと疑問を抱いた。大量に生産されているから貧しい人が食べられていて、生産を減らしたら食べられなくなる人が出るのではなかろうかと。無駄を減らすなんてそう簡単にできんのかなぁというスタンスの人間なんで。土地を減らすにゃ農業生産の集約化と効率化も大事だよね。 食品残さの研究に触れていた人間としては喰っちまうのが一番という論旨はそうそうそのとおりと深く頷いた。おからとかさー食えっつーのなー。 正直なところ西欧のスーパーの事例はいまいち頭に入って来なかった。それだけに日本のスーパーだとどうなんだろうなと思った。フードバンクとかあるのかしら。あとはもう少しフリーガニズムの話が多かったら嬉しかったかも。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フリーガニズムという立場がある。環境保護者の抗議活動の一環として、ごみとして捨てられた食料を拾って食べるという運動だそうで、長年フリーガンであった著者が食べ物のムダについて熱く語る。資料なども詳細で読み応えがある。 全世界で収穫される食料は一日一人あたり4600kCalになるが、実際に消費される分は2000kCalに過ぎない。このうち1/3は食べ残しなど消費者の問題であるが、2/3は食品業界の問題だという。先進国ではスーパーの基準が厳しすぎて、規格に合わないサイズや傷がある野菜などは廃棄される(まっすぐなニンジンを好むなど、消費者の姿勢にも問題がある)。また、どこも過剰な品揃えを誇っているが、これはそもそも原価の2-3倍で売っているので、品切れで一つ売りそこなうぐらいなら2個売れ残って捨てるほうがよいという損得勘定による。 途上国では穀物の保管場所がない(投資余力がない)ため、多くの食物が害獣や害虫にやられてしまう。 漁業も漁獲のうちの半分以上は小さすぎたり目的外の魚であったりするため廃棄される。 消費期限の問題も大きい。日本の場合は日持ちが5日以内のものを「消費期限」、それ以上のものを「賞味期限」としているそうだが、実際は肉であれば一週間ぐらい期日を過ぎていてもしっかり火を通せば問題ないし、ヨーグルトのような乳製品は一ヶ月過ぎても見た目と匂いが大丈夫なら問題ない。 文化の違いもある。豚を飼う中国では残飯が出ることにあまり抵抗がないが、豚を忌避するイスラム圏では食べ残しに対しては厳しい。日本であれば生食嗜好が強いため、2-3日経った食べ物が捨てられてしまう。 では、どうすればよいか。埋め立ては最悪の処理法で、家畜の飼料や嫌気的消化(メタンガスとしても回収できる)、堆肥化などで再利用することを考えるべき。 乳酸菌は腐敗を防ぎ、栄養価を高める。豚の飼料として使うことで「ヨーグル豚」としてのブランドにもなっている。 客に選択の自由を与えるために何でも取り揃えておく必要はない。例えば、会社や学校などの食堂であれば2-3日前にメニューを聞いて、それを準備しておけばよい。
Posted by
世界ではたくさんの人が飢えているのに、無駄に食料が廃棄されている。困ったことだ。 日本のコンビニの弁当もそうだ。 欧米でもそうだが、インドでもそう。 これは世界的な取組が必要です。 だいたい、規格外の大きさだから捨てるって、あり得ない。。
Posted by
この本を読んで、おおいに反省し、ムダにせず使い切る努力を始めました。少なくとも、一人の読者の生活を変えたということは、世界を変えることにつながるのかも。みんな、読むべきだよ。
Posted by
- 1