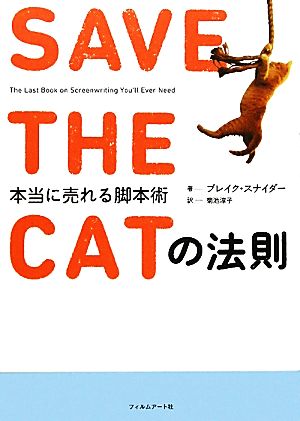SAVE THE CATの法則 の商品レビュー
面白かった! 映画のストーリーから固有名詞を省き、抽象化してプロットだけを抜き出すと様々な映画の共通点がみつかる。 「読んでいない本について堂々と語る方法/ピエール・バイヤール著」でもあるように、批評においてはその本が他の本との関係性における立ち位置を知ることが大事なのだから、ス...
面白かった! 映画のストーリーから固有名詞を省き、抽象化してプロットだけを抜き出すと様々な映画の共通点がみつかる。 「読んでいない本について堂々と語る方法/ピエール・バイヤール著」でもあるように、批評においてはその本が他の本との関係性における立ち位置を知ることが大事なのだから、ストーリーを抽象化することはまさに批評につながるのだ ダイ・ハードとシンドラーのリストが同じプロットだなんてなぁ。
Posted by
「売れる脚本のつくりかた」を細かに分析し、体系化した良書。 ビジネスへの応用可能性の高さはもちろん、単純にいち映画ファンとしても膝を打つ内容がふんだんに盛り込まれていて、タイトルによらず幅広い読者層におすすめな一冊。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
売れる脚本には法則がある。芸術特に時間芸術と言われているものは一定の「型」が見られるが映画脚本においてもそれがあるということである。「三幕構成」が有名だが本書が提唱するのが「BS2(ブレイク・スナイダー・ビート・シート)」である。 BS2は以下で構成されている。この構成がキモである。構成を作った人が「脚本家」として印税を手にできるのだそうだ。また全体を110ページとした場合は下記の長さはほぼ決まっており、業界の人はペラペラとめくって見るだけで良いものかどうなのかの判断ができる。ベンチマークの意味あいもある。なかなかシステマティックである。 1.オープニング・イメージ 2.テーマの提示 3.セットアップ 4.きっかけ 5.悩みのとき 6.第1ターニング・ポイント 7.サブプロット 8.お楽しみ 9.ミッド・ポイント 10.迫り来る悪い奴ら 11.すべてを失って 12.心の暗闇 13.第2ターニング・ポイント 14.フィナーレ 15.ファイナル・イメージ
Posted by
ハリウッドの作品って、中には嫌いという人もいるけれど、私は逆で、どの映画も毎回すごくよく出来ていると心から感心する。 日本映画を見てると眠くなって飽きちゃったり、感情移入できずに終わることも多いのに(すいません、でも事実)、ハリウッド作品にはそれがほとんどなくて、逆にこんな作品で...
ハリウッドの作品って、中には嫌いという人もいるけれど、私は逆で、どの映画も毎回すごくよく出来ていると心から感心する。 日本映画を見てると眠くなって飽きちゃったり、感情移入できずに終わることも多いのに(すいません、でも事実)、ハリウッド作品にはそれがほとんどなくて、逆にこんな作品で泣くー?ってくらい毎回大泣きしたり大笑いしたり。 絶対に、海の向こうのあの国には、何か脚本を書くマニュアルとかシステム的なメソッドが確立されているはず!! そうじゃないと、こんなにいくつもいくつも長期にわたって継続的におもしろい作品が量産され続けられるはずがない! …などと思って、その答えがほしくていろんな脚本術の本を読んだけれど、今まで私が読んだ中では、納得いく答えがなかった。 しかし、やっと、そういうことが書いてある本を見つけた。 絶対あると思っていた。何ページまでに何を書いて、何ページでこういうシーンを入れて、と細かくマニュアル化した本。 それがこの本です。 読み物としてもおもしろかったし、その理論はとても説得力があるように思う。(といってもあくまでも私は映画を見る側なので、受け取り手として感じた説得力ですが) 印象的だったのは、ミッドポイントが必ず45分で訪れる、というのを著者が発見したエピソード。なかなかすごい発見だと思った。 今まで見た映画を思い浮かべても、確かにだいたい1時間くらいでそういうシーンが来る。 そしてそのタイミングは110ページの脚本では55ページ目に来る、という著者の主張にもなんとなく納得。少なくともハリウッド映画を見る時にわたしたちが期待している物語の起伏は、映画のジャンルにかかわらず、大まかにはそのような形になっているように思う。 きっと太古の昔から、人類は「物語を語る」という行為のテクニックを実地で磨いていって、その到達点の一つがハリウッド映画なんだろうなぁ。 ミッドポイントだけじゃなくて、映画は四幕になっていて、それぞれの区切り(第一ターニングポイント、第二ターニングポイント)が来るタイミングも、基本的には決まっている、というあたりになってくると、統計学の箱ひげ図をほうふつとさせられて興味深かった。 ミッドポイントを挟んだターニングポイントは、中央値を挟んだ第二四分位数と第三四分位数みたい。 今後は映画よりも海外ドラマが主流になるんじゃないかと私は感じているが(映画は今の二時間ドラマか、テーマパークのアトラクションみたいな位置づけになるのではないかしら、などと勝手に予測)、その海外ドラマも、一つひとつのエピソードに、やっぱり同じように型があると思う。でも、映画とは時間の尺が違うから、ちょっと違う型。 ということで、次はこの本の海外ドラマ版みたいなのが読みたいな。 私の体の中のエンタメ時計は、もはや映画じゃなくて海外ドラマに合わせてしまっているような気がするので。
Posted by
映画監督になりたかった子供の頃を思い出し購入。全ての映画は特定のジャンルに分けられるなど、衝撃的な内容が多かった。脚本を書く上で、同じジャンルからヒントを得る考え方は納得感が高かった。これから映画を見る際は意識してしまうと思う。映画だけでなく、仕事での発表方法にも活かせそうな点が...
映画監督になりたかった子供の頃を思い出し購入。全ての映画は特定のジャンルに分けられるなど、衝撃的な内容が多かった。脚本を書く上で、同じジャンルからヒントを得る考え方は納得感が高かった。これから映画を見る際は意識してしまうと思う。映画だけでなく、仕事での発表方法にも活かせそうな点が多かった。
Posted by
2021/2/11 本書は映画には10個のテーマの型と15の構成要素があると言う。型と言えばプロップの物語論が想起される。彼は、物語は31の機能から構成されていると言うが、これらの型や構成要素はそれぞれに31の機能が内包されていると考えておけばいいだろうか。 こんな風に考えると...
2021/2/11 本書は映画には10個のテーマの型と15の構成要素があると言う。型と言えばプロップの物語論が想起される。彼は、物語は31の機能から構成されていると言うが、これらの型や構成要素はそれぞれに31の機能が内包されていると考えておけばいいだろうか。 こんな風に考えると、物語は型から構成され、その型も更に細かい型から構成されていることが分かる。著者が物語を科学的だと認識しているのにも納得がいく。(また同時に物語を芸術的だと捉えているが、型の中でいかに主人公、時間、展開などを転がすかという創造的営みのことを言っているのか?) また当たり前だが、著者は映画の鉄則を「語るな、見せろ」だとしている。登場人物にダラダラ状況を語らせずに、映像で1発で見せろ、と。これは意外にも盲点で、僕は「ながら」で映画を観ることが多く、観ることに意識を集中させていなかった。この一言には姿勢を正された。 このような映画に関する技術だけに留まらず、物語一般に落とし込むできるので文学にも応用が効く。 例えば… ・登場人物がプリミティブな欲求(生き延びること、愛すること、セックスすることなど)を持っているか? ・主人公に共感してもらえるか(鑑賞者一般と同ステータスの人間など) ・欠損→取り戻す 回復を目指す ・セットアップの段階で伏線も散らしておく ・全てを失う段階では、何らかの死の気配を感じさせること などなど。 ただ一点、映画の鑑賞者は現実逃避を求めているという前提には疑問だ。鑑賞者は映画を通じて自己の現実を直視すべきで、現実から逃避させるような作品は商業的価値にしかなり得ない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「脚本術」とあるが、規模こそ違えど、プレゼン資料や読書感想文にも活用できそう。脚本家だけでなく、ビジネスマンや学生も一読の価値あり。 全体的にシニカルな口調でさらっと読めるし、映画の名前もたくさん出てくるので、映画評論的な目線でも読めるかと。 各チャプターには練習問題があるし、後半は完全に脚本家向けと感じた。 以下参考になった箇所。 ・ログラインを最初に考える →どんな映画なの?を簡潔に一行で表現 皮肉やパンチが効いているか 観客層が想定できるか 実際に興味を持ってもらえるかテストする ・共感できる主人公であること 主人公は最後には成長すること ・構成を考えてから描き始める →ブレイクスナイダービートシート ・ボードにシーンを書き出して全体を可視化する
Posted by
めちゃくちゃ目新しいことが書かれているわけではないけれどぼんやり考えていたことがちゃんと体型立てて書かれていてとても助かる。
Posted by
脚本が書けなくなって困っていたのでとても助かりました。 語り口も軽快で読みやすいです。 もっと早く読んでいればよかったです。
Posted by
シナリオに興味があるわけじゃない。 でも、魅力的に感じるタイトルだった。 飛ぶように読める。 読みやすいかわりに、不思議と残らなかった。 私がシナリオを描く人だったら、もっと響いたんだろうか。 ちょっと残念。
Posted by