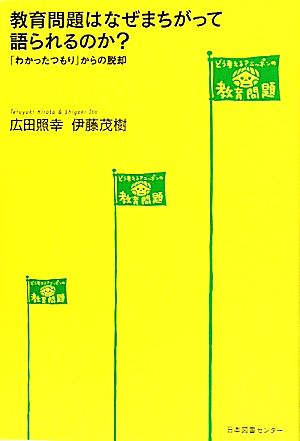教育問題はなぜまちがって語られるのか? の商品レビュー
201107/ 教育問題に限らず、あらゆる社会的な問題は、三種類のレベルで議論がなされています。1)事実認識のレベル(問題となっている事実は何か)、2)診断のレベル(問題点の本質や原因・影響をどう考えるか)、3)対策のレベル(どういう方法で問題が解決・緩和できるのか)/ 世間の人...
201107/ 教育問題に限らず、あらゆる社会的な問題は、三種類のレベルで議論がなされています。1)事実認識のレベル(問題となっている事実は何か)、2)診断のレベル(問題点の本質や原因・影響をどう考えるか)、3)対策のレベル(どういう方法で問題が解決・緩和できるのか)/ 世間の人たちの多くが、「現代の家族は人間関係が希薄化し、親子間のコミュニケーションが少なくなり、家庭の教育力が低下している」と考えているが、一方で、「自分たちの家族のつながりは強いほうだ」という人が9割近くを占めている。/ 何でもかんでも「心の問題」/ 木にたくさんなっているリンゴの一個一個が木から落ちた理由をみると、実が熟して重くなったからとか、風が吹いたからとか、カラスがつついたからとか、人が食べようと思って木を揺すったからとか、いろいろなケースがあってまちまちです。しかしこれらは、リンゴが木から落ちた「理由」というよりは、一つ一つのリンゴの実が落ちるに至った「契機(きっかけ)」と呼ぶべきものです。そしてきっかけとしてはどれも正しいでしょうが、すべてのリンゴの場合に当てはまる「本質的」な理由ではありません。そもそも、あらゆるリンゴがいつかは木から落ちる本質的な理由は、言うまでもなく引力があるからです。その引力が働いてリンゴが落ちることになったきっかけはいろいろあり、それは重くなったり、風が吹いたり、カラスがつついたりといったことですが、これをいくら集めても、引力という「本質」にはいきあたらない、つきとめることはできないというわけです。/ 不登校やいじめや少年非行などの問題は、特に社会現象として見たときには、もっと別の見方が可能になります。「心の問題」として個別的に、個人化して見るだけでは見えてこない、教育や社会全体の構造の問題もあります。また歴史的に見れば、いまのように不登校が増える前、1960年代から70年代という時代は、多くの子どもが学校を休まずに通っていた例外的で特異な時代だった、という見方もできます。こういう角度から見ると、現在の不登校の増加は、単に「問題」「病気」というのとはまったくちがった見え方をしているので、ちがった対策の可能性が導かれることにもなります。たとえば、「ある程度の割合の子どもたちは、さまざま理由から、『学校にいかない』という行動を選択するものだ。だから、そういう子どもたちが社会からはじき出されない仕組みを作るのが、何よりも重要だ。彼らがそれなりに学力をつけることができて、進学や就職で不利にならない仕組みを準備してやれば、多様な生き方の一つにすぎなくなる」というふうに。/
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
教育関係者以外に事実ではなく、どうしてあやまった情報が大きくなっていくのか、その潜在的な構造について、物語的に説明した良書。 教育問題は噂程度の話が大きくなることが多い。それらをどうやって真実とみわけるか、また構造上そのような報道が大きくなるのか、分かった上で判断したい人にはお勧め。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
教育問題の議論をめぐる問題点を抉り出した本。 まず、教育問題となると、権威主義的、実感主義的、体験主義的、情緒的な言説が飛び交います。すなわち、 ・「今の子供は自由と自分勝手を履き違えている。とにかく体罰によって言うことを聞かすべき。体罰に反対する連中は頭でっかちで何もわかっていない」 ・「自分は体罰を受けたからやっていいことと悪いことの判断が付くようになった。今の子供にもそうすべきだ」 ・「昔も若者はもっとしっかりしていたのに、最近の若者はマナーが悪く、勉学にも就職にも消極的だ」 ・「○○国の若者は目が輝いていて素晴らしい。それに比べて日本の若者のなんとだらしないことか」 ・「ダメ親、ダメ教師が増えた」 ・「少年犯罪やいじめは多発化、凶悪化、低年齢化している。心の闇をなんとかしないと」 といったようないい加減な内容。この中には既知の情報も多くありましたが、「教育で対処できることとできないことを峻別する必要がある」という「教育万能主義」の見直しは新しい視点だった。 上記のようなトンデモ言説の対処法として ・(教育をめぐる事件の発生原因やトンデモ言説が蔓延する)社会的要因を考える ・偏った情報にも耳を傾けた上で改善する ・「よくないもの」、「よりよいもの」を選別する ・「偏りのない、無色透明な言説」は存在しないことを自覚する といったことが列挙されている。ここだけピックアップすると何だか情報リテラシーの本みたい。この本は高校生や大学生といった若い世代も対象にした本らしいので、それでいいのかもしれないが。 この本は実直でまともなことしか語っていない。逆に言えばまともなことしか語っておらず、私にとっては斬新さと面白味に少々物足りなさが残ったが、お勧めの一冊で。
Posted by
「教育問題」を切り口に、メディアリテラシーについて論じた一冊。 マスコミ報道が多いから、「凶悪な少年犯罪が増えた」?統計の数字、鵜呑みにしていいの?…身近で具体的な例を取り上げながら、わたしたちがおちいりがちな"思い込みによる問題のすりかえ"に気づかせてくれ...
「教育問題」を切り口に、メディアリテラシーについて論じた一冊。 マスコミ報道が多いから、「凶悪な少年犯罪が増えた」?統計の数字、鵜呑みにしていいの?…身近で具体的な例を取り上げながら、わたしたちがおちいりがちな"思い込みによる問題のすりかえ"に気づかせてくれます。 【今月のおすすめ/2011年3月】
Posted by
「教育問題」と謳っているが、情報リテラシーの重要性を書いた本だな、と思っていたら最終章でそうまとめられていた。 社会的に問題視されて初めて「問題化」すること、事実認識の難しさ、意識の偏りの理解、統計の読みとり方など、非常に示唆に富む内容であり、また何か問題解決にあたっての捉え方...
「教育問題」と謳っているが、情報リテラシーの重要性を書いた本だな、と思っていたら最終章でそうまとめられていた。 社会的に問題視されて初めて「問題化」すること、事実認識の難しさ、意識の偏りの理解、統計の読みとり方など、非常に示唆に富む内容であり、また何か問題解決にあたっての捉え方や考え方などは、教育に限らず、様々なケースで有用だと思われる方法が論じられている。 ただ私にとっては、総じて既に様々な文献などから読み知っていたことでもあり、あまり目新しさはなかった。 よって☆3つとしたが、この情報があふれる社会にあって、惑わされず正しく物事を理解するために、これから社会に出ていく若い世代の人たちには是非読んで欲しい本だ。
Posted by
入門書としては良書。 メディアによる報道の偏りや、有識者とされる人のコメントの不確かさに気づき、批判的に見る視点を教えてくれます。 「問題」とは何なのか、「解決策」はどうあるべきか、様々な問題の根本を解きほぐして提示してくれています。 ただ、これで勉強しようと思うと内容は物足り...
入門書としては良書。 メディアによる報道の偏りや、有識者とされる人のコメントの不確かさに気づき、批判的に見る視点を教えてくれます。 「問題」とは何なのか、「解決策」はどうあるべきか、様々な問題の根本を解きほぐして提示してくれています。 ただ、これで勉強しようと思うと内容は物足りないはずです。 その際は巻末のブックガイドを参考に、次の本を探して行くと良いでしょう。 わたしにとっては、読みたかった内容の一歩手前のものだったので★★★。 amazonで購入したのですが、中身を見ていたら買わなかったかも・・・;と感じました。
Posted by
教育に関することで「問題」といわれている事象を どのように考えればいいのかを、 とてもやさしい語り口で示してくれている本。 識者や学者の意見をどうとらえるかとか 統計の見かたとかについても分かりやすく かみくだいた説明があって、 高校生でも十分読みこなせると思う。 教育問題に限ら...
教育に関することで「問題」といわれている事象を どのように考えればいいのかを、 とてもやさしい語り口で示してくれている本。 識者や学者の意見をどうとらえるかとか 統計の見かたとかについても分かりやすく かみくだいた説明があって、 高校生でも十分読みこなせると思う。 教育問題に限らず、社会学やその他もろもろ、 人と人・環境が作用しあって起こる事柄について 考える際に必要な情報リテラシーとはどういうものか よく分かる内容。 ブックガイドも便利。良書です。
Posted by
教育問題に限らず、情報を吟味して自分の頭で考えるためのステップを教えてくれる良書。高校ではこういうことを教えたい。トンデモ教育論や心理学ブームに対する批判も小気味よい。
Posted by
教育学を学ぼうと考えている高校生や大学生などを対象に、「社会科学的な視点から教育問題を考えてもらえるような、読みやすい本」(p.267あとがき)というコンセプトで書かれた本。内容は、「事実認識を疑ってみる」「正しい情報とは?」「へそまがりな問いから始める」など、社会科学の作法から...
教育学を学ぼうと考えている高校生や大学生などを対象に、「社会科学的な視点から教育問題を考えてもらえるような、読みやすい本」(p.267あとがき)というコンセプトで書かれた本。内容は、「事実認識を疑ってみる」「正しい情報とは?」「へそまがりな問いから始める」など、社会科学の作法からすれば初歩的なことばかりではあるが、たしかに日ごろ目にする教育言説に欠けているものでもある。教育社会学に興味がある方はもちろん、そうでない方(教育問題に関心がある方も、そうでない方も)ぜひ多くの方に読んでいただきたいなと思う一冊(270ページほどですが、読みやすい文体なのでぜひ!)。
Posted by
「教育問題」を語ることの難しさがとても良く説明されています。 私は専門が美術科教育ですが、美術科教育に関わる人たちは、常に「良さ、美しさ」「美術のちから」などの非常にあいまいな言葉を使って、絶対善としての美術を語ってきました。 しかし、そうした議論はアート業界にも、教育業界にも...
「教育問題」を語ることの難しさがとても良く説明されています。 私は専門が美術科教育ですが、美術科教育に関わる人たちは、常に「良さ、美しさ」「美術のちから」などの非常にあいまいな言葉を使って、絶対善としての美術を語ってきました。 しかし、そうした議論はアート業界にも、教育業界にも、社会一般にも影響力をもってきたとはいい難いのが現状です。 現在の美術がおかれている状況を考えれば、必ずしも美術教育がよさや美しさだけで語れないことは明らかです。(問題点は時間が少ないことと、みんなが分かってくれないっていうことだけじゃないでしょ。) ちょっとそれってどうなのよ。と批判的に思うことが不足しているように感じます。 美術に限らず、教師志望、教育学をやってみようかという方は是非一読をおすすめします。手に入りやすい体裁ですし。
Posted by
- 1
- 2